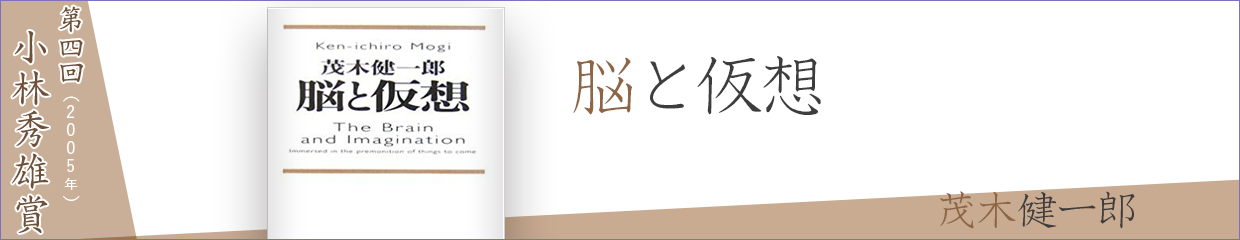インタビュー 茂木健一郎
「意識」という複合競技に挑む
小林秀雄とサンタクロース
「茂木さんの本はジャンル分け不可能ですね」と言われることがよくあります。自分でもそうだと思う。だからこそ賞というものには縁がないと思っていました。それが、敬愛する小林秀雄の名を冠した賞でしょう。だから二重に嬉しい。
小林秀雄のことは、人間の主観的体験の切実さを引き受け考えていたという点で、「同志」と呼ばせていただきたいぐらい尊敬しています。おこがましいかもしれないけど、もし同時代に生きていたら、いっしょにお酒を飲んで、いろいろ議論がしたかったと思うぐらい。心ひかれる人というのは、たくさんいます。でも、心の底から愛することのできる人は少ない。僕の場合それが小林秀雄や夏目漱石、小津安二郎なんです。
高校入試のためにさんざん小林秀雄を読まされた世代ですから、書いたものはいくつか読んでいました。当然そのときは何が書いてあるのかよくわかりませんでした。それからも折に触れて読んでいましたけど、本質はつかめないままでした。それが今から五年前、ある日の新聞に、たまたま二人の人が別の場所で「小林秀雄の講演テープが好きでよく聴いている」と書いた記事が目に止まったんです。それですぐ紀伊國屋の新宿南店までテープを買いに行ったんです。
聴いて驚きました。それまでわからなかった小林秀雄の文章の本質が、一発でわかってしまう気がした。最初に聴いたのは「信ずることと考えること」。非常に不思議な経験でした。語り口は意外にも志ん生のような調子で、文章から受ける印象とは全然違う。でも、こういうしゃべり方をする人がああいった文章を書くんだなと、意外性を経由した納得があったんです。「音楽について」という、中華料理屋で話をしているテープがあるんですが、これが音の本質についてとてつもなく高尚なことを語っているんです。普通、高尚な思想と猥雑な日常は同居しないと思いがちですが、そうじゃなくて、音を立てて食事をし、酔っ払いながら、本質的な話をしている。プラトンに「書き言葉は話し言葉に劣る」という考えがありますが、まさにその通りで。何となく、小林秀雄の書いたものに比べて、話したことは低くみられがちですけど、とても大切なことがあそこには隠れていたんです。
それからはもうテープが擦り切れるぐらい聴き込みました。歩きながらだったり、台所で食器を洗いながらだったり。言葉の意味を理解して終わりというわけではなくて、聴くたびに発見があるんです。あのとき、あのテープに出会っていなかったら、今頃仕事の方向が全然違ったかもしれません。そのぐらい影響を受けました。
『脳と仮想』では、仮想という切り口を用いて、「心脳問題」について考えました。どうしても我々は意識について考えるとき、機械論的に分析しようとしますが、本来意識は、生命現象の一部であって、生命の本質から離れて考えることなんてできっこない。脳が情報処理の機械であるという立場は、ミス・リーディングも甚だしいわけです。脳は、生物が生き延びるために進化させてきた臓器ですから、生きるということがどういうことか考えることが、心と脳の関係を考える上で一番本質的なことのはずなんです。
小林秀雄に「自分や自分の大切な人の切ない願いを聞いてくれない神様なんていらない」というフレーズがあります。ニュートン以来の科学主義は、“私”というものを徹底的に捨象することでスタートして、“私”の切ない思いは問題として抜け落ちたまま来てしまった。もし世間が科学者に対して、「冷たい」というイメージを抱くとしたら、それはそこに由来している。そうしたイメージの対極として、小林秀雄という人がいる。
小林秀雄は、私が直面していた「心脳問題」という大問題について、エッセンシャルなことを熱く語っていました。このことが嬉しかったし、頼もしかった。そんな人はそれまで科学者にも文学者にもいなかったわけですから。でも、これまで小林秀雄が、「心脳問題」という文脈で語られることはありませんでしたよね。ほとんどオブセッションのように、彼は繰り返し心脳問題について語っています。そのこと以外のことは頭にないと言ってもいいぐらい。しかもそれが、現代に対する一種のアンチテーゼになっている。彼のようにあれだけの熱さを持って、自分というものの切なさを引き受けて議論したり考えたりしている人はいません。みんなどこかで自分のことを棚上げしているけど彼は違う。そこに心ひかれたんです。『脳と仮想』が小林秀雄へのオマージュになれば、こんな嬉しいことはありません。
「クオリア」もそうでしたが、どうやら私は具体的なエピソードに衝撃を受けて、そこから思考をスタートさせるようです。『脳と仮想』の場合、ある女の子の問いが「仮想」というものについて思考を深めていくきっかけとなりました。二〇〇一年の暮れ、福岡の学会から戻って羽田空港でカレーを食べていたとき、隣にいた五歳ぐらいの女の子が妹に、「ねえ、サンタさんていると思う?」と問いかけていました。女の子がサンタさんがいるかどうか真剣に悩み、自分より小さい妹に、私はこう思うって言い聞かせている様子。あるいは年末の慌ただしさが漂う空港の雰囲気、出張帰りであること。こうした、その瞬間を包んでいたすべての環境が、独特のニュアンスをもって、ワーッと一気に襲ってきたんです。それからです、仮想について真剣に考えるようになったのは。
そのときにはっきりと、サンタが実在するかどうかより、この世にサンタは実在しないということ自体が、サンタの実在の本質だということがわかったんです。人生において、実現しなかったからこそリアルなことというのはいっぱいありますよね。あの人とあの時いっしょになっていたらとか、あそこで電車に乗り遅れなかったらとか。このリアルな感じこそが意識というものの本質だろうと思うんです。どうしても現実を経由させて、意識という問題を考えがちですが、仮想という局面で考える方が、より強烈に意識がもっている性質が立ち上がることに気づいたんです。そういうことが、その女の子の問いを聞いて頭の中にバーっとよぎったんです。
つまりこの『脳と仮想』は、小林秀雄とサンタさんから生まれた(笑)。小林秀雄は死んじゃったけど、空港で出会ったあの女の子は今もどこかにいるんだろうな。彼女に感謝しないといけないですね。
僕のミッション
『脳と仮想』は、「考える人」での連載がもとになりましたが、こういう雑誌に書くのは始めての経験だったので、とても苦しかったです。それまでは、あくまでも科学者の範疇でものを書いていたと思うのですが、今回はそれじゃダメだと思ったし、今まで以上の集中力がどうしても必要でした。
もし『脳と仮想』が、今までより踏み込んで意識について書いたという印象をもたれたら、その辺りが原因でしょうね。科学者という文脈を気にしないで書いていましたから。自分のフィールドを踏み越えてしまうと、ためらいが生まれたり批判されたりしますが、私の場合は開き直っていました。同業者や科学界からいろいろ言われるのには慣れていますし。そもそも「クオリア」とか持ち出した時点でかなり目を付けられていますからね(笑)。
科学界からのブーイングは今に始まったことではないんですよ。一九九六年の夏に、当時英国留学中だったのですが、日本の神経学者が集まる大会に呼ばれて一時間話をしました。その大会で私は歴史に残るような大スキャンダルを起こしてしまったんです。そのときはちょうど「クオリア」のことばかり考えていて、英国の学者相手に「お前らにはわかってたまるか!」ぐらいの勢いで突っかかっていく日々が続いていて、孤独だった。そうした気持ちが大舞台でそのまま出て、大変攻撃的な講演になっちゃったんです。神経科学の正当なパラダイムに対して「お前らこのままじゃダメだ」って、完全に異を唱えるような話をした。しかもみんなきちんとした服を着ているのに、僕だけジーンズにポール・スミスのTシャツ(笑)。総スカンでした。彼らにしてみれば、普段やっていることの全否定なわけですから。
終わってから「あんな話しちゃダメだよ」っていろいろな人に言われました。本当に最悪。そのぐらい当時「クオリア」という概念は受け入れがたいものだったんです。正統な学会の中では、「クオリア」なんて「あっち行け、シッシッ!」ってなもんで。そういうことばかり経験しているので、幸か不幸か批判に対しては免疫があるんです。
僕も自分で変な奴だと思いますよ。島田雅彦さんにも「お前は宮沢賢治のような奴だということがわかっているの?」と言われたことがあります。その通りだと思う。ティーンエージャーの頃から、社会のど真ん中から外れていて、端の方でおとなしくしている人間だと思っていましたから。中高と共学でしたが、色恋にもあまり縁がなくて。ヴァレンタイン・デーにケーキをもらったときに、「ありがとう。帰ってうちの犬にも食べさせるよ」って言って、めちゃくちゃ怒られました(笑)。最愛の犬にも食べさせたいっていうつもりだったんだけど。そのぐらい世間知らずでした。
理系一辺倒というわけではなかったのですが、高校生ぐらいまでは、アインシュタインのような研究をするのが一番喜びをもたらすはずだと思っていました。今考えると、ある種のイデオロギーに近い。それで将来研究者になろうと、東大の理学部に進んだのですが、大学三年のときの恋愛事件がきっかけになって、卒業後、法学部に学士入学しました。これはいろいろな意味で人生の転機だったんです。それまで僕は偏差値的な意味ではそれなりに秀才だったと思うのですが、人生のことなんて何もわかっていなかった。高校時代に和仁陽君(現東京大学法学部助教授)という、卒業文集に「ラテン民族における栄光の概念について」って書いちゃうぐらいの天才がいて、そういう人を見てきたから、世の中には頭の良い奴悪い奴がはっきり分かれていると思っていたんです。でも、その事件で、どんな奴でも恋愛になるとまったく同じ心理的反応に陥るということがわかった。嫉妬や欲望に高級も低級もない、同じなんです。壁がガラガラ崩れるような発見でした。人間はそういう局面ではみんな同じなんだって。
それで僕も人並みに恋愛で頭がおかしくなって、法学部に(笑)。なぜ法学部かというと、好きだった彼女が法学部だったから(笑)。結局その女性は、他大の弁護士志望の学生に持って行かれてしまった。こっちは、理学部で非常に地味な生活を送っていましたから。『三四郎』の野々宮君みたいなものですよ、まさに穴蔵にこもって「外で逢えば電燈会社の技手位な格である」。俺も将来外交官か弁護士になって見返してやろうと本気で思いました。でも授業に出たらあまりにもつまらなくて、三日でイヤになって行かなくなった。
その後本来の道に戻って(笑)、大学院、理化学研究所と進みました。理系の黄金コースを進んでいるように思われるかもしれませんが、その間も分裂した生活を送っていたんです。芸術や文学を愛する気持ちと、科学主義に基づいて客観的に研究を進めなければいけないという現実の間で。そのときは、両方が結びつくわけがなく、まったく違う世界のように思っていました。C・P・スノーの『二つの文化と科学革命』じゃないけれど、芸術とか文学を経験するという人間の主観的な体験と、科学主義というのはまったく別で、融合不可能なものだと僕も周りもそう思っていました。二つの自分とでも言うのでしょうか。それが九四年二月、「クオリア」という概念に出会うことで、一つになった。これは本当に大きかった。それからの人生が少し楽になりましたから。自分のミッションというかやるべき仕事が何かわかったんです。三十二歳のときです。
だから本当に小林秀雄には驚きました。僕が「クオリア」に出会って六年後だったんですけど、彼は僕がその六年間ずっと考えてきたことを話していたのですから。ちょっと意識のことを考えたというレベルじゃなくて、本気で考えている人の言葉だったんです。
脳科学の現場は今本当に大変なことになっているんです。毎年学生を連れて北米神経学会に行くのですが、海馬だったら海馬、視覚だったら視覚と研究対象が細分化していて、一人ではとてもカバーできないほどの多彩な研究が並行して進んでいる。海馬の研究だけでも追いかけるのは至難の業です。だから、サッカーで言う「リベロ」のポジションにいないと、全体が見えてこないんです。さらにそれを意識や「クオリア」という問題に結びつけるのはもっと大変で、日々悩んでいます。どうしても人間って自分の専門性にひきつけられちゃうでしょう。だから全体を見通せる人は少ない。脳科学、特に意識の研究においては世界的にみても人材難なんです。意識の問題を考えるということは、複合競技に挑むようなもので、それも、囲碁と格闘技みたいに全然違うジャンルの複合競技。何とか必死でくらいついていこうと思っているんですけどね。
プリンストン高等研究所の天文学者であるピート・ハットがこの前、「近代科学はまだ生まれてから三百〜四百年、量子力学や相対性理論ができてから百年。宇宙の歴史から考えるとごくごく短いもので、今の科学の世界観がすべてだと思うのは、天文学的視点からみても聞違っている」と話していました。二十三世紀の科学の教科書に何が書かれているか考えたとき、彼は「二つのシナリオが予想できる。一つは、二十世紀に科学は解明され尽くされ、それ以後はそのディテールの追究に終始するというもの。もう一つは、例えば二〇五〇年頃に新しいパラダイムが現れて、それまでの世界観が書き換えられる、というもの」と言っていました。おそらく後者であろうと彼は予想したのですけれど、僕もそうだと思うし、『脳と仮想』が二十三世紀の科学の教科書に、「形而上のものと科学的なものを統合しようと試みたテキスト・ブックの一つ」と書かれる場面を、サンタクロースを待つような気持ちで想像したりしますね(笑)。
科学者は、一発屋でもいいと思うんです。アインシュタインだって、相対性理論ひとつで当てた。もちろん細分化された一つ一つの研究の文脈をフォローするのは大事なことだと思いますけど、一発屋になるには、すべての文脈を知る必要はありません。リベロの立場で全体を見通し、そのときどきにあてはまる文脈を見つければいい。
補助線という言葉を最近よく使うんです。幾何学の問題を解くのに補助線を一本書き込むことで、はるかに見通しが良くなるように、一見関係がないと思われるものに補助線を引くことで関係がクリアに見えてくることもあるわけです。例えば、文学と科学だったり、「クオリア」と物質としての脳の研究だったり。補助線を引いて、両方の良さをつなぐ。それが僕のミッション。心脳問題にしても、文学や芸術に取材して精緻にクオリアをとらえるという方向と、物質としての脳の活動をとらえる方向と、両方の精緻さをうまく組み合わせないと、本当の意味でこの問題を解くことは難しいと思います。
1962年東京生まれ。脳科学者。ソニーコンピュータサイエンス研究所シニアリサーチャー、東京工業大学大学院客員助教授(脳科学、認知科学)、東京芸術大学非常勤講師(美術解剖学)。東京大学理学部、法学部卒業後、東京大学大学院理学系研究科物理学専攻課程を修了。理学博士。理化学研究所、ケンブリッジ大学を経て現職。〈クオリア〉(意識のなかで立ち上がる、数量化できない微妙な質感)をキーワードとして、脳と心の関係を探求し続けている。現在では、文芸評論、美術評論に取り組むなど、新境地を広げつつある。主な著書に『脳とクオリア』(日経サイエンス社)、『心を生みだす脳のシステム』『脳内現象』(NHKブックス)、『意識とはなにか——〈私〉を生成する脳』『「脳」整理法』(ちくま新書)、『脳と創造性——「この私」というクオリアへ』(PHPエディターズ・グループ)など。(受賞当時)
● ● ●
選評
みずみずしい更新
加藤典洋
第四回にいたって、この賞もはじめて当初から想定されていた一作のみの受賞となった。受賞作は、茂木健一郎『脳と仮想』。初の一作受賞にふさわしい、ある意味では一人の書き手が生涯に一度しか書けない(と評者には思われる)、「命がけの飛躍」をひめた論考である。
茂木氏は、これまで「クオリア(感覚質)」という新奇な概念の提唱者として知られる脳科学者であった。「クオリア」とは何か。夕暮れ、フェンス沿いに家への道を歩いていると、夕陽のオレンジ色がなぜかほんの少し寂しく感じられる。この「感じ」は、何だろう。とこれは、評者の出まかせだが、たしか以前の著書で、氏は、こんな感じで、氏自身の「クオリア」との出会いを語っていた。「人間の経験のうち、計量できないもの」と、この本では言っている。これを氏は、脳はどのように脳自身から計量しえないモノ、すなわち心を、生みだすのか、というように、脳科学の問題として提示した。それは、あざやかな問題提起であった。
しかし、この本で茂木氏は、氏自身の作り出した問題領域である「クオリア」からさらに一歩を踏み出している。人は「クオリア」をもつ。ところでこの「クオリア」とは、人が生きる上でなくてはならない、大切なものなのではないだろうか。「クオリア」は、脳科学に着地した際には、「心」と翻訳されるだけですんだが、人が生きることの地平に着地すると、「心はなぜ人が生きる上に、なくてはならないものなのだろうか」という問いを生む、いわば体言から用言へと変わるのである。だから、ここで「クオリア」は、あこがれ、のようなものになっている。あるいは心の傷、のようなものになっている。「ねえ、サンタさんていると思う?」という幼い女の子の自分の妹に向けた囁きを氏は偶然耳にするのだが、それは、やがて、なぜ自分が生きているのか、生きてきたのか、という問いへと成熟して、今回の「仮想」(imagination)を脳のほうから考えるという試みへと氏を動かすのである。
だから、この問いがそのまま、計量できないものを計量できるかに誤解したために現代哲学の難問が生まれてしまったのではないかと考え、計量できないもの(心、時間、主観)から哲学をうち立て直そうとした、ベルクソン、フッサールの思考の延長上に位置し、またこの一点で、ベルクソンから本居宣長へと進んだ小林秀雄の思考を引き取るものともなっているのは、当然かも知れない。
とはいえ、興味深いことに、氏は、小林秀雄の評論に、現代思想の「常識」に棹さす言葉からではなく、声から、接近する。クオリアから仮想へ。その一歩は、また哲学でいうなら、意識をもとに考えたフッサールから、生きる不安をもとに考えたハイデガーへの、一歩でもある。なぜ、クオリアと言っていれば安心なのに、仮想などという危なっかしい領域に、足を踏み入れるのか。
心は、生きなければならない。心は、生きようとする。心は、生きたいと思う。本書のうちに見られる一歩の更新のみずみずしさのうちに、この氏の答えが、水のように湛えられている。この種の理系の言葉で動く本に心を動かされ、評者は、批評もまた、ここで冒険の舞台となり、更新されている、という感じを受ける。
魂の問題
河合隼雄
「脳」に関する一般の関心は高く、従って書物も多いが、今回の受賞作、茂木健一郎さんの『脳と仮想』は、それらとは一味違う面白さと意味を持つものである。小林秀雄賞にまことにふさわしい作品と思った。
科学技術の驚異的発展によって、科学万能の世界観を持つ人が多くなり、その人たちは「脳の研究が進めば心のこともわかる」と単純に考える。これに対して、茂木さんは脳の研究について語りつつ、かねてから「クオリア」(感覚質)という「人間の経験のうち、計量できないもの」の重要性を指摘してきたが、今回、「仮想」の重要性について語る冒険をしたのが、本書である。
ものごとを単純に考える人は、人間の心の外に、「現実」が絶対的に存在し、それを人間が認識すると考える。しかし、茂木さんは「私たちの認識のプロセスそのものが、一般的に現実と仮想との出会いである」そして、「脳は、様々な『仮想』とのマッチングを通して、周囲の『現実』を認識する」ことを説得的に巧みに論じている。
人間にとって仮想がいかに重要であるかを示した後に、茂木さんは「仮想によって支えられる、魂の自由があって、はじめて私たちは過酷な現実に向かい合うことができる」と言う。「脳」について語る人が「魂」という語を用いることを知って私は驚き、かつ、嬉しく思った。実に、この書物の最終章は、「魂の問題」と題されている。
心理学の世界では「魂」は禁句であった。その重要性について知りつつも、私はスイス留学から帰国後、学界で思い切ってその語を使うまで二十年近く黙っていた。「非科学的」という烙印を押されると、学者生命が絶たれるほどの危険があったからである。
現在でも私に対してそのような批判がなされているとき、脳の研究に関して「魂」が語られることは、私にとって重要な援軍を得たことになり、嬉しく感じたのである。
茂木さんの言う「仮想」は、ユング心理学において重視される「イメージ」とほぼ同様のことではないかと思う。そして、この「イメージ」の研究が、人間の主観と客観、宗教と科学の接点を明らかにするのだという私がこれまで述べてきたことと、ほとんど同じことを茂木さんが脳科学の研究の立場から述べていると思うのである。
「なぜ、単なる物質を、いくら複雑とはいえ、脳というシステムにくみ上げると、そこに『魂』が生じてしまうのか、とんと見当がつかない」ということは「近代科学のやり方に、どこか根本的な勘違いがあるということを意味するのだろう」と茂木さんは言う。
そのうち、人間の「脳」研究者と「悩」研究者が協力して、近代科学を超える新しい科学をつくり出すときが来るぞ、などという「ノー天気」なことを本気で考えさせるほど、この書物は迫力のあるものだった。
声の「クオリア」
関川夏央
小林秀雄賞の選考会には、論証や主張、というより、まず相手の話を聞こうという空気がある。問い返しがあり、思いもかけなかった角度から光があてられる。熱烈でいて不思議に静かな座談が持たれる。なるほど、この本はこう読むのか。私などは自分のうかつさ、知恵の足りなさを始終明朗に恥じている。
選考委員の年齢のばらつきが程よい。昭和戦前と昭和戦後、それに大阪万博世代までを広くカバーして、大げさにいうと五人で現代史を体現している。そうか彼はそう見るのか、とここでも自分を束縛する時代的精神の檻を自覚させられるのである。
理科系がおふた方おられる。もちろん文科系にも造詣が深い。このことも小林秀雄賞の強みだろう。私は理科系の人が書いた本を苦手としているわけではないが、おもしろいと思うのに、どこがどうおもしろいのかうまく言語化できないことがある。そういうとき、河合隼雄さんや養老孟司さんの教えを受けて私はその本を再発見し、またいくぶんか自分を発見するのである。
小林秀雄は聴衆の学生たちに、柳田国男の『山の人生』の序文にある木こりとその子供たちの悲惨な運命を紹介したあと、こういった、と茂木健一郎さんの『脳と仮想』にある。
きっと、子供の魂はどこかにいますよ。ぼくがそういう話に感動すれば、きっとどこかにいるな。
茂木さん自身は、「世界の断絶を知る者にとって、他者の魂とは、元来そのようなものである」と書き、つぎのようにつづけた。
清少納言の『枕草子』を読んで感動するとき、清少納言の魂はきっとそこにある。『それから』を読んで心を動かされる時、代助の魂はそこにある。『たけくらべ』を読みその切なさに涙するとき、私たちの心の中には、美登利の魂がきっと立ち現れる。
このくだりで私は『怒りの葡萄』を思った。小説ではなく、ジョン・フォードの映画の方だ。警察に追われて逃亡する直前のヘンリー・フォンダのことばの感触がここにある。文科系もわかる理科系の人は、こんなふうに盛り上がるのだなと考えた。
これは皮肉では全然ない。私がいいたいのは、そこに「声」を感じるということだ。声の「クオリア」があるということだ。引用された小林秀雄の講演に「クオリア」はあり、また選考会の席上にもたしかにそれはあった。
得がたい人材
養老盂司
茂木さんの作品は、いつ受賞してもおかしくないと思っていた。あとは競争相手の問題だけである。じつは以前にも、別な作品が選考の対象になったことがあるが、そのときはまだ時期が早かったと思う。今回の作品は当時より成熟しており、それ自体について、いうことはない。
脳と文学というジャンルには、世界中でも作品がほとんどない。茂木さんは物理を基礎とし、コンピュータをこなし、脳をよく理解し、文学的でもあるという意味で、得がたい人材である。大学は法学部まで卒業しているというが、それは学問とはあまり関係なく、女友だちとの関係だと聞いた。
こういう人が増えない理由は世界中で同じで、学問が専門性を持ち、学会が固有の価値観を動かさないからである。それは文学という領域内ですら、おそらく同様であろう。知的世界が組織集団を作れば、程度の差こそあれ、かならず教会化する。そういってもいいかもしれない。小林秀雄賞の選考では、なんらかの意味でそれを打ち壊す作品が求められているという気がする。もちろん作品自体が完成していれば、それはそれでいい。
いつも思うことだが、この選考会は、かなり厳しい知的労働である。作品の水準が高く、しばしば頭の格闘技になってしまう。それでも異分野間の疎通性がよくなることで、間違いなく文化が発展する。そう思えば、こういう選考に参加させてもらっているのは、ありがたいことである。
他にもいい作品があったから、そのどれが受賞してもよかったと思う。良い作品を書く人には、いずれまた機会があるはずである。茂木さん自身がそうだった。ともあれ茂木さんのような人たちに育ってもらいたい。それは私の長年の願いだったから、今回の結果は本当に嬉しかった。本望というべきであろう。
おおきな震源
堀江敏幸
茂木健一郎氏の『脳と仮想』を読んでいると、文理融合といった安直な言いまわしをつい思い浮かべてしまうのだが、ここにあるのはあらかじめこうだと定められた概念の敷衍ではなく、理から文へ、文から理へのかぎりない往還そのものを表現してみようとする動的な言葉のあらわれだろう。まだ不安定な状態でゆらゆらと揺れているものを、とにかくいまぐっと腕をのばしてつかみ取っておこうとする果敢な姿勢があって、私はそこに惹かれた。クオリアを核に書かれていた諸作と比較すると、文体は軽快になっているのに、中身は深く、濃くなっている。
本書で示された仮想の捉え方は、現在の文学が模索している領域にも応用可能かもしれない。コミュニケーションにおける必然的な誤読、理解と無理解のあいだの溝とすれちがい、現実の写しのむこうにあるものに対する想像力とその肯定的な把握。心は随伴現象ではなく、脳内現象でありながらそれを超えたなにかであり、この「なにか」が現実におよぼす効果を本気で受け止めなければ、文学や芸術の世界の謎に迫ることはできない。「複数の感覚の経路の間での、あるいは作用の経路の間での整合性」を超えたものを語るに際して、小林秀雄の書き言葉ではなく、声や身体がまっすぐ迫ってくる講演に着目したところにも、本来なら理解できるはずのない「断絶」を前提とした他者の心との「つながり」の可能性に賭けようとする、飛躍への意思が感じられた。
しかも飛躍は、すぐ近くにあってなお遠い場所からやってくる。そして、それをうながす不意打ちは、道頓堀で聴いたモーツァルトの交響曲によってではなく、羽田空港でひとりの少女が発した、「サンタさんていると思う?」という問い掛けによってもたらされる。存在するか否か、ではない。存在する、と想像しなければ意味をなさない存在こそがサンタクロースなのであり、その切実な仮想が生を豊かにするのだ。
「切実な仮想」が、最もつよい現実になるところで、科学と文学がまじわる日がくるのかもしれない。いや、「まじわる」という「仮想」こそが大切なのだ。茂木氏の本は、そんなことをいつまでも考えさせる、おおきな震源になってくれるだろう。

2007/3/28発売
この記事をシェアする
「小林秀雄賞」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥