せっかく老人になったのに古典を自在に読みこなす力がない。しかし、そんな私にだって、伊藤比呂美のように、活字化された「説経節」をそれなりに気を入れて読んだ経験がないではないのですよ。という意味のことを前回にちょっと書いた。今回はそこから――。
いまはむかし、1970年代もそろそろ終わり近くなっていたと思うが、私もその一員だった演劇集団「黒テント」が、「物語る演劇」と銘打って、喫茶店や河原や大学構内の小空間で、戯曲ではなく、詩や小説や童話を地の文ごと演じてしまう出前芝居(呼ばれたらどこにでもでかける小型演劇)のシリーズをつづけていたことがある。斎藤晴彦と福原一臣という、いまは亡きふたりのタフな俳優が、隣国の詩人、金芝河の『源氏物語』をもじった長編風刺詩『糞氏物語』を、そのまま掛け合いで演じてみせるとかね。
ほかにも『宮沢賢治旅行記』とか、内戦で殺されたスペインの詩人、ガルシア・ロルカの作品をコラージュした『ラ・バラッカ』とか、いろいろやったうちのひとつに説経節の「小栗判官」があった。
それにしても、あのころなぜ「小栗判官」だったのだろうか。
いま思いかえすと、この時期――1960年代の後半から70年代にかけて、それまでの対話や会話中心の近代劇に物足りなくなった演劇人たちの一部が、それとは別の演劇のすがたをもとめて、いっせいに近代以前の社会にあった民衆的な「語りもの」への関心を深めていった。そんな「時代の空気」とでもいったものが濃厚にあり、たぶんそれが私たちの背中を押していたのだろう。
具体的にいうと、この関心から、平家琵琶や義経伝説にもとづく秋元松代の『常陸坊海尊』(1967年初演)や、宮本常一の『忘れられた日本人』による坂本長利のひとり芝居『土佐源氏』(同)に端を発し、早稲田小劇場の鈴木忠志と白石加代子による『劇的なるものをめぐってⅡ』(70年)などをへて、木下順二の『平家物語』にもとづく朗読劇『子午線の祀り』(79年)や、黒テントの「物語る演劇」の集大成ともいうべき『西遊記』(80年)あたりにまでつづく演劇の流れが、じっさいに生じていたということ――。
それにもうひとつ、「小栗判官」にしぼっていうと、1973年に、前記の東洋文庫版『説経節』(荒木繁・山本吉左右編注)が平凡社からでて、それに刺激されたという面もあったにちがいない。なにしろ伊藤比呂美とおなじく、私も、ほかの何人かの演劇人たちも、この本ではじめて「小栗判官」「信徳丸」「山椒太夫」などの説経節のテキストを読み、すくなからぬショックをうけていたのだから。

そしてさらに踏み込んでいうなら、この東洋文庫版『説経節』の刊行は、演劇以前に、まずは日本文学研究の領域に生じた新しい波のあらわれでもあった。そのことをつよくアッピールしてみせたのが、巻末におかれた山本吉左右の解説「説経節の語りと構造」です。
この解説はのちに「口語りの論」というより大きな論文に成長してゆく。そこで以下はそちらによって話をすすめると、この論の勘どころは、説経節の語り手(=歌い手)たちはなにも物語をまるごと暗記していたわけではない。いまものこるゴゼ歌やイタコがそうであるように、かれらはそのつど、既成の「決り文句や口語りの単位を自由に運用しながら物語を構成」していたのだという発見にあった。
「記憶の経済」という点では、それは既成のユニットを組み合わせてつくる現今のプレハブ建築に似ている、と山本はいう。ただし、
プレハブ建築の各ユニットはそのために新しく生産されたものだが、口語りの決り文句は師匠がかつて具体的な物語として語ったものの断片であり、この点からは廃物なのである。口語りはその廃物をさまざまなコンテキストの中で生かすのである。(山本吉左右『くつわの音がざざめいて』)
たとえば「一引き引けば、千僧供養。二引き引けば、万僧供養」という例のフレーズの場合、もとはといえば城普請で重い石をはこぶさいの「車引き」の歌だったものが、説経節の「小栗判官」では、地獄からよみがえり餓鬼阿弥と化した小栗を車にのせて熊野にむかう「道行き」の場面で使われる。ところが、おなじ説経節でも「山椒太夫」では、おなじ文句が、のこぎりで罪人の首を「引き切る」処刑の場面に平然と流用されていたりするのだ。ことほどさように――。
と山本の解説は、こうした「説経節の語りと構造」を、つまりは説経節の「つくり方」や「おぼえ方」を、おおくの実例とデータ分析によって子細に解きあかしてくれた。
――口承文芸などと、つい気軽にいってしまうけれども、文字の助けなしに、どうやってかれらはこんなに味のこい物語をつくりあげ、どうやってそれを記憶しつづけていたのかしらん。
なんとなくそうふしぎに思っていた私などは、一読、パッと目をひらかれる思いがした。いや、けっして読みやすい文章ではないのですよ。でも我慢して読むうちに、
――よおし、これまでだれもやらなかったことを、とうとうやってのけたぞ。
と意気ごむ筆者の声がどこからともなくきこえてくる。さきに「新しい波」といったのはそういう意味なのである。
しかも、これはあとになって知ったのだが、この新しい波は、かならずしも山本ひとりの力で起きたものではなかった。
この解説「説経節の語りと構造」(=「口語りの論」)をふくむ「語りもの」研究の成果を、のちに『くつわの音がざざめいて』という論集にまとめたさい、その「あとがき」に、山本は「この間、私をはらはらとしながら見守って下さっていたのは、二人の師、西郷信綱先生(おや、またしても)と広末保先生であった」としるしている。

山本吉左右は私の三歳上で、私とおなじ60年代に大学生活をおくった。かれの場合は法政大学文学部の大学院だったが、そこで先生として出会ったのが西郷(古代文学)と広末(近世文学)のふたりで、中世文学専攻だった山本も、かれらによって古い「語りもの」への関心をはじめて植えつけられたらしい。
とりわけ、かつてイギリスの大学に身をおいていたことのある西郷信綱の影響が大きかった。そう推測するのは、イギリスをふくめての当時の英語圏で、文字以前のオーラルな文芸の「語りと構造」の研究が着々とすすんでいたからです。
そして、そのかなめの位置にあったのが1960年に刊行されたアメリカの比較文学研究者、アルバート・ロードの『物語の歌い手《The Singer of Tales》』という本。――この本でロードは、古代ギリシャの吟遊詩人ホメロスが文字のない世界で、どのようにして『イーリアス』や『オデュッセイア』のような複雑な長編叙事詩をつくりあげ、それを語りつたえることができたのか。その「つくり方」や「おぼえ方」を明快に解きあかしてみせた。
おそらくは若き山本吉左右も西郷のもとでこの本を読んだのだろう。そして、そこからまなんだ新しい研究手法(決まり文句の効用など)を、長い時間をかけて、説経節や幸若舞などの中世日本の「語りもの」にあざやかに適用してみせた。それがじつはあの解説だったのではないだろうか。断定はしませんよ。ただのシロウトの勘です。
*
そして、これもまた勘にたよっていうのだが、おそらく伊藤比呂美もこの山本の解説を読んでいたのだと思う。伊藤は「先人たちの手を借りて、テキストをしつこく読み込んだらしい。(略)その結果、説経節では同一の決まり文句が頻繁に使いまわされていることが次第にわかってきた」と前回で私はのべた。その「先人たち」がさしのべた「手」の一本が、じつはこの解説だったのではなかろうか。
ただし伊藤は「女の詩人」で、私のような「男のインテリ」ではないから、おなじ説経節でも読み方がちがう。あたまだけでなく、じぶんの人生も、身ぢかな人びとや動植物との関係も、すべてをひっくるめて、からだごと説経節に突っ込んでゆく。たとえば「わたしの説経節」(『新訳 説経節』)冒頭のこんな一節――。
苦の多い人生を送ってきました。
結婚は何回もしましたし、男の苦労も、子の苦労もさんざっぱら。支払日は通帳かかえて右往左往してますし、ここ数十年は他国に流離し、ビザの苦労にことばの苦労、老いた親を看取る苦労もありまして……。自業自得とはいいながら、苦労の国から苦労の宣伝販売にきたようなもんだ、それが日々の暮らしか、人生かと観念していますけれども、それはわたしだけにあらず、事情こそ違え、女と生まれたからには、みなそうかも。で、つらいとき思わず知らず口ずさむのが説経節のちょっとしたフレーズです。
ここでいう「ちょっとしたフレーズ」とは、ことわるまでもなく、いまもふれた「えいさらえい」や「心は二つ、身は一つ」などの山本いうところの「断片」――つまり流用可能な決まり文句のこと。
あるいは「しんとく取って肩に掛け」もそう。伊藤訳では「むんずとつかんで、肩にかつぎあげ、支えて、ともに歩き出す」となるが、ふつうなら天秤棒や連尺(背負子)を「えいや」とかつぐさいの決まり文句が、説経節「しんとく丸」では、ヒロインの乙姫が目を病んだ恋人のしんとくをサポートする場面で使われている。その流用の異様さが生む「はげしさ」を伊藤は見逃さなかった。
親の反対にも負けずに、親を説き伏せ、旅に出て、苦労して、やっと見つけたしんとく丸を、むんずとつかんで、肩にかつぎあげ、支えて、ともに町に向かって歩き出します。その踏み出す一歩一歩が、たくましいこと、この上もない。「おひめさま」という設定なので、つい可憐な美人を思い浮かべますが、もしかしたら、レスラーのように筋骨のりゅうとした女だったのかもしれないのであります。(「わたしの説経節」)
もうだれにも頼れず、親も子も男も、ひとりでひきずっていくしかなくなったとき――そういう目にはなんども遭遇したが、そのつど、この「しんとく取って肩に掛け」というフレーズを口ずさんで、じぶんを元気づけ、立ち上がった、と伊藤はいう。
「そうなんです、説経節の女たちは、みんなわたしだった。苦労している女はみんな言うでしょう、これはわたし、と」――
なんのかんのいっても私は男だから、伊藤とちがって、なかば自動的に、説経節の物語を小栗やしんとく丸や厨子王たち、病んで壊れて落魄した男たちの側に感情移入して読んでしまう。
ましてや説経節を最初に読んだころは、まだ30代で、おまけにひとり身の中年男だったからね。なさけないかな、かれらを懸命にささえる照手姫や乙姫や安寿を、型どおりの、けなげで可憐な女性とだけ理解し、彼女たちの「隆々たる筋骨」のたくましさの方にはまったく気づかずにいた。
そして半世紀のち、そんな認識のまま伊藤比呂美の現代語訳や「わたしの説経節」にせっしてガクゼンとした。とうぜんだろう。むかしとはちがい、いまや私も「哀れにも無残な状態になり果て」、私の照手たちによって「むんずとつかんで、肩にかつぎあげ」られる半幽霊、伊藤いうところの「ゾンビ」まがいの存在になってしまっているのだから。
冒頭で申しあげたように、わたしは女として、男を知り、男に期待し、失望し、絶望もし、男とともに、子作りも子育てもしてきました。その結果、男とは、とても魅力的に見え、社会的にはたくましく、有能そうに振る舞っている人たちも、本質的には餓鬼阿弥のような存在であるという感想を持つにいたりました。これは、定義ではなく、むしろ、わたしの知ってる男たちはみんなそうだった、そういう男こそ魅力的だったという個人的な感想にすぎません。(「わたしの説経節」)
これを読んで年老いたひとりの男としてどう思うか。
――まいった。しかし基本的には異論なし。よくもまあ、ズバリといってくださった。おかげで頭がスッキリしましたよ。
そして、そのスッキリした頭であらためて考えてみると、青年や壮年諸氏はともあれ、いまやまぎれもない老人となった男たちは、じつはそう指摘される以前から、「強くてよく働く」女たちにくらべて、われわれはまさしく「餓鬼阿弥のような存在」であったなと、ひしひしとそう感じざるをえなくなっていたのである。あんがい早くその事実に気づき、だったら残された短い時間を餓鬼阿弥なりにどう生きていこうかと、私にかぎらず、みなさん、むっつりと黙りこんだ腹の底で、それなりに必死で考えているのではないかな。
いまや一老耄と化した男の感想はここまで――。
いそいで伊藤比呂美にもどると、これほどまでに全身で説経節にのめりこんでしまえば、プロの詩人や小説家として、あとはもう、じぶんで「わたしの説経節」をつくるしかない。
そこで、いくつかの小さなこころみをかさね、そこから、2005年に長編詩『河原荒草』、2007年に「語りもの」ふうの長い小説(かな?)『とげ抜き 新巣鴨地蔵縁起』という、前世紀末から日米間をあわただく往来してきた母親(『とげ抜き』では伊藤しろみ。東京下町そだちなのでヒがシになってしまう)と複数の子どもたち(その代表が長女のカノコ)の体験にもとづく、21世紀版「説経節」ともいうべきふたつの異形の傑作が生まれてくる。

一方、読者としての私はというと、本がでてすぐのころに『とげ抜き 新巣鴨地蔵縁起』を読み、だがこのときはあえなく中途で挫折した。
そして、それから10年ほどのち、古本屋でみつけた『新訳 説経節』に手もなく感心させられ、感心のあまりいくつかの箇所を原典と読みくらべ、いきおいにのって『河原荒草』を読んだら、それがまた途方もなくおもしろかった。そこでもういちど『とげ抜き』に挑戦し、なんであのとき私はこの本が読めなかったのだろうと怪訝に思いながら、いまもちびりちびりと読みつづけている。老来、とみに集中力がおとろえ、このような高密度のテキストとなると、時間をかけてゆっくり読むしか手がないのです。
*
むかしとちがって、いまの日本人には古典を読む力がいちじるしく欠けている。そのことをみとめた上で、それでも信頼できる注釈本と古語辞典の力を借りて、なんとか原典で読むようにしたほうがいい。現代語訳でつるつる読んだって読んだことにはならんよ。
それがまっとうな忠告であることはわかります。しかし、だからといって、現代語訳をあたまからアンチョコなみの実用品や代用品とみなしてしまうのは、いまの私にはむずかしい。断じるに十分な実力に欠けるという私的な事情もあるが、それだけではない。現代語訳のもつ意味が、つまりは原典と現代語訳との関係のしかたが、この10年ほどのあいだにいくぶんかなりとも変化しはじめた。そんな気配がたしかに感じられるからです。
その変化のさまを如実に示したのが池澤夏樹編集の河出版『日本文学全集』だったが、ほかにもいくつかの兆候がみつかる。その先駆的な、そしてもっとも強力なひとつが、ここまでのべてきた伊藤比呂美による説経節や、それに先だつ、般若心経、白骨(蓮如の御文章)、観音経などの仏典の現代語訳。このことはもう繰りかえすまでもないでしょう。
これまで古典の現代語訳は、おもに学生向けの参考書として専門研究者の手にゆだねられてきた。その場合はあくまでも原文が中心で、現代語訳は注釈とともに小さな活字で組まれる。
もうひとつ現役の文学者による現代語訳があって、こちらは原文や注釈なし。それだけで1冊の本になっている。ただし、れっきとした作品というよりも、だいたいは古典につよい小説家や詩人や評論家が一般読者むけに書いた啓蒙的な教養書として出版されていた。
そして、こうした参考書や教養書としての現代語訳にくらべると、池澤夏樹や伊藤比呂美といった人たちの新訳には、いくつかのめだったちがいのあることがわかってくる。
まず第1に、現代語訳にとりくむのが、研究者や古典につよい文学者(たとえば佐藤春夫、石川淳、福永武彦のような)ではなく、おおかたの読者と同様に、ろくに古典を読んだこともない、ただのシロウトであること。池澤や伊藤もふくめて、河出版『日本文学全集』に参加した作家たちも、ほぼ全員がその側に属する。
第2に、したがって伊藤訳が典型的にそうであるように、古典を「わたしの経験」によって読み込む傾きがつよい。イタリアの作家、イタロ・カルヴィーノにならっていうと、かれらもまた「古典を読んで理解するためには、自分が『どこに』いてそれを読んでいるかを明確にする必要がある。さもなくば、本自体も読者も、時間から外れた雲のなかで暮らすことになる」(『なぜ古典を読むのか』)とつよく感じているのです。
そして第3に、いまの世界に生きる作家の体験とコトバの技術をもちいて、原典の構造に、しばしば思いきった工夫をくわえていること。伊藤比呂美が「道行き」にほどこした「行かえ」もその一例だが、おなじ技法が、やはり詩人でもある池澤夏樹訳の『古事記』冒頭の「国生み」と、それにつづく神々の系譜リストの箇所でも、いっそう複雑なしかたで駆使されている。
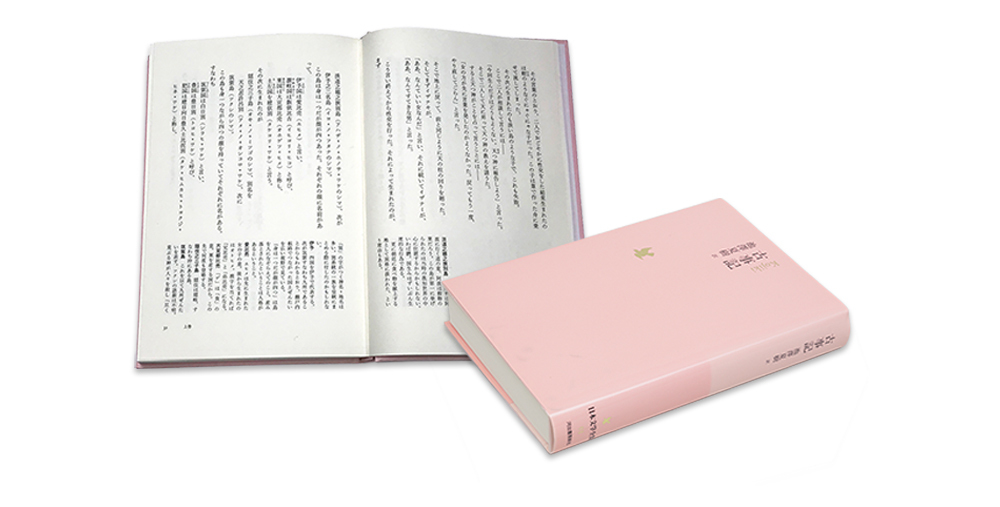
そこで地上に戻って、前と同じように天の柱の回りを廻った。
そしてまずイザナキが、
「ああ、なんていい女なんだ」と言い、それに続いてイザナミが、
「ああ、なんてすてきな男」と言った。こう言い終えてから性交を行った。それによって生まれたのが、まず
淡道之穂之狭別島(アハヂ・ノ・ホノサ・ワケのシマ)、次が
伊予之二名島(イヨ・ノ・フタナのシマ)。
この島は身は一つだが顔が四つあった。それぞれの顔に名前があって、
伊予国は愛比売(エヒメ)と言い、
讃岐国は飯依比古(イヒヨリ・ヒコ)と呼び、
粟国は大宜都比売(オホゲツ・ヒメ)と称し、
土左国を建依別(タケヨリ・ワケ)と言う。……
このあと12ページにわたって神々の系譜が延々とつづく。したがって説経節の「道行き」がやはりそうであったように、原文でも現代語訳でも、読む者は退屈して、たいていは、つい読みとばしてしまう。
ところが、これを巧みに「行かえ」してしるすと、それだけのことでつよいリズムが生じ、おなじ記述が、読む者のこころを深々と揺する「読む語りもの」に変貌する。その変貌ぶりたるや、こんな簡単なテクニックなのに、なぜこれまでやってみた人がいなかったのだろう、とふしぎに思えてくるくらい。
しかし考えてみれば、原典に忠実であることを旨とするアカデミックな世界の研究者に、この種の思いきった、いってみれば乱暴な変貌をもとめるのは、もともとむりな話なのです。その役割はかれらでなく、べつの世界の、べつの基準でうごく人たちの手にゆだねたほうがいい。となれば、いまのところ、専門的な意味ではシロウトだが、ことばの世界ではクロウトの詩人や作家がその役を担うしかない。「いまのところ」というのは、いずれどこかから、その仕事を専業とする書き手があらわれてくるかもしれないから。
ただし実際にそうなるかどうかはだれにもわからない。いまのところ、はっきりいえるのは、私たちの社会に、
――シロウトにしかできない現代語訳を、おなじシロウトである読者がたのしむ。
というあり方をよしとする空気が生まれる気配がようやく見えてきた、というところまで。
シロウトといっても、なにも素手で原典にとりくむわけではない。いまじぶんが生きている場で、じぶんの知らない遠い過去に生まれたテキストとまともに取り組むには、伊藤比呂美や池澤夏樹が現にそうしたように、専門の研究者たちのすぐれた仕事にたよるしかない。『日本文学全集』に参加したほかの作家たちも、かならずや、おなじような努力をかさねたにちがいないのです。
そして、こうして生まれた現代語訳では、読者はそれを古典のたんなる「代用品」ではなく、それ自体を、もともとの作者、おおくの研究者、そして現代の詩人や作家――その三者の力がひとつに縒り合わされた「それだけでも自立しうる作品」として読むことができる。
その点では、諸外国の詩や小説やエッセイを翻訳で読む場合とおなじ。
私たちは外国語では本が読めない。読めても、せいぜい数カ国語。たとえ英語やフランス語が読めても中国語やスワヒリ語は読めない。そこで、たとえば『西遊記』は岩波文庫の中野美代子訳で読むことになる。
同様に、モンテーニュの『エセー』を宮下志朗訳で、マーク・トウェインの『ハックルベリー・フィンの冒けん』を柴田元幸訳で、カフカの『城』を池内紀訳で、フィッツジェラルドの『グレート・ギャツビー』を村上春樹訳で読み、それでその作品を読んだことにする。わざわざそう決めなくとも自然にそうしている。なにしろそうするしかないのだから。
とすれば、古典がうまく読めなくなった私たちがそれ自体で充実した「作品としての現代語訳」を必要とするようになるのは、とうぜんのなりゆきなのです。
とはいうものの、日本の古典は外国語ではなく日本語で書かれているから、そこからさかのぼって、多少の努力をすれば、原典を「信頼できる注釈本と古語辞典の力を借りて」読むこともできる。もしも、そうした欲求をかきたてる魅力をひめた新訳がさらに増えてゆくなら、「古典が読めない!」という私たちの悲鳴は、かつて存在した古典教養のゆたかさからの劣化のあかしではなく、私たちが古典とのあいだに新しい関係をきずく、ささやかな号砲に変わるかもしれない。
そうなるという確証はもちろんありません。でも、できればそうなってほしい。私たちだけでなく、この先、いっそう古典が読めなくなるにちがいない未来の私たちのためにもね。
―――――――――
伊藤比呂美訳『新訳 説経節』平凡社、2015年
荒木繁・山本吉左右編注『説経節』平凡社・東洋文庫、1973年
山本吉左右『くつわの音がざざめいて――語りの文芸考』平凡社選書、1988年
Albert B.Lord『The Singer of Tales』Harbard University Press. 1960年
伊藤比呂美『河原荒草』思潮社、2005年
伊藤比呂美『とげ抜き 新巣鴨地蔵縁起』講談社、2007年
イタロ・カルヴィーノ『なぜ古典を読むのか』須賀敦子訳、みすず書房、1997年
日本文学全集『古事記』池澤夏樹訳、河出書房新社、2014年














