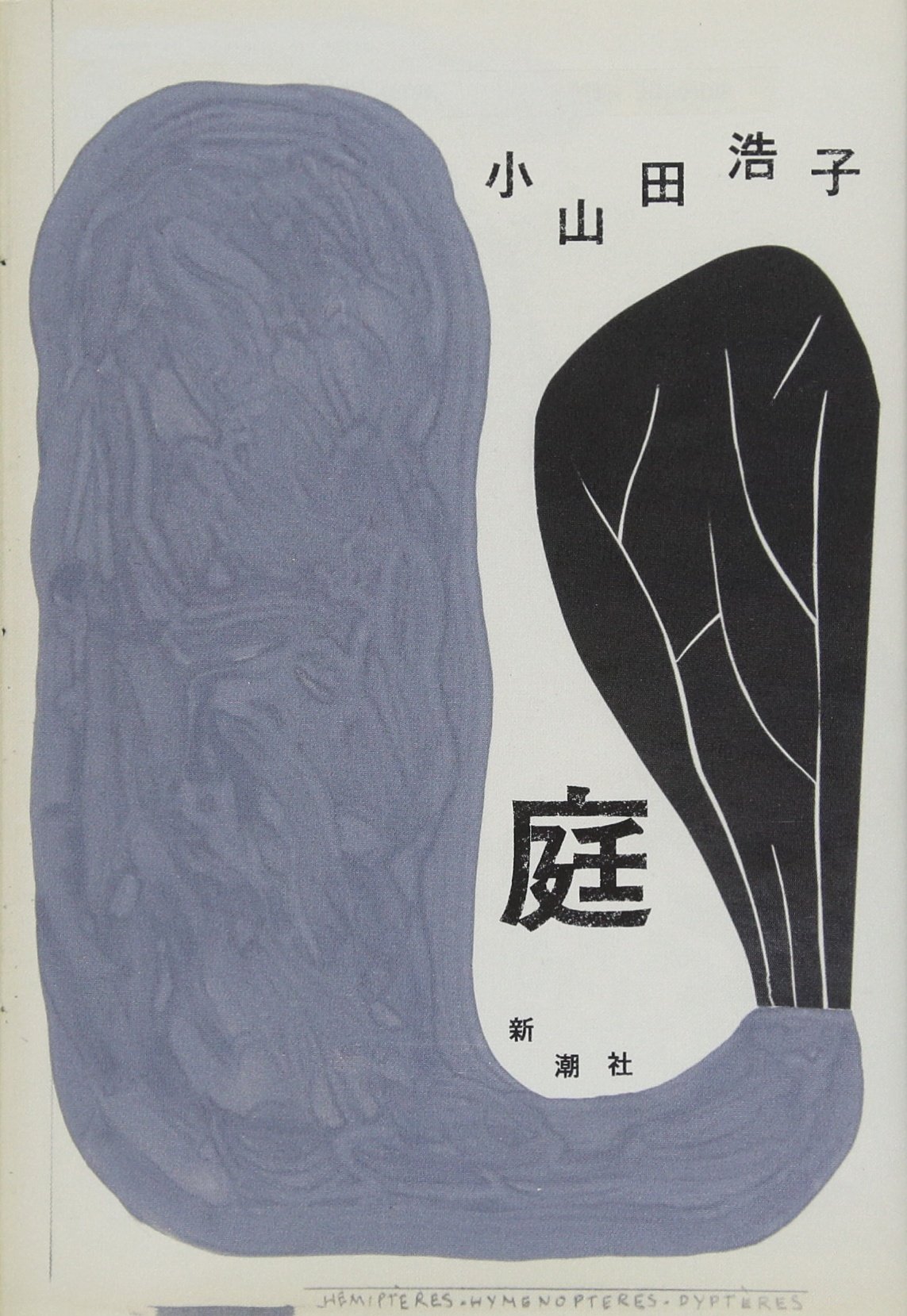2018年8月31日
[後編]老人の話と実家の話
小山田浩子さんの最新刊『庭』の刊行を記念して行われた、作家・津村記久子さんとの初対談。後半では、小山田作品の中でも重要な役割を占める「老人」と「実家」について、そしてとくに最近の作品の中で活躍している子どもたちの「嘘」などについても、お話が盛り上がります。
津村 小山田さんの作品は、老人が喋る話と並んで、実家に帰る話が多いと。
小山田 そうなんです。都会の人を田舎に連れて行くパターンが多くて。私自身も田舎で暮らしているのに、それを都会の人間に憑依してから書きたくなってしまうようです。
津村 確かにそうですね。都会に住んでいる人が実家に帰って、生活や習慣の違いに「うわー」ってなっている。小山田さんご自身は、ご自分や旦那さんの実家に帰ったりはよくされるんですか。
小山田 はい。自分も田舎に住んでいるのに、また別の田舎である実家に帰った時は、それはそれで「うわー」ってなったりしています(笑)。嫌じゃないけど違うなあって。
津村 私も去年、色々なところに行く仕事をしていたんですけど、同じ日本やのに場所によってずいぶん違うなと感じました。たとえば四国でいうと高知と徳島でも全然違うらしいですね。
小山田 多分全然違いますね。体感温度とか湿度が違うんではないかというぐらい。
津村 小山田さんはその違いを、空気から書きはるのがすごいなと。とても小さなところから放射するように世界を立ち上がらせている感じがします。実家に帰る話のひとつ、「彼岸花」という作品には「義祖母」が出てきますが、「義祖母」って珍しいですよね。
小山田 「義母」、つまり「姑」だと、すでにその「姑」という言葉に物語的なものがくっついていますよね。「義祖母」だとまたちょっと違って、敵なのか味方なのかわからない。味方なんやけど、その立場は一回姑が絡んだ状態で味方なんじゃないか、とか。結構色々なことがあり得るなと。
津村 その感じが面白い。他にも、夫の実家に泊まるか駅前のホテルに泊まるかっていう、妙に細かい言い争いがあったりするのも巧い。こうやって、家に泊まってくれっていう人いますよね。
小山田 います。部屋が余っているのに何でホテルなんか取るんだって言われたら、説得できないんですよね。ホテルに泊まりたいという気持ちは絶対に理解してもらえない。
津村 わかります。高知の友達の家に行くってなったときに、「大きい家だからぜひ泊まってね」って言ってくれたんですけど、私はだらだらするから恥ずかしいんで「私すごくだらだらするので……」と言うんですが、「誰も気にしないよー」と返答されて、いや、私が気にするんで……と申し訳なかったことがあります。
小山田 そんなんじゃ全然だめです(笑)。「全然いいのよ! 襖立てたらいいのよ、開けないし!」みたいに返されますから、きっと。
津村 「どら」っていう掛け声で立ちあがる義祖母の存在が、不穏なような可愛いような感じですよね。この義祖母の話の嘘だか本当だかわからないドリーミーなところと、どっちに泊まるのかっていう現実的な齟齬とが混ざり合った世界がとても立体的で、その混ざり合い方は本当に小山田さんだけのものじゃないかと思います。でも描かれているのは普遍的なことで、読んでいるとちょっとめまいに近い感覚がある。小山田さんご自身は、旦那さんの実家に帰るとどんな感じがしますか。
小山田 年に一、二回しか帰らないので、かなりお客さん扱いされます。申し訳ないと思うんですが、でも手伝ってね、手伝いますとなっても、やっぱり義母のルールがあるので困ってしまう。たとえば「食器洗います」って言っても、スポンジから何から、確認しないとできない感じ。考えずにやって、ちゃんとできて「できましたお義母さん!」と言えるお嫁さんもいると思うんですが、私はそうではないので逐一確認してるうちに、なんかもういいよ、ってお互いなってしまうのが申し訳なくて、楽だけど悩ましいです。
津村 ありますよね、その場所の作法みたいなものって。自分の親でさえ、やっぱり気を遣ってしまうところがある。姑もそうやけど、ある程度年のいった女の人には、踏み込めない作法や世界みたいなものが結構あるでしょう。「彼岸花」や「名犬」を読みながら、自分もそんな風になるんかなって思ったりもしました。
小山田 でも、今の私が70歳、80歳になった時に、こうなれるのかって考えると、たぶんなれないと思うんですよね。だから、失われたひとつの文化みたいな感じがして、ちょっと寂しいという思いもあります。
津村 もっとニュートラルな老人になるのかも知れないですね。ひとつの土地のことしか知らん人、その土地でずっと暮らしている人のエネルギーってありますよね。
小山田 あります、磁場みたいなのが明確にあると感じます。
津村 最近は、たとえば東京からどんだけ離れてるとか、よそとの距離をはかりながら生きている人が多いと思うんです。でも『庭』に出てくるおじいさんおばあさんには、距離みたいなものがないんですよね。点で生きているという感じがします。そういう原初的な何かが漂っているところに惹きつけられます。
小山田 そうなんです、魅力的なんですよ。田舎に行って「うわー」って思うのも、嫌だとか嫌いだとかということではなく、ただあまりの違いとわかり合えない、ずっと平行線であろう感じを思って、「うわー」となる。でも好きだし、魅力を感じるんです。
津村 「どじょう」という短篇では、近所の人がどじょうを掬いに来て、引っ越してきたばかりの視点人物が「うわー」ってなる。でも元々その場所に住んでる人にとってはそれが普通やから、それについて書こうとすら思わないのかも。外側から見るから書ける。
小山田 そうですね、そうかもしれません。
津村 「名犬」の舞台は「さるなし温泉郷」なんですけど、これは本当にあるんですか?
小山田 そういう地名はないんですが、さるなしっていう果物があるんです。親指みたいな細長い形をしていて、甘くて美味しい。滋養強壮の効果があって、そのまま食べてもいいし、ジャムにしても、お酒に漬けてもすごくいいらしい。まだ実物を食べたことはないんですけど、図鑑で読んで以来、私の憧れの品なんです。とにかく田舎の山の方に生えていると。
津村 そうなんですね。では実際にこういう場所があるわけではない?
小山田 イメージの元になったものはあります。義両親と私たち家族で温泉に行ったことがあって、その時に猟犬と遊んだんです。その時のことを私小説のように書いていたら、途中からどんどん違ってきてしまって。だから「名犬」は私の憧れのさるなしと、家族で行った温泉旅行がくっついてできたんです。
津村 おばあちゃんが交互に喋っているところ――「これがさるなしちゅう」「アマカロ」「ウマカロ」「体にええわ」「滋養になるわ」「ワイが山で採ったちゅう」「えがい苦労してこんなもんを採るわ年寄りは」――このあたり、ずっと読んでたい心地よさがあります。老人って、突拍子もないことを言ったりして本当に面白いですよね。特有の世界軸で生きてはるからかな。
小山田 そうなんですよ。だから通じないところは、びっくりするほど通じない。倫理観など、通じない部分がぽこっぽこっと出て来て戸惑ったりします。
津村 スタジアムに行ったときに、2つ隣の席のおばあさんがカレーを見せて話しかけてきたことがあるんです。「このカレー買ったんだけど、どうも素人っぽい子が売ってるから美味しいかどうかわからないの。どう思う?」って。「それは素人さんに見えてもプロですよ、スタジアムに出店しているんだから、それなりに修行した人ですよ」と応えたら「どうかなぁ」とか言っている。話しかけてきておいて、全然私の話信じてくれないんです(笑)。もうなんやのこれって。でもそうやって振り回されたりするのが心地いい。なんかいい目にあったような気分になる。それと同じように、『庭』の中に出てくるおばあさんやおじいさんの会話を読むのは、本当に面白い。普段の暮らしの中で、お年寄りを観察する機会があるんですか。
小山田 特に何かがあるわけではないです。ただ、子どもを連れて歩いていると、すれ違うお年寄りがにこやかに話しかけてくる。大体は軽い天気の話くらいなんですが、ときどき長い距離を並んで一緒に歩きながら、半生を聞いてしまうようなこともあります。相手の目的地が同じ方向で、ずっと一緒に歩くことになったり。
津村 その時の話はどう思って聞いてはるんですか。
小山田 どうしようと思いながらも、私でよければいくらでも聞きますという気持ちにもなります。あとありがたいなとか、私は仲間に見えるんかなとか。
津村 高齢者の方って、不意に喋りはる。それに予想もつかないこと喋り始めますよね。
小山田 そうですね。間合いを一気につめてくるから、初対面なのに気づいたらすごく個人的なことをがっつり聞いてるということもあります。
津村 そして、高齢者が突然喋り始める時は、基本ハズレがなくて面白い話ばかりだと思うんです。その話を聞いているのが小説家やって知ったら、どんな反応されるんやろう。小説家であることは隠しておきたいですね。
小山田 そうですね。あんまり喋らなくなってしまうのか、逆に喋ってくるのか、どっちでしょう。
津村 たぶん、小説家だとわかったら用意したことを喋ってくるんやと思います。でもそうじゃない、不意に喋りたくなった話の方が当たりが多い気がします。
-
小山田 浩子/著
2016/7/28
子どもの嘘
津村 「予報」の中で、会社のパートさんが職場での顔と家庭での顔がどうも違うということがわかるところや、最後の「家グモ」で娘がやたらと巧妙な嘘をつくところなどは、読んでいてスリルがありますね。土着の世界のある種の素朴さと、日常にある齟齬が、小説の中で渾然となっている。日常の中では小さすぎて流れていきそうな物事ですが、こうして小説にしてもらったら、これは確かに知っているという感覚があります。これは小山田さん自身が実際に見聞きしたものなんですか。
小山田 「予報」は私自身の体験ではなく知り合いから聞いた話がきっかけです。その人はショッピングモールのフードコートでパートをしているんですが、時々信じられないようなマナーの悪いお客さんがいて、しかもそれが親子連れなんだ、って話を聞いたときに、ちょっと絶望を感じたんです。そこからこの小説を書き始めました。書くときには、たとえば「実はお母さんも虐待をうけて、心に傷を持っていて……」という風に展開させたり、もしくは偶然に支配させることもできるかもしれない。でもそうではない書き方で書きたいと思いました。
津村 わかります。もっともらしく書かないからこそ、よりリアルに感じるんですよね。花見の季節にはあちこちでマナーの悪い人を見かけて、とてももやもやした気持ちになるんですが、小山田さんの小説を読むと、その人たちのことを説明してもらったような感じがする。もやもやさせる人たちが、一体どんな別の側面をもって生きているのかということを、説明してもらえたような気になります。だから読むと少し気が晴れるんですよね。
小山田 それは嬉しいです。「家グモ」の方は、4歳の娘がいるお母さんが語り手です。私の子どもも4歳なんですが、本当に毎日嘘をつくんです。それで心配になって育児書を読んだら、子どもの嘘には2種類あると書いてある。1つ目は、空想が本当と混じっちゃってる嘘。行ってもないのに「ディズニーランドに行ったんだよ」と言っちゃうような嘘です。
津村 めっちゃ言ってました、私(笑) 。
小山田 そういう嘘は4歳ぐらいであれば問題ないそうです。2つ目の嘘は、怒られたくないからつく言い訳の嘘。これは親が叱りすぎているのが原因だから、普段の接し方をもう一度改めましょうと。親の方が悪いみたいな感じで説明されている。でもそれも、まあ理解できるんです。でも娘は、全く何の役に立つのかわからない嘘をつくんです。空想でもないだろうし、言い訳でもない嘘を。
津村 どんな嘘を言っていたか聞いていいですか?
小山田 たとえば保育園で給食の時に、「他の子にはマヨネーズがなかったのに、私のお皿にだけ先生がマヨネーズをくれたんだ」と言ったり。でも子どものお皿を見て「よし、じゃあ君にはマヨネーズをあげよう」なんてするわけないじゃないですか、先生はそんな暇じゃないし。そういう嘘をずーっと言われ続けていると、オオカミ少年みたいになってきて、何も信じられなくなったりもして。「今日はボール遊びしたよ」すら疑ってみたり(笑)。今は、意図のわからない嘘には、怒らずに、否定も肯定もしないみたいな態度でいる。そうすると、どうもちょいちょいバレてるなっていうのがわかってきたみたいなんですけど、まだまだそういう攻防を繰り返しています。だから「家グモ」を書いていた時に悩んでいたこともあって、私にしてはそのくだりが暗いんです。
津村 子どもの頃って、喋ってるうちに自分の中で本当のことになったりするじゃないですか。あれ、小説書くようになったらいい性質やなあと思う時があります。
小山田 もしかしたら皆そういう自分のおはなし創作能力を試しているのかもしれませんね。
津村 そうかもしれない。小説を書くことって、空想でも言い訳でもない嘘を、ずーっとつき続けていくことじゃないですか。それに近いことを娘さんがやり始めたのかも。小山田さんは娘さんに自分の職業は小説家だよって言うんですか。
小山田 お話を作る仕事をしてるみたいなことは聞かれたら言いますね。そう考えると、遺伝かもしれない。私も子どもの頃にそういうことをしていたような気もするので。
津村 小説家に向かってどこまでやったらバレるのかを試しているなんて、贅沢な娘さんですね。子どもが子役みたいにつまらない喋り方をする、という場面も好きです。実際にそういうことはあるんですか?
小山田 あるんです。考えてみたら当たり前で、子どもは親と保育園の先生の他に、テレビで見る人ぐらいしか知らなくて、その中で真似しやすいのは子役なのかな、と思うんです。私は最初子どもに対して幻想があって、ものすごく独創的なことを言うんだろうと思ってたんです。でも実際は、本当に子役みたいに両手を挙げてわーいわーいって言いながら部屋走り回ったりするんですよ。そんなんじゃないだろ、君の喜びの表現は!と思ったんですけど(笑)。実際には子どもの表現はそんなところから始まるんですね。
津村 最初は誰もが模倣から入りますもんね。だから、ほとんど違いが出ない。人間の個性ってそこを凌駕して獲得してくるもんなんやな、乗り越えてきた結果なんやなと思うと、なんだか尊いもののように感じます。
小山田 本当にそうですね。子どもの話はきっと、これからの作品にも出てくると思います。
津村 今日はいろいろなお話を伺えて本当に面白かったです。小山田さんの小説って、近くに来て「こんなことがあってね」って話しかけてくるようなものではなくて、遠くにいる人が500%の倍率で見ているような感じがある。そして、その遠い人たちは、共感を求めるような身振りをしていないんですよね。起こっていることに関して読者に意見を求めずに、ただ起こっていることを見て淡々と受け止めている。その状況がすごく面白い、小山田さんの小説でしか読めないものだと思います。
小山田 本当にありがとうございます。お話しできてとても楽しかったです。皆様もありがとうございました。
2018年4月6日、大阪・心斎橋アセンスにて
企画・構成:磯上竜也(心斎橋アセンス)
-

-
小山田浩子
1983年広島県生まれ。2010年「工場」で新潮新人賞を受賞してデビュー。2013年、同作を収録した単行本『工場』が三島由紀夫賞候補となる。同書で織田作之助賞受賞。2014年「穴」で第150回芥川龍之介賞受賞。他の著書に『庭』『小島』『パイプの中のかえる』など。
-

-
津村記久子
1978(昭和53)年大阪市生まれ。2005(平成17)年「マンイーター」(のちに『君は永遠にそいつらより若い』に改題)で太宰治賞を受賞してデビュー。2008年『ミュージック・ブレス・ユー!!』で野間文芸新人賞、2009年「ポトスライムの舟」で芥川賞、2011年『ワーカーズ・ダイジェスト』で織田作之助賞、2013年「給水塔と亀」で川端康成文学賞、2016年『この世にたやすい仕事はない』で芸術選奨新人賞、2017年『浮遊霊ブラジル』で紫式部文学賞を受賞。他の作品に『アレグリアとは仕事はできない』『カソウスキの行方』『八番筋カウンシル』『まともな家の子供はいない』『エヴリシング・フロウズ』『ディス・イズ・ザ・デイ』『やりなおし世界文学』など。
この記事をシェアする
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 小山田浩子
-
1983年広島県生まれ。2010年「工場」で新潮新人賞を受賞してデビュー。2013年、同作を収録した単行本『工場』が三島由紀夫賞候補となる。同書で織田作之助賞受賞。2014年「穴」で第150回芥川龍之介賞受賞。他の著書に『庭』『小島』『パイプの中のかえる』など。
連載一覧
対談・インタビュー一覧
-

- 津村記久子
-
1978(昭和53)年大阪市生まれ。2005(平成17)年「マンイーター」(のちに『君は永遠にそいつらより若い』に改題)で太宰治賞を受賞してデビュー。2008年『ミュージック・ブレス・ユー!!』で野間文芸新人賞、2009年「ポトスライムの舟」で芥川賞、2011年『ワーカーズ・ダイジェスト』で織田作之助賞、2013年「給水塔と亀」で川端康成文学賞、2016年『この世にたやすい仕事はない』で芸術選奨新人賞、2017年『浮遊霊ブラジル』で紫式部文学賞を受賞。他の作品に『アレグリアとは仕事はできない』『カソウスキの行方』『八番筋カウンシル』『まともな家の子供はいない』『エヴリシング・フロウズ』『ディス・イズ・ザ・デイ』『やりなおし世界文学』など。
連載一覧
対談・インタビュー一覧
著者の本

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら