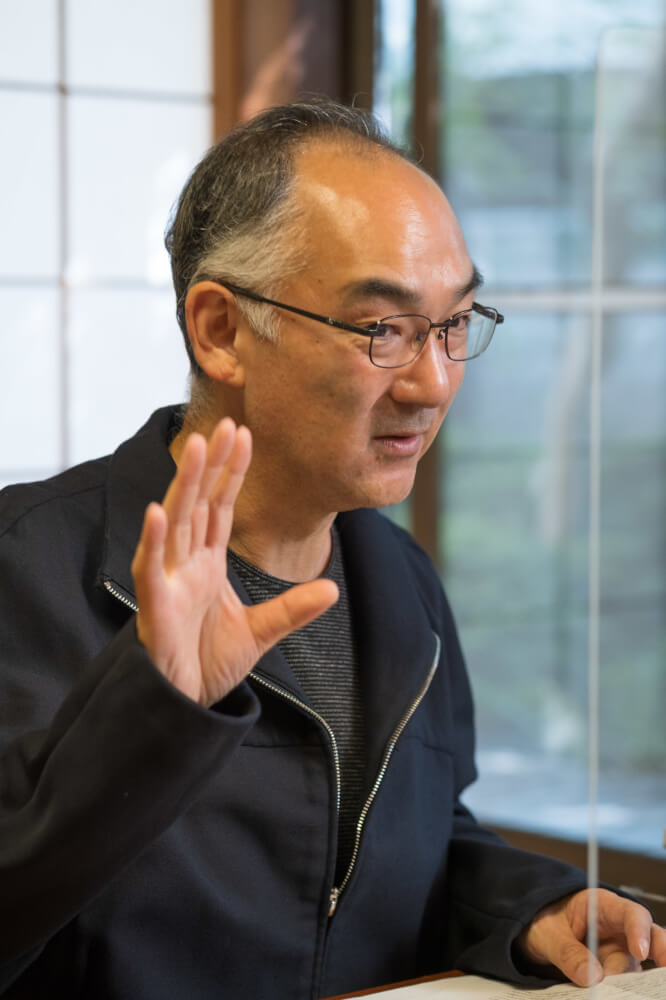2021年12月3日
後篇 国家に対する違和感を持ち続けて
『「海の民」の日本神話 古代ヤポネシア表通りをゆく』刊行記念対談
出雲と筑紫、そして若狭、能登、糸魚川から諏訪まで続く「海の道」—―古代日本、「表通り」は日本海側だったことを、『古事記』等の文献はもちろん、考古学や人類学も含めた最新研究から丹念に追った『「海の民」の日本神話 古代ヤポネシア表通りをゆく』(新潮選書)。著者の三浦佑之氏(千葉大学名誉教授)と安藤礼二氏(多摩美術大学教授)による、古今東西を自由に駆け巡る、刊行記念対談をお届けします。
(2021年10月18日、於・新潮社クラブ)
(前回の記事へ)
邪馬台国はどこにあったのか
三浦 安藤さんは邪馬台国についてはどうお考えですか? ヤマトか、ヤマタイかという問題、九州説と畿内説、そして邪馬台国へ至るルートの問題といろいろありますが。
安藤 ルート的には、どう考えても瀬戸内ではないですよね……。
三浦 この本でも書いたように、私は日本海側ルート、かつ邪馬台=ヤマトであるとして畿内説をとっています。「魏志倭人伝」にある投馬国は出雲のことではないかとも思っています。今では下火になっていますが、日本海ルート説自体は、割合古くからあるんですよね。日本海側の出雲、そして若狭から内陸へ南下すると、ヤマトの地まではすぐともいえます。そして日本海は、冬に荒れることはありますが、それ以外の季節であれば、太平洋側のような外海とは違って、基本的には穏やかで航海しやすい海であることを指摘する海洋学者もいます。出雲はじめ、各地に半島やラグーン(潟)があったことも述べた通りです。航海しやすいルートだったと思われるのです。
安藤 確かに、日本海側のルートが一番、説得力がある気がします。
三浦 それがなぜ下火になってしまったのか……不思議なんです。
安藤 箸墓古墳(奈良県桜井市)はおそらく卑弥呼の墓だろうと言われていますよね。
三浦 発掘されないと何とも言えませんが、現状では私もそう思います。何より「邪馬台国」は「ヤマタイ国」ではなく、「ヤマト国」と読むのが自然ではないかと。
安藤 纏向遺跡(奈良県桜井市)の発掘も進んでいます。
三浦 九州の人はなぜ、あれほど邪馬台国=九州説に固執するのでしょう。もちろんヤマトという地名は一般的な意味合いもありますから、九州にも「ヤマト」と呼ばれる地はあるだろうとは思いますが。
安藤 古代九州は完全に海民国家ですよね。太平洋側だけではなく、沖縄や大陸、朝鮮半島など、すべての方向に開かれていますから。ヤマトの中央集権的国家を簡単に容認するとは考えづらいですよね。九州の人が邪馬台国=九州だと思いたがるのは、やっぱり皆さん、「国家」が好きなのかなあ。
三浦 吉野ケ里遺跡が出てきたのも大きいでしょうね。でも、国家がなきゃいけないみたいに考えるのは不思議です。
安藤 国家など存在せず、九州はそれ自体でもっと開けた世界だったと考える方が、私などはより納得できるのですが。縄文時代を4万年前の旧石器から考えるとすると、国家という制度なんて最近も最近、人類史においてはほんのひととき前にできたものなんだということを、もっと認識してみるべきですよね。そうすると今までとはまったく異なった風景が見えてくるはずです。
インドネシアの村と壱岐の古墳をつなぐ鯨漁
安藤 私が師事した渡辺仁(1919~1998、古学者)先生は、北方民族を中心に民族考古学を展開なさっておりました。北方民族の中でも、遊牧民は清や金のように国家を築いたり、天孫降臨のような垂直神話を持っていたりもしますが、その多くは、基本的には南方とよく似た生活形態を持っています。すなわち、狩猟採集、半猟(漁)半農的な生活で、特に鮭が重要な食べ物なんです。なぜなら勝手に故郷の川に戻って来てくれるからです。全然能動的に働く必要がないんですよね(笑)。
三浦 アイヌも、鮭がなければ生活がまったく違ったのではないかと思います。寒い冬場、鮭で暮らせるわけですから。あとは植物からでんぷん質をとっておけばいいわけで。
安藤 そういえば、アメリカ北西沿岸部の先住民も巨大な家を造っていたようです。冬季の家、ウィンターハウスというのですが、渡辺先生は、縄文の巨大建築の原型ではないかとおっしゃっていました。
三浦 そこで何をすると思われますか?
安藤 わかりません(笑)。ただ、北方でも冬になると、そうした特別な家で、祖先を祀る儀式を、巨大な仮面などを身にまとって行っていました。夏は家族単位で狩猟採集に励み、しかし冬になると家族という枠を越えて一族でそこに集まって祝祭を行っている。それとパラレルなのではないかと。マルセル・モース(1872~1950、の社会人類学者)が言うポトラッチ(アメリカ先住民の祭りで「贈り物」の意。裕福な者が客を集めて大盤振る舞いする)のような、贈与を伴う祝祭が行われていたのではないかと推測されるとおっしゃっていました。
三浦 縄文時代は、いくら今より暖かったとはいえ、やはり冬にはそれほど狩猟に励むことはなかったでしょうね。
安藤 ええ。ただ、冬にも大きい動物、クマやシカなどはいたので、皆無ではなかったでしょうが。
三浦 三内丸山遺跡の発掘では、陸地の生き物よりも、津軽湾の海の生き物の方が圧倒的によくとられていたこともわかっています。
安藤 シャチやアザラシなどもいたし、回遊する魚類たち、鯨もイルカもいましたからね。
三浦 本書でも触れましたが『鯨人』(石川梵著、集英社新書)という本で、インドネシアのラマレラ村という、木造船と銛でクジラ漁を行っている村の事を知り、大変に興味を持っています。
安藤 かつては壱岐、そして出雲や熊野、和歌山の太地町、高知の室戸などでもクジラ漁が盛んでしたものね。
三浦 我々が忘れている海の道がずっとあったらしい、そう考えると、熊野と出雲は遠いように見えて案外と近いんです。そしてそれはひょっとしたら、もっと広い範囲でも言えることなのではないか。本書でも紹介しましたが、壱岐の鬼屋窪古墳には、このラマレラ村の鯨漁の様子とそっくりな、当時の鯨漁の姿が描かれています。というより、私はラマレラ村の漁の様子が、6世紀末~7世紀といわれる古墳の線描画とまったく同じだと感動しました。オホーツクにも同じような鯨漁の絵がありますよね。
安藤 あります。北と南では気候は違うものの、海という共通の生活の場からみると、互いの文化はかなり似ていたのでしょう。
土器造りは女性の役割だった?
三浦 三内丸山遺跡において、墓に入れた人と、入れなかった人は、完全に分かれていました。
安藤 墓に入れた人が、火焔型土器のように装飾性に富んだ複雑な土器、宝器としての土器を造っていたのでしょうね。生活に追われていたら、あんなものは造れないですから。
三浦 そうでしょうね。そうして、特殊な技能を持っている人というのは必ずいます。土器にしても、誰もが造ることが出来たわけではないでしょう。あんな複雑な造形ですから。狩猟採集や漁労においてもそうです。鯨に銛を打つのでも、絶対にうまい人と下手な人がいる。そうした差があるのは当然のことだったでしょうね。
安藤 世界の民族事例をみていくと、土器造りは大抵の場合、女性の仕事ですよね。縄文中期の土器や土偶のフォルムが女性を思わせるのは、女性の仕事だったこともあるのではないかと私は思っています。
三浦 昔のテレビのドキュメンタリーなどでアフリカの狩猟民の生活などを見ていても、キリンなんかの大物は追いかけるけれども、日常では男性は、ほぼ何もしていないですよね。毎日の食料を集めるのは、ほぼ女性で。
安藤 アイヌの人たちも、男性は森のクマや海のカジキなどの大物を狙うけれど、それは命がけではありますがレクリエーション的なところがあり、日常の食事のためではありませんよね。
三浦 ほぼ、とれない(笑)。鯨だってそうですよね。ラマレラ村の鯨漁なども、今は鯨が減ったから年に数頭しか獲れないのかといえば、昔も同じくらいなんです。遠洋にまで行くわけじゃなく、あくまでも近海で、迷い鯨を狙っていたから。アイヌでは「寄り鯨」という言い方をしましたね。神が寄せてくれる鯨だと。
安藤 アイヌでも、栽培したり、採集したり、家具や日用品を作ったりするのは、ほぼ女性の仕事ですよね。ですから縄文時代、土器造りや造形的な仕事を女性が担っていたと考えることも充分に可能で、そうするとサイケデリックなファッションなども含めて縄文を見る目はかなり変わってきます。なかなかモノが残りにくいし、実証しにくいのですが。
三浦 一方で、安藤さんは考古学の方ですから「考古学はモノですよ」といった仰り方もなさってますよね。物証が大事であると。
安藤 はい。しかし、日本の場合は、開発によって遺跡が出てきても、記録するだけで精一杯で、研究までは追いついていないのが実情です。調査というよりは、開発がまずあって。
三浦 期限をきられたりしますね。
安藤 記録は残っても、遺跡自体は破壊されたりもしています。そこへ旧石器捏造事件のようなことが起こると、誰も検証し直すこともできずにすべてがいきなり0になってしまいます。今、ようやく大きな遺跡は保存されるようにはなってきましたが、まだまだ大変でしょうね。あと「モノ」だけですと正直、ほんとうになにも判断できないんですよ。かろうじて民族事例からも類推できるのですが、本当にそれで使い方があっているのかといえば、実際には判らない。
三浦 だから安藤さんは、考古学でわかるのはごく一部で、あとはフィクションだとおっしゃる。そういう点で、たとえば縄文の火焔型土器はどのように使われていたのでしょう。
安藤 あんな複雑な装飾をもったものは煮炊きには使えないですよね。装飾性に富んだ土器はあちこちから出土するけれども、おそらくは産地によるものと思われる特徴がハッキリしている。造られた場所によって、装飾が決まっていたのでしょう。ヒスイと同じく「贈与」に使われたのではないかと当然推定できます。それも女性が造っていたのであれば、ある種の嫁入り道具的なものだったのかもしれません。コミュニティとコミュニティの結びつきを表していた、あるいは女性が持つ技術を婚姻によってやりとりしていくというネットワークがあった。それも実証は出来ないのですが。
三浦 婚姻自体が、嫁入り婚なのか入り婿なのかという問題もありますしね。
安藤 ヒスイ、黒曜石、そして火焔型だけではなく様々な特色を持った土器も、各地へ移動していったことが判っています。
三浦 しかもヒスイなどの石類は、加工して持って行く場合と、原石を持って行く場合がありますよね。
安藤 黒曜石は原石を運んでいて、各地にそれを加工する場所もあったようです。三浦さんがこの御本でご指摘されているように、旧石器時代から縄文時代にかけては黒曜石が中心で、縄文時代から古墳時代にかけてはヒスイが中心だったというのも面白いですよね。
栗を栽培していた縄文人
三浦 埴原和郎(1927~2004、自然人類学者)さんの、日本人の「二重構造説」(東南アジア起源の縄文人に、北東アジアの渡来系集団である弥生人が混血したという日本人の起源説)の受け売りでいえば、やっぱり日本列島には旧石器から連なる同じ人たちが広くいたんだろうなと思います。
安藤 それは間違いのないところだと思います。旧石器でいえば、那覇の山下洞で見つかった一番古い人骨で3万5千年前までさかのぼると言います。石垣島で新たに発見されたものでも2万7千年前までさかのぼります。いきなり石垣島や那覇にヒトが生まれたわけではなく、おそらく台湾から渡って来ているでしょうし。3万年前には北海道にもマンモスハンターたちがいたわけです。
三浦 天皇家の祖先でもある弥生系の人たちが、朝鮮半島経由で稲作を携えて入って来る、その前から、稲作そのものは入っていたとみられていますし、縄文的世界で生活をしている人々がいるところへ、北方の大陸系の人が入って来る前に、海から来た人々、海の生活を得意としていた人々がかなり入って来ていたのではないかと考える方が自然ですね。
安藤 縄文も狩猟採集といいながら、栽培も行っていますし、定住生活もしているんですよね。
三浦 三内丸山遺跡ではかなり大規模な栗の栽培跡が見つかっていますね。
安藤 農耕が入ってきて定住化しても、それが国家化するか、あるいは遊動性を保っていくかが重要で、遊動性を保ったままネットワークでつながっていたのが、今回書かれたような出雲に代表される、日本海の文化になっていく。日本海という呼び名が相応しいのかは、本書でもご指摘なさっている通りで、「青海」という言い方が本当はいいのかもしれません。ヒスイの道でもあったわけですから。海もそこで磨き上げられたヒスイも青く輝いているわけですから。
三浦 青海という言い方は共通性を含みますからね。
川を遡る「海の民」
安藤 日本海側の糸魚川から諏訪までは川沿いでまっすぐいけますが、熊野も海から川沿いでいけますよね。北海道のアイヌの人々も、やはり川沿いに住んでいます。
三浦 長野県の安曇野市の「安曇」は、九州北部、筑紫にいた海民の安曇氏がそこへ行ったからその名が残ったという伝えは広く知られています。実際に、安曇野市の穂高神社には船型の山車をぶつけあう「御船祭り」が行われていますし、諏訪大社の祭神タケミナカタのミナカタは、同じく筑紫にいた海民の宗像氏の「ムナカタ」に通じるのではないかとも言われていますね。どうも海の民は、川を見つけると必ず遡る。川筋にしか生活圏を作れないですからね。
安藤 本書でも描かれたように、出雲のオホナムヂが、高志のヌナガワヒメと婚姻を結んで、子が産まれる。それがタケミナカタであるという、まさに三浦さんの仰っていることを裏付けるような神話が遺されているのもすごいなと思いました。
三浦 高志のヌナガワヒメ、糸魚川のヒスイの女神が、諏訪と出雲をつないでいる。ところが諏訪の人たちも、自分たちの文化をヤマトと結び付けがちなんです。でも日本海文化に結び付けた方が、理にかなっているし、第一そっちの方が面白いですよ。
安藤 それが「先代旧事本紀」などに残っているというのがまた、素晴らしいですね。タケミナカタはヌナガワヒメとオホナムヂの子なのだと。
三浦 古事記はそれを取りこぼしていますが。またカムムスヒの娘がキサカヒヒメというのも、出雲国風土記にふっと出てきます。
安藤 そうした隠されているものが出てくる瞬間を捉える、そうした読み方が実にスリリングで面白かったです。特にカムムスヒとタカミムスヒ、古事記で最初に現れるこの二神を、本居宣長は一つの神であるとしましたが、三浦さんはハッキリと切り分けられましたね。カムムスヒとタカミムスヒは別の神であると。私も深く納得いたしました。
三浦 そう認めて頂けるのは嬉しい限りです。ムス=「生す」ですから本来は生成的な神であるのにもかかわらず、タカミムスヒは何も作らないでしょう。単に命令して壊すだけ。古事記では高御産巣日神、または高木神、とあるように、彼は、もともとは高い木に神を寄りつかせるシャーマンだから高木の神と呼ばれたのでしょうね。
安藤 古事記を簒奪した人が、ムスヒの二神も奪ってしまった。
三浦 そしてセットにしてしまった。
安藤 もう一つ、アイヌの神話とダイレクトに繋げるのはやや危険がありますが、カムムスヒの娘たちは貝の女神たちなんですよね。カムイ・ユーカラにも貝は出てきます。本当によく似ていますよね。
三浦 「稲羽のシロウサギ」の話も、あれは古事記では三人称で語られていますが、ウサギを「我」と一人称の語りにしちゃうと、完全にカムイ・ユーカラになります。他にも共通の要素は多々あり、たとえば英雄神の物語がカムイ・ユーカラにはありますが、あれもオホナムヂとよく似ています。戦う時には大きくなったりしますでしょう。そうやって結び付けていくことは出来ますが……。
安藤 実証が難しいですよね。クロード・レヴィ=ストロース(1908~2009、文化人類学者)も「因幡のシロウサギ」を取り上げています。レヴィ=ストロースは北米、南米の神話を含め、環太平洋にまたがる巨大な神話の環(サークル)を考えていました。日本が好きだったのも何となくわかる気がします。環太平洋に分布する祭祀の際に身につける仮面もどこか似ていますよね。
三浦 ヒスイはインカ帝国でも珍重されましたね。やがて忘れられたところも同じです。
安藤 忘れ去られるというのは、そこに一つの歴史の転換があったからでしょうね。
三浦 おそらく。
安藤 日本では縄文的なものとしてヒスイが古墳時代までは残ったものの、それ以降完全に忘れ去られて、日本原産だったことも判らなくなってしまっていた。
三浦 1939年に、糸魚川市にある小滝川上流にヒスイの原石産地があるという論文が発表されましたが、本格的に発掘調査がなされたのは1950年代以降のことでした。それまでは、ヌナガワヒメがヒスイの女神だという形跡が、越後国風土記とか、万葉集などに少し残っていても、正しく読めなくなっていたわけです。
安藤 さまざまなものを忘却させる装置を、日本書紀などの神話が作り上げていったのかもしれませんね。テキストというものには、裂け目を塗り固めていく作業が施されている場合も多々ある。それをどう壊していくのか。それこそが一番面白い読み方だし、ある意味文学的読み方の本当の姿なのかもしれません。どうすればそういう読み方が出来るのかといえば、たとえば地名が記されている場合には、実際にそこに行ってみることですよね。行かないと判らない事が沢山ありますから。
三浦 行く事で見えてくることは、ありますね。
安藤 糸魚川に立ちますと、能登も佐渡も見えますよね。そこから気多大社にも行けます。ああ、こんなに近いのかと実感できます。能登は陸路で行くと絶海の孤島みたいな感じですが、海から行くとそうではない。
三浦 先日も出雲へ行っていたんですが、出雲の北海岸は20~30年前までは道が不便で、隣の集落に行くのにも、一旦は南へ大回りして行かねばならなかったそうです。ですから基本的にはずっと船で移動していたんでしょうね。それが基本の移動手段だった。
放浪の民だった玉の加工集団
三浦 僕は若狭の役割がすごく面白いなと思っているんです。越前でもないし、丹後、丹波でもない、狭間のようなところなんですが。僕は、律令国家の成立が、日本海の西側と東側とを分断するための楔として若狭国を置いたのではないかと勘ぐっています。
安藤 東大寺のお水取りに使われる水も、若狭から送られますよね。
三浦 福井県小浜市の神宮寺の井戸から「お香水」が汲まれ、遠敷川に注がれ、それが地下を通って、東大寺の若狭井に通じているとされます。そういう物語を作るというのは、若狭には何かがある。東大寺という国家を代表するような寺の重要な儀式ですから、権力側が若狭を繋いでおかなければならなかった理由があるのでしょう。
安藤 奈良の、当時のヤマト朝廷の一番の寺院ですから。それに奈良や京都から向かうと、思った以上に若狭って近いですよね。
三浦 琵琶湖経由で川沿いを行くと、かなりの部分、船でも行けましたし。距離的にも近いです。
安藤 それから本書で紹介されている、丹後国風土記にある、浦島太郎の話も大変興味深かったです。丹後といえば天橋立の近くに、眞名井神社という神社がありますでしょう。伊勢神宮の元宮とされる籠神社の奥宮で、井戸水が湧き出ており、境内からは縄文時代の石斧や、弥生時代の勾玉なども出土しています。天照大神はここから伊勢へ行ったといわれる。
三浦 元伊勢とも呼ばれていますね。伊勢系の神話が、いつできたのかといえば、たとえば垂仁天皇の皇女である倭姫が、大和から伊勢まで行くのに丹後などの各地を巡ったという話などは、おそらくかなり新しくて、中世あたりだろうと思われます。なんでそれが丹後あたりの地域を中心とするのかといえば、やはり土地の持つ力でしょうね。
安藤 能登と同じく、半島があって、湾があって、非常によく似た地形ですよね。
三浦 海と繋がっているという要素が大きいでしょうね。もちろん近いので、ヤマトの要素は7世紀頃から大きく入り込んでいて、前方後円墳なども造られていますが、それ以前には、中国や新羅の遺物もかなり入り込んでいます。
安藤 ただ、陸の道が出来てしまうと、海の道は廃れてしまう。
三浦 陸の道が整備されなければ、富の蓄積は出来なかったと思いますね。そして、海の道と陸の道が入れ替わるのは、やはり律令制度の施行以降です。
安藤 海の道が消えると、ヒスイも消えて、完全に忘れられてしまう。
三浦 あれは不思議ですね。
安藤 ヒスイって磨かないと、ただの石に見えますよね。だから当時も海に寄せていたのを見つけていたと聞きました。
三浦 今でもヒスイ海岸に打ち上げられている石を拾う人がいますね。でもあれは素人だとまったくわからないです。
安藤 そうですよね。玉作の遺跡も、糸魚川市だけでなく各地で発掘されていますが、そうした関係性もとても面白いですね。
三浦 出雲にもあります。ただ、それはもうヒスイではなく、メノウなんです。
玉作でいうと、古事記でも「地得ぬ玉作」という諺の由来が語られますが、玉作の人々には所領がない、放浪する人たちだったのかもしれません。出雲から大和へも移っていきますし。しかし、ヒスイの硬度はかなりのもので、現在の技術をもってしても、簡単に加工できるようなものではありません。
安藤 勾玉の穴をどうやってあけたのか、今でもよく判らないようですね。
三浦 あれは男の仕事だったのか、女の仕事だったのか、どう思われます? 力任せなのか、あるいは根気よく磨くのか……冬、外に出られない時の仕事だったのでしょうか。
安藤 ヒスイって、それこそ1日かけて磨いても、それほど変わらないんですよね。根気なのかなあ……それこそ、ヒスイを磨くのは特別職として衣食住の面倒を誰かが見てくれていた、そうしたことが許される社会だったということでしょうね。
三浦 ずっと磨いてたら、食べ物をとりにいくことなど出来ませんからね。
アステカの武器と細石刃
安藤 長野の旧石器の遺跡から、細石刃という、カミソリの刃のような小さな黒曜石が見つかっています。それは木の槍の先端部分に幾つも付けて、刃がかけたり、なくなったりすると、新しい刃に交換しながら使った、最も効率的に動物を殺せる武器、狩猟道具だったんですね。これがシベリアにもあるんです。おそらく旧石器時代、新潟や能登経由で入って来て、糸魚川から諏訪へ入っていったのだろうとも思われるんです。そしてシベリアのシャマニズムにも来訪神を迎える祭祀とよく似た側面が存在します。上から降りて来る、圧迫する神ではなく、お迎えして帰って頂くという、きわめて水平的な感覚です。三浦さんが今回ご指摘されたように、古代の日本には、海沿いに、そこから上陸するための様々な入口とルートがあったのだろうと思います。
三浦 折口(信夫)などが指摘しているように、「神迎え」の世界が、現代に至るまでずっと繋がっているんですよね。
安藤 それをどういう言葉で表現していくのか。現在の学問はすべて実証、実証で、みんな薄々は分かっているのに、なかなかハッキリと言うことができない。
三浦 証拠があるのかと言われれば、実際に発掘される遺跡の研究結果や、DNA研究なども含めて、コツコツと積み重ねるしかないでしょうね(笑)。
直木賞を受賞した『テスカトリポカ』(佐藤究著、KADOKAWA)という作品を読んだのですが、アステカ神話をベースに、実によく調べてある面白い小説でした。そこに一番の武器、砥いだ黒曜石を先端部分にたくさんつけた神器が出てくるのですが、これが先ほどの細石刃にそっくりなんですよね。
安藤 南米の研究者が言うところでは、黒曜石でなければ効果的に獲物を殺せないそうです。刃物とかでは駄目で、なぜなら黒曜石にはそれに特有の呪術的な力が強くあるのだそうです。
三浦 ええ、小説としてのフィクションではなく、元々アステカには、そうした殺す儀式があったようですね。生贄を捧げる儀式が。
安藤 同じ直木賞受賞作である『熱源』(川越宗一著、文藝春秋)はアイヌを取り上げていますし、SFやミステリーも含めて、文学者たちがこうした世界に大きな関心を持ち続けているのは嬉しいですよね。
三浦 やはり国家に対する違和感を持っている人を惹きつけるのでしょう。
安藤 新型コロナの問題では、全世界が今、否応なしに一つに結び付けられていますし、経済帝国主義的な姿勢が新型コロナの問題をより複雑化させていることは間違ありません。こうした帝国主義的な国家のネットワークとはまったく異なった、もう一つ別のネットワークを求める切実さが、急速に高まってきてもいるのではないでしょうか。
三浦 執筆中は、新型コロナで家にこもっていましたから、特に都市集中型のもろさを感じましたね。これは何とかしないとダメだろうと。
安藤 そうですよね、北海道などでも札幌などの都市部では感染者数も多かったですけれど、それ以外は……。
三浦 密集しなければ、うつりようがないですよね。分散させていくことは、実はすごく大事だと思います。地方と中央だと、地方の不利な点ばかりが強調されますが、現在のリモートワーク的な働き方改革の方向も追い風となるように、解消の方法は何かしらあるはずです。
安藤 海民たちが行っていたような広い空間を移動していく生活、あるいは広い空間に分散していく生活を今だからこそもう1度考え直す必要がありますね。そうした生活は、おそらくホモサピエンスの原型的な生活でもあったはずです。資本主義的なネットワーク以外の様々なネットワークを人類は生きてきたということに、皆、気付きはじめましたよね。しかもそれは遠い過去の問題ではなく、現在進行中の問題でもある、と。会議なんて本当は実際に集まってやる必要なんてないんだ。あるいは、一つの中心にあらゆるものが集中するってこれほど脆いことだったんだ、等々。そのようにして我々の生活を再考していくとき、出雲や若狭、そして能登など、この御本でご指摘されたようなネットワークをあらためて生かす方向に、関心が集まるかもしれませんね。
三浦 ええ。新しい生活圏のようなものが、これから出来上がるのではないかと期待しています。
(了)
-
三浦佑之『「海の民」の日本神話 古代ヤポネシア表通りをゆく』
2021/9/24
公式HPはこちら。
-

-
三浦佑之
1946年三重県生まれ。千葉大学名誉教授。成城大学文芸学部卒業。同大学院博士課程単位取得退学。古代文学、伝承文学専攻。『村落伝承論――「遠野物語」から』(第5回上代文学会賞)、『浦島太郎の文学史――恋愛小説の発生』、『口語訳 古事記』(第1回角川財団学芸賞)、『古事記を読みなおす』(第1回古代歴史文化みやざき賞)、『風土記の世界』、『列島語り――出雲・遠野・風土記』(赤坂憲雄氏との対談集)、『出雲神話論』等著書多数。
-
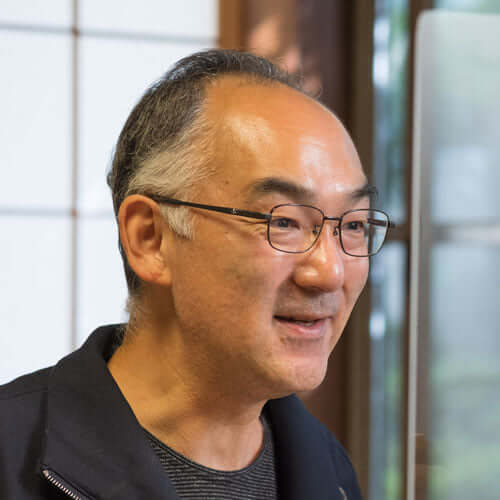
-
安藤礼二
1967年東京生まれ。文芸評論家、多摩美術大学美術学部教授。東京大学客員教授。出版社勤務を経て、2002年「神々の闘争―折口信夫論―」で群像新人文学賞評論部門優秀作受賞。2009年、『光の曼陀羅 日本文学論』(講談社)で大江健三郎賞と伊藤整文学賞を受賞。2015年、『折口信夫』(講談社)でサントリー学芸賞と角川財団学芸賞を受賞。著書に『場所と産霊 近代日本思想史』、『大拙』、『熊楠 生命と霊性』など。
この記事をシェアする
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 三浦佑之
-
1946年三重県生まれ。千葉大学名誉教授。成城大学文芸学部卒業。同大学院博士課程単位取得退学。古代文学、伝承文学専攻。『村落伝承論――「遠野物語」から』(第5回上代文学会賞)、『浦島太郎の文学史――恋愛小説の発生』、『口語訳 古事記』(第1回角川財団学芸賞)、『古事記を読みなおす』(第1回古代歴史文化みやざき賞)、『風土記の世界』、『列島語り――出雲・遠野・風土記』(赤坂憲雄氏との対談集)、『出雲神話論』等著書多数。
-
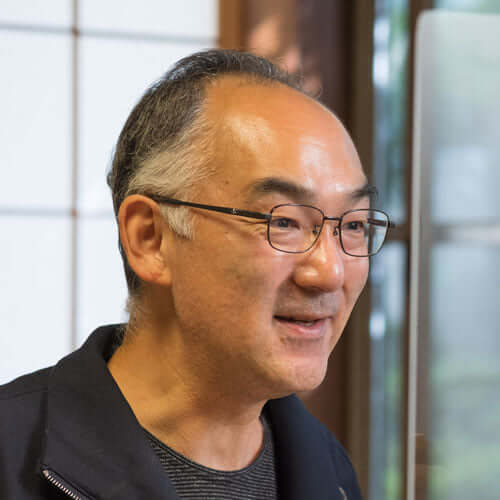
- 安藤礼二
-
1967年東京生まれ。文芸評論家、多摩美術大学美術学部教授。東京大学客員教授。出版社勤務を経て、2002年「神々の闘争―折口信夫論―」で群像新人文学賞評論部門優秀作受賞。2009年、『光の曼陀羅 日本文学論』(講談社)で大江健三郎賞と伊藤整文学賞を受賞。2015年、『折口信夫』(講談社)でサントリー学芸賞と角川財団学芸賞を受賞。著書に『場所と産霊 近代日本思想史』、『大拙』、『熊楠 生命と霊性』など。

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら