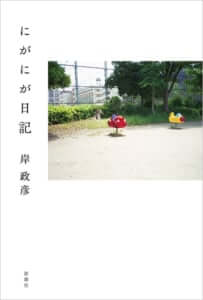お知らせ(2023.10.19)
岸政彦さんの連載「にがにが日記」が10月末に新潮社から単行本として刊行されます。最愛の猫とのかけがえのない日々を綴った書き下ろし「おはぎ日記」を加えて一冊に。どうぞお買い求めください。
登場する家族(所属は連載当時)
きし(私、俺) 岸政彦。社会学者。立命館大学先端研教授。打たれ弱い。
おさい 連れあいの齋藤直子。大阪市立大学人権問題研究センター特任准教授。主著に『結婚差別の社会学』(勁草書房)。よく寝る。
おはぎ 猫。17歳。もじゃもじゃで穏やかで優しくて人懐こくてよく喋る。さいきん夜泣きをする。
きなこ 猫。デブでセクシーで美人で、神経質で怒りっぽくて甘えんぼう。2017年11月に17歳で亡くなる。おはぎときなこを合わせて「おはきな」という言い方をする。
1月15日(月)
昼から会議、そのあとゼミ、終わって夕方から研究室の本の整理。立ったりしゃがんだりするので、わざわざそのためにジャージのズボンを持っていった。前任校からここに着任するときにすでに本は3分の1ぐらいに減らしてあるが、さらにそこから半分ぐらいにするつもりだが、ここまで絞り込んでくるとさすがに勢いで捨てられない。これは捨てる本か、保管しておくべきか、1冊ずつ悩んでしまう本ばかり残っているから、時間がかかる。それにしても俺はほんとうに本を読んでない。記憶力がほとんどなくて何も覚えてないから、読んでないように思うだけなのだろうか。
ウェーバーやマートンなどの古典、沖縄の本、生活史やエスノグラフィなどの質的調査の本、さっぱり理解できないけど趣味で読んでいるプラグマティズムと分析哲学の本、大きくわけてこの4つのカテゴリー以外は全部捨てようと思っているのだが、たとえばエスニシティやナショナリズムの本をどうするかで小1時間悩む。本を捨てる、ということは、これまでの自分の人生を整理して、残り少ないこれからの人生をどうするかを決める、ということと同じだ。私はたぶんこの先、沖縄と生活史以外の本は読めないし、書けない。同じ社会学という領域の本でも、その大半は読めないまま年を取っていく。だからそのかわり、ひとりでも多くの方に聞き取りをしようと思う。せめてそれぐらいしかできない。
掃除は半分ぐらいでやめて、熊田陽子『性風俗世界を生きる 「おんなのこ」のエスノグラフィ』(セックスワーカーの参与観察、沖縄の女の子の事例が面白かった)とアメリカのエスニシティ論の本をぱらぱらと読む。自分の頭が悪くてイライラしながら読む。
晩飯は中華料理屋で、おなかいっぱいになりたくないので、わざとミニ炒飯。そのため帰りに猛烈に腹が減ってしまい、西院駅のモスでモスチーズいっこ食べてしまう。帰りの電車で柴崎友香の『千の扉』を読了。感動してしばらくぼうっとしていた。俺なんかが小説書く意味はやっぱりないなあ、と思いながら帰る。大阪も京都も穏やかに寒かった、寒かったが穏やかだった。
帰ったらおはぎは居間のテーブルの上のカゴのなかにいた。さわるとわーわー言う。よく喋る猫だ。日課になっている「物件ファン」を見て、京都の古い小さな町屋が6500万という法外な値段で売られているのを見て、大阪で家を建てて正解だったと思い、今日も安心する。ほかの物件も見ていて、湘南というところに稲村ヶ崎という駅があって、その駅前の小さなコーヒースタンドが月8万で貸し出されていて、ちょっといいなあと思った。湘南というところは行ったことがない、どころか、どこにあるのかもわからない。物件のGoogleマップを見ていたら、江ノ島が近くにあるらしい。江ノ島は名前だけはなんとなく知っている。どういうところで、どういうひとたちが暮らしているのだろう。海がきれいなところなのだろうか。たぶん行くことは一生ないと思う。
そもそも、そういうところでコーヒースタンドなんかやっても、私みたいな声も態度も体もでかい関西弁のおっさんは、こういうところでは嫌われて、客なんか来ないだろう。それでも、そういう人生もあったかもしれないと思う。
1月16日(火)
昨夜寝るまえに「ランボー 怒りのランボー」というネタを思いつき、おさい先生もげらげらと笑ってくれたので、これは絶対バズるなと思ってTwitterに書いたのだが、「いいね」が3つ付いただけだった。先日、大学キャンパスのなかでおこなった荻上チキと立岩真也との鼎談が『現代思想』に再録されますよ、というツイートには100以上のいいねが付いている。
絶対面白いと思ったんだが。
会議、教授会、あわてて研究室で書類作成、駆け込んでゼミ。
センター試験で30秒早く終わっちゃっていちど回収した回答用紙をもういちど配布して30秒間だけ回答させたとか、うっかり居眠りしちゃっていびきかいたら保護者からクレームがきて、いびきかいちゃった教員が大学で処分されたりとか、そういう話が昨日からたくさん出回っている。人間がやることなので、現場ではいろいろある。こういうことが「あってもよい」とは言わないが、たとえば回収するのが30秒だけ早かったからといって、どれくらいの「実害」があるのか、それはこれほど大きく報道されるべきことなのかはわからない。
わからない、というか、報道するなよ、と思う。こんなことほんとにこんなに大きく報道されたり大学で処分されたりするようなことなんだろうか。なんでこんなにみんな、あらゆることでギスギスするようになっちゃったのか。こういう流れはもう止まらないのか。果てしなく不寛容に、完璧主義に、一切のミスを許さない社会になるほかないのだろうか。
先日、ある会議で、奨学金を返さない卒業生に対して、法的に厳しい対処をすべきだという意見が、教員の側から出て驚いた。理由は、「一所懸命真面目に返してるほかの卒業生に対して不公平になるから」というものだった。大学っていったい何だろう。
「ほかのひとに対して不公平になるから」という言葉は、呪いの言葉だ。もうひとつ、「何かあったときにどうやって責任をとるのですか」も、きわめて大きな効力を持つ呪いだ。このふたつの言葉によって、私たちは自分たちの首を徐々にだが確実に絞めていくのだ。

1月17日(水)
雨。震災から23年か。大阪市の北のほうにあった私のアパートでも、食器がたくさん割れた。とっさに本棚を押さえてたんだけど、キッチンのほうでがちゃんがちゃんと食器が落ちて割れる音がずっと聞こえてた。長いこと揺れるなあと思ったのを覚えてる。まだ夜も明けてなかったので、とりあえず割れた食器類の上に古新聞(これがいまだによくわからない。新聞なんて取ってなかったのに、なんで古新聞なんかあったんだろう)をざっと敷いて、そのまままた寝た。
と思ったら友だちや別れた女の子から電話がかかってきてなんども起こされた。だいじょうぶ? いや、ぜんぜんだいじょうぶ。食器ぜんぶ割れたけど。だいじょうぶちゃうやん! 回線がパンクしたせいか、そのうち電話がかかってこなくなって、静かになった。
もういちど1、2時間寝て、起きたら大変なことになっていた。その日はたしか、修士論文の提出日だったが、どうせ提出日は延期されるだろうと思って、事務室に電話もかけなかった。そんなことどうでもよかった。
数日して落ち着いてきたころに、大阪のYMCAを通じてボランティアにひとりで参加した。たいしたことはしていない。物資、とくに衣料の整理と仕分け、あとは被災地で一軒ずつ訪ねて水を配った。
最初に派遣されたのは西宮と芦屋で、十三で乗り換えて阪急電車の神戸線に乗り、神崎川を越えたあたりから街の風景が一変した。戦争が起きたらこういう感じだろうか、と思った。
芦屋では家はびくともしていなかった。一軒ずつ呼び鈴を押して水を配ったのだが、それはそれと同時に暮らしの様子や困り事を聞くというアウトリーチの意味もあったのだが、うちは裏庭に井戸がありますんで、もっと困ってる方にあげてください、とよく言われた。
長田は焼け野原になっていた。階層格差というものはこういうものか、と思った。
あの感じ。あの感じをよく覚えている。男も女も子どもも大人も年寄りもみんな汚いジーパンで、ダウンジャケットで、風呂に入ってなくて、寒い路上にいて、真剣な顔で、優しくて、ときどきひどい冗談を言う、あの感じ。誰も助けにきてくれない、誰も頼りにならない、でも話しかけるとみんな親切な、あの感じ。自分がたいして役に立てていないことを恥じながら、無言で仕分け作業をする若いボランティアたち。
1月18日(木)
例によっていつものようにおはぎが夜中に何度も起こしにきた。朝になるとちゃんと私の布団のなかでくっついてぐうぐう寝ている。ほんとうにかわいい生き物だと思う。そしてまたきなこのことを思ってベッドのなかでちょっと泣く。朝遅く起きて、おさい先生を見送ったあと、昼間にひさしぶりにひとりでちょっとゆっくりする。いくつか溜まっていたメールやほったらかしになっていて迷惑をかけたメールに返事をして(皆様本当にすみませんでした)、少しだけ原稿を書いて、柴崎友香『千の扉』を再読。ほんとうは書評の原稿、昨日までなんだけど。しかしほんとうにこれ素晴らしいね。
夕方から京都大学で非常勤の授業。今日を入れてあと2回だが、教室の学生が減らない。いろいろ話を聞いてみると半分ぐらいモグりの学生や院生や社会人だった。そのわりには学生の履修者が少なくて、要するに正規の履修学生の大半が来てなくて、モグりできてるひとが一所懸命に毎回来てる。いつも来てる。だからいつも熱を込めて喋る。終わるとフラフラである。京大社会学の某先生のところに挨拶に行ってお茶をいただき、そのあと京阪で帰る。
京大の授業は、というか学部の授業はいつもそうなんだけど、講義ノートを作ったことがない。まずざっくりとした授業計画を年度の始めに組み立てて、毎回の授業はそれに沿ってそのつどその場でイチから考えて喋る。講義ノートを作ってしまうと必ず学生が寝る。筋書きがあるとつまらないのだろう。その場でゼロから、イチから考えて喋らないと、面白い話はできない。あくまでも私の場合は、ということだが。
だから、さいきんちょこちょこトークイベントにお呼ばれするのだが、たまに主催者が話の流れや組み立てをあらかじめ考えたり、あるいは当日1時間以上も早い時間に集合させて「打ち合わせ」をさせることがあって、それがとても苦手だ。そういうことをすると逆に喋れなくなるので、本番ぶっつけのほうがいいです、と言うと、こんどは打ち合わせやミーティングをバカにする偉そうなおっさん、みたいな感じになる。「やっぱり打ち合わせは必要だと思います」などと逆ギレされることもある。要りません。
1月19日(金)
おさい先生の目覚ましで起こされてしまい、そのまま眠れなくなる。猛烈な頭痛。しかし琉球新報のエッセーの校了日、というかもう掲載の前日だったので、さすがにもうこれ以上は延ばせない。痛む頭をこらえて30分ぐらいで1000字書いて送る。そのあと一緒に載せる写真を選定していて(いつもこっちに時間がかかる)、きなこの写真を大量に見てしまい、また泣く。悔しいので仕事中のおさい先生に無理やり送る。めっちゃ怒られた。
昼から先端研のゼミ。『ポーランド農民』の下訳。翻訳メンバーを確定して、分担を決め、今年度最後の授業終わり。他の授業はまだある。
院生が2人、書類にハンコをもらいに来て、そのまま2時間ぐらいうだうだと喋る。衣笠の和風ファミレスで揚げ物の定食食って帰る。5時間ぐらい経つけどいまだに胃もたれしている。
帰ってきて明日の資料に目を通す。いくつかメールの返事。風呂、洗濯。
17年間も毎日いっしょに暮らした家族が急にいなくなった。最初は受け入れられなかったが(家の中にまだいるような気がした)、いまではむしろ、いたときの暮らしのほうが幻だったのではないかと思うようになった。いまのこの、悲しい、さみしい状態が本当で、きなこが生きていたときの、なにも考える必要のない、ただかわいいなあとしか思わなかった暮らしのほうが、嘘。そういう気がする。
数万枚の写真が残されている。そのうち涙も出なくなるだろうから、泣けるうちにたくさん泣くつもりだ。手触りや重さや柔らかさや匂いを、できるだけ長く覚えていられるようにするために、写真を見る。写真を見て泣く、ということだけが、私たちときなことの間に残された、唯一の直接的なつながりである。
『Hanako』が届く。バレンタイン特集に俺なんかのエッセーを載せていいんだろうか。恐縮してしまう。こういう特集なら、雨宮まみさんの文章が読みたかった。何を書いただろう。
小室哲哉が不倫疑惑で、謝罪会見で引退を表明。この国はほんとうに、どんどんつまらない、くだらない国になっていくような気がする。
前に別のところで「雰囲気デフレ」という言葉を書いた。デフレマインドというか、経済的な状態であるデフレは、社会的、文化的な私たちのありようを変える。デフレ、あるいは不景気とは、椅子取りゲームをしている最中に、目の前で椅子がどんどん減っていくようなものだ。お互いが足の引っ張り合いになるのも仕方ないのだが、それにしても息苦しいニュースばかりだ。
どこか東京のほうの、電車のなかで赤ちゃんが生まれたらしい。久しぶりにすごいニュースだ、おめでたいニュースだと思っていたら、「電車のなかで出産するなんて迷惑」って言ってるひとがけっこういるらしい。
すごい時代になったもんやなあ。
1月20日(土)
昨夜のおはぎはほんとうにうるさかった。めっっちゃ起こされた。そのかわり朝ゆっくり寝る。土曜日だが12時から先端研のゼミ、補講。そのあと明治学院の石原俊さんをお招きした先端研のイベント。二次会まで行って、大阪に帰ったらちょうど友人Bのところに友人Kが来ていたので寄る。Mも参加。そのあと泊まったKが赤ワインのゲロを和室の畳で吐いたらしい。午前2時ごろに帰る。8時間飲んでた。
2月7日(水)
めちゃめちゃ間があいた。なぜかというと、この連載のことを忘れていたからだ。あたらしい『新潮』が届いて、52人がリレーする日記1年分の記事を見て、あっっそうや俺続き書かな、と思ってあわてて書いている。この間何をしていたかというと、いろんなことをしていた。京大教育学部の小さなイベントにお呼ばれしてお話ししたり、家族社会学会の大きな調査チームにお呼ばれしてお話ししたり、あと何だっけ。前任校で1クラスだけ残ってしまったゼミの卒論の口頭試問をして、そのあと大阪の鶴橋を歩いて、20人で焼肉を食って、有志でミナミに行って終電近くまで安い居酒屋で飲んだ。
前任校では毎年、20名以上のゼミ生を沖縄に連れていって取材をさせたり、大阪や神戸に連れていって合宿したり、そういうことを11年ほどしてきたのだが、それもこれで本当に最後になる。もうおおぜいの学部生を連れて歩く、という仕事自体をすることはないだろうなあ。ものすごく大変だったので、ものすごくホッとしながら、ものすごくさみしい。
あとは中谷美紀さんが主演する舞台『黒蜥蜴』を観にいったぐらいかな。共演する山田由梨さんにチケットを取っていただいて、ほんとうに久しぶりにこういう「メジャーな舞台」を観た。帰りに楽屋にも挨拶にいって山田さんとお話ししたのだが、あいかわらず若くて元気いっぱいの方で、なにかほんとうに眩しいというかうらやましいというかかわいらしいというか、これからのお仕事がほんとうに楽しみな女優さんだ。山田さんが主宰する「贅沢貧乏」という劇団の公演に招かれてアフタートークに出たのがきっかけで知り合ったんだけど、その舞台『フィクション・シティー』が、岸田戯曲賞にノミネートされたようだ。素晴らしい。
俺はあとは歳とって死ぬだけだ。
(つづきは単行本『にがにが日記』でお楽しみください)
-

-
岸政彦
1967年生まれ。社会学者。著書に『同化と他者化─戦後沖縄の本土就職者たち』『街の人生』『断片的なものの社会学』(紀伊國屋じんぶん大賞2016受賞)『愛と欲望の雑談』(雨宮まみとの共著)『質的社会調査の方法─他者の合理性の理解社会学』(石岡丈昇、丸山里美との共著)『ビニール傘』(第156回芥川賞候補作)『図書室』など。最新刊は『リリアン』(2/25発売)。
この記事をシェアする
「にがにが日記―人生はにがいのだ。」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 岸政彦
-
1967年生まれ。社会学者。著書に『同化と他者化─戦後沖縄の本土就職者たち』『街の人生』『断片的なものの社会学』(紀伊國屋じんぶん大賞2016受賞)『愛と欲望の雑談』(雨宮まみとの共著)『質的社会調査の方法─他者の合理性の理解社会学』(石岡丈昇、丸山里美との共著)『ビニール傘』(第156回芥川賞候補作)『図書室』など。最新刊は『リリアン』(2/25発売)。
連載一覧

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら