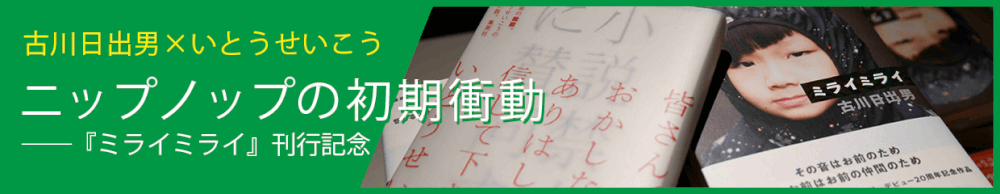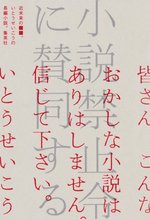古川 『小説禁止令に賛同する』の中でヒップホップマナーだなと思ったのは、いとうさんらしく映る一人称の語り手の批評の言葉や、漱石や中上の作品を嵌め込んだ上で、最後に自分が書いた架空の小説をこの世で一番素晴らしいと言い切ってしまうところ。でも、そのお終いの部分を、さらに誰かが改竄して違う小説を組み込むことも可である。すなわち何でもサンプリングして混ぜてしまうことをもって、いくらでも違ったバージョンを作り出せる。そのサンプリングを許容している構造が面白かったです。
いとう 基本的にサンプリングは大好きですからね。あんなに豊かな行為はないと。もちろん日本には昔から本歌取りというものが存在しますけれど。文脈を少し変えて、同じように見える言葉を乗せるのもお洒落だし、全く文脈が違うトラックに、一見合いそうもないセンチメンタルな歌を乗せてしまうミックスも好き。
古川 ズラすことでドラマが生まれるわけですよね。
いとう そこが腕というかセンスの見せ所だから、どの箇所がどの本のマナーに乗っているのか、読者に少しだけ分かるように書きたい。どのレコードからサンプリングしているのかということです。古川さんのニップノップというのは、その場所特有の音をサンプリングして作る音楽ですよね。僕は□□□(クチロロ)というグループに入っていて、自分が加入してから初めて作った『everyday is a symphony』というアルバムがある。これはメンバー3人が全員レコーダーを持って一日一日を記録して、トラックメーカーの三浦康嗣に渡して作ったんです。
-
□□□(クチロロ)
古川 彼がミックスしてトラックにしたということですか。
いとう そう、それらの音素材を完全にチョップ(音を切り刻むこと)して。たとえば冒頭の曲では、僕が当時浅草にいたので、おじさんの木遣り歌から始まって色々な音が段々とリズムを構成していく。あるいは「卒業」という曲では、本当の卒業式の様子を録って、先生の挨拶や校歌もチョップしてメロディを全部変えている。だから古川さんと音楽に求めたいものが似ていると感じたんです。しかも実は2枚目を作るときに僕は、もう日本の中にある音は大体分かったから、インドに行こうと言った。結局、実現されなかったのですが。だから今回『ミライミライ』を読んでいて、どこまでがフィクションなのか分からなくなって、もしかしたら自分の妄想を読んでいるのではないかと(笑)。
古川 そこでインドがどーんと繋がってくるわけですね。いとうさんが自分で考えていたことが、なぜかここに古川日出男の名前で書かれていると。しかもそれ、10年前くらいの出来事ですよね。
いとう 僕にとっては10年前、だけど『ミライミライ』にとってはもっと前から物語があるわけだから、一緒に過去に飛んで行くような感覚だった。そういったリアルさがあったんです。ニップノップの音を考えてみると、ヒップホップは元々レコードをサンプリングして、レアグルーヴなんかの切れ端みたいな音を繋いで、その上にラップを乗せて行った。そのときに実はレコーディングされたスタジオの音も入っているから、環境音楽とも言えると思う。それがニップノップにも通じる。僕は昔からなぜヒップホップが好きなのか上手く説明できないのですが、『ミライミライ』のニップノップの中には、そのヒントがある気がする。
古川 やはり音楽というのは本来、どこで誰といつ作ったというように、空間や時間も明確に記録(レコード)しますよね。これはどんな表現にも重要だと思いますが、今は色々な音楽がそうした特性を捨て去ろうとしているように見える。そうすると、いつの時代、どこの場所の制作でも同じものになってしまう。反対に、そういった空間や時間がきちんと記録されているのが、いとうさんが最初に出会ったヒップホップだったのだと思います。場所という点で言えば、先ほどのインドでアルバム制作をするとのアイデアに触れて考えたことですが、日本人の僕らって幼い頃から海外の音楽を聴いても、言葉が、歌詞や主張が分からなかった。だから自分の魂のセンスだけで好き嫌いを判断した。これを踏まえると、もし言葉が分からないインド亜大陸にメンバーの方々で渡って音を選んでミックスしてアルバムを作ったら、逆にセンスで物凄く反応できるものに仕上がるんじゃないですかね。どうですか。
いとう じゃあもう一度メンバーの尻を叩きますか(笑)。ヒップホップという音楽の最初のスピリットは、過去の音楽を使うことなんです。サンプリングするわけだから、過去であらざるを得ない。僕は当時「演奏」というものを馬鹿にして、ついつい非音楽的なものが現代音楽だから良いと言っていた。過去の曲を演奏すると蘇るものがあるから「今」なんだけど、ヒップホップはもう死んだ人のジャズのレコードをそのままサンプリングしたり、20年前に自分の叔父さんたちが熱狂していたロックンロールの一節を使ったりする。言ってみれば、全部死んだものなんです。そこから生き生きしたものを取り出すとは、何て素晴らしいアイデアなのかと当時大興奮した。それに自分で演奏しないのがカッコいい。演奏するのは、ただスクラッチの雑音だけ。今思えば、僕はその面白さに、どこか文学的なものを感じていたのかもしれません。先ほどの本歌取りのように考えると、一度読んだものだからこそ、そこを引用できるわけで。そうやって音楽と文学を比較すると、音楽を演奏するときは多少ならず自分の音が出てしまう。けれど文字は誰が打っても文字ですよね。自分らしさなんて出せない。
古川 文字の場合は書き手から少し距離がある感覚がありますね。しかも僕らの手書きの文字っていうのは本には入らない。印刷所が持っているフォントでしか「小説用の文字」は出てこない。
いとう そこが元々ヒップホップっぽいのかも。
古川 ヒップホップ以外の、楽器を使って演奏する音楽の場合には、ギターやバイオリンのような楽器を自分の身体の延長部分のようにしてマスターしますよね。そうすると結局自分の身体の補完部としてサイボーグのように扱っているから、もし楽器から良い音が出ても、それは自分を愛していることになる。言ってみれば「自分リスペクト」です。しかし楽器を使わない場合は、活字のように身体からは完全に離れていくので、今度はこの音へのリスペクトであるとか、死んだアーティストのことをリスペクト、このロックンロールの一節をリスペクトするということになる。だからヒップホップの場合、自分以外のものを全部愛し尽くして作った文化ということになるのではないでしょうか。
いとう 確かに最初の頃のヒップホップのアナログは、大体ラベルの裏に、サンプリングした相手のアーティストへのリスペクトが書かれている。当時はまだ裁判がなかったから、リスペクトと言いさえすればジェイムズ・ブラウンなんかでも皆オーケーな時代で。仁義みたいなものですが、豊かなことでもある。もうひとつ、40歳を超えてからよく分かって来たことがあります。ヒップホップの最初のDJはジャマイカ系のクール・ハークという人だとされていますが、それ以前のディスコDJは、Aという曲をかけて、次にAに一番テンポが近いBという曲を上手く選び、BPMを少しだけ合わせて繋いでいた。繋ぎの上手い人は、Aで鳴っているギターの音に割と近いフレーズが聞こえるBを繋ぐ。それをC、D、EFG……と一晩中聞かせるのが上手いDJ。そんな奴らが世界中に沢山いたわけです。しかしクール・ハークの何が凄いかというと、あるレコードの中の20秒間の間奏に目をつけた。つまりブレイクビーツというものですが、もう一枚同じレコードを買って来て、その間奏を繋いだわけです。AからAなんですよね。AからAに行って、またAに戻る。それで一晩中やることを思いついた。こんなコロンブスの卵はない。続ければ続けるほど同じものを繰り返すから、土俗的でプリミティヴ。ミニマルであることが一番最高潮のところまで人を持って行くという可能性を、クール・ハークが発見したわけです。
古川 なるほど。Aを繰り返しているだけなのに最終的に最高潮のZにたどり着いてしまうというのは、驚くべき発見ですよね。

いとう それから僕がもうひとつヒップホップの面白さに驚嘆したのは、政治との関係です。ヒップホップ初期のパーティラップの時代よりもっと前に、ラスト・ポエッツというグループがいた。彼らはニューヨークの詩人で、ほとんど打楽器だけをバックにユニゾンで詩を語りながら、意識的に公民権運動とつながっていく。彼らを起源として、その後時代が下っていくと、政治的なラップで人々を踊らせるようになる。昔は拳を上げるだけだったけれど、踊っている連中もいると広がりが出て来る。僕はマーヴィン・ゲイという人も大好きで、彼の「ホワッツ・ゴーイング・オン」という曲は、「長髪という理由でなぜ弾圧されなければならないのか、皆デモに出よう」と歌っています。だけど、本人が胸をはだけさせてセクシーに歌っているから、女性ファンたちは立ち上がって黄色い歓声を上げている。それが出来るのが音楽の素晴らしさだし、社会の中で自分の問題を歌いつつ、政治的なものを越えていくことだと思うのです。だから今でもケンドリック・ラマーはもちろん、ほとんど麻薬のことしか歌ってないような連中も、どこかで必ず黒人問題を見据えて歌っていて、それが多くの人々に聞かれヒットするアメリカを自分としてはリスペクトする。日本では同じようにはいかない。ただ、昔パブリック・エネミーのフロントアクトをやったとき、彼らが途中で観客に拳を上げさせて、全ての白人は敵だから忠誠を誓えというように迫ってきたときに、これは少し違うんじゃないかと。
古川 それはある時期を超えてしまったパブリック・エネミーですよね。
いとう そうです。あるときからプロフェッサー・グリフというメンバーが過激化していって、その頃から僕はヒップホップから一度離れてしまった。今度は古典芸能に目を向けて、日本語の世界では何があったのか、あるいは日本語の演説はどうだったのかと掘っていった。公民権運動ではなくて自分たちの問題、オッペケペーはどうだったのか。翻ってアメリカでは、アフロアメリカンの演説はどうだったのか、スピーチはどうだったのかという方向に行ったんです。
古川 先ほどの□□□で色々な音を取ってくるという発想がありましたが、自分の小説のニップノップにも反映させたのは、実はパブリック・エネミーのサウンドプロダクションなんです。街中のサイレン音や色々な音を集めてきて、都市の現実、「今ここ」の時間も空間も記録するという作り方自体が、大きな可能性だった。先ほどのいとうさんの話だと、たとえばマルコムXがスピーチしても拳を上げるしかない。でもパブリック・エネミーが同じことをすると踊る人たちがいる。活動の途中で一線を越えてしまったけれど、ある段階までの彼らは政治性を外部に向けて解放した。黒人問題のことは分からない人々をも音に乗せてしまうことで、ボーダーを越えてしまうような力がありました。そこから数年後に、たとえば西海岸のコンソリデイテッドのようなバンドが、さらにどんなメッセージも発信できるラップを始めたとき、またヒップホップの可能性を感じた。つまり、レペゼンするのがひとつの集団だけだと自閉するので、全員レペゼンすべきだという考え方があったんです。
-

-
いとうせいこう
1984年早稲田大学法学部卒業後、講談社に入社。86年に退社後は作家、クリエーターとして、活字/映像/舞台/音楽/ウェブなど、あらゆるジャンルに渡る幅広い表現活動を行っている。
-

-
古川日出男
1966年福島県郡山市生れ。1998年に『13』で小説家デビュー。2001年、『アラビアの夜の種族』で日本推理作家協会賞、日本SF大賞をダブル受賞。2006年『LOVE』で三島由紀夫賞を受賞する。2008年にはメガノベル『聖家族』を刊行。2015年『女たち三百人の裏切りの書』で野間文芸新人賞、2016年には読売文学賞を受賞した。文学の音声化にも取り組み、朗読劇「銀河鉄道の夜」で脚本・演出を務める。著作はアメリカ、フランスなど各国で翻訳され、現代日本を担う書き手として、世界が熱い視線を注いでいる。他の作品に『ベルカ、吠えないのか?』『馬たちよ、それでも光は無垢で』『MUSIC』『ドッグマザー』『南無ロックンロール二十一部経』など。特設サイト「古川日出男のむかしとミライ」http://furukawahideo.com/
この記事をシェアする
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- いとうせいこう
-
1984年早稲田大学法学部卒業後、講談社に入社。86年に退社後は作家、クリエーターとして、活字/映像/舞台/音楽/ウェブなど、あらゆるジャンルに渡る幅広い表現活動を行っている。
対談・インタビュー一覧
-

- 古川日出男
-
1966年福島県郡山市生れ。1998年に『13』で小説家デビュー。2001年、『アラビアの夜の種族』で日本推理作家協会賞、日本SF大賞をダブル受賞。2006年『LOVE』で三島由紀夫賞を受賞する。2008年にはメガノベル『聖家族』を刊行。2015年『女たち三百人の裏切りの書』で野間文芸新人賞、2016年には読売文学賞を受賞した。文学の音声化にも取り組み、朗読劇「銀河鉄道の夜」で脚本・演出を務める。著作はアメリカ、フランスなど各国で翻訳され、現代日本を担う書き手として、世界が熱い視線を注いでいる。他の作品に『ベルカ、吠えないのか?』『馬たちよ、それでも光は無垢で』『MUSIC』『ドッグマザー』『南無ロックンロール二十一部経』など。特設サイト「古川日出男のむかしとミライ」http://furukawahideo.com/
対談・インタビュー一覧

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら