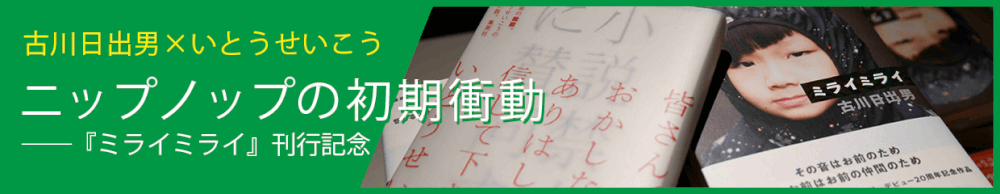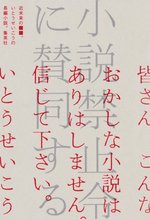いとう このあいだの『文藝』に批評家でヒップホップも詳しい陣野俊史さんの「泥海」という小説が掲載されていましたが、これがめちゃくちゃ良かった。彼はフランスにいた人ですが、この物語の主人公はシャルリー・エブドの一連の事件の当事者たちなんです。でも、何と言えば良いのか、いやらしい形容詞がない。
-
2018/4/7発売
古川 これまで小説が発達させてきた装飾のようなものが落ちているということですか。
いとう すごく落ちている。そのリアリティを感じて、なぜこんなにも引き込まれるのだろうかと今もまだ考えている最中です。久しぶりに人の作品に恋をした。
古川 僕はまだその作品を読んでいないのであくまで想像ですが、フランスのテロリストの目線で小説を書こうとするときに、彼らは移民系すなわちフランス語のネイティヴスピーカーではない、あるいは二世や三世であって、そこまでフランス語が上手でないという目線で世界を眺めることになりますよね。そもそも装飾的な言葉がない世界に生きているから、そういった直接的な言葉で書かれたのではないかという気がします。
いとう なるほど、それはあるかもしれない。同時に僕が思ったのは、この小説は最初、日本語で書かれなかったのではないかと。
古川 つまり別の言語で書いてから日本語に訳したということですね。
いとう 訳すことによって落ちていくものがあるはずなので、これは自分でもやってみるべき方法だとは思っています。日本語で書くと、シンプルにしたくてもどうしても自分たちのテクニックが付いてきてしまう。そこでクール・ハークのようにAからAに翻訳することは、勇気がいるけれど重要なのではないかと。
古川 僕は20年作家やってきて去年辺りから、長編小説の場合ですが、異様に書き直しをしています。要するに、Aを書いた後に、大体4回くらい書き直して、A→A→Aと来てその次で突然Dになるような、そういった書き方を始めています。書き直す度に視点が少しずつズレていって、同じことを書いていても、同じ文章にはならないし、書き直すうちに初めてぴったり合うところがある。
いとう どこのカメラから撮るのが一番良いか、実際に書いていかないと分からないということですね。
古川 だから必ずしも翻訳しなくても、執拗に書き直すことで同じ様なことはできるんじゃないか。でも実際は書き直したくない、捨てたくないと思いながら書き直すんです。もし編集者にこれを見せたら、全然これでいいと言われてしまうから見せられない。自分自身で却下しないといけない。一番厳しくて、最もレベルが高いものを要求してくる読者は自分です。これはこのあいだ書いた作品の真似だとか、かなり厳しい批評をされる(笑)。
いとう 編集者は許しても、自分は許さない。これをこのまま出版して大丈夫なのかと一番冷や汗をかいているのはやはり本人です。本が出た後に、あの箇所は別の書き方をすれば良かったと思うという、因果な商売ですよね。しかしその古川さんのやり方はほとんど短編のやり方で長編を書いているみたいなものですね。
古川 だから最近は多分3000~4000枚くらい書きながら、最終的に1000枚以下にしているような感覚なんです。
いとう それは驚くべきやり方ですね。これは奥泉光さんとの文芸漫談でもたまに話すことですが、小説の面白さのひとつは「車が走ってきた」と書くのと、「黒く車高の低い車が、ゆっくり走ってきた」と書くのと、どちらが良いかと考えると実は前者かもしれないところ。なぜなら小説は読者が想像する以外ないメディアだからです。映像や演劇は視覚に訴えてくるから、ある程度のものは視覚で共有できるけれど、小説は読者へのアクセシビリティや読者側のイマジネーションがないと読めない。彼らが「こういう場合は、車はゆっくり来るでしょ」と想像する。そういう意味では小説は、演劇でいうところの演出が入る前段階なのではないか。脚本家が「そこはゆっくりに決まっているだろ」と怒鳴って、灰皿が飛んでくる段階(笑)。
古川 皆が灰皿投げるわけじゃないですけどね(笑)。一方で戯曲の面白いところは、台本の「台」に当たる部分であって、つまり単に前提を作るだけの土台でしかないところです。役者が自分で想像して、演出家がさらに刺激を与えるというところが良い。小説もいったんそこまで戻った方がいいのかもしれません。おそらく小説の描写というのは、映像文化が登場したから現在のように細かくなったと思うんです。以前はそこまで詳細に描かれはしなかった。それが30年前の出来事であれ200年前の事象であれ、さらに源氏物語まで遡れば千年前ですが、過去を参照して初めて未来への可能性も出てくるのではないか。
いとう 源氏物語にしても細かく書いてあるのは衣装のことばかり。それはおそらく書き手が身分を描写するためだったり、あるいは当時の読者たちが、カタログのように読んだからじゃないでしょうか。
古川 宮仕えの女官たちが主人の代理で朗読したり、まあ朝廷のサロンで皆さん読んでいたわけですよね。
いとう そうすると何が一番盛り上がるかといえば、ファッションだったはず。源氏も訪問者の顔が見えないままセックスしたり、好きになったりする。その人の香りが良かっただとか、情報が少ないわけです。でもそれが皆をワクワクさせるものだった。だから後から色々な絵をつける人たちが出てくるのは、演出家のようなものですよね。僕はインターネットが出てきたときに、ネット上で連載した小説に色々な人が勝手にイラストを付けたり、書き換えることが出来るようにしてみた。それは平安の頃の楽しみ方というか、それこそ初期衝動のようなものです。元々は手で書かれていた小説の何が抜群に面白かったのか、もう一度この印刷社会の中で考えてみたかった。今は手書きだった頃とは真逆で何でも読めすぎてしまう時代ですよね。
古川 だからこそ読者が色々想像して、イラストを付けうるような可能性を残す、と。読者を信用するということでもある。
いとう 登場人物のエモーションや、生き方の選択といったものに対する尊敬といった、読者に感じて欲しいものはある。でもそれは、ごく少ない言葉で示せるようにした方がいいのかなと。今回の『小説禁止令に賛同する』は特に上手な小説というのではなく歪な形で書いていて、先ほど話した18世紀のヘタウマみたいなものを意識しています。日本で言えば平安時代のように、下手ではないけれど今みたいな技術がない中で面白さを出すのはどういうことなのかと。だからそれは、古川さんが何度も書き直す中でどれが一番ぴったりくるかは、そのカメラの角度なのだと言っているのと同じですね。どのような言葉を飾って描写するかということよりも、語り手の位置から仰ぎ見ているのか、それとも見下げているのかという、対象との位置関係じゃないですか。削っていってしまえばそこだけが残る。
古川 別な喩え方をすると、何か美しいものがあって、その対象を囲んでいる全員がこれをiPhoneで撮影したら全部の画が揃って美しくなるかというと、そうではない。ただひとりプロがあるポジションからピシッと撮ることで、そのとき初めて対象の「美」を正確に他の人に伝えられる。我々はどうしてもそのポジション、その角度を追求していかないといけない。美しいものを、同じような言葉で月並みに書けば再現できるわけではない。それをセンスという安易な言葉には還元したくないと思いつつの発言ですけど。
いとう それは深い問題ですが、結局のところ、やってみなければ分からないところがある。つまり具体的なものがなければ判断できない世界ですよね。ある種、職人的なものかもしれない。
古川 だから我々はまず書いてみるわけですよね。一度そこから書けると思ったのなら、失敗覚悟でとりあえず書くと。
-

-
いとうせいこう
1984年早稲田大学法学部卒業後、講談社に入社。86年に退社後は作家、クリエーターとして、活字/映像/舞台/音楽/ウェブなど、あらゆるジャンルに渡る幅広い表現活動を行っている。
-

-
古川日出男
1966年福島県郡山市生れ。1998年に『13』で小説家デビュー。2001年、『アラビアの夜の種族』で日本推理作家協会賞、日本SF大賞をダブル受賞。2006年『LOVE』で三島由紀夫賞を受賞する。2008年にはメガノベル『聖家族』を刊行。2015年『女たち三百人の裏切りの書』で野間文芸新人賞、2016年には読売文学賞を受賞した。文学の音声化にも取り組み、朗読劇「銀河鉄道の夜」で脚本・演出を務める。著作はアメリカ、フランスなど各国で翻訳され、現代日本を担う書き手として、世界が熱い視線を注いでいる。他の作品に『ベルカ、吠えないのか?』『馬たちよ、それでも光は無垢で』『MUSIC』『ドッグマザー』『南無ロックンロール二十一部経』など。特設サイト「古川日出男のむかしとミライ」http://furukawahideo.com/
この記事をシェアする
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- いとうせいこう
-
1984年早稲田大学法学部卒業後、講談社に入社。86年に退社後は作家、クリエーターとして、活字/映像/舞台/音楽/ウェブなど、あらゆるジャンルに渡る幅広い表現活動を行っている。
対談・インタビュー一覧
-

- 古川日出男
-
1966年福島県郡山市生れ。1998年に『13』で小説家デビュー。2001年、『アラビアの夜の種族』で日本推理作家協会賞、日本SF大賞をダブル受賞。2006年『LOVE』で三島由紀夫賞を受賞する。2008年にはメガノベル『聖家族』を刊行。2015年『女たち三百人の裏切りの書』で野間文芸新人賞、2016年には読売文学賞を受賞した。文学の音声化にも取り組み、朗読劇「銀河鉄道の夜」で脚本・演出を務める。著作はアメリカ、フランスなど各国で翻訳され、現代日本を担う書き手として、世界が熱い視線を注いでいる。他の作品に『ベルカ、吠えないのか?』『馬たちよ、それでも光は無垢で』『MUSIC』『ドッグマザー』『南無ロックンロール二十一部経』など。特設サイト「古川日出男のむかしとミライ」http://furukawahideo.com/
対談・インタビュー一覧

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら