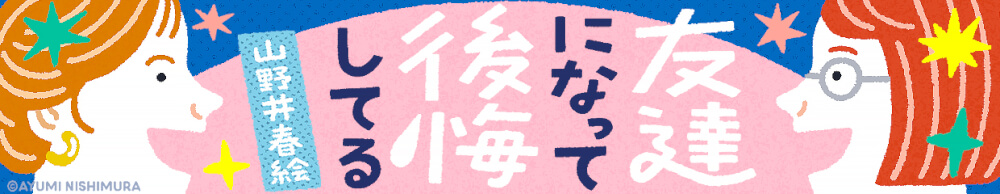第1回 もう友達なんていらないなんて、言わないよ絶対。
著者: 山野井春絵
「LINEが既読スルー」友人からの突然のサインに、「嫌われた? でもなぜ?」と思い悩む。あるいは、仲の良かった友人と「もう会わない」そう決意して、自ら距離を置く――。友人関係をめぐって、そんなほろ苦い経験をしたことはありませんか?
自らも友人との離別に苦しんだ経験のあるライターが、「いつ・どのようにして友達と別れたのか?」その経緯を20~80代の人々にインタビュー。「理由なきフェイドアウト」から「いわくつきの絶交」まで、さまざまなケースを紹介。離別の後悔を晴らすかのごとく、「大人になってからの友情」を見つめ直します。
※本連載は、プライバシー保護の観点から、インタビューに登場した人物の氏名や属性、環境の一部を変更・再構成しています。
さようなら、美しきママ友よ
いつからか、彼女からのLINEの返信は遅れがちになった。おやなんだか様子がおかしいな、と気づいたころには、もう手遅れだったと思う。返事の早い人だったが、数日の既読スルーは当たり前、なかなか既読にならないことも増えた。
私は友達を失ったのだ、その事実をはっきりと認識したのは、ある夏の午後、最寄り駅のホームで電車を待っているときだった。
数日前、私は思いつめて彼女にLINEを送っていた。何か私はあなたの気に障ることをしてしまったのでしょうか、もしもそうであれば教えてほしい、嫌な思いをさせるつもりはなかった、反省しています、元通りに仲良く付き合いたいです、つきましては近日中で会える日はないでしょうか、日時はあなたに合わせます……というようなことを、なるべく重くならないように冗談を交えつつ、推敲したメッセージだった。が、その時ようやく届いた彼女からの返事は、あっさりとしたものだった。先に私が送った内容にはまったく触れず、なんということもない世間話が少しと、絵文字。行間からは、「あなたと会うつもりはない」という明確な意思が感じられた。むせるような暑さのなか、立ったまま電車を一本やり過ごし、私は彼女とのこれまでのやりとりのすべてを削除した。西日を照り返す薬局の看板。ひぐらしの鳴き声。その記憶はあまりにも鮮烈で、いまでもあのホームに立つと時おり思い出す。悲しかった。若いころ好きだった男と別れたとき以上につらいと思った。恋をしていたわけではない。彼女は10年以上付き合った、年下のママ友だった。
彼女は美しく、優しかった。おっとりとして品があり、ロングヘアでファッションもエレガント。ハリー・ウィンストンで買い物するような、経済的にもたいへん恵まれた専業主婦である。しがないライター稼業、カジュアルおばさんの私とは、見た目も年齢もライフスタイルもまったく重なるところがなく、周囲からはよく不思議がられたものだ。お互いに飲兵衛で、たまたま地元が近かったこともあって、気を許し合う仲になった。お互いに、子どもは一人っ子。夫同士も気が合ったため、家族ぐるみの付き合いが続いた。
関係の終焉は、子どもたちが小学校高学年になったころ。何が原因だったかは、いまだにわからない。何か大きな出来事があったわけではない、と思う。いや、実はいくつか思い当たる節はある。おそらくは複合的な理由で、私に対する「イヤだな」という感覚が彼女の中で塵のように積み重なった挙句、いよいよ溢れて「この人との付き合いは不要」という結論に達したのだと推察する。が、まあ確かめるすべはない。最後にL I N Eでやり取りした後は音信不通、インスタグラムのアカウントも削除されて、彼女が新しく開設した鍵つきのアカウントは、共通の友達の間では私にだけ知らされなかった。
返事がないこと、それこそが返事。これが大人の関係における終焉の特徴だ。何々が嫌だからあなたと離れる、そんなことすら、もはや“伝える必要がない”という心理。彼女が私を嫌った明確な理由はわからないが、切り捨てにいたる感情のプロセスは、よく理解できる。なぜなら私だって同じように誰かとの関係をこちらから終わらせたことがあるからである。
毎夜寝床で繰り返す、不毛な一人反省会
昔からずいぶん友達には恵まれてきたと思う。学生時代、バイト先、社会人になっていくつか渡り歩いた仕事先でも、それぞれに親しい仲間ができた。子どもを持ってからはたくさんの“ママ友”ができたし、地域のコミュニティもフレンドリーで、年齢、既婚未婚、子あり子なし、性別も関係なく交流を楽しんだ。その間にはいくつかの別れもあったが、ほとんどが仕事や住む場所の変化といった環境的な理由だったと思う。「インタビューを主とするライター」という仕事柄、人と話すことが好きだし、つねに新しい出会いには期待がある。外から見れば、私は「社交的」で「友達の多い人」という印象なのだろう。
それが50代に入ったころから、様子が変わってきた。ある時期を境に、2、3人、いや、考えてみれば5、6人ほど、潮が引くように私から離れていった。この人数が曖昧なのは、確実に関係が終わったかどうか、今ひとつ判断しづらい人も含まれるからである。
数年前までよく会っては語らい、飲み食いし、一緒に旅をした大好きな女友達が、煙のように消えてしまう……これは相当ヤベーことになった、と気づいたときには、時すでに遅し。なかでも冒頭に記した、特に大切に思っていたママ友と縁が切れたのは、ダメージが大きかった。やがて彼女との共通の友達はもちろん、なぜか別のコミュニティに属する友達までもが芋づる式に離れていく。
いったい、何が起こっているのか。誰かが怪文書でも回したかと疑心暗鬼にもなった。しかしそれはすぐに、内省へと変化した。私はあの人に、何をしたのだろう? 何が悪かったのか? 布団の中で一人反省会をする夜が続く。何もわかりっこなかった。誰も教えてくれないし、自分自身の変化には気づくことができないのだ。
みんなが私を嫌っている、それは私がおかしいからだ。そんな被害妄想に取り憑かれ、特に関係が変わらない友達にすら疑念を抱くようになった。LINEの返事が遅れれば、「この人とも終わったか」。約束をしていた相手がインフルエンザで来られなくなった時も、「仮病じゃないか。本当は別の予定を優先したのではないか」などと疑う。
今も続くさっぱりした性格の友達は、「いい加減にして、あんた病気だよ」と笑った。メンタルクリニックのお世話になるほどではなかったけれども、確かに、一時期の私は病んでいた。更年期症状も相まって、私のメンタルは箸でめった刺ししたはんぺんのように、ぐちゃぐちゃ潰れていった。
「親しかった人が離れるのは、あなたのステージが上がった証拠だよ」
そんなふうに慰めてくれる人もいたが、すっかり心を強張らせた私には素直に受け入れられない。それなのに一方で、引き寄せ系の本を買ったり占いサイトに課金したり、スピリチュアルな言葉を探してネットをさまよったりした。
「縁があればまた繋がる」
「去る人があれば、本当にわかってくれる人が現れる」
「絶縁? おめでとう! 涙が出るほどいいことが起こる予兆です」
S N Sにはそういう言葉ばかりが流れてくるようになってしまった。こんな誰が言ったかわからないような言葉にすがったり、スピ系のYouTubeを見漁ったりと、ありとあらゆる手で尊厳の回復に努めたが、モヤモヤは晴れない。時間だけが虚しく過ぎた。
あんなに仲が良かった人たちも……
それでも表面的には元気よく振る舞っていた。こんなときは忙しくしているにかぎると考え、来る仕事はすべて拒まず、がむしゃらに働いた。子どもの中学受験本番が迫ってきて更年期症状もエスカレート、汗だくでテキストをコピーする日々。夜中は一時間おきに目が覚めた。浅い眠りの夢に、去った友達が出てきて「あなたのあの××××が本当に嫌だったんだよね」と言われたところで、飛び起きたこともある。肝心な部分は聞き取れなかった。「待って、待って」と呟きながら、真っ暗な寝床でほのかに光る時計を呆然と見つめた。
そんなカオスな状況が続いていたころ、地方に引っ越した懐かしい人から「久しぶりに東京へ行くので、ランチしませんか」という誘いを受けた。職種は違ったが先輩のような存在で、たまに会っては近況報告をする仲。コロナ禍の期間は会えなかったので、数年ぶりの再会となった。
彼女(仮にA子さん)には「お姐さん」と呼ぶ世話焼きの年上友達がいて、私も何度か宴席で一緒になったことがあった。その日何気なく、「そういえば、お友達のお姐さんはお元気ですか?」と私が尋ねると、A子さんは表情を曇らせて、言った。
「ああ。お姐さんね。実は、もう長いこと会っていないの。いろいろあってね。会わなくなってしまったの。私が、もうダメで」
「ええっ。彼女とは、とても長い付き合いだったのでは?」
「そうなんだけど、そういうこともあるわよ。それでよかったと思っているし、今では向こうもそう思っていると思う」
勝手ながら「彼女たちは絶対に一生の友達に違いない」と思い込んでいたので、私は心底びっくりした。その内容は、ざっくりいうとこうである。
A子さんとお姐さんは職場の先輩後輩の間柄で、20年以上の友人だった。A子さんはお姐さんのツテで男性を紹介され、結婚。お姐さん夫妻が仲人を務めた。数年前、A子さんの夫の不倫が発覚。不倫関係はすでに終わっていたものの、気持ちがおさまらないA子さんは信頼するお姐さんに相談した。お姐さんからは「終わったことだからもう忘れなさい」と諭された。その態度を不審に思ったA子さんが夫を問い詰めると、ずいぶん前からお姐さんは不倫の事実を知っており、「A子には絶対にバレないように早めに女と別れろ」などとアドバイスをしていたという。A子さんは離婚しなかったが、お姐さんとは距離を置くようになった。お姐さんからは何度も連絡があったが、そのうちに途絶えた。
「お姐さんは、私がヘソを曲げただけと思ったかもしれないけど、違うの。私、わかっちゃったのよね、ずっとお姐さんにばかにされていたんだなって」
そうだろうか?と思ったが、私は口には出さず、「お姐さんには、きちんとA子さんの気持ちを伝えたのですか」と尋ねた。するとA子さんはこう答えた。
「伝える必要ある? 私のことを理解して、気持ちを考えてくれる相手なら、こんなことにはならなかったと思うしね」
帰りの電車の中で私は、彼女が語ってくれた「お姐さんとの別れ」を反芻した。
そうしているうちに、「なるほど……」という思いがこみ上げてくる。A子さんがお姐さんに抱いた気持ち、他方お姐さんの気持ち。自分の身に起こった出来事ではないし、特にお姐さんについては想像でしかないけれども、どちらの気持ちもわかる気がした。誰かの離別の話を聞くと、少しずつではあるが、自分を客観視できることに気づいた瞬間だった。
いくつになっても、友達と別れる
そこから、である。タイミングがあれば、私はさまざまな人に「友達との離別経験」を尋ねるようになった。すると思いがけず、ほとんどの人に離別経験があり、それぞれのストーリーはオリジナリティに富んでいた。自分の経験から、これは更年期症状に紐づく女性ならではの感情かと思い込んでいたが、そうとは限らなかった。20代から80代まで年齢はさまざま、さらには男性でも特別な離別の思い出を持つ人がいた。
切り捨てホヤホヤのストーリーを語る人は、まだどこか相手への嫌悪感が生々しく、カッカしていた。出来事が過去になるほど客観性が高まり、相手を慮ったり、反省の言葉を口にしたりする傾向にある。一方、自分が切り捨てられた思い出を語る人は、一様に目を伏せる瞬間があった。インタビューを重ねて気づいたのは、友達に去られた経験には、羞恥心のようなものがつきまとうということである。
「大事にしていた人に去られるほど、私は“ヤバい奴”なのかもしれない、そう考えたら夜も眠れない日が続きました。……今話してて、わかりますか? 私ってどこかヤバいですか? 教えてほしい」
そう言ったのは幼馴染みに去られた30代の既婚女性だったが、強く共感した。私も自分自身の見えざる「ヤバさ」に苦しんでいた。友達に去られたという事実を、恥ずかしくて情けなくて、家族にもしばらく話すことができなかったのだ。それはいじめられている事実を親に言えない子どもの心境にどこか似ている気もする。
何がいけなかったのか。あの一言か。原因探しからはじまり、どうすべきだったかとシミュレーションし、悲嘆し、怒り、やがて自分とはどんな人間なのかと問いはじめる。友達との離別経験は、嫌でも内省を迫る。
が、明瞭な答えはない。ほとんどの相手は理由を教えてくれない。第三者が「……だからだってよ」などといらぬ情報を与えてくることもあるが、それが真実とは限らない。
なぜ友達との離別は起こるのか。長く続く友達もいるではないか。何が違うというのだろう?
人は変わる。人との交わりのなかで、考え方も変化していく。軌道のズレがやがて大きく開くように、友達と離れるのは自然なことなのだろう。……そう達観できればいいが、なかなかそうはいかない。忘れた方がいい、なかったことにしよう、そんなふうにすっきりさっぱり考えられないのは、楽しかった思い出も共有しているから。そろそろ心が癒えてきたかな、と思うと、FacebookやGoogleフォトが思い出の写真を一方的に見せてきて、ふたたび瘡蓋を剥がす。あの日の笑顔がこんなデジタルタトゥーになるとは、誰が想像しただろう。
もちろん、時間が過ぎればある程度は忘れることができる。早い段階でさっさと前を向ける人もいる。インタビューした中にも、「時間のムダ!」と言ってのける人がいた。「理由なんてどうだっていい。生き方、価値観が合わなくなった、それだけ!」と。
そのドライさに憧れつつ、友達との離別におけるあらゆる反応について、文章にして残してみたいと思った。
インタビューの中には、あなたの離別体験に近いものも、あるかもしれない。出来事を通してあなたは何を考えたか。相手は何を考えていたか。逆の立場から見ることで納得ができるかもしれないし、「どうでもいい」と一蹴するかもしれない。インタビューから浮かび上がるさまざまなストーリーは、見る人の立場によって、また時間の経過によっても、印象が異なってくる。
友達との離別は誰にでも起こりうるもの。一度起こったから二度と起こらないとは限らず、何歳になってもしっかり傷つく。が、傷ついてもなお、友達の存在というものは、人生にとってかけがえのないものだと思う。
友達との離別は、人生にどんな意味をもたらすのか。少しでも得るものはないか。なんとか回避する方法はないものか。せっかくならそこから「人生の役に立つ何か」を探してみたいというのが、この連載の目的である。
もう友達なんていらないなんて、言わないよ絶対。そんな気持ちで、書いている。
(※本連載は、プライバシー保護の観点から、インタビューに登場した人物の氏名や属性、環境の一部を変更・再構成しています)
-

-
山野井春絵
1973年生まれ、愛知県出身。ライター、インタビュアー。同志社女子大学卒業、金城学院大学大学院修士課程修了。広告代理店、編集プロダクション、広報職を経てフリーに。WEBメディアや雑誌でタレント・文化人から政治家・ビジネスパーソンまで、多数の人物インタビュー記事を執筆。湘南と信州で二拠点生活。ペットはインコと柴犬。(撮影:殿村誠士)
この記事をシェアする
「山野井春絵「友達になって後悔してる」」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら