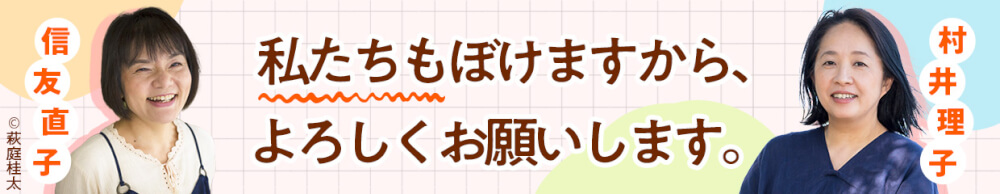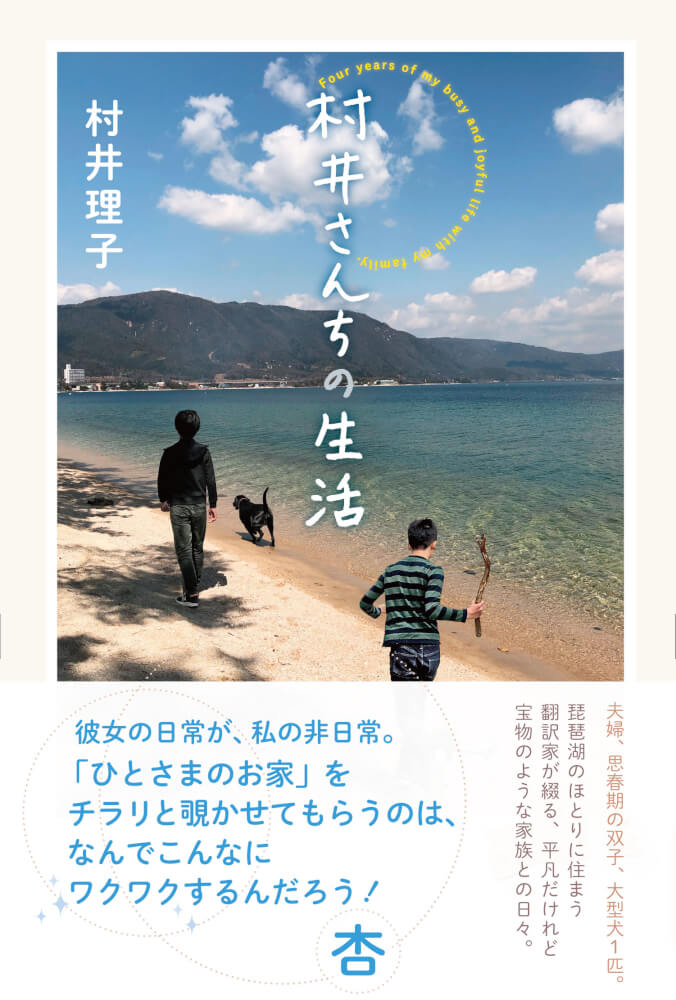2025年3月28日
信友直子×村井理子「私たちもぼけますから、よろしくお願いします。」
後篇 目指すは「かわいらしい」年寄り
翻訳家・エッセイストの村井理子さんと映画監督の信友直子さんの「親の介護」をめぐる対談後篇。親が歳を重ねていく姿を村井さんは文章に、信友さんは映像に残しています。「親を記録する」という行為、そして自分たち自身がどのように歳を重ねていくべきか、まだまだ話は尽きません。
(「前篇 認知症になってわかった「本来の姿」」はこちら)
親の「声」を残す
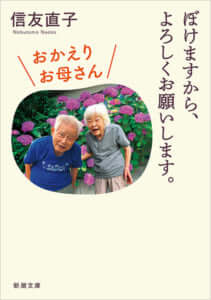
村井 映画の中で、まだお元気だったころのお母さんが買い物しているところを遠くから撮影しているシーンがありましたね。スーパーではなく、商店街のお店を一軒ずつ回る買い物の仕方を、うちの母もしていたなと懐かしくなりました。帰り道、日傘をくるくる回しながら、ゆったりと歩いて来られて……カメラの存在に気づいてちょっと照れ笑いをして。とても素敵な場面です。
信友 あのシーンは、じつは約20年前、私が乳がんになったときのドキュメンタリーを撮影していたときのものなんです。自分で撮ったのではなく、別のカメラマンに撮影を依頼していたのですが、テープが余ったからといって、ふだんの生活を撮ってくれたようなんです。コロナ禍で外出が制限されていたあいだ、仕方なく家の大掃除をしていて偶然発見しました。
村井 それはとても貴重ですね。私は父親を10代の時に亡くしていて、もう声も思い出せません。とはいえ、親が元気だったとしても、子どもの写真ばかり撮って、親を撮ろうとは思わなかったかもしれません。
信友 今は誰でもスマホで動画が手軽に撮れるんだから、撮れるうちに撮っておいたほうがいいと思いますよ。本当にいい思い出になります。
確か本で読んだのですが、人の記憶を呼び起こすのに一番強い感覚は嗅覚、においで、二番目は聴覚だそうです。動画に撮れば、声が残りますよね。写真でもいいんですが、後から動画を見返すと声をきっかけにいろいろと懐かしく思い出せる気がします。
村井 7~8年前に母が亡くなったのですが、その母の声が留守番電話に残っているんです。電話機ごと納戸に閉まってありますが、今はまだ生々しくて聞き返せないですね。家族がみんな死んでしまっているという大きな欠落を感じます。信友家の映画を繰り返し見てしまうのは、もしかしたら自分の家族をそこに重ね合わせてしまっているのかもしれません。
信友さんは仕事柄、何でも映像に収めようという習性があるかと思いますが、私も写真やメモで毎日大量の記録を残しています。兄が突然死した部屋の写真は3000枚ほど撮っていました。
信友 なんでもネタにしてやろうと思ったりしませんか?
村井 しますします! 私たち、業が深いかもしれませんね(笑)。兄が亡くなった時、まずは宮城県塩竈市に向かったのですが、その行きの新幹線ですでにメモを書き始めていました。ただでは転びません。
信友 私も乳がんになってから撮影を始めたときに、やはり「ただでは転ばないよね」と言われました。
村井 「よくそんなこと書けるね」とも言われますが、書いてよかったなと思うんですよね。書かないと全部忘れてしまうんです。両親や兄との思い出も。
信友 映像に定着させていてよかったと私も思います。撮っていても、映画に入れなかったシーンはすでに忘れてしまっていますね。
村井 書くことで事態を俯瞰で見ることができている気がします。対象から離れることで、ちょっと冷静になれるというか。
信友 カメラを向けることで第三者の目を持てるようになりますね。それからカメラは回していれば撮れますが、文章にすることで、その時の自分の気持ちを表すにはどんな日本語がいちばんしっくりくるのか、どんな気持ちを抱えていたのかを言語化する作業が発生しますから、気持ちを整理するためにも重要だと思います。
村井 必ずしも文章を発表しなくてもいいと思うんです。書くのが苦手だという方もいらっしゃるので、まずは短い日記でもいいから、記録に残すことをおすすめします。介護生活は長いから、後から読み直すと、その時は分からなかった変化に気づくこともありますし。
信友 映画を見返していると、そのシーンを撮っていた時の自分の気持ちをありありと思い出すこともあります。たとえば、母が「自分がおかしくなってしまった」と私に訴える場面。母はものすごく小さい声で言ってるので聞こえないかもしれないのですが、「どうしてかね、大事なときに」と言ってるんですね。「せっかくあんたがおるのにね。どうしてわからんようになるんかね」と。その瞬間、私、涙がこみ上げたんです。私が呉に帰省しているときは母にとって「大事なとき」だったんだと気づいて。なのにそれまで私は仕事にかまけて、年に1回、お正月の時だけ、義務的にちらっと顔を出すばかりでした。なぜもっと頻繁に帰らなかったんだろう、なんて可哀想なことをしていたんだろう。そう思ったことを、今でもあの場面を見るたびに思い出します。
村井 その場面、覚えています。しかも、その後ろでお父さんはタラッタ~♪と鼻歌を歌いながら新聞を読んでるんですよね。こういうズレこそが日常の妙。ドラマだったら絶対そんな鼻歌は入らない。
もしも病気になった順番が逆だったら
村井 信友家も我が家も、しっかり者の妻のほうが先に認知症を患って、夫がそれを支える姿が共通しています。もし病気になられたのがお父さまだったらどうなっていたと思いますか?
信友 もし父が先に認知症になっていたら、すんなり母と私がタッグを組んで介護したと思いますが、何の発見もなく、映画にはなっていなかったかもしれません。母が病気になったから、父は代わりに家事を担うようになり、社交性も出てきたように思います。
村井 うちの義父もそれまで家のことはすべて義母任せでしたが、張り切って家事をするようになりましたね。歳を重ねても人間は成長できるし、変わることができると教えてもらいました。
信友 父も昔は本当につまらなくて、なんでこんな人とお母さんは結婚したんだろうと思っていたくらいです。ご近所づきあいもすべて明るく社交的な母が窓口になって、父は母に頼りっきりで黙っているだけでしたから。
村井 義父が認知症になっていたら、義母は張り切って完璧に自分で介護をこなそうとしたでしょうね。私にも手伝わせなかったと思います。「お義父さんは私の恋人だから!」という想いの強い人なので。介護サービスにすら頼らなかったんじゃないかな。義父が脳梗塞を起こしたことがあり、今思えばその時すでに義母は認知症を発症していたのではないかと思うのですが、周りの助けをすべて拒否していましたからね。まさか順番が逆になってしまうとは。
信友 ヘルパーさんが台所に入ることすら、うちの母は嫌がっていましたから、村井さんのお義母さんのお気持ちは分かります。助けを借りればいいのに、もうできないでしょ?と家事能力を否定されているような気持ちになってしまうんでしょうね。それまで完璧にこなしていたから余計に。だから、「誰の助けも借りない!」と頑なになってしまう。
歳を取ったら安心して「社会に甘える」
村井 うちの義父母は、本当は一刻も早く特養に入った方が生活の質はグッと上がると思うんです。でも本人たちがそれはイヤだ、家にいたいというのであれば、それを尊重せざるを得ない。
信友 まさに同じ状態です。父は「あんたは東京で好きな仕事をしんさい」って言ってくれますが、やはり一人では心配なので、結局呉にいる時間を長くせざるを得なくて……私は海外旅行が大好きで以前は年に2回は行っていたのですが、もう何年も行けていません。でも父の「住み慣れた家で暮らしたい」という気持ちも、痛いほどよく分かりますし……。
村井 ゴールが見えないのが介護のツライところですね。お父さまには「年寄りの社会参加は『社会に甘えること』だ」という名言がありますね。100歳のお誕生日での目標として「みんなにかわいがってもらえるような、かわいらしい年寄りになる」ともおっしゃっていましたが、すでに十分可愛らしいし、甘えられると思うのですが。
信友 私もその発言を聞いたときに素晴らしい! と思ったのですが、いざとなると「そうなこと言うたかいのう」って全然社会に甘えてくれなくて。デイサービスに行けば、職員さんもチヤホヤしてくれるんだし、行けばいいじゃないって言うんですけどねえ。病気ならともかく、体のどこも悪いところはないから、家にいるっていう理屈なんですよね。
周りが助けようとしてくれている時は、周りから自分が「大丈夫ではない」ように見えている時だ。そういう時に助けを断っても心配かけるだけだから、そういう時は委ねるって言っていたはずなのに。
村井 社会には制度がしっかり整っているんだから、そこに安心して甘える。そして甘えても嫌がられない可愛げを持った年寄りになる。とても大事なことだと思います。お父さまは「可愛さの塊」だと思いますが、その可愛げは先天的なものなんでしょうか。
信友 いえ、父は努力して可愛くなったんだと思います。周りのみんなに「ありがとうね」と言うことを自分に課しているみたいです。昔は不愛想なほうでしたが、社会とのハブを担っていた母が立ちいかなくなったころから、母の代わりに周りの人にも挨拶をしたり、社会とのつながりを維持しようとした。そのおかげで、今は近所の方々にもよく声をかけていただけるようになったのだと思います。
村井 90歳を過ぎて、そこに自覚的になって変革しようとしたのが本当に素晴らしいです。
信友 周りの方々も、100歳超えたおじいちゃんに「ありがとう」って言われると、かえってうれしいみたいなんですよね。うれしいというか、ありがたいみたいな(笑)。でもその反応を狙っているわけではなくて、心から言ってるのだとは思います。実の娘にはあまり感謝の言葉は言ってくれなくて、ムスッとしていることも多いのですが。
うちの父は早々に出世を諦めたサラリーマンだったようです。当時としては珍しく家庭第一で、飲み会に誘われても断って真っすぐ帰宅するから「変わり者」扱いされていたようです。だからこそ、妙なプライドやわだかまりもなく、周りの人ににこにこと頭を下げられるのかもしれませんね。
村井 勤めていた会社でエライ役職についていた男性が歳を取ると、その偉そうな雰囲気のまま振舞ってしまうので、周りとうまくいかなくなるという話はわりとよく聞きます。施設に入っても、職員の方に対して高圧的に命令したり、言うことを聞かなかったり……。
うちの義父は料理人だったせいか、先日お試しで入ったショートステイで「食事提供のタイミングが遅い」「職員の笑顔が足りない」と文句を言っていたので、思わず「旅館じゃねえんだよ!」とツッコミそうになってしまいました。
信友 それまでどう生きてきたのかが歳の取り方にも直結しますよね。父のように穏やかに暮らせるのであれば、100歳過ぎまで長生きするのも悪くないなと思えるようになりました。介護ってどうしてもネガティブなイメージが付きまといますよね。とくに私は一人っ子なので、すべてを一人で背負わなければいけないと思っていましたし、逆に兄弟がいたらいたで、助け合うこともあれば揉めることもあるでしょう。ただ、介護とは親の生き方を見つめ直すことでもあって、そのなかで勉強になることも多いですし、生きていく上でのヒントなどたくさん学べる豊かな時間でもあると思います。今は娘業を味わい尽くす時期だと感じています。
村井 うちの義父母には、「人が老いていくとはどういうことか」をたっぷり教えてもらった気がします。とくに認知症になったとき、人間がどのように変わっていくのかを見せてもらった。認知症が、こんなに悲しく残酷な病気だって知らなかったし、ある程度自分の行く末にも覚悟が芽生えました。
50代で老後について考えるきっかけをもらったので、今すごい勢いで身辺整理をしています。相当スッキリしましたが、まだまだこの先も続けていくつもりです。いつどうなってもよいという心構えができた気がします。それがお義父さんお義母さんからもらった最大のプレゼントですね。
信友 肝が据わっていてかっこいいですね! 覚悟を決めて、周りに感謝できるかわいらしい年寄りになりましょうね。
村井 「私たちもぼけますから、よろしくお願いします。」なんてね。
(おわり)

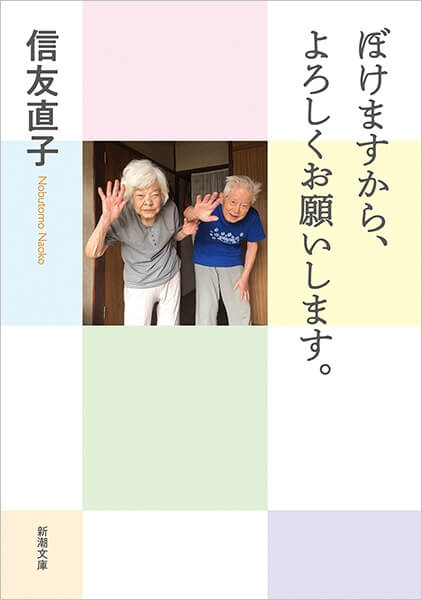
信友直子『ぼけますから、よろしくお願いします。』(新潮文庫)
2022/08/29
公式HPはこちら。
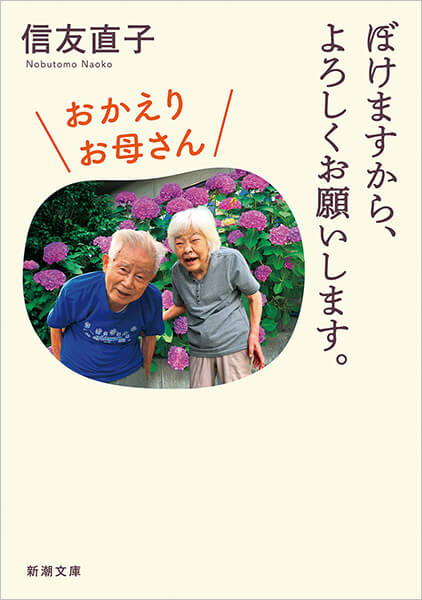
信友直子『ぼけますから、よろしくお願いします。 おかえりお母さん』(新潮文庫)
2024/12/24
公式HPはこちら。
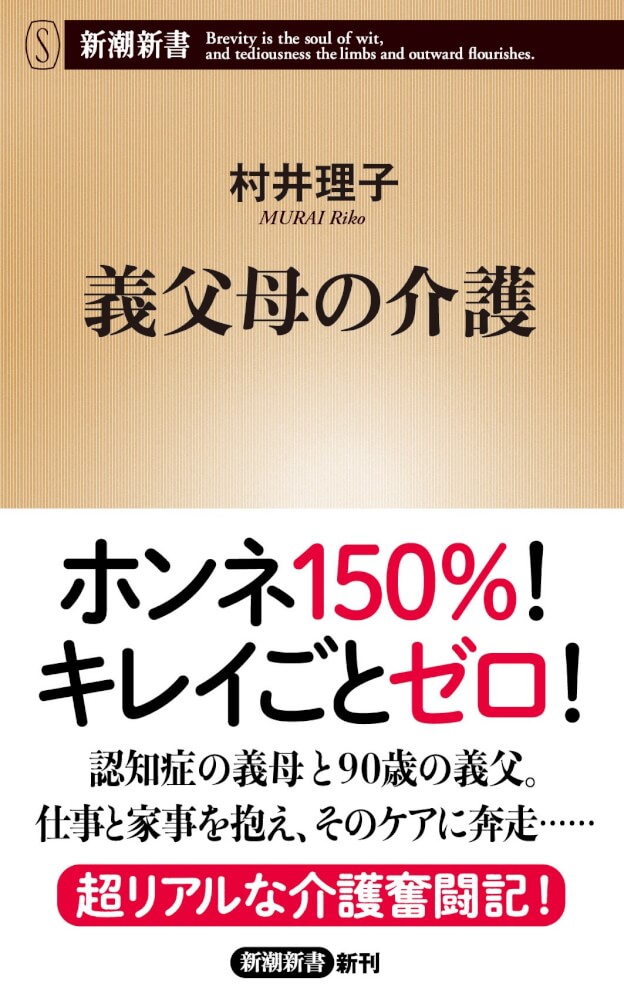
村井理子『義父母の介護』(新潮新書)
2024/07/18
公式HPはこちら。
-

-
信友直子
1961(昭和36)年、広島生れ。映像作家。東京大学文学部卒。2009(平成21)年、自らの乳癌の闘病記録である『おっぱいと東京タワー〜私の乳がん日記』でニューヨークフェスティバル銀賞、ギャラクシー賞奨励賞などを受賞。2018年には、初の劇場公開作として両親の老老介護の記録『ぼけますから、よろしくお願いします。』を発表し、令和元年度文化庁映画賞文化記録映画大賞などを受賞。2022(令和4)年には続編『ぼけますから、よろしくお願いします。〜おかえりお母さん〜』が公開された。著書に『ぼけますから、よろしくお願いします。』『ぼけますから、よろしくお願いします。 おかえりお母さん』『あの世でも仲良う暮らそうや 104歳になる父がくれた人生のヒント』などがある。
-

-
村井理子
むらい・りこ 翻訳家。訳書に『ブッシュ妄言録』『ヘンテコピープル USA』『ローラ・ブッシュ自伝』『ゼロからトースターを作ってみた結果』『ダメ女たちの人生を変えた奇跡の料理教室』『子どもが生まれても夫を憎まずにすむ方法』『人間をお休みしてヤギになってみた結果』『サカナ・レッスン』『エデュケーション』『家がぐちゃぐちゃでいつも余裕がないあなたでも片づく方法』など。著書に『犬がいるから』『村井さんちの生活』『兄の終い』『全員悪人』『家族』『更年期障害だと思ってたら重病だった話』『本を読んだら散歩に行こう』『いらねえけどありがとう』『義父母の介護』など。『村井さんちのぎゅうぎゅう焼き』で、「ぎゅうぎゅう焼き」ブームを巻き起こす。ファーストレディ研究家でもある。
この記事をシェアする
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 信友直子
-
1961(昭和36)年、広島生れ。映像作家。東京大学文学部卒。2009(平成21)年、自らの乳癌の闘病記録である『おっぱいと東京タワー〜私の乳がん日記』でニューヨークフェスティバル銀賞、ギャラクシー賞奨励賞などを受賞。2018年には、初の劇場公開作として両親の老老介護の記録『ぼけますから、よろしくお願いします。』を発表し、令和元年度文化庁映画賞文化記録映画大賞などを受賞。2022(令和4)年には続編『ぼけますから、よろしくお願いします。〜おかえりお母さん〜』が公開された。著書に『ぼけますから、よろしくお願いします。』『ぼけますから、よろしくお願いします。 おかえりお母さん』『あの世でも仲良う暮らそうや 104歳になる父がくれた人生のヒント』などがある。
-

- 村井理子
-
むらい・りこ 翻訳家。訳書に『ブッシュ妄言録』『ヘンテコピープル USA』『ローラ・ブッシュ自伝』『ゼロからトースターを作ってみた結果』『ダメ女たちの人生を変えた奇跡の料理教室』『子どもが生まれても夫を憎まずにすむ方法』『人間をお休みしてヤギになってみた結果』『サカナ・レッスン』『エデュケーション』『家がぐちゃぐちゃでいつも余裕がないあなたでも片づく方法』など。著書に『犬がいるから』『村井さんちの生活』『兄の終い』『全員悪人』『家族』『更年期障害だと思ってたら重病だった話』『本を読んだら散歩に行こう』『いらねえけどありがとう』『義父母の介護』など。『村井さんちのぎゅうぎゅう焼き』で、「ぎゅうぎゅう焼き」ブームを巻き起こす。ファーストレディ研究家でもある。
連載一覧
対談・インタビュー一覧
著者の本

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら