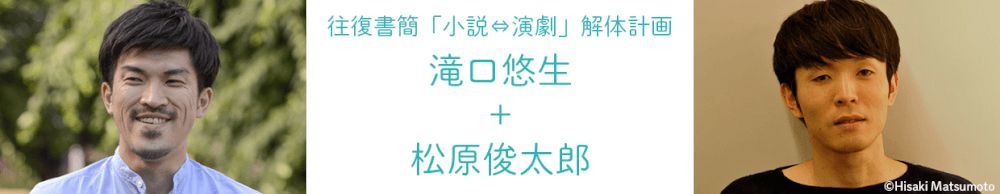滝口悠生→松原俊太郎
いかがお過ごしでしょう。僕はお盆過ぎからアメリカのアイオワに来ていて、ちょうど一週間が経ちました。ほとんど英語が聞き取れないものですからとてもくたびれて、刺激もたくさんですが、まだいろいろと順応の最中という感じです。というわけで締切を2日(アメリカの日付だとまだ1日……!)過ぎて、ホテルでこれを書いています。すいません。
これまでのやりとりを継ぐかたちで、前回もいろんな話題が出ましたが、最後の方に出た自作(『高架線』)の演劇化の話からはじめてみようと思います。とりこぼした問いや疑問は、そのうち拾えるでしょう。
自分の書いた小説が演劇として上演されるというのは、当然ながら書き手として特別な経験でした。僕は脚本・演出の小田尚稔さんには何も注文せず、改変でもなんでも自由にどうぞとお伝えしました。企画・プロデュースの佐々木敦さんも小田さんの制作にはノータッチです。結果的に小田さんはかなり「原作に忠実」と言ってよい演劇をつくったのですが、ここで「忠実」というのは、物語の筋とか、モノローグの語り手が交代していく構成において、という意味であり、小説と上演された演劇が似ているか、と言ったらそういうわけでもないんですよね。
僕は原作者としても、いち観客としても上演を楽しみましたが、原作者として(あるいは小説家として)気づけたことがあるとすれば、小説と演劇では、同じ言葉が同じ属性のキャラクターによって語られても、全然違う性質になるんだな、ということでした。これは意味内容とか言葉の印象が、ということではなく、その声の様相とか発話の構え、とでも言えばいいでしょうか。演劇の語りが、実際に声を発するのに対して、小説の語りというのは、むしろ誰かの声を聞くようなことなのではないか、と僕は上演を観ながら思いました。もう少し言葉を補うと、小説の文章というのは、聞こえた誰かの声、という感じがすると思いました。これは松原さんが言っている演劇における「異化」とどこか響くものでしょうか。そして、戯曲を書く際に「聞かれることを大前提に」書いていた、という発見と何かつながるものがあるでしょうか。という問いを投げてみます。
小説にはト書きも上演も物理的な声も身体もありません。文章であるということの制限は決して少なくないですが、演劇とくらべ「前提」は多くないように思います。読まれることさえ「前提」なのかどうか微妙なところです。そこで言葉をつまらなく響かせないために小説家ができることは、用いる言葉の操作以外の何物でもないのですが、じゃあそれをどう行っているかと考えると、小説家が主体的に改稿したり推敲したり……いやそういうことではないよな、というのが実感です。
そこに、あるいはどこかに、言葉を発しようとしている誰かがいて、その人の声を聞こうとする。聞こえにくいその声を聞こえるように工夫をする、という感じ……。ラジオの受信状況が悪い時に、アンテナをちょっと動かしたり、受信機の向きを変えたり、チューニングの目盛りを微妙に調節したり、あんな感じの作業をイメージしているのですが、それはあくまで言葉や表現の処理(もちろん実際的にはそういう作業なのですが)ではなく、姿勢を変えるとか、耳抜きをするみたいな、身体的でどこか当てずっぽうな感じがあります。ラジオのたとえはよくなかったかも、といま思ったのは、ラジオだと発信元も受信できた時に聞こえる音声もはっきりし過ぎていて、スピーカーのハウリングとか、テルミンの演奏とか、なんかそういうたとえの方がいいのかもしれません。これは僕が小説において大事だと思っている「思い出す」ということとも近い感じだと思います。思い出せることを思い出すというよりは、事故みたいに、偶然に、思い出せなかった何かの記憶を思い出す。正確さや、それが本当に自分の記憶かどうかは、わりとどうでもいいと思います。
松原さんが前回〈異化を意図して書いているのではなく、自分が異化されながら書いている感覚です〉と書かれてましたが、小説家にとっては、書き手であると同時に、仮想的に語り手として異化される(これを受け身で言いたくなるのがやっぱりよくわかるし、大事なとこだと思います)というのが小説との関わり方と言えるのかもしれません。
で、ここからが本題というか、松原さんが書いていた前回の内容へと戻っていくのですが、紋切り型から逃れ、かつ「言い方」を気にしている、という言葉がありましたよね。これをもう少し詳しく訊いてみたいです。もしかしたら僕が上で書いたようなラジオとかハウリングみたいなことなのかもしれないし、全然違う、もっと具体的な作業なのかもしれない。「愛する人」に頼らず、紋切り型から逃れてその場限りの意味を持つ「言い方」を探る、というのは、松原さんにとってどういう作業なのでしょう。たとえばそれが演出家による演技への指示であるならまだイメージができるのですが、演出をされない松原さんは紙上で上演をしてみながら戯曲を書く、ということでした。松原さんの戯曲は、どうしてこれがこう書かれたのか、という問いや疑いを含む、というかその問いや疑い自体を動力とするような文章だと思います。その問いに対する答えがあるのかはわからないし、なくてもいいと思うのですが、たとえば「言い方」を探って探って、これ、と決める時に、松原さんの判断あるいは決断のもとには何があるのか。これは「終わり方」ともつながる話のように思います。具体的でもいいですし、抽象的な説明に言葉を費やしてもらっても構いません。
僕も小説の終わり方のことはずっと気になっています。これは京都のトークでも話した気がしますが、読んでいて終わり方に納得のいく小説というのは本当に少ないです。終わることへの疑問とか抵抗があるということなんだと思います。自分の作品の終わり方もなにか確信があるわけでなく、それじゃこれで、と切り上げる感じになるようにと意識してはいるのですが、何をもって終われるのか、うまく説明ができません。映画も同じで、映画の終わり方といえばキアロスタミ監督の「ライク・サムワン・イン・ラブ」を観ていた時、ある場面で、ここでいきなり終わったら最高だな(でも続くんだろうな)と思って観ていたら本当にそこで終わって感動しました。ですが、小説でも、映画でも、なかなかそんな終わり方には出会えません。なぜなのでしょうか。
こっちは暑いと聞いていたんですが、気候以前にどこもかしこも冷房がよく効いてて寒いです。そんなアイオワからでした。なかなか野菜を食べる機会がなくてビタミン不足を感じています。
8月26日 滝口悠生
『演劇計画Ⅱ -戯曲創作-』
委嘱劇作家:松原俊太郎、山本健介(The end of company ジエン社)
演劇計画Ⅱアーカイブウェブサイト http://engekikeikaku2.kac.or.jp/
京都芸術センター http://www.kac.or.jp/
KAC S/F Lab. オープンラボvol.6「創作と批評」
公開された松原俊太郎らの委嘱戯曲第二稿を読解・批評するオープンラボを開催します。
ゲスト:大森望(翻訳家、書評家)、平倉圭(横浜国立大学准教授)
委嘱劇作家:松原俊太郎、山本健介(the end of company ジエン社)
日時:2018年9月27日(木)19:00~21:00
会場:京都芸術センター 大広間
入場無料、要事前申込
http://www.kac.or.jp/events/24109/
-

-
滝口悠生
1982年、東京都八丈島生まれ。埼玉県で育つ。2011年、「楽器」で新潮新人賞を受賞してデビュー。2015年、『愛と人生』で野間文芸新人賞を受賞。2016年、「死んでいない者」で芥川龍之介賞を受賞。2022年、『水平線』で織田作之助賞を受賞。2023年、同書で芸術選奨文部科学大臣賞を受賞、「反対方向行き」で川端康成文学賞を受賞。他の著書に『寝相』『ジミ・ヘンドリクス・エクスペリエンス』『茄子の輝き』『高架線』『やがて忘れる過程の途中(アイオワ日記)』『長い一日』『いま、幸せかい? 「寅さん」からの言葉』『往復書簡 ひとりになること 花をおくるよ』(植本一子氏との共著)『ラーメンカレー』『三人の日記 集合、解散!』(植本一子氏、金川晋吾氏との共著)等。
-

-
松原俊太郎
作家。1988年熊本生まれ。2015年、処女戯曲「みちゆき」で第15回AAF戯曲賞大賞受賞。2019年、『山山』で第63回岸田國士戯曲賞受賞。他の作品に戯曲「忘れる日本人」、「正面に気をつけろ」(単行本『山山』所収)、小説「またのために」など。
この記事をシェアする
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 滝口悠生
-
1982年、東京都八丈島生まれ。埼玉県で育つ。2011年、「楽器」で新潮新人賞を受賞してデビュー。2015年、『愛と人生』で野間文芸新人賞を受賞。2016年、「死んでいない者」で芥川龍之介賞を受賞。2022年、『水平線』で織田作之助賞を受賞。2023年、同書で芸術選奨文部科学大臣賞を受賞、「反対方向行き」で川端康成文学賞を受賞。他の著書に『寝相』『ジミ・ヘンドリクス・エクスペリエンス』『茄子の輝き』『高架線』『やがて忘れる過程の途中(アイオワ日記)』『長い一日』『いま、幸せかい? 「寅さん」からの言葉』『往復書簡 ひとりになること 花をおくるよ』(植本一子氏との共著)『ラーメンカレー』『三人の日記 集合、解散!』(植本一子氏、金川晋吾氏との共著)等。
連載一覧

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら