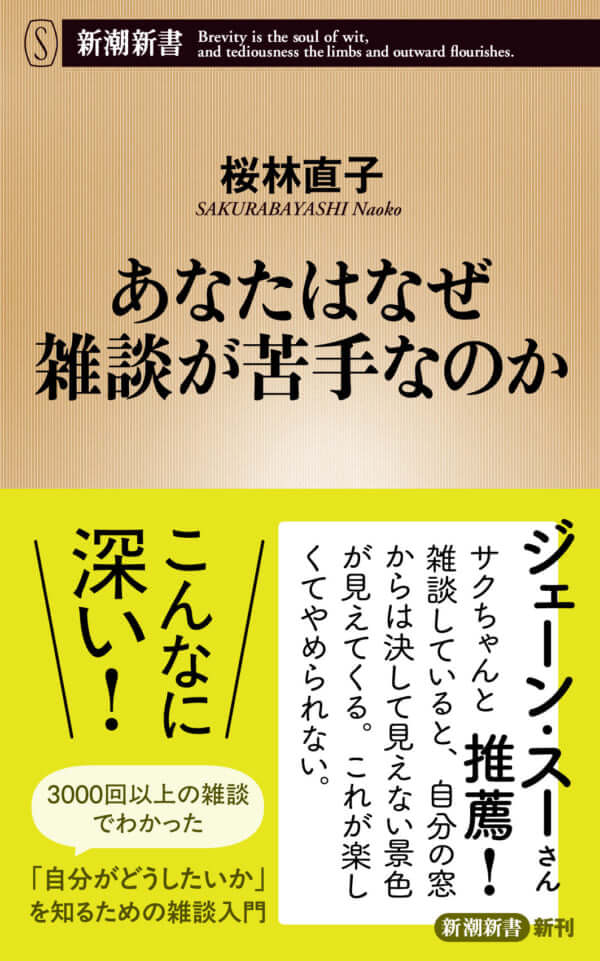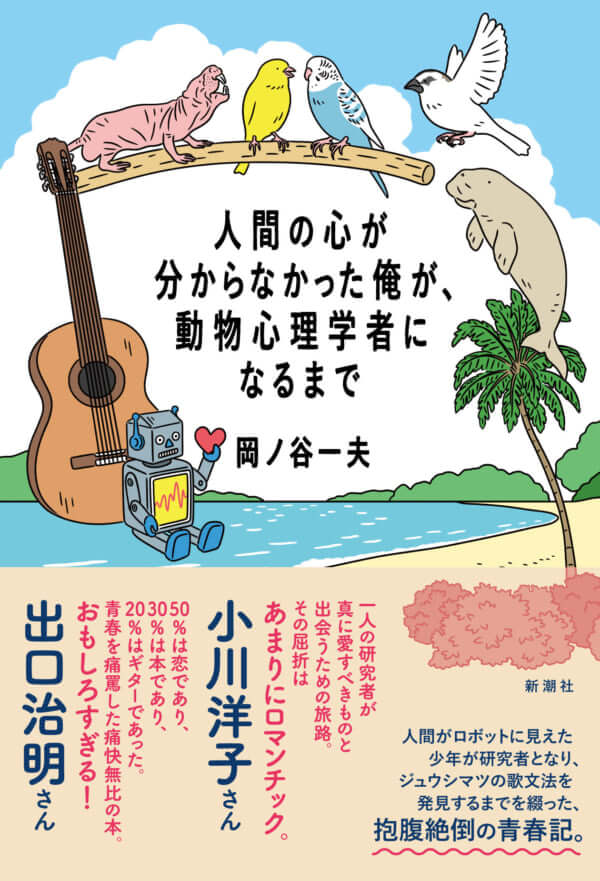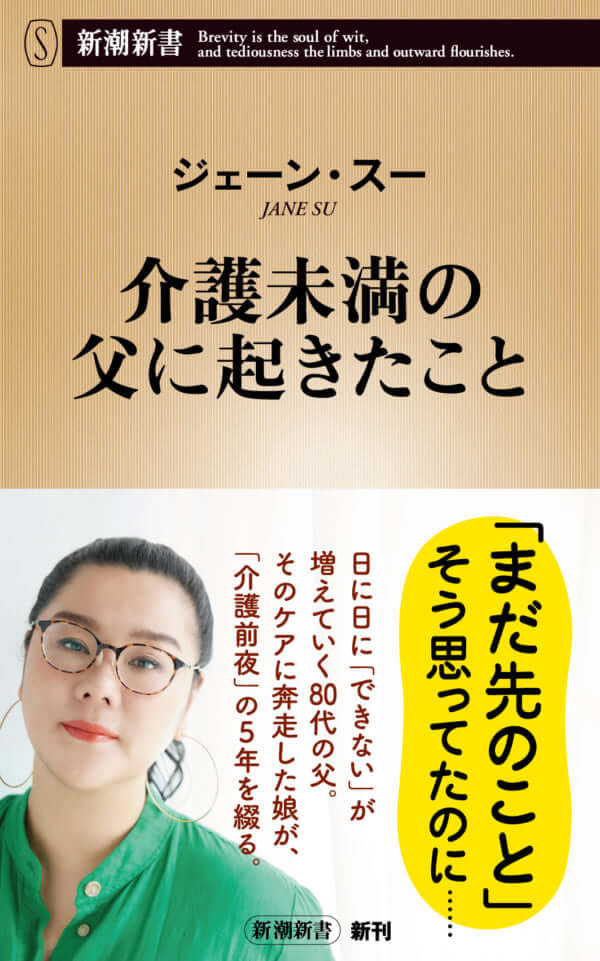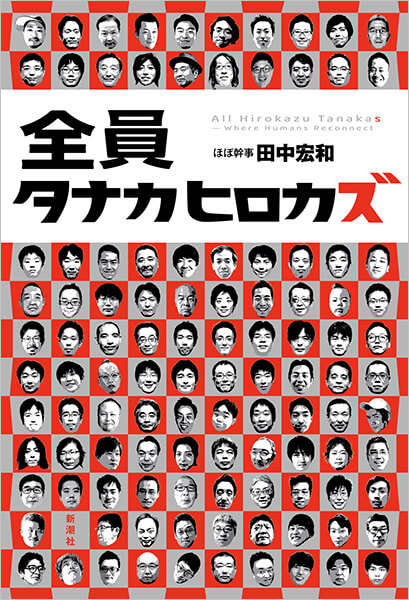「クラシック」一覧
-
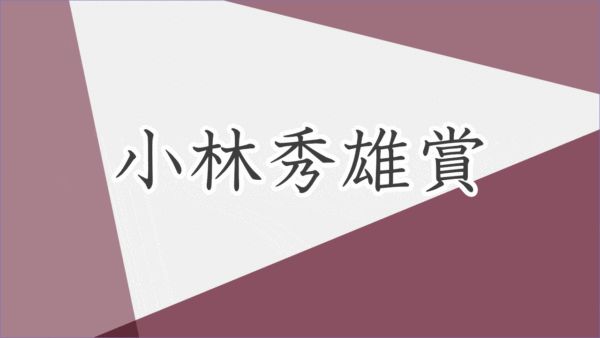
-
- こころ
- まなぶ
- 評論
第20回(2021年度)小林秀雄賞 受賞……
8月26日午後、一般財団法人 新潮文芸振興会の主催による「小林秀雄賞」「新潮ドキュメント賞」選考会がオークラ東京にておこなわれ、小林秀雄賞受賞作品が決定しましたので……
-
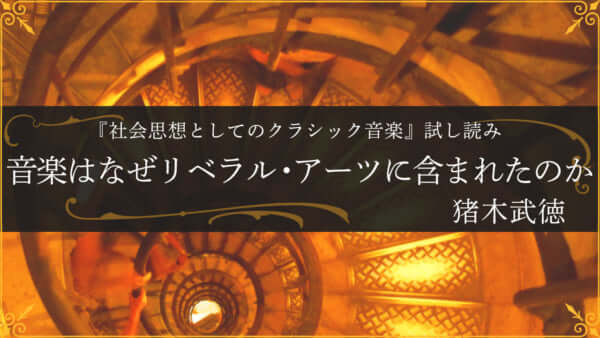
-
- こころ
- まなぶ
- 評論
音楽はなぜリベラル・アーツに含まれたのか
音楽は「生の根幹」に結びついている 音楽は、少し贅沢な、余った時間の娯楽だとみなされることがある。確かに気持ちに余裕が生まれれば、ふと音楽が聴きたくなるものだ……
-
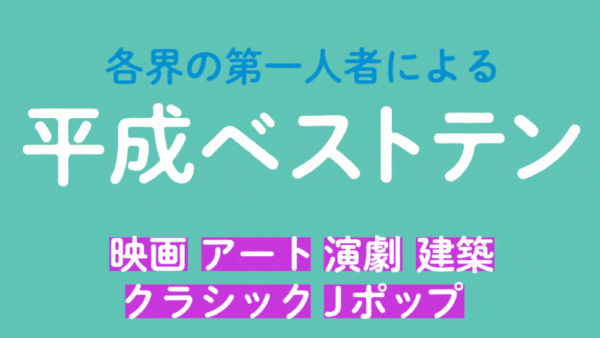
-
- こころ
- エッセイ
平成クラシックベストテン
平成はポスト・モダンが徹底された時代だった。そこでは芸術を担うご立派な近代的個人が立場を失ってゆき、何もかもがキッチュに取って代わっていった。その意味での日本……
-

-
- こころ
- 世の中のうごき
- ルポ
「態度的価値」としての音楽
ドイツ滞在の最終日になってようやく抜けるような青空に恵まれた。 3月14日、この日の午前中はベルリン独日協会の厚意により、市内のガイドツアーが実現した。これまで……
-

-
- こころ
- 世の中のうごき
- ルポ
震災から5年の日の演奏会で
ドアを開けて中に入ると、モーツァルトの「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」の勢いあふれる響きが耳に飛び込んできた。 ベルリン・フィルハーモニーでの大舞台を終……
-
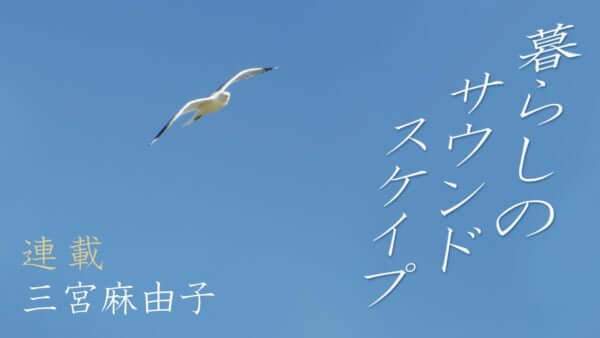
-
- くらし
- こころ
- 思い出すこと
- エッセイ
体感で聞く音楽
小学校三年生くらいのとき、ピアノ曲「ラ・カンパネラ」と出会ったことで、私の音楽の聞き方が決まったような気がする。 私は四歳で失明した直後から現在まで、ピアノ……
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥

ランキング
「考える人」から生まれた本





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら