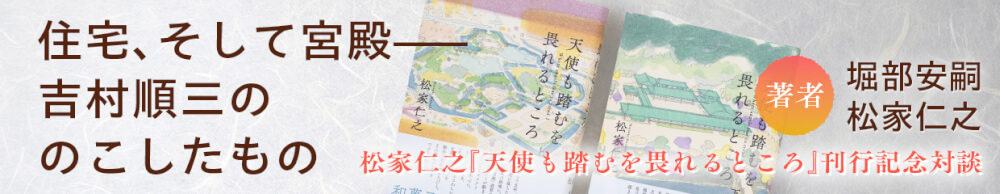2025年6月10日
松家仁之『天使も踏むを畏れるところ』刊行記念
住宅、そして宮殿――吉村順三ののこしたもの
1945年5月、東京大空襲に次ぐ大規模な山の手空襲により、皇居内の明治宮殿が焼失しました。松家仁之さんの新作長篇『天使も踏むを畏れるところ』は、その23年後、「新宮殿」が完成するまでの物語。主人公の村井俊輔には、実際に「新宮殿」造営を手がけた名建築家・吉村順三が投影されています。史実をもとに、この国家的プロジェクトをめぐる人間ドラマを描きだした本書について、建築家・堀部安嗣さんと著者の松家仁之さんが語りあいます。
思い出のなかの吉村順三
松家 堀部さんと吉村さんの出会いはいつ頃でしょうか。
堀部 僕が大学生だったときです。バブル経済の最盛期でした。うちの大学にはインターンシップの授業があって、当時は売り手市場だったから、みんな行きたい企業を簡単に選ぶことができました。でも、僕にはとくに志望する会社がなくて。ぼんやりしているのを見かねた指導教官に、吉村順三のところに行ってきなさいと言われました。そう言われても、吉村順三が誰だかわからない(笑)。バブルのような華やかな時代には、吉村さんのような質素な品格を持つ建築表現は忘れられるんですよ。結局、大学の先生に言われるがまま、吉村さんの事務所にやっかいになりました。
松家 目白の事務所ですね?
堀部 はい。僕は模型を作るのが下手くそだったんです。それでも一生懸命作ったら、スタッフの方が吉村さんに、お見せできるようなものではないんですがといいながら見せてくれて。吉村さんは、「なかなかハートのあるいい模型じゃないか」と言ってくださったんです。それで一気に心を鷲掴みにされましたね(笑)。
松家 吉村さんには一度だけ、お会いしたことがあります。そのときの吉村さんのたたずまいは記憶に鮮明に残っています。1990年だったと思いますが、当時私は「小説新潮」編集部にいて、「日本人の仕事場」という連載を担当していました。さまざまなジャンルでクリエイティヴな仕事をしている人たちの仕事場を訪ねて、篠山紀信さんに撮影してもらうという巻頭のカラーグラビア企画です。
あるとき、篠山さんに「建築家の吉村順三さんを撮っていただきたいのですが」と恐る恐る打診してみたんですね。恐る恐るというのは、「誰それ?」と言われるかもしれないと危惧したからです。篠山さんは快諾してくれました。それどころか、「吉村さんの一番弟子が、私の家を設計してくれたんだよ」とおっしゃって、びっくりしました。一度だけ篠山さん宅の玄関先を訪ねたことがあったので、ああなるほどそうだったのか、と腑に落ちました。
一緒に目白の事務所に行き、撮影したあと、所長室で少しだけお話をうかがうことができました。いくつかの話題が出たんですが、一つ忘れられないのは、建築というのは向こう三軒両隣を意識しないとダメだとおっしゃったことです。ちょうど都庁舎が竣工となる前後で、そのことについてうかがった流れで出た言葉でした。乱暴な言い方になりますが、ポストモダンな建築には辺り一面をすべてならしてしまって、そこにあった土地の記憶をいったんゼロにした上で築かれるものが多いのではと思います。吉村さんがそれとは正反対の建築観を述べられていたのがとても印象に残っています。
堀部 言ってみれば当たり前のことなんですよね。近代建築家がわざわざ言わないようなことを発言するのが吉村さんのすごいところだと思います。僕も若い頃、吉村さんがいい住居というのは家事が気持ちよくできる家のことなんだよと書いているのを読んで、地味なことを言う人だなと思いました(笑)。だけど今になってみると、吉村さんが言わんとしたことがよくわかる。家事が快適にできる家に住むと、人生が豊かに思えるんですよね。当たり前のことを当たり前に言い続けてきた吉村さんにはアーキテクトとしての本当の力強さがあると思います。
船のような新宮殿
松家 吉村さんは設計のディテールについて何か質問されても「そうしたほうが気持ちいいだろう?」と答える場合が少なくなかったようです。家事が気持ちよくできる、というのも同じですね。そこで思い出されるのが天井高のことです。吉村さん設計の住宅は、寝室やキッチンなどそれぞれの空間で天井の高さが異なるんですよね。機能が十全に果たされた合理的な天井高がある。それが満たされれば、その空間にいる心地よさが生まれる。つまり吉村さんの設計は人間のスケール、合理性と切り離せないものになっているわけです。
しかし、住宅と新宮殿の設計では、スケールがまったく異なります。仮に堀部さんが吉村さんだったとしたら、新宮殿の造営という大規模な建築を、それまでやってきたことの延長線上で考えられるものだと思いますか。それとも頭を切り替えないとできないものなのか。
堀部 うーん、どうでしょう。やったことがないのでなんとも……。ただ、確かに国家事業となると住宅設計とは作り方も関わる人もそこで必要な技術も全く異なりますが、住宅設計の経験があれば怖くはないような気がします。でも、その逆はない。大きな再開発や超高層ビルの建設を手掛けている建築家が小さな住宅を作るのは難しいと思う。建築は小は大を兼ねるのです。そう考えると、吉村さんが新宮殿造営というそれまでとはスケールの異なる仕事を前に困惑したことはなかったのではないでしょうか。
松家 堀部さんも住宅建築の規模を超えたお仕事を手掛けられていますよね。なかでもいちばん驚いたのは瀬戸内海の客船「ガンツウ」の設計です。あのクルーズ船の設計を堀部さんに依頼された方はなかなかの目利きだと思いました。どんな経緯で「ガンツウ」の依頼がきたのですか?
堀部 地域振興事業の会社からの依頼でした。以前、広島県の鞆の浦という街にある旅館の改築の話をいただいたことがあったのですが、そのときは話がまとまらずにまた機会があれば一緒にやりましょうと約束して別れたんです。それから二年後に、今度は船の設計をお願いします、と。乗り物の設計をしてみたいという気持ちはずっとあったし、さっきも言ったように、住宅建築を一生懸命やっていればどんなこともできるという自負もあったので、喜んで引き受けました。というか、あの船の設計はたぶん住宅設計をやっていなければできませんでしたね。
松家 「ガンツウ」は客室はもちろんですが、最上階のオープンデッキがほんとうにすばらしいですね。海に面して腰の高さのあたりにガラス張りの手すりがめぐらされていて、そこから海景を眺めることができるんです。その写真を見たとき(『堀部安嗣作品集II』平凡社)、新宮殿の長和殿のベランダが思いだされました。新年の一般参賀で天皇や皇后、皇族がたが広場に集まった人たちに手を振ってこたえる、新宮殿のベランダとどこか重なるイメージがありました。あとで調べてみたんですが、長和殿のベランダは百メートルあまりの長さがあって、「ガンツウ」のオープンデッキは七十五メートルほど。スケールも近いといえば近い。ここにも吉村順三がいるぞ、なんて思ったりしました。
堀部 実は僕の知り合いに現在の上皇上皇后両陛下の主治医をされていた方がいて、新宮殿についてのお話をうかがったことがあります。そして、皇居のなかも実際に案内してもらうことができたんです。
松家 え? 侍医の方がみずから案内してくれたんですか?
堀部 はい。宮内庁の許可を得てくださり、誰もいない皇居を見学させてもらいました。新宮殿の新年祝賀の儀を執り行う場所も見ましたが、船だな、と思いました。
松家 やっぱり。そうですよね。
堀部 ええ。つまり、広場に面する建物のスケール感はそれ以上足すことも引くこともできない絶妙な寸法でできている。そしていい意味できわめて機能的で即物的にできている。船って恣意性のない機能的で即物的なフォルムが基本となっていますがそれゆえに船を感じさせるのでしょう。
『天使も踏むを畏れるところ』には、1分の1の原寸大模型を作って確認している場面が書かれていましたね。
松家 実際に大広間棟(長和殿)の一部で、原寸1分の1模型を作った記録が残されています。天皇がベランダに立ったとき、広場はどのように見えるのか、逆に広場にいる人たちの目にはベランダに立つ人がどのように映るのかを入念に検討した形跡がある。それから屋根の勾配が広場からどう見えるか。屋根の勾配については吉村さんはかなりこだわっていたと思います。
堀部 屋根がどういう印象を与えるか、ということですね。
松家 はい。屋根は勾配がきつくなればなるほど、広場にいる人々にある種の威圧感を与える。だからあまり勾配をつけ過ぎるのもいけないのですが、勾配が足りないと今度はあざやかな緑青におおわれた銅板葺きが見えない。屋根の美しさを見せつつ、威圧感は抑える絶妙の角度を決めるのに苦心されたはずなんです。1分の1模型を作ったのは、その確認もあったのだろうなと私は想像しています。
言ったかもしれない言葉を想像する
堀部 作中では原寸大の模型の前に昭和天皇が立って広場からの見え方を確かめながら侍従と話をしていますね。
松家 原寸大の模型を天皇が視察したのは間違いないんです。ただ、どのようなことをおっしゃったのかまでは記録が残っていない。
堀部 小説のなかには昭和天皇が侍従と交わしていただろう会話が言葉にされていて、昭和天皇が表現しそうな言葉を松家さんが誠実に、そして慎重に選んでいることが伝わってきてこれこそが小説の醍醐味だと思いました。
松家 ありがとうございます。昭和天皇を描くにあたって参考にした本はいくつもあるんですが、なかでも驚いたのが、連載が始まって以降に岩波書店から刊行され始めた『昭和天皇拝謁記』(全7巻)です。あの本には初代宮内庁長官の田島道治が昭和天皇と執務室などのクローズドな場所でやりとりしていた会話が詳しく記されています。そこから浮かび上がってくるのは、記録映像などを通して私たちが見てきたのとはずいぶん異なる昭和天皇のイメージです。
もう一つ、これがなければ書けなかったのが昭和天皇の侍従をずっと務めていた入江相政の『入江相政日記』(文庫版全12巻)。この日記には『昭和天皇拝謁記』ほど踏み込んだ発言は出てこないのですが、私たちのイメージする昭和天皇の像がさらにもう一段、親密なかたちで浮かび上がってきます。このふたつの長大な記録があったので、昭和天皇だったらこういうことをおっしゃるのではないかと想像することができました。
堀部 天皇だけではなく、村井俊輔の言葉も吉村さんならきっとそう言うだろうなと思わせるものばかりでした。松家さんが実際にお会いされたときに表情や会話のテンポや空気感がインプットされたから、自然と村井の言葉として表現することができたんでしょうね。
松家 私が吉村さんに抱いている印象は30分ほどの短い撮影時間と撮影後の雑談の折に経験したものに過ぎませんが、そのときにベテラン俳優のような独特の語り口をお持ちの方だなと思いました。余計なことは言わないんだけど、肝心なことを最小限に切り詰めて、聞き手の心にスッと入ってくるような話されかたをするというか。さっき、「ハートのある模型じゃないか」と吉村さんに言われたとおっしゃいましたけど、まさにそうした端的な言葉づかいなんですね。そのイメージが短い面会の間で私のなかに埋め込まれて、それがフィクションとして結晶するタネのようなものになっているかもしれません。
堀部 昭和天皇に関しては実際にお会いされたことがないでしょうから、記録を頼りに書くしかないわけですよね。こういうことを言うだろうなと想像しながらも作者の勝手な解釈があってはならないという松家さんの慎重な書き方によって、とても透明感のある物語に仕上がったように感じられました。これは書くのが大変でしたよね。
松家 連載が始まって完結するまで4年かかりました。毎月、原稿用紙40枚から50枚、多いときで60枚ほど書いたので、上下巻で2200枚を超える分量になってしまって。書籍化する際に、かなり手を入れたのですが、これ以上は切り詰められませんでした。連載でなければ書けなかった分量ですね。
-

-
堀部安嗣
建築家、京都芸術大学大学院教授、放送大学教授。1967年、神奈川県横浜市生まれ。筑波大学芸術専門学群環境デザインコース卒業。益子アトリエにて益子義弘に師事した後、1994年、堀部安嗣建築設計事務所を設立。2002年、〈牛久のギャラリー〉で吉岡賞を受賞。2016年、〈竹林寺納骨堂〉で日本建築学会賞(作品)を受賞。2021年、「立ち去りがたい建築」として2020毎日デザイン賞受賞。主な著書に、『堀部安嗣の建築 form and imagination』(TOTO出版)、『堀部安嗣作品集 1994-2014 全建築と設計図集』『堀部安嗣作品集Ⅱ 2012–2019 全建築と設計図集』(平凡社)、『建築を気持ちで考える』(TOTO出版)、『住まいの基本を考える』、共著に『書庫を建てる 1万冊の本を収める狭小住宅プロジェクト』(ともに新潮社)など。
-

-
松家仁之
1958年、東京生まれ。1982年、新潮社に入社。1998年、「新潮クレスト・ブックス」を創刊。2002年、季刊誌「考える人」を創刊。「芸術新潮」編集長を兼務ののち、2010年に同社を退職。以降、作家として活動する。2012年発表のデビュー長編『火山のふもとで』で第64回読売文学賞を受賞。2018年『光の犬』で第68回芸術選奨文部科学大臣賞、第6回河合隼雄物語賞を受賞。その他の小説作品に『沈むフランシス』『優雅なのかどうか、わからない』『泡』。共著に『新しい須賀敦子』。
撮影:清水玲那
この記事をシェアする
「住宅、そして宮殿――吉村順三ののこしたもの」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 堀部安嗣
-
建築家、京都芸術大学大学院教授、放送大学教授。1967年、神奈川県横浜市生まれ。筑波大学芸術専門学群環境デザインコース卒業。益子アトリエにて益子義弘に師事した後、1994年、堀部安嗣建築設計事務所を設立。2002年、〈牛久のギャラリー〉で吉岡賞を受賞。2016年、〈竹林寺納骨堂〉で日本建築学会賞(作品)を受賞。2021年、「立ち去りがたい建築」として2020毎日デザイン賞受賞。主な著書に、『堀部安嗣の建築 form and imagination』(TOTO出版)、『堀部安嗣作品集 1994-2014 全建築と設計図集』『堀部安嗣作品集Ⅱ 2012–2019 全建築と設計図集』(平凡社)、『建築を気持ちで考える』(TOTO出版)、『住まいの基本を考える』、共著に『書庫を建てる 1万冊の本を収める狭小住宅プロジェクト』(ともに新潮社)など。

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら