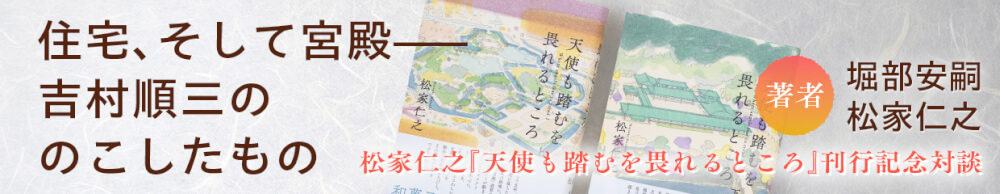2025年6月10日
松家仁之『天使も踏むを畏れるところ』刊行記念
住宅、そして宮殿――吉村順三ののこしたもの
1945年5月、東京大空襲に次ぐ大規模な山の手空襲により、皇居内の明治宮殿が焼失しました。松家仁之さんの新作長篇『天使も踏むを畏れるところ』は、その23年後、「新宮殿」が完成するまでの物語。主人公の村井俊輔には、実際に「新宮殿」造営を手がけた名建築家・吉村順三が投影されています。史実をもとに、この国家的プロジェクトをめぐる人間ドラマを描きだした本書について、建築家・堀部安嗣さんと著者の松家仁之さんが語りあいます。
日本社会と建築の結びつきを描く
松家 『天使も踏むを畏れるところ』という長い小説を書きました。主人公は村井俊輔という建築家ですが、彼にはモデルとなった人物がいます。戦後の建築界では他に類のない、特別な足跡を残された吉村順三さんです。住宅建築の名手を一人選べと言われたら、吉村さんの名前を挙げる人は私ばかりではないだろう、という存在でもあります。
堀部安嗣さんは吉村さんが遺した建築の精神も継承しながら、時代に流されない独自の建築を淡々と手掛けていらっしゃる建築家です。この長篇をめぐっては、ぜひ堀部さんとお話ができればと思い、お声をおかけしました。が、……小説が長いので、かなりご苦労をおかけしたんじゃないかと(笑)。
堀部 大変でした(笑)。感想として最初に申し上げたいことは、小説の内容とは関係のないことなんですが、本って素晴らしいということです。というのも、今回のお話をいただいたときはまだ本のかたちになっていなかったので、新潮社さんから分厚いゲラの束を送ってもらい、上巻はそれで読んだんです。ページがバラバラにならないようにするだけでけっこう大変で(笑)。
上巻を読み終わったタイミングで、できあがったばかりの見本を送っていただいたんですが、ゲラで読むのとはまるで違う感覚をおぼえました。読んでいるうちに作中のいろんなできごとがどんどん身体化していったというか。表紙もあり、地図もあり、何より本文紙の手触りの温かさがある。本ってすごい発明だったんだな、と改めて気づかされました。何百年も前から世界中で同じ形状のまま続いているのは、アーキテクチャーとして優れている証拠なんでしょうね。
松家 本当にそうだと思います。ウンベルト・エーコとジャン=クロード・カリエールの共著『もうすぐ絶滅するという紙の書物について』(阪急コミュニケーションズ)で、本という形態は人類の長い歴史の上で、車輪と同じように完成された発明品なのだと称賛しています。本も車輪も基本的なかたちは変わらない、そこが素晴らしいのだと強調するんですね。きっと今の堀部さんの意見を聞いたら、ウンベルト・エーコもおおいに頷いたでしょうね。
堀部 この感動は電子書籍でも味わえないものだと思います。それを再認識することができたのが、今回の大きな発見でした。小説はもちろん面白くて、僕の関心ともぴったり合致していました。戦前から戦後にかけて社会と建築がどう結びつくのかを以前からずっと考えているのですが、コロナ禍で家にいる時間が多くなったときに、そうした時代の人々の暮らしについて書かれた本をたくさん読みました。この小説をめぐるトークのご依頼をいただいて、松家さんはどうして僕の興味を知ってるんだろうと思ったほどです。
松家 堀部さんの作品集を見たり、読んだりしていると、いわゆるポストモダン的な建築思想とはあきらかな異なる部分があると感じます。それは遠い過去に意識が向いていらっしゃることです。堀部さんは作品集(『堀部安嗣作品集II』平凡社)のなかで、人類の太古の記憶というものは現代的な生活のなかでも蘇る瞬間がある、と書いていらっしゃいますね。そうした意識は昔からお持ちだったんでしょうか?
堀部 そうかもしれないですね。新しい何かを自分の力だけで創造するのが苦手なんですよ。見たこともない、感じたこともないものを自分が表現できるとは思えなくて。自分が作るもののヒントは過去や死者たちの声のなかにあるという考えは昔からずっと持っていました。
なので、激動の時代をくぐり抜けた日本社会と建築の関係を描いているこの小説を読んで、自分の頭のなかを今一度、整理することができました。建築家がいかに大変な仕事なのかを改めて突きつけられたし、これからの時代において建築家がどのような責任を持ってどんな役割を担っていくべきかも考えさせられました。それくらい自分にとって有意義な読書体験でした。
松家 ありがとうございます。以前、橋本治さんと対談したときに、橋本さんが、小説とはつまるところ鎮魂なんだとおっしゃっていたんですね。過去に生きた人たちがどのような人生を送り、何を感じて去っていったのか、これを丹念にたどって描くことでその人を鎮魂する──それが小説の役割なんだとおっしゃっていたことを思い出しました。
人びとの幸せにつながる建築のあり方
松家 堀部さんは吉村順三さんをとても尊敬されていますよね。吉村さんがどのように素晴らしいのか、堀部さんの言葉でうかがってみたいのですが。
堀部 戦後昭和という時代には、機械技術が向上し、人々の暮らしが豊かになり、未来は必ずいいものになるという考え方が一般的でした。建築も登り坂の社会のなかで明るいビジョンを示し、人々を鼓舞する役割を担っていました。吉村順三さんはそのような状況に警鐘を鳴らしていた数少ない建築家です。成長することばかり考えている社会がうまく行くわけはない。もう少し足もとを見つめて、表層的なことだけじゃなく、中身を充実させなきゃダメだ――声高に言ったわけではありませんが、彼は作品を通じてそう伝え続けてきたと僕は思うんです。
日本が下り坂になってきた現在、吉村さんが表現してきたことの意味を痛感するようになりました。内容が伴わないものは必ず廃れる。今の時代になり、ようやくそのことが証明されているような感じを受けます。同じようなタイプの建築家に前川國男さんがいますが、彼のような人物も小説に出てきますよね。
松家 はい。前川さんをモデルにした人物も登場します。吉村順三も前川國男もあくまでモデルであって、彼らをそのまま描いたわけではないのですが。
堀部 そうですよね。前川さんも吉村さんと同じく日露戦争の勝利の時に生まれ、喜びも束の間、その後関東大震災や太平洋戦争といった国の崩壊に向かう時代に人生の前半を生きています。つまり、日本が下り坂だった時期の危機を身をもって知っている。あの激動の時代を乗り越えた前川さんと吉村さんは、それゆえに権力者や強者の論理に傾くことなく、弱い立場の人へのまなざしを持つことができたんだと思います。権威のための建築だけではなく、市井の人々の幸せにつながる建築のあり方をしっかりと考えなくちゃいけない、そう考え続けた彼らの姿勢を、僕は尊敬しています。宮殿の設計も、国の威信のためや権力のためではなく、民衆のために設計しているところが素晴らしい。
松家 新宮殿がつくられる前に、前川國男さんの代表的な仕事のひとつである国立国会図書館が完成します。ここでもやはり、設計を最後まで管理したがる国家との対立が生じていました。前川さんも吉村さんと同様に、計画の向こう側にいる、建築の言葉で言えば施主が国家であることをつねに意識しながら建築計画を進めていったわけですが、二人とも国家と対立する場面が出てきたときに、結果的にすべてを押し戻すことができたわけではありません。しかし、譲れないところは譲らないという姿勢、態度を貫いた。そこが二人の共通点ですね。
堀部 吉村さんには隠れた名作が多いですよね。それが「隠れた」となっているのが歯痒いところではあるんですが。
松家 吉村さんの作品を二つ選べと言われたら、私は軽井沢の「吉村山荘」と新宮殿を挙げたいですね。後者は延べ面積が前者の260倍以上で、規模で言えば両極端な作品です。しかし、やはりその二つは紛れもなく吉村さんでしかつくりえないかたちをしている。八ヶ岳高原音楽堂も素晴らしいです。音楽堂のホールのぐるりがガラス張りになっていて、八ヶ岳の木々の緑が風にゆらいだり、みごとないちめんの紅葉を楽しみながら音楽を聴くことができる。多くの人に足を運んでいただきたい、晩年の名作の一つです。
-

-
堀部安嗣
建築家、京都芸術大学大学院教授、放送大学教授。1967年、神奈川県横浜市生まれ。筑波大学芸術専門学群環境デザインコース卒業。益子アトリエにて益子義弘に師事した後、1994年、堀部安嗣建築設計事務所を設立。2002年、〈牛久のギャラリー〉で吉岡賞を受賞。2016年、〈竹林寺納骨堂〉で日本建築学会賞(作品)を受賞。2021年、「立ち去りがたい建築」として2020毎日デザイン賞受賞。主な著書に、『堀部安嗣の建築 form and imagination』(TOTO出版)、『堀部安嗣作品集 1994-2014 全建築と設計図集』『堀部安嗣作品集Ⅱ 2012–2019 全建築と設計図集』(平凡社)、『建築を気持ちで考える』(TOTO出版)、『住まいの基本を考える』、共著に『書庫を建てる 1万冊の本を収める狭小住宅プロジェクト』(ともに新潮社)など。
-

-
松家仁之
1958年、東京生まれ。1982年、新潮社に入社。1998年、「新潮クレスト・ブックス」を創刊。2002年、季刊誌「考える人」を創刊。「芸術新潮」編集長を兼務ののち、2010年に同社を退職。以降、作家として活動する。2012年発表のデビュー長編『火山のふもとで』で第64回読売文学賞を受賞。2018年『光の犬』で第68回芸術選奨文部科学大臣賞、第6回河合隼雄物語賞を受賞。その他の小説作品に『沈むフランシス』『優雅なのかどうか、わからない』『泡』。共著に『新しい須賀敦子』。
撮影:清水玲那
この記事をシェアする
「住宅、そして宮殿――吉村順三ののこしたもの」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 堀部安嗣
-
建築家、京都芸術大学大学院教授、放送大学教授。1967年、神奈川県横浜市生まれ。筑波大学芸術専門学群環境デザインコース卒業。益子アトリエにて益子義弘に師事した後、1994年、堀部安嗣建築設計事務所を設立。2002年、〈牛久のギャラリー〉で吉岡賞を受賞。2016年、〈竹林寺納骨堂〉で日本建築学会賞(作品)を受賞。2021年、「立ち去りがたい建築」として2020毎日デザイン賞受賞。主な著書に、『堀部安嗣の建築 form and imagination』(TOTO出版)、『堀部安嗣作品集 1994-2014 全建築と設計図集』『堀部安嗣作品集Ⅱ 2012–2019 全建築と設計図集』(平凡社)、『建築を気持ちで考える』(TOTO出版)、『住まいの基本を考える』、共著に『書庫を建てる 1万冊の本を収める狭小住宅プロジェクト』(ともに新潮社)など。

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら