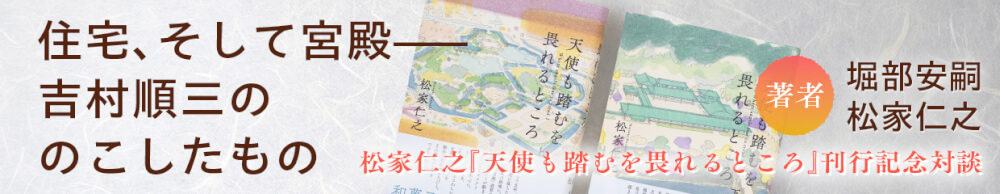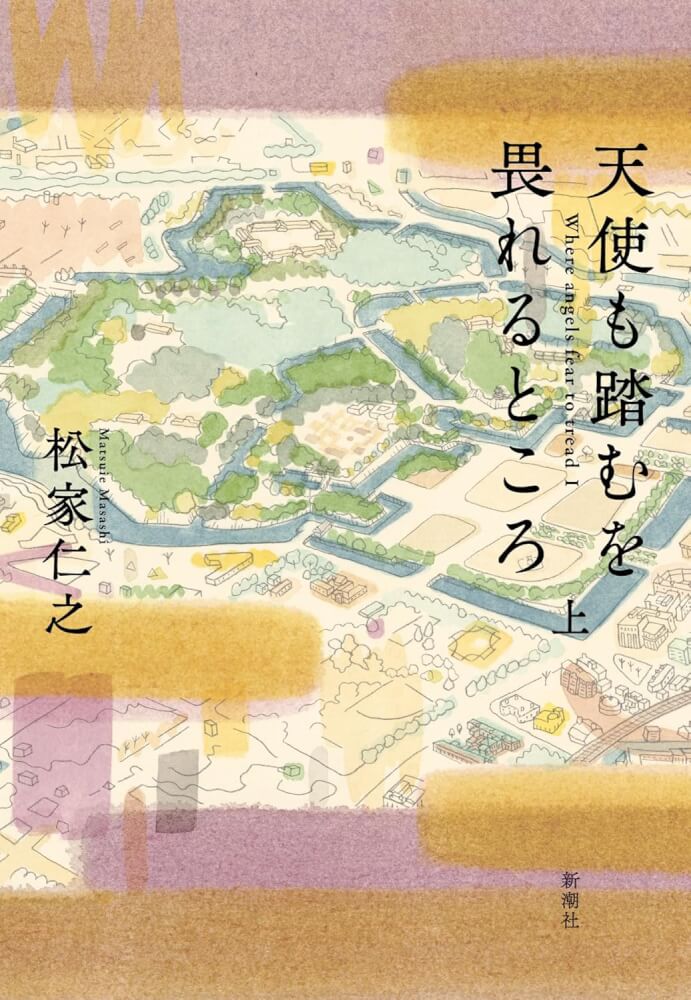2025年6月10日
松家仁之『天使も踏むを畏れるところ』刊行記念
住宅、そして宮殿――吉村順三ののこしたもの
1945年5月、東京大空襲に次ぐ大規模な山の手空襲により、皇居内の明治宮殿が焼失しました。松家仁之さんの新作長篇『天使も踏むを畏れるところ』は、その23年後、「新宮殿」が完成するまでの物語。主人公の村井俊輔には、実際に「新宮殿」造営を手がけた名建築家・吉村順三が投影されています。史実をもとに、この国家的プロジェクトをめぐる人間ドラマを描きだした本書について、建築家・堀部安嗣さんと著者の松家仁之さんが語りあいます。
時代を越えて残り続けるもの
堀部 『天使も踏むを畏れるところ』を読んで考えたのは、建築の素晴らしさと難しさについてでした。オリンピックや万博が開催されて、みんなが未来の方ばかり見ている戦後の世の中で、建築の可能性と危険性の両方をバランスよく見つめることは非常に難しい。そしてあまりにも時代の変化が早すぎるので、建築のような巨大な形あるものを作り、そこに永続性を与えることはなかなかできない。けれども、社会が変化し続ける時代に、あえて形あるものを残すことができるのも建築の力なんだなと改めて思い知りました。
作中で村井のパートナーとなる藤沢衣子が、建築が生き残る長さの話をするじゃないですか。村井の図面やプランはいつまでも残るんだ、と。宮殿も天皇という役割の人間がいなくなったとしても残り続けるんだと言っていて、胸に刺さりました。建築は時代とともにいろんな解釈がされるけど、建築の役割と意味を変えながら人々の心に残り続けるのです。新宮殿はまさにそのことを伝える建築なんだと気付かされました。
松家 皇居を見学なさったとき、新宮殿の大広間棟以外に印象に残ったところはありましたか。
堀部 皇居の中の自然環境がとにかく雰囲気が良かったです。おそらく太田道灌が江戸城を築城したときの姿がそのまま残っているんじゃないでしょうか。
松家 そうだと思います。焼け落ちたものはたくさんありますが、土地そのものの大幅な改変は基本的に行われていないと思うので。
堀部 外国の人からすると東京の街の作り方は不思議な感じがするそうです。中心に行けば行くほど何もなくなるのが面白い、と。中がすっからかんになっているように見えるらしい。じゃあ、その中心に何があるかというと皇居なわけで、そこにずっと昔からの自然を残し続けているという見方ができるのではないかなと思います。皇居の雰囲気って昔の日本の田舎みたいなんですよ。贅沢はできないという天皇の意思がそこには反映されているんでしょうね。
松家 堀部さんの感想を昭和天皇が聞いたらとても喜んだでしょうね。皇居には実に豊かな自然が残されているんです。昭和天皇はかつての武蔵野を形成していた樹木や草花を、時間をかけて少しずつ皇居に移植していったんですね。いつか武蔵野の自然が失われてしまう可能性も考えてのことだったかもしれません。小説のなかにも書きましたが、ある研究者の報告によると、皇居に生息している蝿はお濠の外側で生息する普通の蝿と、遺伝的な系統が違うらしい。お濠を越えて外に出ていくことができないから、皇居のなかで江戸時代からの蠅がガラパゴス化して生き残っているらしいんです。
私は皇居は内部をもっと公開してもいいんじゃないかと思っていますが、同時に皇居内にしかのこされていないものをどうやって守っていくか、これも考えなければならないのではと思っています。それは何かの目的のためではなく、残されてきたものをこれからも残してゆく、というトートロジーのように聞こえるかもしれない考えかたなんですが。直接にはなにかの役に立たないものが東京の中心に広々と残されてゆくことは、百年千年単位で考えたら、おおきな意味があるだろう、と私は考えています。
堀部 東京というビジネスシティの真ん中にお金を生み出さない場所があることが大切な時代になるかもしれませんね。
匿名性と責任のあいだで
堀部 作中で村井俊輔が辞退したように、吉村さんは新宮殿造営の計画から降りますよね。だから新宮殿を設計したのが吉村順三だということは、今ではそれほど知られていません。もしあれが丹下健三さんだったら設計者の名前が強く残り続けていたような気がします。フランク・ロイド・ライトもそうですよね。帝国ホテルの建設計画を途中でクビになったのに、ライトの帝国ホテルとずっと言われ続けている。なぜ吉村さんがそうはならないかというと、無私のたたずまいと言うべき謙虚さゆえなんじゃないかと思います。そこに吉村順三という建築家のたぐいまれな個性があるんでしょうね。
近代以降、建築家の名前が建築物に刻印されるようになりました。エッフェル塔はエッフェル、ルーヴルのピラミッドはイオ・ミン・ペイ、サグラダファミリアはガウディと、今では設計した人間と建築物が紐づくかたちでおぼえられています。でも、近代以前はそうでもなかった。建築家の名前が前面に出てくるようになって意外とまだそんなに時間が経っていないんですよ。だからこれから時代が変わるにつれ、誰が新宮殿を作ったのかはまた違うふうに議論されていくんじゃないでしょうか。
松家 そのお話はそのまま吉村順三論として成立するものだと思います。吉村さんは匿名性が高い建築家でした。最終的に誰が建てたかわからなくなってもいいと考えていた節がある気がします。新宮殿の設計から手を引くことを発表したときの文章の冒頭に、吉村さんは「建築家として、もっとも、うれしいときは、建築ができ、そこへ人が入って、そこでいい生活がおこなわれているのを見ることである」と書きました。夕方、自分が設計した家に電灯がつき、幸せそうな暮らしが外から感じられたときに建築家としての喜びが湧き上がるんだ、と。こういうことを言える建築家はなかなかいませんよね。
堀部 市井の人々の小さな暮らしまで責任を取ろうとしていたんだと思います。そこに建築家としてのやりがいがあったんでしょう。今、建築において誰が作り、誰が責任を取るかがとても曖昧になってきています。関わる人それぞれにぼんやりとした責任があるんだけど、うまくいかなかったときには誰も責任を取ろうとしない。そんな今だからこそ、吉村さんが示した建築家としての姿勢が教えてくれることは多いと思います。
松家 今のお話で一つ思い出したことがあります。吉村さんが設計を辞退されてから新宮殿が竣工するまでのあいだに、上棟式やボイラーの点火式などいくつもの儀式が行われました。吉村さんは皇居から遠ざかっていらっしゃったので、どのような儀式が行われようが無縁だったのだろう、招待もされなかったのだろう、と想像していたんです。ところが、施工を担当していた共同企業体の編集する新宮殿造営の膨大な記録をいちいちめくっていって、儀式ごとの出席者の名前をひとつひとつ確認していったら、ある儀式の出席者に、吉村さんの名前があったんです。銅板葺の屋根が完成した際の儀式にだけは出席されていたとわかった。これには驚きました。
堀部 小説にもその場面が描かれていますね。
松家 はい。資料に名前を見つけてびっくりしたんですよ。これは小説に書かなくてはと思いました。もちろん資料には出席者名しか記されていません。なぜ出席したのかまではわからないのですが、おそらく屋根がどのように完成したのかを、自分の目で確認せずにはいられなかったのだろうと。
堀部 責任を感じていたんでしょうね。辞任したあと、自分が責任を持つべき範疇とそうじゃない部分が吉村さんのなかではっきりと分かれていたんじゃないでしょうか。皇居を案内してくれた元侍医の方いわく、新宮殿は世界各国から称賛されているようです。これほどエレガントな宮殿はないとみんな口を揃えて言うらしい。
ふつう王族の暮らす宮殿には戦利品などその国の栄華を象徴するものが並んでいるんですが、皇居はそういう派手さがありません。住む人や働くスタッフの快適性を保ちつつ、天皇制の本質を見事に表現している宮殿は他に類を見ないんですよ。松家さんがこの小説を書いた動機の一つに、新宮殿への評価はこのままでいいのかと考えたことがあると思いますが、時代が変わるにつれ評価のされ方も変化しているんだと思います。
白でもなく、黒でもない小説
堀部 『天使も踏むを畏れるところ』はかなり抑制された文章で書かれているように感じました。ドラマチックにならないようにできるだけ淡々と綴っていこうと作者が慎重になっている様子が終始伝わってきたのですが、自覚的にそういう書き方をされたんですか?
松家 大きな音や派手な動きはどうも苦手なんです(笑)。たぶんですが戦場が出てくるような小説は書けそうにない、というか自分には向かないんですね。抑制的に書いたのは、たんに自分の資質の問題かもしれませんが、今回初めて史実をベースにした小説を書くにあたって、無用にドラマチックにするのは避けつつも、記録に残されていない余白部分では想像力をはたらかさせてもらおうと考えました。おとなしく構えていますが、大胆なところもあって(笑)。
堀部 その気持ちははっきりと伝わってきました。同時に、村井俊輔の建築思想と松家さんの文体が見事に重なっている感じもしました。作中で村井が「オリジナリティなんていうものは、ないんだよ」と言いますが、これは松家さんご自身の言葉でもあるんでしょうね。
松家 建築もそうだと思うのですが、これまで誰も書いたことがない小説なんてもはや存在しないのではないかと私は考えています。橋本治さんが「小説は鎮魂なんだ」とおっしゃった言葉にもつながりますが、私がこれまで生き延びてこられたのは食べたり飲んだりすることはもちろん、本を読むことができたおかげだという気持ちがつよいんです。それに対する返礼のようなものをこの小説に込めた部分はあるかもしれません。
堀部 上巻はゲラで読んだので、本で読むより松家さんの言葉の手触りを感じづらかったのですが、それでもオリジナリティをめぐるさっきの言葉に出会ったときには大事なものに触れた気がしました。上巻はとりわけ抑制が効いていますね。
松家 目的地に向かうルートで考えるとすると、上巻はいちばん遠回りの道を選んでいるんですね。それは私なりに理由があるんです。村井俊輔の幼少期からの個人史をおさえておかないと、建築家になった彼が重要な局面でなぜそのような判断をするのかが見えてこないのではないかと考えたことがひとつ。また、これは下巻にかかわる部分ですが、村井と対立する牧野という宮内庁側の役人についても、たんなる役人としての彼を描くだけではフェアではないな、と考えたんですね。彼が佐渡で生まれ、父親を早くに亡くし、大雪の田舎道を歩いて学校に通い、やがて旧制一高に合格して幅広い教養を身につけ、東大法学部を卒業後はまず内務省に入り、さらに宮内省に移ったこと。戦後は宮内省の人員の大幅な削減や皇室典範の草案にも関わってきた──そうした個人史をしっかり描いておかなければ、新宮殿をめぐっての牧野の言動を理解することはできないのではないか、と考えたんです。
そうやって書いているうちに、戦前の旧制一高が想像していた以上にリベラルな魅力的な学校だったことが見えてきましたし、東大法学部を出てエリートの階段を登るような人間であるからには、古典的な文学作品を読むのが当たり前であった時代があったんだ、という発見も見逃せず、どうしても延々と続く螺旋階段をのぼってゆく、あるいは降りてゆくようになってしまって。
堀部 小説をもっとエンターテイメント化するのであれば、誰かを善に仕立てて、対立する人間を悪とみなすのが手っ取り早いと思うんですけど、それだとこの小説にある魅力は失われますよね。僕は善悪を決めつけるような表現を松家さんが周到に避けているところに共感しました。村井俊輔が仕事を降りたことや昭和天皇の戦争責任などを一方的なベクトルだけで考えていないからこそ、読んでいて気持ちいいなと感じることができたんです。
松家 大江健三郎さんはアンビギュアス(両義性)という言葉を大事にした小説家でした。私もできれば、人間をめぐるあらゆる出来事や物語を両義的に考えたいんですね。私たち日本人は天皇制という問題設定を前にすると、肯定か否定かの二項対立でとらえてしまいがちなんですが、そのあわいに立つことで見えてくるものがあるのではないか、そここそを書きたいと思ったんです。
堀部 つまり、分厚いグレーな本ということですね。白でもなく、黒でもない。グレーの諧調がずっと貫かれているからこそ、いろんなことを考えさせる力に満ちているんだと思います。
そして本を読んでいる時より、読んだ後の方が余韻に浸れて数倍気持ちがいいんです(笑)。読者にとって読後の時間の方が圧倒的に長いわけですから。この本に関わらず松家作品は余韻の芸術ですね。
松家 自分にはそういう書き方しかできないので、そこを汲み取っていただけたとしたら、ありがたいです。でもきっとそれは堀部さんのお仕事にも通じることですね。
(2025年3月29日、紀伊国屋書店新宿本店/構成・長瀬海)
-
松家仁之/著
2025/3/26発売公式HPはこちら
本対談にて語られている松家仁之さん渾身の小説
『天使も踏むを畏れるところ 上・下』は小社より好評発売中です。
-

-
堀部安嗣
建築家、京都芸術大学大学院教授、放送大学教授。1967年、神奈川県横浜市生まれ。筑波大学芸術専門学群環境デザインコース卒業。益子アトリエにて益子義弘に師事した後、1994年、堀部安嗣建築設計事務所を設立。2002年、〈牛久のギャラリー〉で吉岡賞を受賞。2016年、〈竹林寺納骨堂〉で日本建築学会賞(作品)を受賞。2021年、「立ち去りがたい建築」として2020毎日デザイン賞受賞。主な著書に、『堀部安嗣の建築 form and imagination』(TOTO出版)、『堀部安嗣作品集 1994-2014 全建築と設計図集』『堀部安嗣作品集Ⅱ 2012–2019 全建築と設計図集』(平凡社)、『建築を気持ちで考える』(TOTO出版)、『住まいの基本を考える』、共著に『書庫を建てる 1万冊の本を収める狭小住宅プロジェクト』(ともに新潮社)など。
-

-
松家仁之
1958年、東京生まれ。1982年、新潮社に入社。1998年、「新潮クレスト・ブックス」を創刊。2002年、季刊誌「考える人」を創刊。「芸術新潮」編集長を兼務ののち、2010年に同社を退職。以降、作家として活動する。2012年発表のデビュー長編『火山のふもとで』で第64回読売文学賞を受賞。2018年『光の犬』で第68回芸術選奨文部科学大臣賞、第6回河合隼雄物語賞を受賞。その他の小説作品に『沈むフランシス』『優雅なのかどうか、わからない』『泡』。共著に『新しい須賀敦子』。
撮影:清水玲那
この記事をシェアする
「住宅、そして宮殿――吉村順三ののこしたもの」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 堀部安嗣
-
建築家、京都芸術大学大学院教授、放送大学教授。1967年、神奈川県横浜市生まれ。筑波大学芸術専門学群環境デザインコース卒業。益子アトリエにて益子義弘に師事した後、1994年、堀部安嗣建築設計事務所を設立。2002年、〈牛久のギャラリー〉で吉岡賞を受賞。2016年、〈竹林寺納骨堂〉で日本建築学会賞(作品)を受賞。2021年、「立ち去りがたい建築」として2020毎日デザイン賞受賞。主な著書に、『堀部安嗣の建築 form and imagination』(TOTO出版)、『堀部安嗣作品集 1994-2014 全建築と設計図集』『堀部安嗣作品集Ⅱ 2012–2019 全建築と設計図集』(平凡社)、『建築を気持ちで考える』(TOTO出版)、『住まいの基本を考える』、共著に『書庫を建てる 1万冊の本を収める狭小住宅プロジェクト』(ともに新潮社)など。

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら