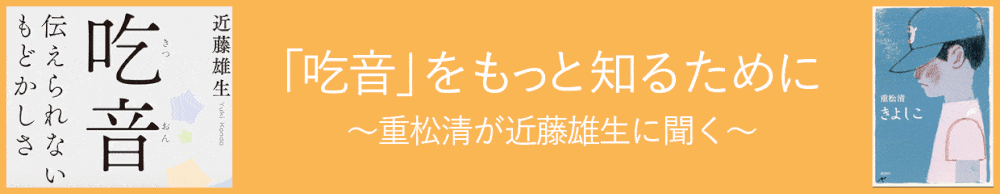2019年12月6日
第3回 吃音は「個性」か
吃音とはどういうものか。『吃音 伝えられないもどかしさ』を執筆された近藤雄生さんと、『きよしこ』『青い鳥』といった吃音をテーマにした小説を書かれている重松清さん。リクエストの声にお応えして、貴重な場の記録としてまとめました。第3回をお届けいたします(全4回)。
(前回はこちら)
2019年1月に上梓した『吃音 伝えられないもどかしさ』は、吃音を持つ人の困難を当事者としての私自身の経験を踏まえて書いたノンフィクションです。その帯推薦文と書評を寄せてくださったのが、吃音の当事者であり、『きよしこ』『青い鳥』といった吃音をテーマにした小説も書いてこられた重松清さんです。
2019年5月31日、東京・下北沢「本屋B&B」にて、本書の刊行記念イベントとして、重松さんとのトークショーが実現しました。重松さんが聞き手となってくださったそのトークをまとめたのがこの連載記事です。
第1回、第2回は、重松さんからいただくご質問を糸口に、吃音全般についての事柄から本の具体的なエピソードまで、話を進めていきました。第3回と第4回は、会場からの質問に二人で答える形で進みます。核心を突く質問の数々と重松さんの的確な質問選びで、トークの内容はさらに深まっていきました。
近藤雄生

吃音があっても生活がしやすくなるように
重松 皆さんからたくさんの質問や感想をいただいています。ありがとうございます。後半は、それらに二人で応えていく形で進めていきます。よろしくお願いします。
まず、「入場の際に名前を言わないでいいという配慮があったことに驚いて、うれしかった」という声があります。
近藤 発売直後に京都でイベントをやったとき、そこまで考えが及ばずで、会場の雰囲気からしておそらく困った方がいらしたと感じました。申し訳なかったという反省からのことでした。
重松 本の中でも、髙橋さん(※)が「吃音カード」というものを使われていましたよね。
※^ 本書は複数の吃音当事者の話で構成されていますが、その軸となるのが、重度の吃音を抱えた髙橋さんという30代の男性です。吃音のために就職など様々な困難を抱えていた髙橋さんが、一人娘のももちゃんとともに生きていくためには吃音を改善させるしかないと、訓練に身を投じる様子を追っています。
近藤 はい。吃音という障害があることを明記したもので、話す相手に、問題を理解してもらうためのカードですね。
重松 そういうものを普及させるような流れはあるんですか。
近藤 やはり店で店員さんと話すときなどに、補助的に利用できるものがあると気持ちの負担も減るので、そういうものを作ろうという当事者の試みは複数あります。吃音カードも、元々は当事者の方が作って広がったものなんです。また、しゃべらなくても意思表示ができるようにと、吃音のある人が利用しやすい電子メモを作った方もいます。しかしそもそも、ファストフードで注文するときなどは、指でさせるメニューがあるとすごく助かりますよね。
重松 そう。「指でさせる」というのは大きいですよね。
近藤 大手チェーンのお店に、「自分は吃音があるのだけれど、好きなものを注文したいので注文時に指でさせるようにしてもらえないか」と直接連絡してお願いしたという当事者の方もいます。そうしたら、あるうどん店のチェーンは、とても好意的な返事を下さったようなんです。安心して来ていただけるように考えます、と。そういう対応はとてもうれしいですよね。
吃音がなければ、もの書きにはなっていない
重松 次の質問です。「近藤さんも重松さんも、職業はものを書くことです。ものを書くことを職業にしたことと、自分が吃音であるということの関係、影響はありますか」。
重松・近藤 (顔を見合わせて)どうですか?
一同 (笑)
重松 俺の場合、もう完全に……。それがなかったら、ものを書いていない。
近藤 重松さんは、初めに出版社に入られましたよね。就職時の面接などでは吃音による困難はなかったのですか。
重松 僕は、普通の試験を受けて入ったわけではないんです。実は中上健次さんなど作家さんの推薦でぽんと入ってしまったから、結構ずるいんですよ(笑)。でも、入った会社が「角川書店」で、電話で社名の一文字目の「か」が言えなかった。しんどいなと思いながら働いていました。
近藤 社名が言えないというのは、大変だったと思います。
重松 僕は、自分の思いを伝えたい、という気持ちが強くあります。でも、話すことでは伝えられなかったから、文章を書こうと思ったんです。ただ、とてもシンプルな、小学生でも読めるようなものしか書きたくなかった。伝えられなかったもどかしさが根っこにあるから、伝わる文章を書きたいという思いがすごくあって……。文学的にどうこうではなく、シンプルでわかりやすく、真っすぐに伝わる文章だけで小説を書いていきたい。それだけは常に念頭にありました。
近藤 なるほど……。
重松 近藤さんはどうなんですか。
近藤 僕自身は、いまも、自分がもの書きをしているのが不思議に思えたりすることがあります。そのぐらい僕は、文章を書くことに一切縁のない人間だったんです、もともとは。

重松 そもそも理系ですよね。
近藤 はい、僕は数学や物理が好きで、物理学者になりたいと思っていました。本は一切読んでなくて、高校を卒業するまでに読んだ本は通算10冊あるかないかだと思います。それくらい読まなかった。大学に入った当初も、よし、これからは本なんて一切読まずに(笑)、理系のことだけを学んで物理学者や宇宙飛行士になろう、という気持ちでした。でも、ふとしたきっかけで本の面白さを知るようになったりするうちに、だんだんとサイエンスジャーナリストという仕事に興味が湧き、そこから徐々にノンフィクションを書きたいという意識が芽生えました。そのように元々の「夢」から離れていった背景としては、単純に、難解な物理学に頭がついていかなかったということもあるのですが、宇宙飛行士になりたいといっても、緊急時にどもって話せないのはさすがにまずいよな、それでは無理だよな、といった思いもありました。
一方、文筆業に惹かれた過程には、本や友人との出会いも大きかったのですが、思うように話せずに悩んでいたことも、大きく関係していたと思います。無意識かもしれないですけど、気持ちが文章に向かったのは、やはり根幹で、文章であれば吃音がもたらすような制約がなく、一応ちゃんと、伝えたいことが伝えられるはずだ、という気持ちがあったと思うんです。だから、そうですね、僕にとっても、ものを書くことと吃音は少なからず関係しています。
「吃音は個性」と思えない人の気持ちを
重松 「近藤さんが取材された中で、幸せだった当事者の話も聞きたいです」という質問にはどうですか。
近藤 幸せだった当事者の話……。僕はこの本では、吃音でつらいという思いを持っている人を主に取り上げていますが、だからといって、当事者の誰もが同じように深く悩んでいるわけではないだろうとも思っています。吃音があってもそれほど苦にしていなかったり、吃音とは別のところに意識を向けて生きていたり、という方も少なからずいると思います。
重松 おそらくその問題は、吃音は治すものなのか、受け入れるものなのかという一番大きな命題とかかわってきますよね。
近藤 はい、そうですね。
重松 言友会の「吃音者宣言」(※5)なんかの、「吃音とともに生きる」という道を選んだ人もいれば、「治す」という方向を向いている人もいる。近藤さんご自身は……、二つのうちのどちらかだときっぱりと言うことはできないとは思うのだけど、どんなスタンスなのでしょうか。
※5.^ 言友会は、1966年に設立された、吃音がある人たちの当事者団体。基本的なスタンスは《吃音と向き合いながら豊かに生きる》ことを目指すというもので、その基盤にあるのが、1976年に採択された「吃音者宣言」です。
近藤 僕自身について言えば、吃音で悩んでいたころに「吃音者宣言」を知って、読んでみたのですが、そのとき、「ああ、そうか」とは、正直思えませんでした。吃音を受け入れて生きていこう、という気持ちにはなれなかった。受け入れようと言われても、好きなものが注文できないとか、自分の名前が言えないという問題をどうすればいいんだっていう気持ちが強かった。受け入れようと言われて受け入れられたら、それはいいと思います。でも、それはなかなか難しいのでは……、というのが僕の実感としてあります。
重松 この本の中でも、吃音を障害と考えるのか、個性と考えるのかという点について近藤さんは、本人が自分の吃音を個性だと思えるのだったらそれはいい、しかし、一般化はできない、と書いていますね。
近藤 「吃音は個性だよね」と言う人がいたとしても、「いや、困っているんだよ」と言う人も少なからずいる。「受け入れましょう。べつに問題じゃないよ」と言われても、いや、でも、いま注文できないことがとても辛いんだ、という人がいる。僕はそういう、困っている人たちの思いを知ってもらいたいという気持ちがあります。ただ、本人が受け入れているというのであれば、もちろんそれはいいと思うし、受け入れられれば幸せだろうなと思います。
吃音のある人生も、悪くない

重松 「いまになってみて、吃音になってよかったと思えることはありますか」という質問です。
近藤 はい。
重松 僕はね、もし、吃音がなくて、小説も書いていない人生があったとしたら……、そっちの方が、よかったかもしれないな、という気持ちがちょっとあります。なんとなく……。もちろん、いまの人生も好きだけれども、あっちの人生も、俺には、よかったなという感じはする……。吃音になってよかった、とは思わない……、やっぱり。
近藤 はい、吃音は、やはりそれだけ、重いですよね。僕も同感です。僕は、旅をしたのも、文章を書くようになったのも、少なからず吃音とつながっていて、だから吃音は、僕の進路の重要なところを決めた要素になっているのは確実です。だから現状としてみたら、吃音があったからいまの人生があるんだと感じています。
でも、吃音があってよかった、とはやはり言えない。吃音があるからいまがある、と言えるのは、おそらく自分の場合、いまはひとまず、吃音で悩んでいないという事実が大きいと思うんです。リアルタイムで悩んでいたときは、そういうふうには言えなかった。
でも、吃音があったことによって、いま自分がものを書く上で重要な気付きを得たというのは、確かにあります。それは、人がどんなことで悩んでいるかは、決して簡単には分からない、という確信です。自分の吃音の悩みは、周囲のほとんどの人が知らなかったのにもかかわらず、自分にとっては人生を変えるぐらいのものでした。本人の認識と、周囲からの印象というのは、それだけ違う。だから、例えば、ある人を何時間かインタビューしても、わかるのはその人の人生の本当にわずかな部分でしかない、と思っています。深いところの気持ちなどは、まず理解できないと思った方がいい。そのことを認めた上で、自分に何が書けるのかを、熟慮して書いていく。わかった気になっては絶対にいけない。そのような意識が、僕には、書き手としての根幹にあります。
そういう意味では、吃音があったことによって書けている部分は、結構あると思います。それは必ずしも吃音である必要はなかったと思うのですが、僕にとっては吃音が、文章を書く上ではすごく重要な意味を持っているのだろうなと。
でも、とはいえ、じゃあ吃音があってよかったかと言えるかというと、そう簡単には言えない、というところですね……。
重松 うん、そうだよね。おそらく、僕も近藤さんと同じように感じています。あってよかったかと言われたら、いや、そうではない。しかし、吃音のある人生だって、悪くない……と思う。
近藤 吃音のある人生も、悪くない……。ああ、はい。そうですね。
重松 あってよかったというのと、あった人生の肯定は……、違うからね。
近藤 まさに、そうですね。
(第4回はこちら)
-

-
近藤雄生
こんどう・ゆうき 1976(昭和51)年東京都生まれ。東京大学工学部卒業、同大学院修了。2003年、旅をしながら文章を書いて暮らそうと、結婚直後に妻とともに日本を発つ。 オーストラリア、東南アジア、中国、ユーラシア大陸で、約5年半の間、旅・定住を繰り返しながら月刊誌や週刊誌にルポルタージュなどを寄稿。2008年に帰国、以来京都市在住。著書に『遊牧夫婦』シリーズ(ミシマ社、角川文庫)、『旅に出よう』(岩波ジュニア新書)、『吃音 伝えられないもどかしさ』(新潮社、講談社本田靖春ノンフィクション賞・新潮ドキュメント賞最終候補、本屋大賞ノンフィクション本大賞ノミネート作)、『オオカミと野生のイヌ』(エクスナレッジ、本文執筆)など。最新刊に『まだ見ぬあの地へ』(産業編集センター)。大谷大学/京都芸術大学/放送大学 非常勤講師、理系ライター集団「チーム・パスカル」メンバー。
-

-
重松清
しげまつ・きよし 1963(昭和38)年、岡山県生れ。早稲田大学教育学部卒業。出版社勤務を経て執筆活動に入る。1991(平成3)年『ビフォア・ラン』でデビュー。1999年『ナイフ』で坪田譲治文学賞、同年『エイジ』で山本周五郎賞を受賞。2001年『ビタミンF』で直木賞、2010年『十字架』で吉川英治文学賞、2014年『ゼツメツ少年』で毎日出版文化賞を受賞。現代の家族を描くことを大きなテーマとし、話題作を次々に発表している。著書は他に、『きよしこ』『流星ワゴン』『疾走』『その日のまえに』『きみの友だち』『カシオペアの丘で』『青い鳥』『くちぶえ番長』『せんせい。』『とんび』『ステップ』『かあちゃん』『ポニーテール』『また次の春へ』『赤ヘル1975』『一人っ子同盟』『どんまい』『木曜日の子ども』など多数。
この記事をシェアする
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 近藤雄生
-
こんどう・ゆうき 1976(昭和51)年東京都生まれ。東京大学工学部卒業、同大学院修了。2003年、旅をしながら文章を書いて暮らそうと、結婚直後に妻とともに日本を発つ。 オーストラリア、東南アジア、中国、ユーラシア大陸で、約5年半の間、旅・定住を繰り返しながら月刊誌や週刊誌にルポルタージュなどを寄稿。2008年に帰国、以来京都市在住。著書に『遊牧夫婦』シリーズ(ミシマ社、角川文庫)、『旅に出よう』(岩波ジュニア新書)、『吃音 伝えられないもどかしさ』(新潮社、講談社本田靖春ノンフィクション賞・新潮ドキュメント賞最終候補、本屋大賞ノンフィクション本大賞ノミネート作)、『オオカミと野生のイヌ』(エクスナレッジ、本文執筆)など。最新刊に『まだ見ぬあの地へ』(産業編集センター)。大谷大学/京都芸術大学/放送大学 非常勤講師、理系ライター集団「チーム・パスカル」メンバー。
対談・インタビュー一覧
-

- 重松清
-
しげまつ・きよし 1963(昭和38)年、岡山県生れ。早稲田大学教育学部卒業。出版社勤務を経て執筆活動に入る。1991(平成3)年『ビフォア・ラン』でデビュー。1999年『ナイフ』で坪田譲治文学賞、同年『エイジ』で山本周五郎賞を受賞。2001年『ビタミンF』で直木賞、2010年『十字架』で吉川英治文学賞、2014年『ゼツメツ少年』で毎日出版文化賞を受賞。現代の家族を描くことを大きなテーマとし、話題作を次々に発表している。著書は他に、『きよしこ』『流星ワゴン』『疾走』『その日のまえに』『きみの友だち』『カシオペアの丘で』『青い鳥』『くちぶえ番長』『せんせい。』『とんび』『ステップ』『かあちゃん』『ポニーテール』『また次の春へ』『赤ヘル1975』『一人っ子同盟』『どんまい』『木曜日の子ども』など多数。

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら