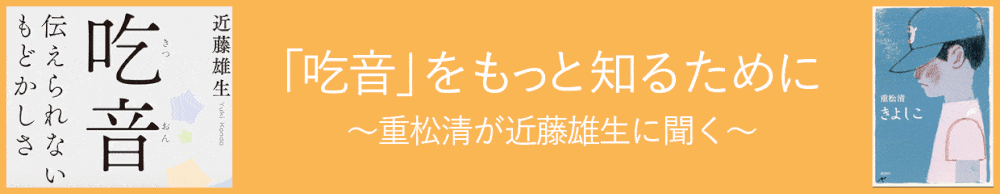言葉がつっかえる、いわゆる「どもる」吃音の人は、詰まり方や軽重の度合いはさまざまでも、日本中におよそ百万人いるとされる――僕も、その一人である。
決して症例が少ないわけではないのに、吃音が起きるメカニズムは不明。治療法も確立されていない。なにより〈本人にとっては深刻でも、他人からは問題がわかりにくい場合がある〉。苦手な言葉でも場面や体調などによってうまく話せるときがあるから、ややこしい。さらに〈うまく話せなくなりそうな場面で沈黙すれば、他の人から見たらそもそも何が問題なのかほとんどわからないということにもなりうる〉......。
著者の近藤雄生さん自身、本書の中でも詳細に記しているとおり、かつて吃音に苦しんできた。ところが二十代も残り半年になった頃、二〇〇五年の終わりに突然症状が軽減して、〈吃音は、私の中からその姿を消していった〉。そうなのだ。そういうことがあるのだ、吃音には。僕も一番症状がひどかった十代後半の頃に比べると、五十代後半のいまはずいぶん楽に話せるようになった。しかし、近藤さんはこうも言う。〈もしかすると、何かをきっかけにすべてが元に戻ってしまう可能性もあるだろう〉。自分を引き合いに出しすぎて申し訳ないが、僕も体調の悪いときや、その場に嫌いな奴がいるところでは、ひどいことになってしまう。
なんともやっかいな吃音に、近藤さんはじっくりと腰を据えて向き合った。取材に約五年、本書の出発点でもある吃音矯正所についての短編ルポルタージュに取り組んだのは二〇〇二年というから、じつに十七年もの歳月の元手がかかっている。掛け値なしの労作なのだ。
その取材で、近藤さんはほんとうに多くの人に会っている。吃音に悩み苦しむ当事者はもとより、家族や周囲の人たち、研究者や医療関係者、吃音はコントロールできるはずだと語る言語聴覚士、吃音を受け容れようという自助グループ、かつて吃音を苦に自殺を図った男性、苦しみを誰にも語らずに/語れずに命を絶ってしまった青年の遺族......。
重い取材である。つらい旅でもあっただろう。吃音を持つ人の就労支援をおこなうNPO法人を起ち上げた男性は、吃音を理由に職場を去らざるを得なかった彼自身の過去を語りながら、「なんで涙が出てくるんだろう」と照れ笑いを浮かべる。僕も泣いた。彼の涙よりも、むしろ照れ笑いのほうに胸を衝かれた。彼の話だけではない。頁をめくるごとに、つらかった記憶や悔しかった記憶、言葉がうまく出ないもどかしさに地団駄を踏んだ記憶がよみがえって、何度も泣いた。いい歳をして子どものように――子どもの頃の自分のために、涙をぽろぽろ流した。
だからこそ、うれしかった。にこにこ笑ううれしさではなく、万感の思いを込めて、無言で、近藤さんに最敬礼したくなった。吃音のある人も、周囲の人も、一色に塗りつぶせるものではない。十人十色。誰もに〈その人だけの物語〉がある。しかし、その物語を語るには、彼や彼女の言葉は詰まりすぎる。〈吃音は、言葉だけでなく、その人自身の姿もまた、内に閉じ込めてしまう〉――それをゆっくりと、丁寧に、寄り添うようにして引き出してくれたのが、近藤さんではないか。最敬礼とはそういう意味である。
だが、急いで言っておく。本書は断じて「こんな可哀相な人たちの、こんな悲しい物語」ではない。本書の縦軸となって描かれる一人の父親――髙橋さんという男性の、少年時代からいまに至るまでの歩みが、それを教えてくれるはずである。何度もけつまずきながら(つまりは、どもりながら)髙橋さんは歩きつづける。その背中からたちのぼるのは、吃音の物語にとどまらない、人が人とつながりながら生きていくことの普遍の尊さなのだ。
〈人が生きていく上で、他者とのコミュニケーションは欠かせない。/吃音の何よりもの苦しさは、その一端が絶たれることだ。言葉によって相手に理解を求めるのが難しい。さらに、その状況や問題を理解してもらうのも容易ではない。二重の意味で理解されにくいという現実を、吃音を持つ人たちはあらゆる場面で突きつけられる〉
理解されない苦しさを理解されない――その苦しさは、いまの社会では(悔しいけれど)吃音を持つ人だけのものではないだろう。本書は、吃音をめぐるノンフィクションであると同時に、他者とつながること、他者を理解することについて問いかける一冊として、広く、深く、開かれている。
(しげまつ・きよし 作家)
「波」2019年2月号より
-

-
近藤雄生
こんどう・ゆうき 1976(昭和51)年東京都生まれ。東京大学工学部卒業、同大学院修了。2003年、旅をしながら文章を書いて暮らそうと、結婚直後に妻とともに日本を発つ。 オーストラリア、東南アジア、中国、ユーラシア大陸で、約5年半の間、旅・定住を繰り返しながら月刊誌や週刊誌にルポルタージュなどを寄稿。2008年に帰国、以来京都市在住。著書に『遊牧夫婦』シリーズ(ミシマ社、角川文庫)、『旅に出よう』(岩波ジュニア新書)、『吃音 伝えられないもどかしさ』(新潮社、講談社本田靖春ノンフィクション賞・新潮ドキュメント賞最終候補、本屋大賞ノンフィクション本大賞ノミネート作)、『オオカミと野生のイヌ』(エクスナレッジ、本文執筆)など。最新刊に『まだ見ぬあの地へ』(産業編集センター)。大谷大学/京都芸術大学/放送大学 非常勤講師、理系ライター集団「チーム・パスカル」メンバー。
-

-
重松清
しげまつ・きよし 1963(昭和38)年、岡山県生れ。早稲田大学教育学部卒業。出版社勤務を経て執筆活動に入る。1991(平成3)年『ビフォア・ラン』でデビュー。1999年『ナイフ』で坪田譲治文学賞、同年『エイジ』で山本周五郎賞を受賞。2001年『ビタミンF』で直木賞、2010年『十字架』で吉川英治文学賞、2014年『ゼツメツ少年』で毎日出版文化賞を受賞。現代の家族を描くことを大きなテーマとし、話題作を次々に発表している。著書は他に、『きよしこ』『流星ワゴン』『疾走』『その日のまえに』『きみの友だち』『カシオペアの丘で』『青い鳥』『くちぶえ番長』『せんせい。』『とんび』『ステップ』『かあちゃん』『ポニーテール』『また次の春へ』『赤ヘル1975』『一人っ子同盟』『どんまい』『木曜日の子ども』など多数。
この記事をシェアする
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 重松清
-
しげまつ・きよし 1963(昭和38)年、岡山県生れ。早稲田大学教育学部卒業。出版社勤務を経て執筆活動に入る。1991(平成3)年『ビフォア・ラン』でデビュー。1999年『ナイフ』で坪田譲治文学賞、同年『エイジ』で山本周五郎賞を受賞。2001年『ビタミンF』で直木賞、2010年『十字架』で吉川英治文学賞、2014年『ゼツメツ少年』で毎日出版文化賞を受賞。現代の家族を描くことを大きなテーマとし、話題作を次々に発表している。著書は他に、『きよしこ』『流星ワゴン』『疾走』『その日のまえに』『きみの友だち』『カシオペアの丘で』『青い鳥』『くちぶえ番長』『せんせい。』『とんび』『ステップ』『かあちゃん』『ポニーテール』『また次の春へ』『赤ヘル1975』『一人っ子同盟』『どんまい』『木曜日の子ども』など多数。

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら