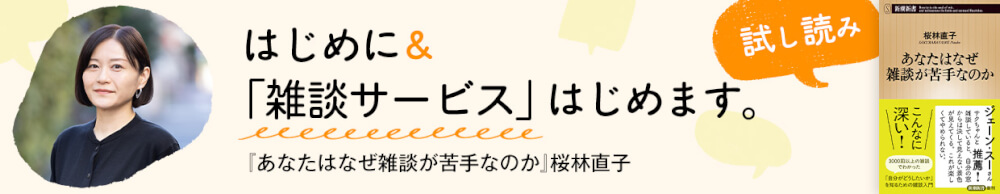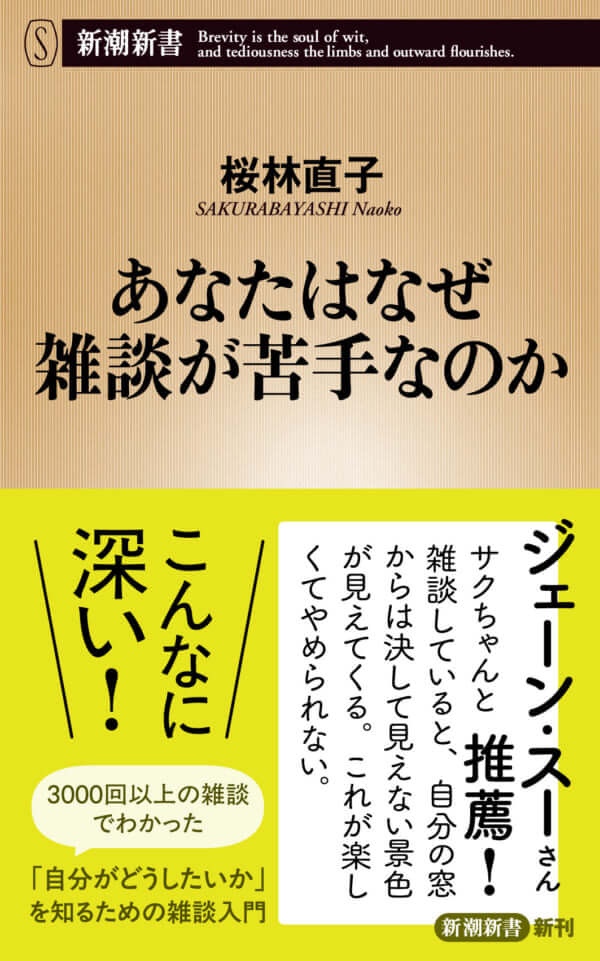2025年11月11日
はじめに&「雑談サービス」はじめます。
著者: 桜林直子
桜林直子さんの連載「あなたには世界がどう見えているか教えてよ 雑談のススメ」が、『あなたはなぜ雑談が苦手なのか』として、11月17日に新潮新書より発売されます!
「自分の話がうまくできない」「いつも聞き役ばかり」……そんな悩みに、これまで3000回以上のマンツーマン雑談を行ってきた桜林さんがこたえます。よい雑談の条件やそのメリット、話が苦手な人の共通点とは? そのエッセンスをやさしく伝える雑談入門です。
本書の刊行を記念して、「はじめに」と、雑談を“仕事”にしたきっかけを綴った「「雑談サービス」はじめます。」を公開いたします。
はじめに
2020年のはじめに「雑談」を仕事にしてから5年半が経つ。マンツーマンで1回90分の雑談を、今までのべ3000回以上している。始めた頃は別の仕事をしていたこともあり、ゆるく続けられるといいなという感じだったのだが、今ではすっかり本業となり、毎日いろいろな人の話を聞きながら、みんなもっと雑談をしたほうがいいという気持ちは日に日に強くなっている。
雑談というと、通常は天気の話や軽い世間話などで隙間を埋める会話や、わたしは敵ではないですよとお互いに毛繕いをするような会話を想像すると思うが、わたしが仕事にしている「雑談」は、少し違う。
90分と時間をたっぷり用意しているので、序盤は近況報告などの何気ない会話から始まるものの、最近気になっていることや話してみたいことがあるかと聞くと、自分がモヤモヤ感じていることなどが自然と出てくる。一度出てくると、口の中からツルツルと万国旗が出てくる手品のように次々と言葉が出てくる。
慣れないうちは、話しながら「自分の話ばっかりしてすみません」と引け目を感じる方もいるが、「いやいや、ここはそういう場で、自分の話をする時間ですよ」と言う。引け目に感じてしまうのは、普段、思い切り自分の話をし続けていい場や時間がほとんどないからだろう。
雑談をして自分の話をしたほうがいいと思うのは、そうしないと自分がいったいどうしたいのかわからなくなってしまうからだ。何が好きで、何が嫌で、どんな状態が快適で、どうありたいか、なにをしたいか、自分でわかっていないと、先に進むための選択がむずかしくなる。選択をしないと、ちょっとした不快を無視したり、不満があるのに我慢したりすることになる。自分を快適な場所に連れて行くのは自分にしかできないのに、周りのせいにしてしまう。そうならないためには、自分のことをもっと知らないといけない。自分のことを知るために、雑談で自分の話をするといい。
わたしのところに雑談をしにきてくれる人の多くが、「雑談が苦手なんです」と言う。普段友人とおしゃべりをすることはあっても、聞き役になることがほとんどで、自分の話をするのが苦手なのだと言う。しかし、雑談をし始めればどんどん言葉が出てきて、話せない人はいない。「こんなに話せると思わなかった」「こんな話をすると思わなかった」と自分から出てきたものに驚くこともある。そんなとき、わたしは「出せてよかったね」と思う。雑談を仕事にしているのは、話を聞くことで誰かの問題を解決するためではなく、話してもいいと思える場所を作りたかったからだ。
「雑談が苦手だ」と言う人が、安心な場さえあれば話すことができるのならば、本当に苦手なのは「雑談」なのか。「雑談」とは一体何をしているのか。「雑談」の中に含まれている様々な要素を分解しながら考えたものが本書である。
要素を分解しながら考えるというのは、雑談の中でしていることのひとつでもある。よくわからないものや大きなモヤモヤを、話しながら分解して一緒に観察する。大きなモヤモヤをそのままにして避けていると、その中に大事なものが含まれているのに気付かないこともあるし、避けたつもりが形を変えて何度でも目の前に現れることもある。だから、ああでもないこうかもしれないと話しながら、自分の中のモヤモヤを細かく分けてどんな要素があるのかを知る必要がある。
「雑談」とは何なのか、その中に含まれている要素を分解している本書は、「雑談」について雑談をしているとも言える。読みながら雑談にお付き合いいただけると幸いです。
-

-
桜林直子
1978年、東京都生まれ。洋菓子業界で12年の会社員を経て、2011年に独立。クッキーショップ「SAC about cookies」を開店。noteで発表したエッセイが注目を集め、テレビ番組「セブンルール」に出演。20年には著書『世界は夢組と叶え組でできている』(ダイヤモンド社)を出版。現在は「雑談の人」という看板を掲げ、マンツーマン雑談サービス「サクちゃん聞いて」を主宰。コラムニストのジェーン・スーさんとのポッドキャスト番組「となりの雑談」( @zatsudan954)も配信中。X:@sac_ring
この記事をシェアする
「桜林直子『あなたはなぜ雑談が苦手なのか』試し読み」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら