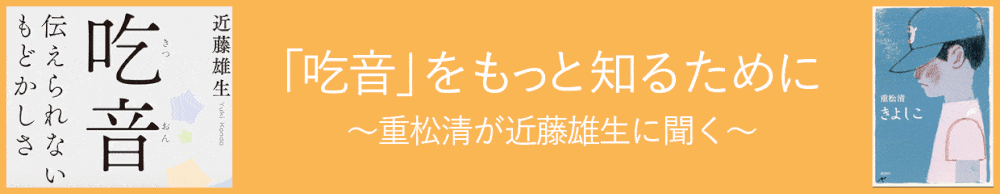2019年12月4日
第1回 当事者の苦しみとは
吃音とはどういうものか。『吃音 伝えられないもどかしさ』を執筆された近藤雄生さんと、『きよしこ』『青い鳥』といった吃音をテーマにした小説を書かれている重松清さん。リクエストの声にお応えして、貴重な場の記録としてまとめました(全4回)。
2019年1月、『吃音 伝えられないもどかしさ』を上梓しました。この本は、吃音を持つ人の困難を、当事者としての私自身の経験を踏まえて書いたノンフィクションです。その帯推薦文と書評を寄せてくださったのが、重松清さんでした。
重松さんは、ご自身も吃音の当事者であり、『きよしこ』『青い鳥』といった吃音をテーマにした素晴らしい小説を書かれています。その両作品が多くの当事者に読まれ、愛されていることを、私は取材を通して実感してきました。そこで重松さんに、本書にお言葉をいただくことができれば……と、思い切ってご依頼したところ、ご快諾いただき、帯に次のような推薦文を寄せてくださいました。
<よくぞここまで吃音と向き合ってくれました。吃音を持つものとして、最敬礼。>
書評でも、当事者としての深い思いがこもった文章を綴ってくださいました。そしてそれらのお言葉をいただいた上でさらに厚かましくも、トークショーなどでご一緒いただけたらと思いお願いをしたところ、お引き受けいただくことができました。
そうして2019年5月31日、東京・下北沢「本屋B&B」にて、本書の刊行記念イベントとして、重松さんが聞き手となってくださる形でのトークショーが実現しました。
それは自分自身にとって、深く心に残るイベントでした。そして、来場してくださった皆さんにとっても少なからずそうであったらしいことを後に知り、これは多くの方と共有したい内容だと改めて思いました。そこで、当日のトークをまとめました。吃音を知る方にもそうでない方にも、是非読んでいただければうれしいです。
本稿は全4回の第1回となります。
近藤雄生

当事者の苦しさを知ってほしい
重松 今日は僕から質問をさせてもらいながら、進めたいと思います。
近藤 よろしくお願いします。
重松 僕はいつも、講演など人前で話すときは、マイクを手にもって、反対の手で横隔膜の辺りを押さえるようにしています。そうしないとどもっちゃうからです。でも今日は、趣旨から考えると、盛大にどもった方がいいのかな……。そう思うと、少しだけ気持ちが楽です。
さて、『吃音』については、書評やインタビューがすでにたくさん掲載されていますが、近藤さんのもとにはどんな感想が届いていますか。
近藤 当事者とそうでない方々、両方から多くの感想をいただきました。この本は、特に当事者ではない方に吃音の苦しさを知ってほしいという思いで書いたので、当事者ではない方から、発売直後から多数の連絡をいただけたことはうれしかったです。吃音がこんなに苦しく、人生に影響するものだとは知らなかった、と多くの方が驚かれたようでした。
その一方で、吃音の当事者からは、読んでいて苦しいという声も届き、それは自分としては辛いところでした。ただ、希望を感じるとおっしゃってくださった当事者の方も少なからずいて、多くの方にとってそういう本でありえたらと思うのですが、その辺りはいまも葛藤があります。
重松 希望はあっても、励ましの言葉は安易には使っていませんよね。当事者を励ますだけの本ではないという感触を、僕は強く持ちました。一方、当事者ではない人にとっては、この本に書かれている吃音の苦しさは、きっと想像をはるかに超えるものだったのでしょう。
近藤 そうですね。僕自身は、本に書いた通り、30歳になるころに大きな変化が訪れた結果、いまはほとんど吃音の症状は出ないようになったのですが、吃音で悩んでいた高校や大学時代でも、一見しゃべった感じはいまとそれほど変わりませんでした。だから当時の友人も、僕が吃音で悩んでいたことはほぼ誰も知らなかったと思います。
僕の場合、自分の名前など言い換えのできない言葉を出そうと思うと、「こ、こ……」みたいに詰まってしまうのが主な症状でした。言えない場合も、「いや」や「あの」を挟んだりして、言えるタイミングが来るのを待てば、なんとかわからないように伝えることができたので、周囲から見てすぐにわかるという感じではなかったんです。
でも、いつもそのように意識しながら話すのはとても疲れ、苦悩は大きなものでした。そしてその問題をきっかけの一つとして、僕は普通に就職するのをやめて、旅をしながらライターをするという進路を選ぶことになりました。周囲には一見わからないほどだったものの、自分にとって吃音は、そのような大きな方向転換をしようと思うぐらい重大な問題でした。
周りからはわからないけど当事者にとってはものすごく大きな問題、というのは、吃音以外にも多くあると思います。この本は、吃音の苦しさを知ってもらうとともに、吃音を通じて、他の人の問題に想像力を持つ大切さを感じてもらえれば、という気持ちで書きました。
松屋と吉野家とすき家があったら、松屋に入る
重松 近藤さんが、ライターを志して5年以上の間ご夫婦で旅した経験を書かれた『遊牧夫婦』という本の中にも、吃音を隠すために費やすエネルギーは膨大で、常に激しく疲労していた、という表現がありますね。やっぱり隠したいと思うものなんですよね。
近藤 僕自身としては、どもって、「ぼ、ぼ、ぼ」となったり、声が出ないまま口だけがぱくぱくするのを、恥ずかしいと思う気持ちがあったので、なんとか隠そうと必死でした。でも一方で、症状を隠せれば解決するということでもありませんでした。
例えば、ファストフードに行って、テリヤキバーガーを頼みたくても「て」がどうしても言えなそうだったら、どもらずに言えそうな別なものをぱっと頼んだりしていました。そうすれば吃音は隠せるものの、ああ、また言えなかった、という気持ちが圧し掛かります。
それでも、自分のことだったらその時に少し落ち込むだけで済むのですが、たとえば、友だちと店内で食べた後に、「ちょっと近藤、ナゲットを5個買ってきて」なんていわれることもありますよね。そうなったら、ナゲットを5個買わないといけない。さすがに「ごめん、間違ってアップルパイを買っちゃった」というわけには、いかないですよね。だから僕はそういう場合、絶対に「買ってきて」と頼まれないような一番奥の出づらい席に、何気なく座るようにしていました。そういう積み重ねに、すごく疲れてしまうんですね。
重松 とてもよくわかります。僕も同じく、言い換えができない固有名詞が苦手なのですが、特に、重松清の「き」が本当に言えなくて。そのくせ転校はたくさんしたから、いつも最初の挨拶が大変でした。いまも、電話の通信販売なんかで「お名前は」と聞かれて「重松です」と言った後に、「下のお名前は」と聞かれると、わあ、来た……ってと思います。その場合は、もう一度「重松清です」と一気に言ったり……。一気に言えば、なんとかなるから。
近藤 ご自身の名前の言いづらさについて、『きよしこ』に書かれていましたよね。
重松 うん、そうなんです。言いたい言葉が、もう、そこにはっきりあるのに言えないって、本当につらいんだよね。……実は、『吃音』の中で、自殺してしまった看護師の飯山さん(※1) が、死を選ぶ前の最後の食事が回転ずしだった、というところがありました。それを見たときに、俺は、泣いちゃったんだよね……。回転ずしだったら、黙って食べられるじゃないですか。欲しいものをね。もしかしたら、飯山さんにとって回転ずしというのは、唯一、黙って自分の欲しいものが食べられる場所だったのかなって、想像したんですよね。
※1.^ 飯山さんは、吃音の影響で警察官になる夢をあきらめ、30代で看護師になった男性です。しかし就職先の病院で周囲の理解が得られず、看護師になって4カ月後に自死されました。
近藤 そこは、気づきませんでした。うん、確かに、そうかもしれないですね……。

重松 僕は昔、松屋と吉野家とすき家があったら、絶対に松屋に入っていたんです。
近藤 ああ、食券なんですよね、松屋だけは。
重松 そう! 券売機だから。
近藤 わかります。券売機がある店ってホッとしますよね。
重松 そう、吉野家では注文の時、卵の「た」が言えないんですよ。だから「大盛り卵」みたいに、一気にぱんと言わなければいけない……。
近藤 僕も、ほしい商品の名前を店員さんに言わなければならないのに言えないときは、「あれ?」とかなんとかつぶやいて、考えるふりをしてタイミングをはかり、言えそうになった時に一気に言うということをよくしました。でも、そうすると結構、相手が聞いていなかったりして、「え? もう一度お願いします」とか言われちゃうんですよね。
一同 (笑)
重松 せっかく頑張って言ったのにね。
近藤 もうそうなるとアウトです。「いや、あの……」と、よくしどろもどろになっていました。「もう、ちゃんと聞いてよ。お願いだから」って……(笑)。
話をしてもらえることへの感謝
重松 この本のサブタイトルは「伝えられないもどかしさ」です。「『伝えられない』というもどかしさを、伝えられない」という二重のもどかしさが、きっと吃音の当事者の皆さんにはあるのだろうと思います。そういう人が、日本に100万人ほどいる。とすれば、おそらく誰でも、知り合いや同級生にいたと思うんだよね。この本を読んだ人の多くは、その顔を思い出して、ああ、あのときあいつはあんなふうに苦しんでいたのかって思ったんじゃないかな。
近藤 そういった感想は、とても多かったです。この本を読むまでは、身近に吃音の人がいるという意識はなかったけれど、そう言えば小学校のときの彼はそうだったのでは、とか、同僚のあの人はもしかすると……と読みながら思った、とか。
重松 そう。だからこの本は、そういう人の顔を思い浮かべながら、みんなかみしめて読んでいるんじゃないかって思うんです。そこがやはり、100万人という数の多さの意味なのだろうなと思います。まさにそのような当事者の方が、この本の中にはたくさん登場しますが、登場してくれた皆さんの、本に対する感想はどのようなものでしたか。
近藤 この本の中心的な存在である髙橋さん(※2) は、つらい経験も含めて何から何まで話してくださった上で、それをどう書くかについては僕に託してくださいました。まずそのことにすごく感謝の気持ちがあります。髙橋さんには、本の発売前に直接会ってお渡しして、その何日か後に感想をいただいたのですが、その中には「思っていた以上に細かいところまで書いてあって、正直戸惑いがあります」とありました。でも、その一方で、そこまで書いてくれたからこそこの本には価値がある、読まれるのは正直つらいところがあるけれども、多くの人に読んでほしいと思う、ともおっしゃって下さいました。
他人の人生を書くというのは、非常に重い。その重さや責任を、いまなおずっと感じています。本を書いて終わりではいけない。本が完成しても、もちろんその人の人生は続いていくし、自分は書き手としてそのことを意識し続けないといけないと、この本を書いて改めて感じています。
※2.^ 本書は複数の吃音当事者の話で構成されていますが、その軸となるのが、重度の吃音を抱えた髙橋さんという30代の男性です。吃音のために就職など様々な困難を抱えていた髙橋さんが、一人娘のももちゃんとともに生きていくためには吃音を改善させるしかないと、訓練に身を投じる様子を追っています。
重松 髙橋さんをはじめとして、自分の一番しんどい体験を話してくれた皆さんの、取材を受けてくれた一番の理由というのは何だったのでしょう。皆さん、なぜ近藤さんの取材オファーに応えて、そこまで話してくれたのだと思いますか。
近藤 なかなか理解されないもどかしさ、それが皆さんの根底に共通してあるのではないでしょうか。でも同時に、そこにはそれぞれ、違った思いもあるのだろうと思います。
重松 こういうイベントに来てくれた人の中で、「実は自分も吃音があるんです」と近藤さんに言ってくる人も、おられるのではないですか。
近藤 はい、当事者の方がいらしてくださることは多いですね。だから今回のイベントではあらかじめ、入場の際に予約した名前を口頭で言う必要はないことを明記しておいてもらいました。スマホの画面やチケットを見せればOKです、と。会場で名前を言うのが嫌で来られない人がきっといると思って。僕自身がかつて、そうだったからです。
(第2回はこちら)
-

-
近藤雄生
こんどう・ゆうき 1976(昭和51)年東京都生まれ。東京大学工学部卒業、同大学院修了。2003年、旅をしながら文章を書いて暮らそうと、結婚直後に妻とともに日本を発つ。 オーストラリア、東南アジア、中国、ユーラシア大陸で、約5年半の間、旅・定住を繰り返しながら月刊誌や週刊誌にルポルタージュなどを寄稿。2008年に帰国、以来京都市在住。著書に『遊牧夫婦』シリーズ(ミシマ社、角川文庫)、『旅に出よう』(岩波ジュニア新書)、『吃音 伝えられないもどかしさ』(新潮社、講談社本田靖春ノンフィクション賞・新潮ドキュメント賞最終候補、本屋大賞ノンフィクション本大賞ノミネート作)、『オオカミと野生のイヌ』(エクスナレッジ、本文執筆)など。最新刊に『まだ見ぬあの地へ』(産業編集センター)。大谷大学/京都芸術大学/放送大学 非常勤講師、理系ライター集団「チーム・パスカル」メンバー。
-

-
重松清
しげまつ・きよし 1963(昭和38)年、岡山県生れ。早稲田大学教育学部卒業。出版社勤務を経て執筆活動に入る。1991(平成3)年『ビフォア・ラン』でデビュー。1999年『ナイフ』で坪田譲治文学賞、同年『エイジ』で山本周五郎賞を受賞。2001年『ビタミンF』で直木賞、2010年『十字架』で吉川英治文学賞、2014年『ゼツメツ少年』で毎日出版文化賞を受賞。現代の家族を描くことを大きなテーマとし、話題作を次々に発表している。著書は他に、『きよしこ』『流星ワゴン』『疾走』『その日のまえに』『きみの友だち』『カシオペアの丘で』『青い鳥』『くちぶえ番長』『せんせい。』『とんび』『ステップ』『かあちゃん』『ポニーテール』『また次の春へ』『赤ヘル1975』『一人っ子同盟』『どんまい』『木曜日の子ども』など多数。
この記事をシェアする
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 近藤雄生
-
こんどう・ゆうき 1976(昭和51)年東京都生まれ。東京大学工学部卒業、同大学院修了。2003年、旅をしながら文章を書いて暮らそうと、結婚直後に妻とともに日本を発つ。 オーストラリア、東南アジア、中国、ユーラシア大陸で、約5年半の間、旅・定住を繰り返しながら月刊誌や週刊誌にルポルタージュなどを寄稿。2008年に帰国、以来京都市在住。著書に『遊牧夫婦』シリーズ(ミシマ社、角川文庫)、『旅に出よう』(岩波ジュニア新書)、『吃音 伝えられないもどかしさ』(新潮社、講談社本田靖春ノンフィクション賞・新潮ドキュメント賞最終候補、本屋大賞ノンフィクション本大賞ノミネート作)、『オオカミと野生のイヌ』(エクスナレッジ、本文執筆)など。最新刊に『まだ見ぬあの地へ』(産業編集センター)。大谷大学/京都芸術大学/放送大学 非常勤講師、理系ライター集団「チーム・パスカル」メンバー。
対談・インタビュー一覧
-

- 重松清
-
しげまつ・きよし 1963(昭和38)年、岡山県生れ。早稲田大学教育学部卒業。出版社勤務を経て執筆活動に入る。1991(平成3)年『ビフォア・ラン』でデビュー。1999年『ナイフ』で坪田譲治文学賞、同年『エイジ』で山本周五郎賞を受賞。2001年『ビタミンF』で直木賞、2010年『十字架』で吉川英治文学賞、2014年『ゼツメツ少年』で毎日出版文化賞を受賞。現代の家族を描くことを大きなテーマとし、話題作を次々に発表している。著書は他に、『きよしこ』『流星ワゴン』『疾走』『その日のまえに』『きみの友だち』『カシオペアの丘で』『青い鳥』『くちぶえ番長』『せんせい。』『とんび』『ステップ』『かあちゃん』『ポニーテール』『また次の春へ』『赤ヘル1975』『一人っ子同盟』『どんまい』『木曜日の子ども』など多数。

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら