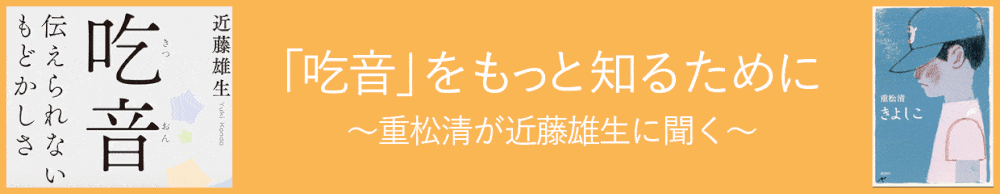2019年12月5日
第2回 家族の物語として
吃音とはどういうものか。『吃音 伝えられないもどかしさ』を執筆された近藤雄生さんと、『きよしこ』『青い鳥』といった吃音をテーマにした小説を書かれている重松清さん。リクエストの声にお応えして、貴重な場の記録としてまとめました。第2回をお届けいたします(全4回)。
(前回はこちら)
2019年1月に、『吃音 伝えられないもどかしさ』を上梓しました。この本は、吃音を持つ人の困難を、当事者としての私自身の経験を踏まえて書いたノンフィクションです。その帯推薦文と書評を寄せてくださったのが、吃音の当事者であり、『きよしこ』『青い鳥』といった吃音をテーマにした小説も書いてこられた重松清さんです。帯には、
<よくぞここまで吃音と向き合ってくれました。吃音を持つものとして、最敬礼。>
というお言葉をいただき、書評でも、当事者としての深い思いがこもった文章を綴ってくださいました。その上、トークショーもご一緒していただけることになりました。
そうして、2019年5月31日、東京・下北沢「本屋B&B」にて、本書の刊行記念イベントとして、重松さんとのトークショーが実現しました。重松さんが聞き手となってくださったそのトークをまとめたのがこの連載記事です。
第1回では、重松さんからのご質問を糸口に、吃音にまつわる様々な経験、読者からの感想などについて話を進めていきました。第2回では、重松さんが特に印象的だったという部分を中心に、本の中身へと踏み込んでいきます。
近藤雄生

全然忘れていなかった、少年時代の辛さ
重松 僕は自分が小学生のときに、吃音で本当にしんどかった経験があるので、この本の中では、小学生の晴渡君(※3)の話が特に印象的でした。大人の当事者の話とはまた違う、吃音のある子どもの気持ち、そのお母さんの思い、というのは、書くのが大変だったのではないでしょうか。
※3.^ 晴渡君は、本書に登場する吃音のある小学生。吃音があることで学校生活などに少なからぬ困難を抱える彼と、息子の問題をなんとか軽減できないかと悩みながら力を尽くすその母親の姿を本書の中で描いています。
近藤 悩む部分は、多かったです。晴渡君は当時小学校の低学年でしたが、その年齢の子に、自身の吃音について尋ねるのはどうなのだろう、という思いがまずありました。訊くこと自体の是非に加え、訊いたとしても、返ってくる言葉はこちらが無理やり誘導したようなものになりかねない。そこでここは、晴渡君と一緒に時間を過ごす中で感じたことを書くのが一番いいように思い、そうしました。一方、お母さんの胸中は、直接たくさん聞かせていただき、それを本の中に収めることはそれなりにできたように思っています。ただやはり、どこまで晴渡君の気持ちを表現できたのかについては、いまなお心もとないものが残っています。
重松 それこそ晴渡君が中学生、高校生になったら、自分の吃音に対する思いも、また変わってくるかもしれない。描き方も、全く変わってくるだろうし、もしかしたら、取材自体できなかったかもしれない……。
近藤 重松さんは、晴渡君のところを読まれていかがでしたか。
重松 あのね……、僕は、書評と帯の推薦コメントを書くために、いち早くゲラを送ってもらって年末年始に読みました。そうしたら、ものすごく、悪化しちゃったのね、吃音が……。いまもそうなんだけれど、すごく、しんどいんですよ。これを読みながら、当時のことを、いっぱい、思い出してね。自分が忘れたふりをしていたことに、気づかされたんだ。実は全然忘れてなかったんだ、というかね。……うん、俺はまだ、少年時代の、あれやこれやの思い出が、傷になっているんです。
近藤 そうだったんですね……。
重松 うん……。それこそ、近藤さんが就職を断念したのと同じように、僕は先生になりたいと思っていたのを、面接とかが難しいだろうと思って、諦めた。そんないろんなことが思い出されるんです。だから本音を言えば、近藤さんの本を読んだ年末年始は、本当にしんどかった。でもそれだけ本当に、……よくぞここまで吃音と向き合ってくれたなという気持ちが、あるんです。
実名の重さ

重松 晴渡君の日々の苦悩がすごく想像できる一方、本の中では、卓球に夢中になっている時の無邪気な様子も描かれていて、それが救いになっているように感じました。もしかすると、中学生の晴渡君を描こうと思ったら一回フィクションにしておかないとしんどかったかもしれない。そういう意味でも、ノンフィクションで、しかも実名で書いたことに、近藤さんの覚悟が感じられました。
近藤 晴渡君に関しては、実名でよかったのかという気持ちが、いまなおあります。ご両親には了承いただいているものの、晴渡君自身には、聞いて判断を迫るのは違う気がして、直接は聞いていません。もしかしたら彼のところは、例えば名前の漢字を変えるなどするべきかも、とも考えました。検索すると、色々出てきかねない時代ですし、晴渡君が成長していった後に、こんなこと書かれたくなかったと思うこともあり得ると思うんです。雑誌連載では、そんなこともあって苗字は載せなかったのですが、本では、色々と考えた結果、苗字も含めた実名にしました。正解はないと思います。ただいずれにしても、書いたからには、そのことを考え続けていかなければと思っています。
重松 そこまでの葛藤を近藤さんがいまなお持ち続けていらっしゃるからこそ、僕は、この本と、書き手の近藤さんに対して、信頼を持てたのだと感じます。話をしてくれた人の覚悟も含めてすべて、この中にあるように思います。
近藤 実名か仮名かというのは、一見大した違いではないようで、大きいことだと思います。実名だと、リアリティーや重みのようなものが、読み手にとっても書き手にとっても生じます。しかし仮名にすると、どこかで逃げ道ができてしまう。だからできるだけ実名で書きたい、というのが僕の気持ちです。
重松 うん、そうだよね。2016年に障害者福祉施設「津久井やまゆり園」で起きた殺傷事件でも、被害者の名前は当初は伏せて報道されていたけれども、実際には、生きてきた証しとして自分の子どもの名前を出してくれ、と言う遺族も多かったわけですよね。だから僕はやはり、この本を読んで、当事者の人たちの尊厳を守ってくれている感じがしたんですよ。こういう事例がありました、ということではなくて、この人たちそれぞれの人生を、ちゃんと書いてくれているというのが感じられて、すごくうれしかったんです。
家族の物語がたくさんある
近藤 この本へとつながる最初の取材・執筆を行ったのは、2002年、吃音で悩んでいた20代の頃でした。当時、「吃音、治します」といった類の広告を雑誌などに出している怪しげな“吃音矯正所”が少なからずあり、その実態を暴きたいというのが、記事を書こうというモチベーションでした。しかし同時に、吃音をテーマに取材して記事を書いたら、自分の吃音に何か変化が起きるかもしれない、というぼんやりとした期待もありました。結局、何も変わらなかったんですけれど。
重松さんは、吃音をテーマにした『きよしこ』や『青い鳥』を書かれたことで、何かご自身に変化はありましたか。
重松 僕が『きよしこ』を書いたのも2002年でした。もう17年もたっているんだけど、いまでも、もし自分が死んで、棺桶に一冊だけ本を入れてもらうとしたら、それは『きよしこ』なんですよ。
近藤 そうなんですか。
重松 永遠に『きよしこ』です。これを書いて、初めて、作家になってよかったと思ったんです。吃音の子どもを主人公とする小説を『小説新潮』というエンターテインメント小説誌に出してもらえた。絶対にいると思ったんです、こういう小説を必要としている人が。というよりも昔の俺に読ませたかったですね。『きよしこ』と『青い鳥』は。
近藤 取材をしていると、『きよしこ』や『青い鳥』を実際に読んでいる当事者は多く、「重松さんの作品に救われた」「すごく大切な本だ」という人に多く出会いました。
重松 それは本当にうれしいです。『青い鳥』の主人公は吃音のある先生で、もし俺が先生になったら、こんな先生になりたかったという存在を書いたんです。だからある意味、社会性よりも個人的な物語なんです。そこが小説とノンフィクションの役割の違いかもしれませんね。
近藤 『青い鳥』も『きよしこ』も、個人の物語でありながら、社会に通じていますよね。いまは当事者同士もつながれるし、いろんな情報がすぐ見つかるけれど、重松さんが『きよしこ』を書かれたころは、きっとそうではなかった。そのような状況でこういう小説が生まれたのは、当事者にとってとても大きな意味があったのだと思います。
重松 そうですね。サイン会とか以外で一番サインをした本が、『きよしこ』なんです。みんな、ぼろぼろになった本を持ってきてくれる。それが心からうれしいです。
近藤 読み込んで、大事にしてくれている。書き手としては、それ以上の喜びはないですね。
重松 『きよしこ』がそれだけ自分にとって重要な作品だっていう気持ちがあるように、僕にとって、やはり子ども時代の吃音の経験って本当に大きいから、近藤さんの本の、晴渡君のいろんな思いを読みながら、僕ね……、本当に、泣いちゃったんだよね。何度も、何度も。
そして、子ども本人もそうだけど、吃音の子を持つ親の思いも、すごく大事だと思う。晴渡君のお母さんは、晴渡君の吃音のことをずっと心配して、不安を抱え続けてきましたよね。一時は自分を責めたりもして、いろんな段階を経てこられた。そうした後に、気持ちが少しずつ変化して、吃音のことを広く知ってもらおうと小冊子をつくるようにもなる。このお母さんの話は、大事なものだと思うし、心に残っています。
近藤 はい、本当にそうですね。
重松 あと、髙橋さんと娘のももちゃんの話、それから看護師の飯山さんの無念を背負ったお姉さんとお母さん。結果的にこの本には、家族の物語がいっぱいあるんですよね。それは、吃音の話にとどまらない、様々な障害や弱さを持って生きていく子どもと親の物語でもある。すごく、家族があるんだよね、ここに。
近藤 吃音は生活の根幹にかかわるから、必然的に、家族の問題へとつながっていくように感じます。髙橋さんは、娘のももちゃんと二人で暮らしているのですが、彼の、吃音を改善したいという思いの背景にあるのは、ももちゃんを育てていくという希望なのだと思います。先日NHKの番組のインタビューでも髙橋さんは、「娘がいなかったら、自分の人生は、終わっていた」とおっしゃっていました。だから自分にとって娘がすべてなんだ、と。
書き手であり当事者であるという意味

重松 そろそろ前半の最後の質問になります。近藤さんには、当事者として吃音で悩んできた経験があるわけですけど、そのバックボーンがあったかなかったかで、この本の内容は変わったと思いますか。
近藤 そうですね。自分が当事者であったからこそ書けた部分は、少なからずあると思います。一方、あとがきに書きましたけど、当事者としての感覚がありつつも、現状では悩まなくなって、ある程度吃音と距離が置けるようになったことが、この本を最後まで書き切る上で大きな意味を持っていたとも感じます。
ただ、リアルタイムで悩んでいない自分は、いま悩んでいる当事者に対して「気持ちがわかります」とは簡単には言えないと思っています。いま悩んでいるということと、過去に悩んでいた経験があるということの間には、大きな隔たりがあるからです。自分なりに、吃音の苦しさや困難は体験として知っているつもりですが、でもそれは、いま悩んでいる人に対して、わかります、と言うのとは違う……。その辺りの距離の保ち方が、この本を書く上では重要だった気がします。さらに、書き手であり当事者でもある立場として取材相手とどのような距離感でいるべきか、吃音を知らない読者との距離をどう縮めるか、といった点については、担当編集者にも、重要なアドバイスをたくさんいただきました。
そういう点も含めて、当事者という自分の経験は、やはりこの本を書く上では大きかったと思います。
重松 それは、まさにそうですね。うん、わかるということに対する恐れみたいなものをしっかりとお持ちである一方で、取材対象と遠くはないという距離感。それは大きかったでしょうね。
近藤 そうですね。
重松 うん。そのあたり、雑誌で不定期に掲載されたものを単行本としてまとめるにあたって、構成も含めておそらく相当お考えになったと思います(※4)。後半では、そうした点についてもまた、お伺いしたく思っています。
※4.^ 本書は、2014年~2017年にかけて『新潮45』に不定期に掲載された連載記事が元になっています。
(休憩へ)
(第3回はこちら)
-

-
近藤雄生
こんどう・ゆうき 1976(昭和51)年東京都生まれ。東京大学工学部卒業、同大学院修了。2003年、旅をしながら文章を書いて暮らそうと、結婚直後に妻とともに日本を発つ。 オーストラリア、東南アジア、中国、ユーラシア大陸で、約5年半の間、旅・定住を繰り返しながら月刊誌や週刊誌にルポルタージュなどを寄稿。2008年に帰国、以来京都市在住。著書に『遊牧夫婦』シリーズ(ミシマ社、角川文庫)、『旅に出よう』(岩波ジュニア新書)、『吃音 伝えられないもどかしさ』(新潮社、講談社本田靖春ノンフィクション賞・新潮ドキュメント賞最終候補、本屋大賞ノンフィクション本大賞ノミネート作)、『オオカミと野生のイヌ』(エクスナレッジ、本文執筆)など。最新刊に『まだ見ぬあの地へ』(産業編集センター)。大谷大学/京都芸術大学/放送大学 非常勤講師、理系ライター集団「チーム・パスカル」メンバー。
-

-
重松清
しげまつ・きよし 1963(昭和38)年、岡山県生れ。早稲田大学教育学部卒業。出版社勤務を経て執筆活動に入る。1991(平成3)年『ビフォア・ラン』でデビュー。1999年『ナイフ』で坪田譲治文学賞、同年『エイジ』で山本周五郎賞を受賞。2001年『ビタミンF』で直木賞、2010年『十字架』で吉川英治文学賞、2014年『ゼツメツ少年』で毎日出版文化賞を受賞。現代の家族を描くことを大きなテーマとし、話題作を次々に発表している。著書は他に、『きよしこ』『流星ワゴン』『疾走』『その日のまえに』『きみの友だち』『カシオペアの丘で』『青い鳥』『くちぶえ番長』『せんせい。』『とんび』『ステップ』『かあちゃん』『ポニーテール』『また次の春へ』『赤ヘル1975』『一人っ子同盟』『どんまい』『木曜日の子ども』など多数。
この記事をシェアする
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 近藤雄生
-
こんどう・ゆうき 1976(昭和51)年東京都生まれ。東京大学工学部卒業、同大学院修了。2003年、旅をしながら文章を書いて暮らそうと、結婚直後に妻とともに日本を発つ。 オーストラリア、東南アジア、中国、ユーラシア大陸で、約5年半の間、旅・定住を繰り返しながら月刊誌や週刊誌にルポルタージュなどを寄稿。2008年に帰国、以来京都市在住。著書に『遊牧夫婦』シリーズ(ミシマ社、角川文庫)、『旅に出よう』(岩波ジュニア新書)、『吃音 伝えられないもどかしさ』(新潮社、講談社本田靖春ノンフィクション賞・新潮ドキュメント賞最終候補、本屋大賞ノンフィクション本大賞ノミネート作)、『オオカミと野生のイヌ』(エクスナレッジ、本文執筆)など。最新刊に『まだ見ぬあの地へ』(産業編集センター)。大谷大学/京都芸術大学/放送大学 非常勤講師、理系ライター集団「チーム・パスカル」メンバー。
対談・インタビュー一覧
-

- 重松清
-
しげまつ・きよし 1963(昭和38)年、岡山県生れ。早稲田大学教育学部卒業。出版社勤務を経て執筆活動に入る。1991(平成3)年『ビフォア・ラン』でデビュー。1999年『ナイフ』で坪田譲治文学賞、同年『エイジ』で山本周五郎賞を受賞。2001年『ビタミンF』で直木賞、2010年『十字架』で吉川英治文学賞、2014年『ゼツメツ少年』で毎日出版文化賞を受賞。現代の家族を描くことを大きなテーマとし、話題作を次々に発表している。著書は他に、『きよしこ』『流星ワゴン』『疾走』『その日のまえに』『きみの友だち』『カシオペアの丘で』『青い鳥』『くちぶえ番長』『せんせい。』『とんび』『ステップ』『かあちゃん』『ポニーテール』『また次の春へ』『赤ヘル1975』『一人っ子同盟』『どんまい』『木曜日の子ども』など多数。

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら