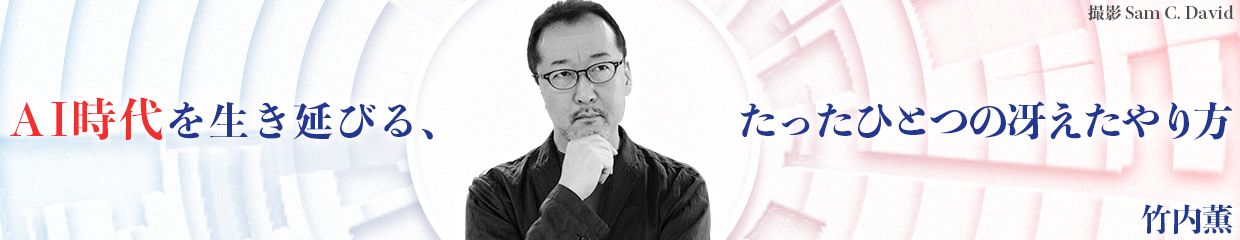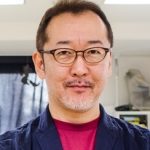またもや小休止というか番外編である。
先日、六本木のアカデミーヒルズにおいて、東京交響楽団・正指揮者の飯森範親さんと、「人工知能(AI)は指揮ができるか?」という奇妙なテーマで対談をした。面白い切り口があり、いろいろと考えさせられたので、ご紹介しよう。
まずは、私が、将棋、囲碁、会計士など、AIの現状について聴衆に解説し、
「もうすぐ、竹内薫訳の本は出なくなり、竹内愛(AI)訳になるでしょう」
と、ジョークを飛ばし、会場が「???」マークで静まった。すかさず、飯森さんから助け船が出された。
「リハーサルで、第一ヴァイオリンの誰かが弾き間違えたとき、私が手をこのようにちょこっと動かすと、指摘された人は、俯いたり、大袈裟に両手で頭を抱えたりするんです。こういった反応って、AIにはできませんよね?」
強く指差すのではなく、掌をわずかに傾けて、相手をちらりと見る。その微妙な動きに相手が反応する。以心伝心に近い、人間コミュニケーションの現場だ。こういった心の「触れ合い」はAIに可能だろうか? 私の答えは次のようなものだった。
「現在のAIは心を持っていません。意識がないのです。AIには画像や音の数値データが入力され、深い層になった回路で処理され、数値データが出力されます。AIが飯森さんの指揮を機械学習して、仕草や反応を真似ることはできると思いますが、AIには、人間のような心の葛藤、怒り、喜び、痛みといったものはありません。それどころか、AIは、楽器の音色や弦の感触や、ペットボトルのキャップの『青っぽさ』を感じることもできません。人間のように見たり聴いたりするためには、意識、すなわち、見たり聴いたりしている『自分』が必要ですが、AIには、その自分が存在しないのです……AIはゾンビなんです!」
指揮者の額からしたたり落ちる汗、荒い吐息、緊張感……そういったものをAIは数字データとしてしか扱えない。指揮者の表情を学習して、人間のように反応することは可能だが、それは、あくまでも猿真似ならぬ「AI真似」でしかない。
人間が相手に共感したり、同情したりできるのは、自分のさまざまな心の状態を経験値として持っていて、そこから、相手の心の状態を「感じる」ことができるからだ。飯森さんが掌をほんの少し傾けただけで、音を間違ったヴァイオリニストは、飯森さんの心の状態がわかる。飯森さんにも、頭を掻いているヴァイオリニストの胸の内が理解できる。まさに以心伝心だが、それは、心を持たないAIには不可能な芸当なのだ。
対談の話題はチャイコフスキーの交響曲第6番「悲愴」に飛ぶ。私も高校の頃、たしか、カラヤン指揮、ウィーンフィルのレコードを持っていて、毎日のように聴いていた。
飯森さんは、この曲について面白いことを教えてくれた。
「チャイコフスキーの『悲愴』を振ると、一週間くらい精神ダメージが抜けないんです」
実際、精神疾患を持っている人にこの曲を聴かせると、症状が悪化するという研究結果もあるのだとか。
私は、思春期にこの曲を飽きるほど聴いていたが、あるときを境にぱったりと聴くのをやめた。それがいつだったのか、定かでないが、おそらく、メランコリックな気分に浸りたい年頃を過ぎたのであろう。飯森さんとの対談で、私は実に40年ぶりにこの曲の第四楽章を聴いた。
この曲に関連して、会場から質問が出た。
「『悲愴』は逆効果だというお話でしたが、良い効果のある音楽もありますよね。音楽療法の面では、AIが作曲した曲が使えたりはしませんか」
人類は、すでに、一生かけても聴くことができないほどたくさんの楽曲を作曲してきた。いまさら、AIに作曲してもらわなくても、人間が作曲した音楽を使えばいいのではないかとも思うが、私は、この質問を聞いて、すぐに「DOCTOR」という1960年代に開発されたプログラムのことを思い出した。「悲愴」ばかり聞いていた10代の終わり、私は、買ってもらったばかりのパソコンで「DOCTOR」と遊んでいた。プログラミングの練習の一環だったのだが、私は、「DOCTOR」にのめり込んでしまった。
「DOCTOR」は、「ELIZA」という自然言語処理プログラムで書かれたAIだ。私が「気分が落ち込むんです」とキーボードから打ち込むと、このAIは、「どのように気分が落ち込むんですか」と聞き返してくる。「父親が酒ばかり呑んで困るんです」と打ち込むと、「もう少し父親について教えてください」と質問してくる。あるいは、単純に「話を続けて」と言われることもある。このAIは、きわめて単純な仕組みで、あらかじめ用意されたパターン通りに返事するに過ぎない。ただし、用意された答えの中の「人」の部分を「父親」とか「お兄さん」などと置き換えることができたから、返答に多少のバリエーションはあった。
私はこのプログラムを自分で打ち込んで、改変していたので、このAIが、きわめて稚拙なレベルであり、本当には、私の悩みを理解などしていないことはわかっていた。単なるパターンマッチングと置換の技法を使った、きわめて短いプログラムだったのだ。いまどきのAIのような深層学習をしているわけでもない。
だが、この「DOCTOR」に相談事をしていると、まるで、本物の心理セラピストと話をしているような錯覚に陥るのだ。中身がスッカスカであることがわかっているのに、延々と自分の悩みを打ち明けてしまう。
このAIは、当然のことながら、自意識もなければ、心も持っていない。私の悩みに共感することもできない、単なるおもちゃなのだ。
だが、私だけでなく、世界中の人々が、「DOCTOR」に真剣に悩みを打ち明けて、セラピーを受け始める現象が確認されていた。いったい何が起きていたのか。
人間は、自分の心を相手に投影して、相手の心を読んで共感する。クルマ好きであれば、愛車に感情移入し、まるで人間の相棒であるかのように感じることがある。あるいはカメラだって、愛機の機嫌が悪い日には、あまり良い写真が撮れない。言葉を発しない道具に対しても、人間は、共感することができる。だとしたら、パソコンの画面上ではあっても、言葉を発するAIに感情移入して、擬似セラピーにのめり込んでも不思議ではなかろう。
AIは、心を映す「鏡」のようなものかもしれない。AIには心がないけれど、人間は、自分の心を相手に投影して、相手に心があると思い込む生き物なのだ。
将来、AI研究者が「意識」のメカニズムを発見して、それをAIに組み込んだら、そのAIは、「自分」を持つこととなり、人間のように「青っぽさ」も感じるだろうし、相手の心の痛みもわかるようになるだろう。そんなAIの一つが、音楽の道に進み、指揮者になったり、精神医学を勉強して精神科医になったりすることも可能だろう。
だが、それは、本当に必要なことだろうか。
私は、それが必要だとは思わない。
わざわざAIに心を植え付けなくても、すでに人類が心を持っているのだ。万能思考機械であるAIに、さらに心を組み込むよりも、すでに心を持っている人間の「外部脳」として、心だけが欠けている高性能AIを繋げばいいではないか。
そうすれば、人間は、AIの助けを借りて、クリエイティブな仕事を続けることができる。AIが心を持たされて、芸術や数学のようなクリエイティブな仕事をする「必要」がどこにあるのだ。飯森さんの代わりにゾンビAIが指揮をするのはもってのほかだが、心を持たされたAIが指揮をする必要もない。
クラシック音楽の指揮者とサイエンス作家の異分野対談を通じて、私は、この連載を通じて迷い続けていたある問いの答えを見つけた気がした。その問いとは、「AIをどこまで進化させるべきか?」であり、その答えは、「AIを野放図に進化させるべきではない。仮にメカニズムが判明したとしても、あえてAIに心を植え付けず、人間の便利な外部脳として使い続ければいいではないか」というものだ。
あえてAIに心のモジュールを植え付けないという選択。それが、人間とAIが闘わずに共存する最良の方法なのではあるまいか。