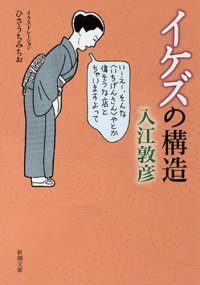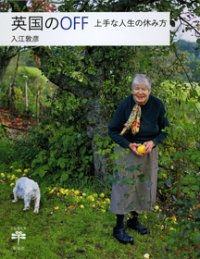羽釜や土鍋で炊かれた旨いごはんが京都を席巻中――という話を書きました。もちろん嘘ではありません。ただ、毎日の生活レベルでたくさんの人たちがそういう特別なごはんを食べてるようになった、と言ったらそれは嘘です。金赤100%の嘘。というか、むしろ普段着の京都人はあまりごはんにこだわらない。だからこそ【ご馳走】としてのごはんを知って感動しているのだと言ってもいいかもしれません。

京都市は日本でも一二を争うパンの消費地。たぶん神戸人より食べてます。美味しい店、個性的なベーカリーにも事欠きません。パン食そのものが根付いたのもどこより早かった。総数は減ったとはいえ、いまでも京都は職住一体型の商いの街の性格を残します。それでなくとも忙しい朝がパン食に切り替わったのはごく自然な成行と申せましょう。
そのせいか日本人にはかなりの割合であるらしい「朝飯には炊きたてごはんが食べたい!」という欲望を彼らはほとんど持っていません。パンでなければ残りもんで〝ちゃっちゃ〟とすますのが京都式。ロンドンに住んでいてもそれは変わりません。以前は昼兼用でお茶漬けをかっこんでましたが、ツレの定年後はトーストも出番が増えました。それでも週の半分は前日の余りで手早くすませます。
その話を葛飾柴又生まれの友人にしたところ「信じられない!」と首を振られました。「あたし、なにがあっても冷ごはんは嫌だわ」なのだそうです。
わたしはむしろ保温ジャーで長時間温められ続けたごはんの匂いが苦手なので、あらためて人の好みはいろいろだなあと驚きました。というか自分、冷ごはんラブなんですよ。電子レンジすら使わない。おかずによっては温めなおしたり、精進揚げとかなら甘辛く煮つけたりとかもしますが、ごはんは冷たいままです。カレーとか冷や×冷やでいったりしますもん。
我が冷ごはんライフはもともとの嗜好に加え、16年前に「たる源」で御つくりおきしてもらったおひつのおかげで、それ以前と比べて格段に味がよくなったからです。おひつはごはんを竈炊きしていた時代、必然性から生まれたわけですが、それにとどまらず幾多の効能があります。わたしにとっては美味しい冷ごはんを作るためのなくてはならぬ道具です。

そもそもごはんというのは空気に触れると甘味を増す性質があります。普通の電気釜からだって、少量ずつお茶碗によそうとぜんぜん味が違うんですよ。ときおり、おひつに移し替えるのは木の香りをつけるためだという記述を目にしますが、それは誤解。炊きあがったお米をたっぷり空気にさらすための行為なのです。「たる源」さんでも匂いのまったくない槇材でおひつを拵えてくださいます。
こちらのおひつで眠ったごはんは、お杓文字で軽くこそげるだけで一粒残らずさらえてしまいます。それは余計な水分がすべて木肌に吸収されているから。冷飯独特の饐えた風味もなし。むろん硬くはなっているけれど、ぎゅっと噛めば米という穀物の味覚がほどけるように口のなかに広がります。
羽釜で炊いたごはんが炊飯器のそれとは別ものの食であるように、おひつで寝かされた冷ごはんもまた、ただの冷や飯とは別もの。むかしから「冷や飯喰らい」というと理不尽に冷遇される身の上の謂ですが、きっとおひつを知らない人の言葉に違いありません。
冷ごはんの味わいは人生の〝ほかほか〟を過ぎてこそ理解できる深い甘さなのです。よう知らんけど。
ちなみに冷ごはんは体にもいいそうですよ。ごはんの澱粉質は冷たくなると、より消化しにくい難消化性澱粉に変化しますが、これは胃で消化され難く小腸でも吸収されずに大腸に届いて食物繊維のように働いてくれます。さらには腸内細菌に分解されて、腸を守る酪酸とか脂肪を燃やすプロピオン酸になってくれる。『おひつ生活で冷ごはんダイエット』。なんか女性誌の特集になりそう。
どうでもいい話ですが、わたし体形はでぶちん以外のなにものでもありませんが体脂肪は14%しかありません。もしかしたら冷ごはんのおかげかも。
もっともこれらの美点に気づいたのはおひつ入手後。最初から分かっていたわけではありません。「たる源」との馴れ初め、ご主人の川尻洋三さんとの出会いを思い出そうとしているのですが、これもはっきりしない。たぶん知るべき年齢に達し、知るべくして知った……というのが正解。
1200年前から京都を動かす原動力【ご縁】の嚮導。
そりゃあ、こんなにいいものならもっと早くにおひつと暮らしたかったと考えなくもない。しかし、このご縁は人生の折り返し点に到達した人間と結ばれたほうが幸せになれる気がします。なぜって、おひつの寿命が約40年ほどだから。あんまり若いうちに手に入れると、自分より先におひつがアカンようになる可能性が高くなる。それってちょっと切ない。
むろん二代目を注文してはいけないわけではないけれど、こんどは最期を看取ってやれないことになる。それも、なんだかもったいない。
というか、おひつが日々の営みに与えてくれるクオリティを必要とするのが、そのくらいの歳まわりからじゃないでしょうか。ごはんをおひつに移すという一手間はほんの僅かなものですが、その一手間を面倒くさいと感じてしまうのが若さってやつです。おひつを使う悦びは歳を喰う余禄かもしれません。
わたしの場合は、不惑を迎えて初めて知った〝間〟のようなものに、おひつという存在がピタリとはまりました。ご縁のお導きならではの納まり具合。
ただねえ、納まりはいいのだけれど、うちのおひつには問題があるのですよ。いや、問題はおひつにではなくイギリスの気候にあるんですけどね。どうもこの国は白木のおひつには乾燥しすぎているらしい。
いろいろ保管に工夫はしています。手を拱いてるだけじゃない。でも、どうしても収縮して銅製の箍が緩んでくる。4年毎に持ち帰って修繕をお願いするんですが、回を追うごとに川尻さんの表情も厳しくなってきました。もしかしたら存外寿命は短いかもしれません。なにしろもはや食卓になくてはならないものなので、でもってそう簡単に替えがきかないので真剣と書いて「マジ」と読むくらい困りました。
なので川尻さんから「鰻用のお重を頼まれて塗りのおひつをこしらえるんですが、それならイギリスでも普通に置いとけると思います」と提案をいただいたときには一も二もなく飛びつきました。今日注文して明日完成するようなものではないので受け取ったのは2年後。それだけにできてきた塗りのおひつ(漆を施したものは「おはち」というそうです)を手にしたときは感動でしたね。茶道具のような美しさ。
というか実は、それこそ菓子器としても使っています。わたしのなんちゃってお点前なら問題ありません。料理を盛りつける鉢としても秀逸です。あと、素麺やうどんをつけ麺にして啜るときも活躍してくれます。おひつの槇材は酢で木肌が黒ずむので寿司桶としては利用できなかったのですが塗りなら大丈夫なのも嬉しい。ばら(ちらし)寿司が鳶色の塗りに映えること。
むろんオリジナルの目的にも使いました。前回紹介した川魚店「大國屋」さんが鰻ごはんの店「大國屋鰻兵衛」を開店される前の話。奥でまかないに炊かれていたごはんを詰めてもらい、お店で売られているできたての蒲焼を載せてもらって食べるんです。マイお箸ならぬマイおひつ。
そんな出自ゆえか、おはちにはとりわけ鰻が似合う気がします。哀しいかなこちらでは「ちょっとそこまで」というわけにはいきませんから、こいつで鰻を食べるには手作りするしかありません。
ええ、イギリスにも鰻いるんです。ゼリー寄せの悪名は聞いたことがおありの方も多いでしょう。
が、なかには日本人の口に合うものもあるんですよ。個人的に気に入ってるのは燻製。黒砂糖と酒、醤油のたれを刷きながらオーブンで照り焼きにしてごはんに載せるんです。癖があるので野菜も一緒にお重にします。今回はルッコラ、薄切りにした蓮根のロースト、それからオリーブ油で蹴った赤玉葱。赤玉葱が合うというのは「草喰なかひがし」で教えてもらいました。仕上げの粉山椒も忘れずに!


そりゃあこんなもの日本の蒲焼とは似ても似つかぬ珍品ですよ。でも、これはこれで悪くないです。代用品としてではなく、これなりの美味しさがある。秋口が旬のブロッコリの花芽をさっと湯掻いて辛子醤油で和えたん。千枚漬けにしたビーツを千切りに刻んだん。肝吸い代わりに焼きアンズタケのおつゆ。悪くない。悪くないです。
白木と塗りの最大の違いはいうまでもなく吸湿性。なので冷ごはん製造機としては、やはり槇のおひつがいいのです。けれどタッパーは論外にせよ、炊いたまま鉄鍋にほったらかしよりも当然ずっといいコンディションに仕上がってはくれます。ぎゅうぎゅうに詰めないで空気を含ませておくといいみたい。
「たる源」のおひつも、おはちも、高い機能性が美的に昇華した【用の美】の極みにあるような道具ですが、決して日常から遊離しないのが本当に素晴らしい。川尻さんの手から生み出されるものはみんなそう。唯一の例外は彼が趣味で拵えているギターくらいかな。あれはもはやアートですから。
こちらのお店はほぼ御つくりおきのみ。おひつの槇材以外にも、檜、杉、椹、桜、様々な木材の様々な部位を、それぞれに適した道具にします。たとえばおひつにおまけでつけてくださるお杓文字の材は昔から桑と決まってるのだそうな。オーダーしてから時間がかかるのは丁寧な仕事に加えて、眼鏡に適った素材の入手がどんどん困難になっているがゆえだそうです。
店頭(というか工房の棚)に並べて売られているのは注文数を作ったあとの余分でできています。これらは普通にその場で御つくりおきと同額で譲っていただけますから、運がよければ、もといご縁があれば欲しいものを即座に我がものとできるかもしれません。さらに運がよければ川尻さんの演奏が聴けるかもしれません(笑)。
老舗であるにもかかわらず「たる源」はとても伺いやすい雰囲気があります。ほんの少し勇気はいるかもしれませんが興味があったらぶらっと立ち寄ってみるが吉。御つくりおきのみだからこそ一見さんにもとても親切。なんのツテもコネもいらない。わたしもおひつのとき飛び込みでしたから。
京都人が冷ごはんを好む理由をひとつ忘れていました。それは「熱くないから、すぐ食べられる」です。京都人は存外せっかち。行列も嫌い。腹ペコを強いられるのはもっと嫌い。でも「たる源」の注文待ちは全然平気。おひつでごはんを一晩置いて異なる旨さに変化させる時間に相当するからでしょうか。

関連サイト
たる源
京都市東山区大和大路通三条下ル
-

-
入江敦彦
いりえあつひこ 1961年京都市西陣生まれ。多摩美術大学染織デザイン科卒業。ロンドン在住。作家、エッセイスト。主な著書に、生粋の京都人の視点で都の深層を描く『京都人だけが知っている』、『イケズの構造』『怖いこわい京都』『イケズ花咲く古典文学』や小説『京都松原 テ・鉄輪』など。『秘密のロンドン』『英国のOFF』など、英国の文化に関する著作も多数。最新刊は『読む京都』。(Photo by James Beresford)
この記事をシェアする
「御つくりおき――京都のひととモノとのつきあいかた――」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら