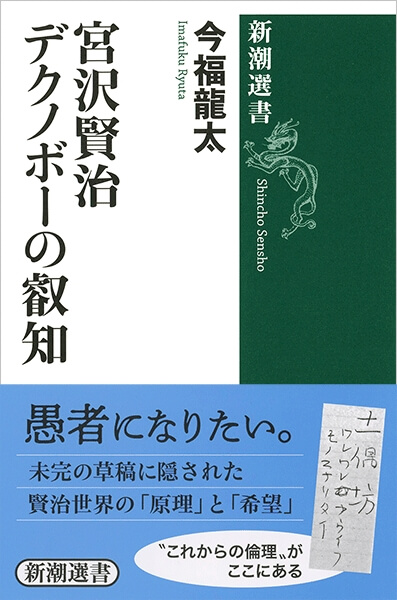2020年8月29日
中編 「小さい」という世界
『宮沢賢治 デクノボーの叡知』(新潮選書) 受賞記念公開
昨年9月に刊行された『宮沢賢治 デクノボーの叡知』(新潮選書)の著者・今福龍太さんが、第30回宮沢賢治賞を受賞することが発表されました。これを記念して、今年1月に下北沢B&Bでおこなわれ、大好評を博した小川洋子さんとの対談を短期連続公開します。前編では、小川さんの小説『小箱』のなかで主人公が“小さくなる”ことに注目しつつ、デクノボーの「前-言語」的な特徴が語られました。両者はどのようにつながるのでしょうか?
(前回の記事へ)

でこ、ぼこ、きなきな、こけし
今福 デクノボーという言葉は、あの「雨ニモマケズ」に使われているので、賢治について考えるためのキーワードのようになってしまっていますが、じつは賢治が自分の全作品の中で三箇所にしか使っていない、稀な言葉です。
しかも「ミンナニデクノボートヨバレ」と書かれた直筆の部分を見ると、実は最初「デコノボー」と書いています。で、「デコノボー」の「コ」を消して、「ク」に直している。別のところでは「デグノボー」とも書いた。それから、「土偶坊」という漢字を当てて書いたこともある。そもそも「デク」は土偶から来たんじゃないかとも言われています。
「デクノボー」、「デコ」、「デグ」、それから土偶。別の詩では、木の偶と書いて「でく」と読ませているものもあります。このように、デクノボーという概念は、実は賢治の中でもそうとう流動的で、揺れているんです。
それから、「デコノボー」の「デコ」とは何かと考えたとき、東北地方でこけしを呼ぶ最も典型的な呼び方の一つが「でこ」です。
方言学者が作った地図によると、特に福島県あたりが「でこ方言区」になっていますが、東北ではだいたい「でこ」と、「ぼこ」と、「きなきな」、「こけし」という、四種類ぐらいの呼び名があります。賢治のいた盛岡や花巻あたりでは「きなきな」や「ぼこ」が使われているようですが、それでもデクノボーが賢治のなかで「でこ」=こけしのイメージと重なっていないはずはないでしょうね。だからつい「デコ」と書いて、「コ」を消して「デク」にしている。
「ぼこ」は、秋田・山形・岩手・宮城で使われていて、四つのなかで一番広い範囲を指していますが、これはおそらく「ぼっこ」から来ています。つまり童子、子ども。座敷童子(ザシキワラシ)というのが東北にいて、賢治も『ざしき童子(ぼっこ)のはなし』という物語を書いていますが、そこでも「ぼっこ」と子どものことを言います。
あるいは、棒子(ぼうっこ)、木の棒とも考えられる。棒のようなもので人形をつくって、そこに子どもの霊や、ある種の精霊、神さまといった神格を与えていくことがあり、今でも東北地方の「オシラサマ」は木の棒でできています。ちょっとした衣装をつけたり、目鼻を描いたものもありますが、単なる木の棒だけというのもあります。
小川さんの小説の中にも、木の細工をする、重要な人物が登場しますが、このアイデアはどこから来たんですか?
小川 いや、もうそれはどこからともなくとしか言えないんです。歯を治療する機械を使って、川原に流れてきた木を細工して楽器をつくる元歯科医を登場させました。
今福 かつて子どもの歯を治療していた歯医者さんが、流木を使って小さな竪琴を作る。『小箱』の世界では、あらゆるところで子どもの記憶が薄れていくなかで、子どもたちと直接かかわっていた人たちの手わざが、楽器のほうに振り向けられていくんですよね。
今の話をもう少し続けますと、そもそも「こけし」という言葉の「けし」は、芥子粒(けしつぶ)とか……。
小川 ああ、小さいもののことなんですね。
今福 芥子本(けしぼん)って、江戸時代にありましたね。豆本のことを、芥子本と言っていた。だから「こけし」というのは、小さいということです。木を使って、小さい子どもをつくったから、こけしと言うわけです。
「小さい」という価値
今福 小川さんは『小箱』の中で、木片の「来歴」という言葉を使っていましたが、元歯医者さんが木片を使って耳の下にぶら下げる竪琴をつくるときには、どんな木でもいいというのではなくて、一つひとつの木が生きてきた物語、来歴を、実にみごとに読み取ってつくると設定されていました。
小川 はい。もう、ソローですね。あるいは、石を探して川原を歩く宮沢賢治です。
今福 オシラサマや、こけしの原形もそうだと思いますが、一つひとつの木片自体に深い意味があって、人間はたぶん、それを拾ったときに感じている。そこからでないと、神や精霊に近いような呪術的なものは、つくることができないはずです。
小川 言葉で説明されていないですからね。その拾った木片なり、石なりに、人間の言葉で来歴を書いてくれているわけではない、そういうものを拾わなくてはいけない。
今福 そうですね。それも前–言語です。
小川 木でつくったこけしや人形は、人間の何かを宿しているけれど、言葉はしゃべらないという意味で、やはり前–言語的な存在ですよね。『小箱』の中で、子どもを失った親たちはそういうものに救いを求めますが、宮沢賢治の作品の中でも数々、デクノボー的な、うまく自分を表現できない存在が、その集団の何かを劇的に変えたり、何かを気づかせたりという、ある広い恵みをもたらします。
今福 そうですね。まとめてみると、デクノボーとは、一つはインファンティアですね。話せないことによって、非–言語的な、前–言語的な知恵の領域を守り続けている存在だと考えられます。
もう一つは、「小さい」ということそのものが、重要なことではないかと僕は思います。小川さんの小説でも、どんどん自分の体が小さくなっていくというのは、単に幼稚園で暮らしている人が、周りのもののサイズに合わせて小さくなっていくという表面的な意味だけではなくて、まさに「小さい」という価値に還ろうとしている、ということなのではないでしょうか。
子どもが小さいのは、成長する前だから小さいという意味だけではなくて、人間にとって重要な価値であるところの「小さい」という、大きいことのほうに価値があるとする現代の資本主義社会からすればネガティブに捉えられがちな一つの価値を、守っているとも捉えることができる。つまり、子どもは「小さい」ということの一つの象徴的なあり方であるとも考えられます。
小川 ええ、ですから『小箱』の中で、主人公が小さすぎる字を解読するのに、字を大きくして読もうとするんじゃなくて、自分が小さくなって読もうとする方向に行く。
あるいは、今福さんのご本の中に、ベンヤミンの言葉が出てきます。「ひとは誰かを助けるためには、愚か者でなければならない」。他者のために何かしようとするときに、その他者よりも強い人が助けるのではなく、か弱い者、小さい者が救いになるという思想です。
カーテンと一体化できた幼年時代
今福 本の中では、ドイツのユダヤ系の思想家ヴァルター・ベンヤミンを引用しながら、デクノボーという概念のいろいろな広がりについて考えていますが、僕はベンヤミンが使った「未完」、「未熟」、「子ども」、「インファンティア」、「不器用なもの」という言葉、それから「せむしの小人」という存在が、賢治が言うところのデクノボーに近いものなのではないかと考えてきました。
ベンヤミンが自分の少年時代の記憶をめぐって書いた「一九〇〇年頃のベルリンの幼年時代」というテクストの中には、こういう文章があります。彼はベルリンのブルジョアの家庭に育っているので、自分の家の中の、立派な家具や、絨毯や、カーテンとねんごろになって、言葉にならない幼少のうちからそうしたものと一緒に遊んでいたわけですが、これはそのときの記憶をベンヤミンが言葉による記憶が消失するギリギリまで遡って言葉にしようとした一節です。
戸口のカーテンの後ろに立つ子供は、自身が風に揺らめく白いものになり、幽霊になる。食卓のしたにうずくまれば、それによって子供は、彫刻を施された脚を四方の柱とする神殿の、木彫りの神像と化す。(……)誰かが私を見つけてしまったら、私は木偶のまま食卓のしたで硬直し、幽霊のまま永久にカーテンに織りこまれ、生涯重たい扉のなかに呪縛されてしまうかもしれなかった
「戸口のカーテンの後ろに立つ子供は」……本当なら「自分は」というべきところですが、この本は不思議なことに、終始「子供」という三人称で書かれています。ですから、これは単なる自伝ではなく、むしろ「子供」という普遍的な存在形態の可能性をベンヤミンが考えようとしたものです。
「戸口のカーテンの後ろに立つ子供は、自身が風に揺らめく白いものになり、幽霊になる」。つまりカーテンになってしまうということです。これは、『小箱』のなかで主人公の体が少しずつ小さくなっていって、幼稚園の園児たちが使っていた椅子や、机や、鏡に収まっていくということと、まさに同じ体験のように思えます。周りのものに自分を擬態させて、そして、ほぼそのものに、なっていってしまう。
小川 模倣ですね。
今福 そう、模倣です。しかしその最中に、外から理性を持った大人が現れて「きみ、何やってるの?」と声をかけられてしまうと、その瞬間にもう自分は硬直して、木偶のまま、家具の中に塗り込められたまま固定化してしまう。そういう敷居がここには描かれています。
理性が芽生えてしまえば、ものは固定化し、テーブルの脚と自分は別々の存在になってしまいます。しかし前–言語の意識だと、そこは未分化です。本来ならば、こうした頃のことはもはや、言語によって記憶として呼び戻すことはできないはずですが、ヴァルター・ベンヤミンは特異な人で、それをやろうとした。そして、僕は宮沢賢治という人も、どうもそこに近づこうとした人ではないかと考えています。
名前をつける前の世界
小川 宮沢賢治の「なめとこ山の熊」の中にも、「滝」と書けばいいのに、わざわざ「白い細長いもの」と書いているところがあります。また、「熊」という言葉をずっと使っているのに、物語の最後には「黒い大きなもの」と、熊と名前が付く前の状態に戻って書いてもいます。
今福 それを僕は「物質言語」と呼んだりしています。言葉は、モノの存在そのものから少しずつ離れていって、意味を伝えるある種の記号になります。でもその大本には、まだ「熊」という言葉はなく、ただ「黒く大きなもの」、「滝」という概念語ではなく「白くて長細くて流れ落ちるもの」と、捉える物質的な感覚が残っている。子どもがまさにそうです。最初はモノの名前を名指すのではなく、「何かがどうしているもの」というふうにしゃべり始めます。
小川 そういう例えでしか言えないというか、そのものの記号は、まだ覚えていない状態。
今福 ヴァルター・ベンヤミンが熱心にやったことは、自分の息子が小さい時に、最初に話した言葉や言い間違いを書き留めることでした。要するに、「熊」という記号化された言葉を、大人が早々と教えないようにするわけです。今はみんな、大人が先に教えてしまう。それは「熊」って言うんだよと。これは一見、親切のようでいて、もしかしたらある種の暴力かもしれません。
小川 子ども時代だけに持っているものを、早く奪おうとしているわけですからね。
今福 ベンヤミンは、息子の発した言葉を細かくメモに取って、決して親のほうから直しませんでした。そして、それを彼は自分の思想のほうに取り込んでいったんです――そういう世界を描写したテクストの中に、「木偶」=デクノボーが出てくるのは、とてもおもしろいことだと思います。
小川 『小箱』にはバリトンさんという、言葉を捨てて、阿呆のように歌うことしかしないデクノボー的な人が出てきますが、言葉以前ということになると、音楽の存在も一つのヒントになるかもしれません。たぶん人間は言葉をしゃべる前に、歌を歌っていたのだろうと思うんです。鳥に対して、こんなに焦がれるような思いを抱くのは、人間は言葉を獲得する前に、歌で心をやり取りしていた時代が長かったからではないかなと。
今福 そう。バリトンさんは言語を拒絶し、前-言語の段階にもう一度戻ろうとした、とても大事な存在ですよね。先ほど、「絵のように文字を書きたい」という話をしましたが、もう一つ言えば、「歌のように言葉を語りたい」というのは、ほぼ平行した欲望としてあります。
小川 小さい子どもが言葉を覚えるときには、単語で覚えていくのではなく、大人がしゃべっている言葉を、音楽的に真似するところから始まります。一個一個の名詞を覚えていくのは、そのずっとあとです。やはり人間の持っている音楽的な能力が重要なのかなと、私は思います。
愚者、かかし、偶像
今福 ベンヤミンが「木偶」と書いたのは、ドイツ語の原文では「ゲッツェ」という言葉です。今回、ドイツ語の専門家にも話を伺ったりしていろいろ調べてみたんですが、グリムのつくったドイツ語辞典というものの中に、このゲッツェが出てきます。この言葉はなかなか深い言葉のようで、三つぐらいの意味の系統があると言うんです。
一つめは、愚者、愚か者という意味です。これは中世ヨーロッパからの伝統があって、ブリューゲルや、ヒエロニムス・ボッシュなどの絵にも描かれていますが、世の中の道徳律に縛られない、愚行を容認された人物というのが、実際にいました。
小川 無礼講ですね。
今福 ええ、そういう人たちがお祭りの中で自分たちの存在を主張して、日常の堅苦しい理性や道徳律を、いわば開放する。宮廷愚者という存在もいて、宮廷の権力の論理だけではいずれシステムが破綻してしまうので、それをたまにショートさせる道化や愚者がいないと権力も存続しないということも知られていました。このゲッツェの最初の意味はそういうものです。
二つめが、小川さんの世界に近づきますが、土偶とか、木偶とか、案山子というような意味です。それは人間が、木や、土や、石を使って、呪術的なものを彫刻のようにしてつくって、そこにある神秘的な、霊的な意味を与えたということですね。
そして最後に、ゲッツェには宗教的な偶像という意味もあります。
こうしてみると、愚者、かかし、偶像。これがベンヤミンの「木偶(でく)のように」という表現の背後にある意味だとすると、それはほとんど賢治の言っているデクノボーのことではないか。賢治のデクノボーも、どうもこの三つの意味系統の統合体として理解できるのではないかと思います。
そして、小川さんの『小箱』の中で主人公がどんどん、子どもの世界に収縮していくというのは、結果的にベンヤミンのちょうど逆になっています。ベンヤミンは先ほど引用した部分の後に、自分が大きくなっていくにつれて、家具たちがどんどん小さくなっていってしまった、と書いています。つまり、自分が家具と一体化していた時代が終わって、言語の理性に取り込まれると、今まで一緒に遊んでいたはずのカーテンや、椅子や、机とかが、どんどん小さくなって、対象化されてしまうということです。小川さんはこの世界を逆行して、主人公がどんどん縮小していくという、そういう想像力をつくられた。
小川 そういう意味があったなんて、今まで一回も考えたことがなかったんですけれど……。
今福 そうですか? 本当に?
小川 本と人との出会いによって、自分の小説がわかってくる。書いた人でもわからないことが、わかってくるんですね。
(後編へつづく)
-

-
今福龍太
いまふく・りゅうた 文化人類学者・批評家。1955年東京に生まれ湘南の海辺で育つ。1980年代初頭よりメキシコ、カリブ海、アメリカ南西部、ブラジルなどに滞在し調査研究に従事。その後、国内外の大学で教鞭をとりつつ、2002年より群島という地勢に遊動的な学び舎を求めて〈奄美自由大学〉を創設し主宰する。著書に『クレオール主義』『群島―世界論』『書物変身譚』『ハーフ・ブリード』『ヘンリー・ソロー 野生の学舎』(読売文学賞受賞)など多数。
-

-
小川洋子
おがわ・ようこ 作家。1962年、岡山県生まれ。早稲田大学第一文学部卒。1988年「揚羽蝶が壊れる時」で海燕新人文学賞を受賞。1991年「妊娠カレンダー」で芥川賞受賞。2004年『博士の愛した数式』で読売文学賞、本屋大賞を受賞。『ブラフマンの埋葬』で泉鏡花文学賞、2006年『ミーナの行進』で谷崎潤一郎賞、2012年『ことり』で芸術選奨文部科学大臣賞を受賞。『薬指の標本』『琥珀のまたたき』『小箱』など多数の小説、エッセイがある。フランスなど海外での評価も高い。
この記事をシェアする
「今福龍太×小川洋子「デクノボーという知恵をさがして」」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 今福龍太
-
いまふく・りゅうた 文化人類学者・批評家。1955年東京に生まれ湘南の海辺で育つ。1980年代初頭よりメキシコ、カリブ海、アメリカ南西部、ブラジルなどに滞在し調査研究に従事。その後、国内外の大学で教鞭をとりつつ、2002年より群島という地勢に遊動的な学び舎を求めて〈奄美自由大学〉を創設し主宰する。著書に『クレオール主義』『群島―世界論』『書物変身譚』『ハーフ・ブリード』『ヘンリー・ソロー 野生の学舎』(読売文学賞受賞)など多数。

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら