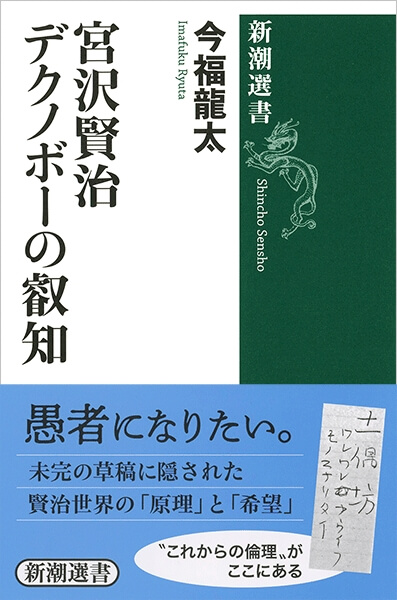2020年8月28日
前編 デクノボーは「言葉以前の人」
『宮沢賢治 デクノボーの叡知』(新潮選書) 受賞記念公開
昨年9月に刊行された『宮沢賢治 デクノボーの叡知』(新潮選書)の著者・今福龍太さんが、第30回宮沢賢治賞を受賞することが発表されました。これを記念して、今年1月に下北沢B&Bでおこなわれ、大好評を博した小川洋子さんとの対談を短期連続公開します。今福さんの前著『ヘンリー・ソロー 野生の学舎』や、小川さんの長編小説『小箱』との驚くべきつながりも含め、たっぷり語られた充実の対話をどうぞお楽しみください。
『ヘンリー・ソロー』と『小箱』のつながり

今福 僕の『宮沢賢治 デクノボーの叡知』は昨年9月末に出ましたが、ちょうど同じ頃に、小川さんの久しぶりの長編小説『小箱』が刊行されました。ですので、きょうは形の上では、僕の本の刊行記念となっていますが、小川さんの『小箱』についても一緒に、お話をしたいと思っています。
というのも、お会いするのは今日が初めてですが、僕と小川さんには『小箱』によって不思議な形でつながった出会いがあって、そこにおもしろい経緯があるからなんです。
始まりは小川さんが、僕の以前の著書を読んでくださったことでした。『ヘンリー・ソロー 野生の学舎』(2016年、みすず書房)という、十九世紀アメリカの思想家ヘンリー・デイヴィッド・ソローについての本ですが、これを小川さんが、深いところで読み、受け止めてくださった。そして、僕がソローのエピソードとして描いたいくつかのことを、小川さんが既に構想されていた物語の構造の中に流し込み、それが僕にとっても驚くべき変容をとげる形で一つの小説に仕立て上げられて、『小箱』という作品が生まれた。そういう、二つの著作のあいだの隠されたつながりがあったんです。
このことを、まずは小川さんのバージョンとして、語っていただけますか? 僕も初めてお聞きするので、ドキドキしているんですが……。
小川 はい。私は、“死んだ子どもを結婚させる”、「ムカサリ絵馬」という不思議な風習が東北地方にあるのを知って、心をひかれました。それが新しい物語の一つの柱としてあったのですが、なかなか書きだせないでいたところに、今福さんの『ヘンリー・ソロー 野生の学舎』に出会いまして、その中に、ヘンリー・ソローが、死を自然の中のものとして捉える文章がありました。死を一個人のものとしないで――、「死はそのような、突風が奏でる音楽のなかの、表情豊かな休止のことである」という言い方をしていました。
更には、ソローが〈言葉〉を森の中の風に発見するというエピソードがあるのですが、――それを象徴するのが、エオリアン・ハープという楽器なんです。この楽器を、ソローは復元・製作するほど愛していた。風の声を拾って、それを人間の言葉に置き換えていくようにしてソローは書いていたんだと、感銘を受けているところに、この『野生の学舎』が読売文学賞を受賞されて、贈賞式で今福さんがスピーチをされました。
そこでお話しされたのが、ヘンリー・ソローの愛好者が集まる会で、みんなそれぞれ、手づくりのエオリアン・ハープを持ち寄ったという忘れがたいお話だったんです。
エオリアン・ハープの音楽会
今福 あれはみんなで一つの楽器をつくったんです。
小川 一つだったんですね。
今福 エオリアン・ハープはギリシア時代からある楽器ですが、人間が弾く楽器ではないんです。ハープというより、小さな日本の琴のようなかたちをしていて、共鳴箱に穴が開いた空洞体になっていて、そこに弦が張ってある。これを風に向けてじょうずに置くと、自然に弦がビーンと鳴ってくるという、古い楽器です。
そもそもピタゴラスなどの古代ギリシアの数学者や哲学者は、多くが音楽学者でもあって、音というものが大気中で発生する原理の中に、自然の一番深いところにある数学的でもあり哲学的でもある、ある定理が潜んでいると考えていたんです。
だから、人間が恣意的に演奏するのでなく、エオリアン・ハープのような形で、風=天空に満ち溢れている音楽を受け止めて、それが自然に鳴り響くというのが、音楽の一つの原形、あるいは最終形、いわば至高形態だと考えられていました。「天球の音楽」とギリシア人は名づけていたんですね。
ソローはそのことに惹かれて、エオリアン・ハープを自作していたんですね。僕は毎年、七月十二日のソローの誕生日に合わせて、四国のある山の中で仲間と一緒に集まって「野生の学舎 ソローヴィアン」というイベントをしていますが、そこで、九州大学のある音楽学者が作っている素朴なエオリアン・ハープの製作キットを手に入れて、参加者で完成させて鳴らしてみることにしたんです。
イベントの会場は山のかなり急斜面に建っている古い民家で、吹き上げる風があるので、そこへ置いておけば鳴るんじゃないかと考えたのですが、その日は全然、風がなくて、ウンともスンとも言わない。するとある人が突然、思い立って、自分でハープを頭の上に担いで走り始めたんです。広くはない民家の中庭の端から端まで、全速力で。するとある瞬間、たぶん角度がちょうど良かったんですかね、鳴ったんです。鳴ったんだけれど、それはわれわれには聞こえない。鳴らした本人だけが、たぶん頭蓋骨あたりがビーンと響いて、それが音として聞こえていたのでしょうが、そのときの至福の表情、幸せそうな表情で、「ああ、鳴ったんだな」と、はたで見ている人間にも分かりました。それからは、その場にいる人みんなが、私もやりたい僕もやりたい、ということになって大騒ぎでした。
ここで僕は、むしろ自分が聞こえない音をある人が聞いている様子を見ることが、その人の幸せを分け与えられるということなのではないかと感じたのです。みんなで同じ音を聞くのではなく、それぞれが他の人には聞こえない音を密やかに聞いているということに、そしてそのことをみなが諒解しているということに、一つ価値があるのではないか、そう思った、という話をスピーチでしたのでした。
小川 そういうすばらしいスピーチを聞きましたら、作家としては、もう黙っていられない(笑)。風がない日にエオリアン・ハープを聞く音楽会のイメージと、自分がずっとそれまで抱えていた「ムカサリ絵馬」の死後結婚の柱、その二つのあいだに、パァーと虹がかかったんです。
今福 あの瞬間に?
小川 ああ、これは小説に書きたい、書けるという劇的な体験でした。それで『小箱』が完成したときに、どういうふうに今福さんに感謝を捧げればよいか、悩みに悩んで、時間をかけてお手紙を差し上げたんです。すると非常に心温かいお返事をいただいて、そのお手紙には、お言葉だけでなく、虫のナナフシの絵も描いてありました。まるで葉陰にジッと摑まって、風に耳を澄ませているかのようなナナフシでした。
そういう不思議なやり取りがあって、きょうを迎えております。
今福 小川さんの素晴らしいバージョンを、ありがとうございました。僕は自分が書いた本や、その本を巡って語ったことが、一つの独立した作品になるという経験をしたわけなんですが、結局、言葉や文学は、個人が所有することができないような大きな言語と文学の歴史の中に一人ひとりがいて、そこで集合的な営みをやっているに過ぎない、とも考えられますよね。そういう集合的な場の存在を、僕も時どき感じることがあるんです。そしてそのことが、著者であることを特権的と捉えるようなある種の傲慢さから自分の身を少し引き離してくれて、人間が言葉を使って表現してきた歴史の中に、いま自分もほんの小さい場を与えられて書いているんだと、思い直すことがあります。
小川さんの今話された『小箱』の経緯も、僕がソローを媒介にして考えてきたことも、言葉を使って人間が思考してきた歴史の一部に、自分自身が連なるということでもあったと思います。
エオリアン・ハープも、まさにそういうものですよね。音楽家が自分で作曲してつくっている、固有の独占的な作品なんてものはなくて、この世の中に溢れている自然の音を、そのままでは聞こえないかもしれないけれど、一人ひとりの音楽家が、たまたま形にして、すくい出しているにすぎない。武満徹という人は、まさにそうして音楽をつくっていた人でした。「音の河」と彼はよく言いましたが、自然界に流れているそうした河の中から、苦しんで自分は一つの音を取り出すのだと、書いていました。
小川さんの今のお話に付け加えると……『小箱』の内容を少し話すことになってしまいますが、いいですか?
小川 どうぞ、どうぞ。
「小さな楽器」と「手紙」
今福 一つは、自分にしか聞こえない音があって、それを小さな楽器をつくって、耳もとで鳴らそうとしている人たちがいる。これは、『小箱』の重要な一つのプロットですね。
小川 そうですね。はい。
今福 これはほんとうに小さな楽器で、自分の耳にぶら下げて、自分だけが聞くという、現実にありそうでありえない、小川さんならではの不思議な仮想世界に展開されています。
ちなみに、「ムカサリ絵馬」というのは、東北地方の習俗として残っているもので、未婚、あるいは幼少時代に亡くなった子どもたちの婚姻を描いた絵を寺に奉納するという、不思議な風習ですね。結婚することなく、若くして亡くなってしまった幼い霊にたいする、親や残された人たちの追憶や供養の気持ちがあるのだろうと思いますが、この風習が『小箱』のまさにタイトルにもかかわっていて、亡くなった幼い子どもたちの死後の“成長”を小箱の中で実現しようとする人たちの物語になっています。
そして、僕が小川さんからお手紙と本をいただいて、いったいどんな形で僕のソローの本が流れ込んでいるのだろうと気をつけながら読んでみたときに、エオリアン・ハープともう一つ、手紙というものがありました。
ソローの時代は、産業の発達によってビジネスの文書が増えて、郵便物の主流を占めようとしている時期でもありました。ソローの生きた十九世紀のアメリカ東海岸は、今のわれわれが享受しているさまざまな社会制度がほとんどすべてつくられた時代で、体系的な郵便制度もこの時期に生まれましたが、そのときに合理的なルールとして、手紙の重さで郵便料金を決めるシステムが始まったんです。
すると、たくさん書くと高いので、枚数を減らすためのさまざまな書き方がこの時代に生まれます。紙の表面・裏面に書くだけでなく、クロスライティングといって、横向きに書いたあと、九〇度、紙を回転させて、そこにまた横向きに書く書き方です。文章がちょうどクロスする感じになります。これが、読めるには読めるのですが、読むのに時間がかかる。
それが今度はまた逆に、時間をかけて読んでもらいたいほど親しい相手にたいする、特別の気持ちを込めた手紙の書き方としての別の意味を獲得して、文人や知識人たちのあいだでしばしば行われるようになったんです。
ソローは、周りの友人たちにひたすらクロスライティングで手紙を書いていたというエピソードも、僕は本の中に書きました。これが『小箱』の中で、実にみごとにもう一つの物語上の設定として展開されています。
小川 そうなんです。今福さんがおっしゃったように、文字が意味を伝えるだけではない、暗号めいた姿に変わって、“特別、あなただけにわかる思いが、ここには綴られているんです”という意味合いをソローの手紙は持っていた。そこからヒントを得て、私の小説の中では、クロスだけでなく、円も出てきて、最終的に余白がまったくない、ほとんど紙が真っ黒になるような恋文を書く女の人がいて、その恋文を主人公が解読する役目を負う、という物語にしました。
もう一つ、おもしろいなと思ったのが、ヘンリー・ソローは字が上手ではなく、読みづらい筆跡だったということです。それを今福さんは、自然物に近い筆跡――葉脈や、あるいは葉を食べた虫の跡など、自然の中にうかがえるいろいろな模様に近い筆跡であると書かれていて、そこにも魅力を感じました。
今福 僕はあるとき、体が不調になって、台湾の薬草の漢方医に診てもらったことがあるのですが、そうしたら僕が何者かを全く知らないその医者に、あなたは字を書き過ぎているんじゃないかと言われた。
小川 えー!
今福 「もう字を書くのをやめなさい、絵を描きなさい」と言われたことがあるんです。この年になって画家になるわけにはいきませんが(笑)、ふと、絵を描くように字を書くことなら、できなくはないんじゃないかと思って。むしろ自分はこれまでも、観念的な記号としての字は書きたくないと思ってきたような気がしたんです。それをこの漢方医は「もっとその方向で行きなさい」と、後押ししてくれているような気がしました。
それ以降、観念的な記号のような文字が連なる文章を書くことからますます離れて、どこかでもっと物質感のある文章を書きたいと思うようになりました。例えば声にしたときに新しいメッセージを持つような文章を書きたいとか、文字を書く行為自体も絵を描くように楽しくやりたいとか。
手紙を書くことって、今まさにそういう場になっていますよね。意味だけを伝えたければメールもありますが、手紙をわざわざ書くとなると、やはりそれは筆跡や、なんらかの文字の姿形を伝えたいということがあるのではないかと思います。だから小川さんとは、これからもずっと手紙でのやりとりをしたいんですが。
小川 今のお話は本当に重要な問題で、そこから『宮沢賢治 デクノボーの叡知』にもつながっていくと思うのですが、この本の中に「前−言語」という言葉があります。つまり、言葉になる前の状態というか、言葉にできない、人間がものに便宜上、意味を与えるより前の状態を、宮沢賢治は書くことができたとある。そういう意味で、賢治はヘンリー・ソローともつながっているんですね。
手紙を“小さくなって”解読する
今福 そうですね。小川さんの『小箱』で、ほとんど真っ黒に縦・横・斜め・円と書かれて、もはや余白がなくなってしまった手紙を、主人公が時間をかけて解読していく時の状況がこう書かれています。
私は、園児用の椅子に腰掛ける時より、手洗い場の鏡に顔を映す時より更に小さく体を縮め、一人きりで手紙の世界を這いずり回る。刻まれた言葉を一つ残らず救い出すため、隅々をさ迷う。
僕がおもしろいなと思うのは、自分がその手紙を解読するために、小さくなっていかなくてはいけないと書かれていることです。自分がどんどん、縮んでいかなくてはいけないというかな。
そもそも、主人公はかつて幼稚園だった場所に住んでいると言っていいんですね。
小川 ええ、住んでいます。
今福 だからすべての家具や、ありとあらゆるものが小さくできています。主人公はそういう小さいベッドで寝たり、小さい椅子に座ったりして生活しているわけですが、そのことを表す一節で、こうも書かれています。
そうしたもろもろが少しずつ埃をかぶり、朽ちるのよりももっと目立たないスピードで、檻の中の少女が奇形になるよりも緩やかに、私の体は幼稚園の輪郭と調和してゆく。短すぎたスプーンを、いつの間にかバランスよく扱えるようになったと思ったら、お遊戯室の椅子に腰掛ける時、いつも行き場に困って窮屈に折れ曲がっていた両膝が、なぜか大人しく机の下に隠れているのを発見する。ある朝、手洗い場の前に立つと、首元から下しか映っていなかったはずの鏡に、自分の顔が丸ごと全部映し出されているのに気づき、はっとする。
これが先ほど引用した手紙の解読の、前段にある部分です。一見、自然の描写のように、自分の体が、どんどん小さくなっているということが書かれています。
ここはおもしろいイマジネーションだと思うんです。デクノボーの話にもつながるのですが、僕は今度の賢治についての本の中で、「インファンティア」という言葉を使いました。
インファント(infant)と言うと、子どものことですけれど、ラテン語でイン(in)は否定です。ファントというのは、ラテン語のフォール(for)という動詞で、もとは「話す」ということです。そうすると、インファントというのは、「話さない」ということですね。話せない、あるいは、ものを言わぬ状態。まだ言語の前の状態ということです。
僕は「デクノボーとは、このインファンティアのことなのではないか」と、宮沢賢治を読みながら考えてきました。人間は言語を獲得することによって、言語による理性をすべての思考と判断の根幹に置き、倫理においてもそれを基盤に置いてものを考え、そこから知識や知恵をつくってきた。ところが、どうやらデクノボーとは、そういう言語によって人間が獲得したと思っている一つの理性のあり方よりも、手前にいる存在です。
賢治には『虔十公園林』という、まさにデクノボー的な存在を主人公にした物語があります。虔十という、あきらかに作者「賢治」の分身でもある、ちょっと頭の弱い、でも町や村の人びとからなんとなく愛されている存在がいて、この人は風がバァーと吹いて、葉がチラチラ光る、それだけを見て、もう嬉しくて、嬉しくて、しょうがなくなるんです。
これはさっきのエオリアン・ハープと一緒ですよね。われわれが何か言語的な意味を張り付けて、すばらしい、感動的だと言う前に、風が吹いて、葉っぱがチラチラするだけで、嬉しくなる。無理やり大きく口を開いて、はぁはぁ息だけついて、その喜びをごまかしている。言葉になっていないわけです。こういうふうに、ブナの葉が風で揺れている姿を、虔十つまりは宮沢賢治が捉え直しています。これは『虔十公園林』という物語の中の根幹をなすシーンではありませんが、こんな細部に、デクノボーのあり方のとてもシンプルな形が書かれていると思うのです。
(中編につづく)
-

-
今福龍太
いまふく・りゅうた 文化人類学者・批評家。1955年東京に生まれ湘南の海辺で育つ。1980年代初頭よりメキシコ、カリブ海、アメリカ南西部、ブラジルなどに滞在し調査研究に従事。その後、国内外の大学で教鞭をとりつつ、2002年より群島という地勢に遊動的な学び舎を求めて〈奄美自由大学〉を創設し主宰する。著書に『クレオール主義』『群島―世界論』『書物変身譚』『ハーフ・ブリード』『ヘンリー・ソロー 野生の学舎』(読売文学賞受賞)など多数。
-

-
小川洋子
おがわ・ようこ 作家。1962年、岡山県生まれ。早稲田大学第一文学部卒。1988年「揚羽蝶が壊れる時」で海燕新人文学賞を受賞。1991年「妊娠カレンダー」で芥川賞受賞。2004年『博士の愛した数式』で読売文学賞、本屋大賞を受賞。『ブラフマンの埋葬』で泉鏡花文学賞、2006年『ミーナの行進』で谷崎潤一郎賞、2012年『ことり』で芸術選奨文部科学大臣賞を受賞。『薬指の標本』『琥珀のまたたき』『小箱』など多数の小説、エッセイがある。フランスなど海外での評価も高い。
この記事をシェアする
「今福龍太×小川洋子「デクノボーという知恵をさがして」」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 今福龍太
-
いまふく・りゅうた 文化人類学者・批評家。1955年東京に生まれ湘南の海辺で育つ。1980年代初頭よりメキシコ、カリブ海、アメリカ南西部、ブラジルなどに滞在し調査研究に従事。その後、国内外の大学で教鞭をとりつつ、2002年より群島という地勢に遊動的な学び舎を求めて〈奄美自由大学〉を創設し主宰する。著書に『クレオール主義』『群島―世界論』『書物変身譚』『ハーフ・ブリード』『ヘンリー・ソロー 野生の学舎』(読売文学賞受賞)など多数。

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら