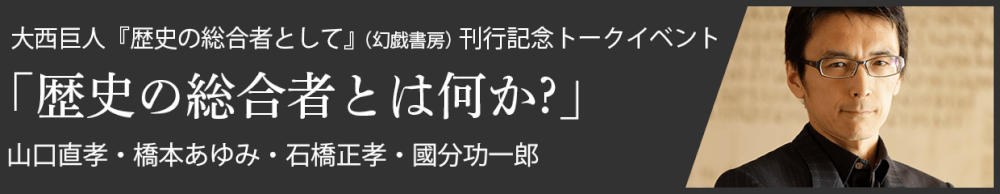2018年7月23日
大西巨人『歴史の総合者として』(幻戯書房)刊行記念トークイベント「歴史の総合者とは何か?」
第4回 大西巨人はなぜ小説で引用を多用するのか? 日仏近代小説の歴史的背景から
著者: 考える人編集部
國分 3人目、石橋正孝さんにお話しいただきたいと思います。石橋さんは何と申しましても、大西巨人について書かれた唯一のモノグラフ、『大西巨人 闘争する秘密』(左右社)の著者であります。先ほども、控え室で、この本しかないという状況はまずいよねという話をしていました。石橋さんはフランスの小説が専門ですので、近代小説との絡みで大西さんを論じています。
今日は批評と小説の関連、両者の絡み合いについてお話をしていただけるということです。では、お願いします。
石橋 ありがとうございます。石橋です。よろしくお願いします。聞きながら興奮してしまうような密度の濃い発表が続いてしまったので、最後の最後でいきなり落とすことになってしまうんじゃないかと心配です。
國分 落とさないでください(笑)。
石橋 頑張ります。先ほど山口さんから、ある意味で大西さんの初期の批評が『神聖喜劇』に至るための迂回として書かれているのみならず、『神聖喜劇』がその迂回をさらに反復するようなかたちで、批評と創作がダイナミックに通底しているとご指摘くださったんですけれども、それとは少し違う観点から大西さんにおける批評と創作の関係について考えてみたいと思っています。大西さんは非常に過激な「小説原理主義者」で、ご自身の書くものについては小説と批評の間に本質的な差異は認めないんだと、要するにすべてを小説として書いているのだと明言しておられました。そして、大西さんが小説に要求した基準というのは基本的に一つしかないわけで、一切の予備知識なしで読んでも理解できなければならない、つまり、テクストとして自立していなければならないということになります。作品が作者から切れているということなんですが、こうした要求は小説に対してならまあできなくもないでしょうけれども、批評に対してそれを行うのは実は非常に難しいことのように、常識的には考えられますよね。
やはり批評というものは対象に対して二次的ですし、当然引用とかもあるわけで、対象の作品を読まないと完全には理解できないと思われるからです。仮に批評も小説として読むとなると、批評が小説に取って代わってしまう、対象に取って代わってしまうということが起こってしまいます。そういう批判を免れるためには、言い換えれば、二次的であることを拒否しながら、同時に対象に取って代わらないようにするには、全文引用ぐらいしか方法は多分ない。そう考えると、大西さんが短詩形文学を愛好していたとか、あるいは短編よりも短い掌編小説を対象にして、アンソロジーを編んだりしたというのは、ひょっとするとそういうこととも関係があるのかもしれない。光文社から刊行された『日本掌編小説秀作選』というアンソロジーは、『神聖喜劇』が書かれたあとに編まれているのですが、興味深いことに、この中には、純然たる小説だけではなく、随筆とか詩とかも小説として選ばれていて、この点については、大西さん自身が、「編者は、十編の詩および随筆をいずれも出色の短篇小説作品と認定して選入した」と書いておられる。続けて、この「認定」という言葉の使用に関して、「私自身が多少の不審ないし拘泥ないし不行き届きを覚えている」と一応の留保を加えつつも、結局は小説にしてしまっているわけなんですね。
つまり、自分の鑑識眼に合ったテクストであれば、それはジャンルのいかんを問わず、既に小説なんだと。ただ、そうなってくると、むしろこれこそが不遜の極みかもしれない。作者当人は自作を随筆なり詩だと、つまりは、自分とは切り離せないもの、己の所有物だと思っている。ところが、読み手である自分(大西)には作者よりもその作品のことがよくわかっており、これは小説と見なす方が正しいのであって、しかも小説として認めているということは、自立したテクストにしちゃっているわけですから、作者から作品を勝手に切り離してしまって読み手のものにしている。おそらく大西さんの小説の定義は、突き詰めると、小説とは読み手のものであるということに帰着するんじゃないか。先ほど引用した大西さんの留保は、実際に優れた作品を書いてしまう作者は読み手としても優れているはずだから、そう簡単に一般読者に作品を奪われることはないとする前提が多分ある。というよりも、優れた小説を書いてしまった以上、その書き手は必然的に優れた読み手であるはずである、少なくとも、無意識のレベルであれ、書いていた時点ではそのはずであって、ただ、大西さんご自身は、書き手が最初から優れた読み手として意識的に書いた小説が実際に優れた小説になっていることをあるべき姿として追求されていたのでしょう。そして、そのことと、大西さんの創作に無意識が関与する余地が大きいのは、矛盾していないと思います。
といいますのも、大西さんは、小説でも批評でも、常に自分は読み手として書いているんだってことをさらけ出しているんですよね。いうまでもなく、引用の多用のことです。大西作品の最大の特徴は、批評と小説で引用の仕方が全く同じであるという驚くべき事実です。非常に長い引用をたくさん行っているのですが、これは特に小説でやってしまうと、それこそ小説の自立性を損なうのではないかと思ってしまっても不思議ではありません。ほかの作品を読まないとちゃんとは読めないということになりますから。しかも、日本語でも小説はしばしば創作と言い換えられるように、近代の小説には「無からの創造」という含意がどうしても付きまといます。現実には無からの創造なんてあり得ないにもかかわらず、読み手としてある自分を抑圧して、ある種の噓の上に小説という制度は成り立たせられているわけです。ですから、小説を批評から区分する基準の一つに、小説では原則として引用は避ける、しても必要最低限の範囲に留めるという暗黙の申し合わせみたいなものがある。これは実は程度問題であって、批評であっても、引用は必要最低限に留めるべきだとみんななんとなく思っていますよね。当然とはいえ、引用ばかりになってしまったら、作者を名乗れなくなって単なる読み手でしかなくなり、任意の読者の誰とでも交換可能になってしまいます。作者としての名を失って、匿名の読者大衆の中に紛れ込んでしまうという由々しき事態が発生するので、引用は極力抑圧するのが近代文学の特徴の一つなんですけれども、こういう問題が浮上したそもそものきっかけはもちろん、努力という代償を支払って勝ち取ったオリジナリティにのみ経済的対価が与えられるという著作権概念の普及です。
しかも、無からの創造を成し遂げた小説家にして初めて主張できるような著作権こそが真の著作権であるという理念が暗黙の前提としてあって、それが最初に確立したのはフランスだと言っていいと思いますが、事実、フランスでは小説(ロマン)といえば長編、つまり、連載を経ることなく最初から単行本として出され、それだけで自己完結した一つの世界を一冊の書物というかたちで具現化しえるようになっているのも、著作権を支える理念としての小説が制度化されていればこそなんですね。ですが、この制度の成立にまで遡って考えると、実はその時点における現実を抑圧することによってこの制度は成立していることがわかります。フランスでは近代文学の前提になるものは1830年代に大体出揃っているんですが、この時期というのは出版不況の真っ只中なんです。要は、本が出せない時代でした。ただジャーナリズムの勃興期ではあったので、新聞や雑誌がそれこそ雨後の筍のごとく続々と創刊されては消えていく。筆一本で食っていこうと思えば、そこに作家は書かざるを得ない。が、逆に言えば、書けば食える時代だった。その際に当然ながら大量に書かないといけないし、様々な媒体にいろいろなかたちで書かないといけないので、意に沿わないものも書かなくてはいけない。あまつさえ、断片的に書かざるを得ないし、自立どころか全く非自立的な文章をたくさん書かなきゃいけない。コピペも横行していました。そういう状況に直面した書き手は、では、どうしたのかといえば、一つには、ペンネームをどんどん変えていくんですね。つまり、これは自分の作品ではないんだという一種のエクスキューズをすることによって、匿名の(無責任な)状態で、単なる読み手の一人として書くことによって、書き手としての自由を逆説的に確保していました。作者になれないという状況こそが、まさにその対極に作者という理想像を生み出したと言えます。
そういう逆境を逆手に取ることに成功した書き手だけが、「作者」になりおおせた。本来は読み手でしかない存在がその事実を隠蔽・抑圧することで「著者」は誕生したのです。いかに匿名の書き手が原稿を粗製乱造しようが、かえってそれに埋没せずに否定しがたい個性が浮かび上がってくる。それを事後的に見いだすのはあくまで読み手なのですが、その事実が見落とされ、忘れられていく。その代表例がかのバルザックで、誇張した言い方をすれば、彼は、断片として方々に書き散らかしたものをあとから自分で読み手として見直したときに、これは全部まとめると『人間喜劇』なる一つの連作にできるじゃないかという具合に、書き手としての非自立性を読み手として逆手に取ることで、断片の寄せ集めに全体性を体現させ、大文字の小説という形で自立性をでっち上げてしまった。そして、このバルザック的な作家の在り方がその後のフランスの小説の方向性、すなわち、長編かつリアリズム、を決定づけたところがあります。そういう小説を書いた人が著者たるにふさわしいということなんですが、そういうモデルを作ったバルザック本人は読み手として作者になった人だったという事実の方はどんどん忘れられて、『人間喜劇』という世界の創造主のイメージだけが一人歩きしてしまった。そのことの端的な証拠を一つだけ挙げるとすれば、小説だと引用ができないという「縛り」なのだと思います。
-

-
考える人編集部
2002年7月創刊。“シンプルな暮らし、自分の頭で考える力”をモットーに、知の楽しみにあふれたコンテンツをお届けします。
この記事をシェアする
「大西巨人『歴史の総合者として』(幻戯書房)刊行記念トークイベント「歴史の総合者とは何か?」」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 考える人編集部
-
2002年7月創刊。“シンプルな暮らし、自分の頭で考える力”をモットーに、知の楽しみにあふれたコンテンツをお届けします。

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら