(1)小説家・町屋良平の10冊
はじめて文章を読むときのように読みたい10冊
著者: 町屋良平
斉藤洋『サマー・オブ・パールズ』
江國香織『落下する夕方』
紫式部/角田光代 訳『源氏物語』
カート・ヴォネガット・ジュニア/浅倉久志 訳『タイタンの妖女』
ウラジーミル・ソローキン/松下隆志 訳『親衛隊士の日』
中尾太一『a note of faith―ア・ノート・オブ・フェイス』
青木淳悟『四十日と四十夜のメルヘン』
山本浩貴+h『Puffer Train』
青柳いづみこ『ピアニストが見たピアニスト』
山城むつみ「ベンヤミン再読――運命的暴力と脱措定」
小説を読みたいけれど、なにを読んでいいかわからない。そう言われることが時々ある。けれど大丈夫。自分もまだなにを読んでいいのか、よくわかっていない。なにを読んでいいのかわからないまま、ひとにすすめられたもの、話題になっているものをなんとなく読んでいる。それで良いも悪いもわからないまま読み終えて、忘れてしまうことのほうが多い。
いつでもまるで「はじめて文章を読むときのように」本を読みたい。
今回はそんな初期衝動に立ち返ってこの文章を書いてみる。年齢も性別も問わない<あなた>を、小説を読むことなくいまここで生きている仮の<自分>と同化させてこの文章を書きはじめる。もし小説を知らない自分に戻れるなら、なにを読みたいか? これを読むかたにもそのあこがれのような気持ちがシンクロするといい。
まず児童文学としては斉藤洋『サマー・オブ・パールズ』。自分は子どものころはあまり小説を読んでいなかった。漫画に現世的価値観や物語を学ぶことがなければ、いまでも小説を読むことができなかったかもしれない。『サマー・オブ・パールズ』では主に恋愛感情や学校生活に寄りそって文章が書かれているため、当時の自分の感覚の「すこしだけ先」が描かれているように思えて読みやすかった。甘酢っぱい中学生どうしの恋愛を描いたひと夏が、株式投資というスパイスを加えてこうも見事にすがすがしく読み終えることができるなんて、うれしい、たのしい、という気持ちがすごかった。読書の原体験としては最高だ。
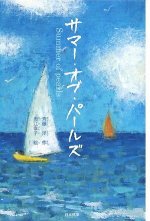
-
斉藤洋
2008/3/1発売
もうすこし大人の小説を、というかたには江國香織『落下する夕方』。恋愛時のままならない身体感覚における卓抜な言語化だけでなく、ただひとが社会に塗れることにおける「ほんもののぜつぼう」を描きだす。ストーリーを無邪気に追っているうちに、登場人物のかかえた人生の重さに震撼する。しかし江國さんのもっともすばらしいところは、絶望を絶望のまま変容させないことにあると思っている。それでこその読後のすがすがしさが、どの小説を読んでいても共通するものとしてあり、読みやすいのに弩級のスケールをもった恋愛小説になっている。美文という観点からも江國香織は最高の作家のひとり。
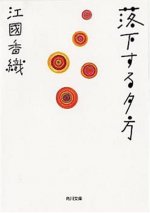
-
江國香織
1999/6/1発売
いや自分は日本の古典にチャレンジしたい、というのなら『源氏物語』。最近中巻までが刊行された角田光代訳はするする読めるうえ、当時の風景や風俗が、いま現在に接続しているもの、していないものをしっかり翻訳で描きわけていてすばらしい。源氏物語は世界最古の長編小説といわれており、なぜ日本に、こんな早くにおそるべき長編が生まれたかという謎が源氏のおもしろさの一端を担っているわけなのだが、個人的には和歌の存在が大きいと思っている。歌の上の句/下の句のあいだの切断、跳躍のなかに、凝縮されきった物語が渦巻いている。それを解きほぐし、丁寧に風俗と合わせてすすむ文章を紡いでいったことで、しぜんあれほどすぐれた長編小説が生まれたのではないだろうか?

-
紫式部/角田光代 訳
2017/9/8発売
いや、自分はSFを読んでみたいんだよねえというひとにはカート・ヴォネガッド・ジュニア『タイタンの妖女』。SF作品としてはコアといえるかどうか、自分はSFにそれほど詳しくないのでわからないが、『タイタンの妖女』には文章にも展開にもとびきりの跳躍力とあたたかみ、そして胆力がある。アイディアが漲る想像力の聡明さも突出しているのだが、その突出を丸めるような文章の温度、なめらかさ、表現そのもののおもしろみがあって、SFになじみのうすい自分でも心からたのしめた。忘れがたい一文→「トーストみたいにあったかだ」。

-
カート・ヴォネガット・ジュニア/浅倉久志 訳
2009/2/25発売
いや、そういうんじゃなくて! 自分は文学的不良になりたいなあ!というひとにはウラジーミル・ソローキン『親衛隊士の日』。言語矛盾しているようだが、突き抜けたほんものの下品さがどこか上品にも思えてきてしまう、そんなソローキンのなかでも比較的不良的価値観の感じられるこの作品、小説としてのたくらみやたくわえられたスケールも突出しているのだが、ソローキン作品に共通する「抜け感」みたいなのがあり、息がしやすいところがとくに好き。自分は時々あまりにもすばらしさのみっちり詰まった文学的名品に疲れてしまうことがあるのだが、ソローキンにはそうした疲労感をおぼえず読めている。

-
ウラジーミル・ソローキン (著), 松下 隆志 (翻訳)
2013/9/25発売
いや、もっと自分はポエジーなんだ。詩をだれにも知られない川原とかで読みたいんだ、というかたには中尾太一『a note of faith―ア・ノート・オブ・フェイス』。小説を書いていて文学について語るとなると、「純文学/エンターテインメント」という二項対立で語られることは多いが、そこに詩歌がくわわることはあまりない。しかしいわゆる「文学」を考えるうえで、それがエンタメ志向であろうがなかろうが、そうした詩歌作品を無視して考えるのは非常にむずかしいと思っている。作品が載る媒体による商業的な区分はあるとしても、作品を文学/エンタメとわけて考えるには、個人的にはその作品そのものが「文学志向」であるか「エンタメ志向」であるかによって規定され、ひとつの小説のなかでさえ揺らぎのあるものだし、まして作家の名前そのものに既定権はないと考えている。作品そのものがつくられていく過程で生まれる言語的な志向が文学へ寄り添うとき、詩はいつでもそこにあるものだ。『a note of faith―ア・ノート・オブ・フェイス』では詩語、詩情、生きることそのものが詩であることへの信頼が、饒舌な洗練によって胸に迫ってくる。中尾太一の詩は、ほんのすこしだけ「語りすぎてくれる」、そのほんのすこしずつの覚悟にいつも胸があつくなっている。

-
中尾太一
2014/7発売
いや、自分は結局あたらしもの好きなんだよな~。「現代」小説をぜひ読みたいんだ!というひとには青木淳悟『四十日と四十夜のメルヘン』と山本浩貴+h『Puffer Train』(Web上にて公開)。山本浩貴+hは大江健三郎論「新たな距離 大江健三郎における制作と思考」(『いぬのせなか座』1号収録)をはじめとする批評や創作のほか、主に詩歌集の企画・編集・造本デザインを行なっている。2015年に立ち上げた制作集団「いぬのせなか座」は「美術手帖」誌上にて現代詩アンソロジー「認識の積み木」を担当するなど詩歌の方面で名前が定着しているが、小説の世界ではまだあまり取り上げられていない。
青木淳悟と山本浩貴+hの作品は発表が七、八年ほど隔たっているが、その共通点として無理にあげるなら「小説の幽霊」がよく書けていることである。神話やエンターテインメントを通じてわれわれの慣れ親しんできた生者/人間の幽霊(生前や死後、肉体を離れた肉体)に呼応する、「小説の幽霊」が書かれている。小説を読み慣れていない読者のほうが、素朴に対すると「難解」といわれがちなこのふたつの小説をたのしめるのではないかという期待をもっている。

-
山本浩貴+h
2012年3月~2013年3月

-
青木淳悟
2009/8/28発売
いや、自分はもっと、とにかくアート! アート、アートなんだよなあ……というかたには青柳いづみこ『ピアニストが見たピアニスト』。楽譜という絶対的書物に立ち向かう「解釈」、翻訳行為としての「演奏」、それをからだごと、人間ごとでひきうけるピアニストという存在が、自分を小説に駆り立てるおおきな動機になっている。小説家が小説家たるゆえんの一端は、小説というのがなかなか一日で書き終わることはなく、日々を繋げていくその生活の胆力こそがひとりの人間を「小説家」にしていることにある。ピアニストが一日十時間ピアノを弾き、そのことをなんら異常と思わない「生活」とは、人間にとってなんなのか? 書くだけではなかなかわかりえない、しんの「生活」の迫力について。

-
青柳いづみこ
2010/1/1発売
自分が今まっさらな気分で出会いたいテキストは山城むつみ『ベンヤミン再読――運命的暴力と脱措定』(「新潮」二〇一七年二月号掲載)。雑誌「新潮」で不定期連載されているこの論文は、こうして書いていることばが意味を獲得し、読者が読むことで認識が交換されるそのことすらに否応なしに含んでしまう暴力に当事者性を持たんとする、その大地をふむ足裏のたしかさをおぼえる、読んでいるだけで特異な勇気をつい抱いてしまう文章。この文章がいま書かれているというだけで、自分はどれだけ救われただろうと思える。はじめて文章を読むときのような気持ちで、またこのベンヤミン論を読む身体を自分はどうやってつくれるだろうかと日々考えつづけている。

-
2017/1/7発売
-

-
町屋良平
1983年東京都生まれ。2016年『青が破れる』で第53回文藝賞を受賞。2017年同作が第30回三島賞候補となる。2018年『しき』が第159回芥川賞候補、第40回野間文芸新人賞候補となる。2019年『1R1分34秒』で第160回芥川賞受賞。
この記事をシェアする
「たいせつな本 ―とっておきの10冊―」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥











