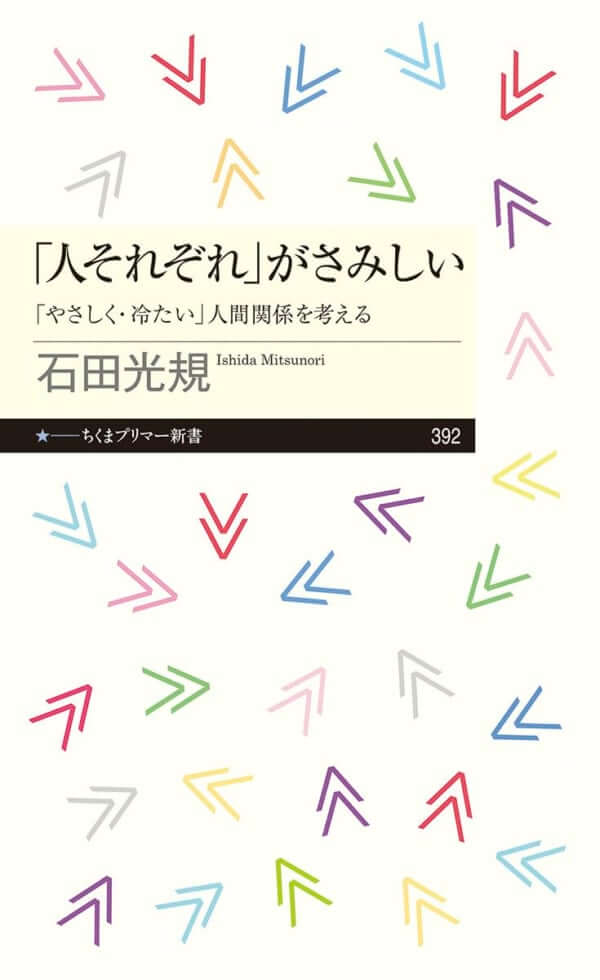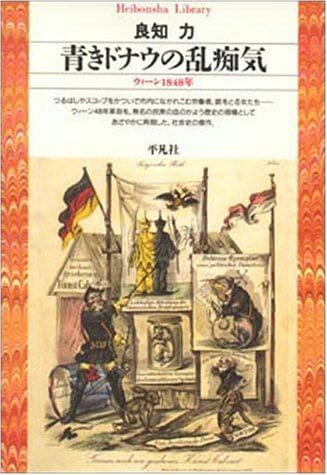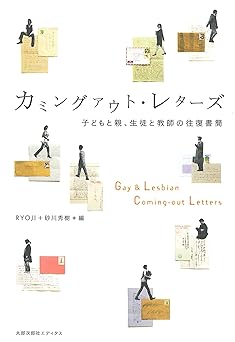(19)評論家&高校教員・林晟一の10冊
深みある〈強さ〉って何? 高校生に読んでほしい10冊
著者: 林晟一
石田光規『「人それぞれ」がさみしい』(ちくまプリマー新書)
加藤陽子『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』(新潮文庫)
良知力『青きドナウの乱痴気』(平凡社ライブラリー)
藤本和子『塩を食う女たち』(岩波現代文庫)
RYOJI、砂川秀樹編『カミングアウト・レターズ』(太郎次郎社エディタス)
岡典子『沈黙の勇者たち』(新潮選書)
荒井裕樹『凜として灯る』(現代書館)
五十嵐大『聴こえない母に訊きにいく』(柏書房)
西加奈子『円卓』(文春文庫)
金城一紀『GO』(角川文庫)
心の奥に良性のひっかき傷を残しつつ、知的な背伸びを歓迎してくれるような本がある。教員として高校生と斬り結ぶ中、私はそんな本を大切に思ってきた。
私の知る高校生は、たとえ快活であっても、笑顔の裏で物憂げなことも多い。この前、授業終わりの廊下で、ある生徒がつぶやいた――「筋肉や腕力とはちがう『強さ』って何ですかね。ほんとに『強い人』って、どんな人なんだろう」。
日々「哲学」する高校生に気の利いた答えを返せないまま、休み時間は終わった。
まったく頼りにならない教員である。
けれど、将来を不安に思う高校生のあなた、そして、心のどこかに高校生の青いわだかまりを宿す大人のあなたが、自分なりの強さを手探りする際に手がかりとなる本は知っている。
そんな10冊を、ここで分かち合いたい。
粘り強く考える
1.石田光規『「人それぞれ」がさみしい』(ちくまプリマー新書)
近年、性別や結婚観など、繊細なテーマについては語らぬが吉とのムードが濃くなった。「人それぞれですよね」。いさかいを避けるにはもってこいの決まり文句に頼ることも多い。
でも、たとえば不平等や貧困も、「人それぞれ」だから仕方ないと済ませていいのか。人それぞれという、一見相手の立場を尊ぶ言葉は、相手と自分の境界線をあまりにくっきりと引きすぎてしまわないか。本当は、あなたと私、みんなの間には、歩み寄れたり共感できたりする部分があるはずなのに。
石田光規『「人それぞれ」がさみしい』は、そんな事実にはっと気づかせてくれる。「人それぞれ」の境界線を越えて、誰かと手をつなごうとするきっかけを、どうにか得られないものだろうか。身近な話題が豊富な本書を手に取り、ぜひじっくり考えてほしい。
2.加藤陽子『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』(新潮文庫)
あれこれじっくり、粘り強く考えることは、大変だけれどやりがいがある。それは、「タイパ」や「コスパ」とは無縁ということでもある。加藤陽子『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』は、まさに時間や手間ひまをかけた傑作だ。
歴史家と高校生が語り合い、なぜ近代日本は戦争の道を歩んだのか考えてゆく。その過程は、ミステリー小説を読むかのような臨場感にあふれる。そして、歴史には定まったコースや必然なんてないことをゆっくり教えてくれる。
3.良知力『青きドナウの乱痴気』(平凡社ライブラリー)
粘り強く歴史に向き合うことの醍醐味は、良知力『青きドナウの乱痴気』でも味わえる。1848年、ヨーロッパ各地で革命が連鎖したことを、高校で学んだ/学ぶ人もいるだろう。本書は、その年ウィーンで起きた革命の複雑な内情を、やさしい言葉で解きほぐす。
どんな人がどう抑圧されていたから、革命へ参じたのか。本書は参加者たちの思いに寄りそいつつも、共感しすぎない。じっくり歴史に向き合ってこその、絶妙な距離感覚である。人いきれが立ち込める、これ以上の社会史の傑作を私は他に知らない。
かんたんに答えを出さない
粘り強く考えれば考えるほどわかることだが、世の中には、かんたんに答えを出せないことのほうが多い。わかった気になってタカをくくったり、気安くレッテルを貼って理解した気でいると、肝心なことを見落としてしまう。
4.藤本和子『塩を食う女たち』(岩波現代文庫)
藤本和子『塩を食う女たち』は、1970年代〜80年代のアメリカで、女性差別と黒人差別の交差点にあった人びとを取材する。理不尽な暴力で命を落とす黒人は、今日まで後を絶たない。それでも、本書に登場する黒人女性たちは、不幸話の中にそっとユーモアを忍ばせる。
〈白人 対 黒人〉といった構図を過信すると、ふくよかな現実が目に入らなくなる。ある黒人女性はいう。抑圧されていることは事実だが、それでも、抑圧が生活のすべてではないし、「希望はある」――。厳しい日常を生きる人びとには、笑顔やユーモア、希望がないと安直に想像してしまうことも、一種の差別だろう。
ウィスコンシン州ラシーヌで、20歳の黒人女性が、恋愛関係にあった50歳の黒人男性に射殺された。葬儀では親族が泣き叫び、気絶し、教会の牧師はたじろいだ。参列した被害女性の知人、その友人、著者の3人は、それぞれ車で帰路についた。
3台の車は道を別れる際、けたたましく、しつこく、はげしく、クラクションを鳴らしあった。被害女性に向けた弔いの曲を、即興で奏でたのだ。絶望の下でも一筋の希望とユーモアを捨てない、女性たちの痛切なる連帯である。
この世は、予期せぬ意外性に満ちている。
5.RYOJI、砂川秀樹編『カミングアウト・レターズ』(太郎次郎社エディタス)
RYOJI、砂川秀樹編『カミングアウト・レターズ』では、性的少数者とその親族、教師が、正直な思いを手紙で伝えあう。ある青年は、性的少数者とは別の少数者に対し、無神経になったり偏見を持ったりしたくないと記す。差別される痛みを知るからこそ、他者の痛みに敏感でありたいとの姿勢は、真に頼もしい。
本書に収められた手紙を読むと、カミングアウトをする側も受ける側も、さまざまに迷い、とまどっていることがわかる。性的少数者にはカミングアウトする選択肢もあるし、しない選択肢もあると編者はのべる。カミングアウトしないことを臆病だと断じたりはしない。
カミングアウトする私、しない私、立場があいまいな私、隠す私。どれもみんな本当の自分だし、現在の態度を将来どう保つか/変えるかは、自分でじっくり考えればいい。
世間が勝手に貼りつける「中途半端だ」「臆病だ」といったレッテルは、びりっと破ってしまおう。あなたには、かんたんに正答にたどり着かない自由がある。
正義を更新する
対象や自分自身について粘り強く考え、安易にレッテルを貼って良しとしない。このことは、みずからの正義をつちかい、更新するいとなみにも直結する。
「これこそが正しい。黙って従っていれば幸せなのだ。おまえのことを思って言ってるんだぞ」。親、先生、政治家をはじめ権力を握る人が、利他をよそおう利己的な命令を下すとき、首をかしげ、背くことはできるだろうか。
6.岡典子『沈黙の勇者たち』(新潮選書)
岡典子『沈黙の勇者たち』は、ナチ政権によるホロコースト(ユダヤ人虐殺)の時代、ひそやかにユダヤ人をかくまったドイツ人たちを紹介する。
あの時代、ユダヤ人を助ければ、自分も拘束される可能性が十分あった。にもかかわらず、「ユダヤ人排除はおかしい」との思いを、さまざまな形で行動に移すドイツ人は少なくなかった。
勇気と表裏一体の感情、それは恐怖である。だが、恐怖を飼いならし、おのれの正義を静かに実践する強さを持つ人が、この世にはいる。本書はそのことを雄弁に物語る。
7.荒井裕樹『凜として灯る』(現代書館)
ただし、静かな強さを持つ人はあんがい「普通」の人かもしれない。迷いもするし、犯した過ちを悔い、反省もする。そうして、みずからの正義を更新し、行動に移してゆく。
荒井裕樹『凜として灯る』が追いかける米津知子は、まさにそんな人である。1974年、上野の東京国立博物館を訪れた彼女は、日本で初めて一般公開されたダ・ヴィンチの名画「モナ・リザ」にカラースプレーを吹きかけ、拘束された。一体なぜ、そんなことを?
女性であり障害者でもある自分に向き合った彼女は、深い挫折と反省を経て、この世の不条理をスプレーで訴えることにした。裁判で、彼女はみずからの行為の正当性を主張したが、最高裁は上告を棄却し、科料3,000円の処罰が決まった。
彼女はこれをどのように支払ったか――。おのれの正義を更新し、それを誰にも引き渡そうとしない彼女のやせ我慢を知り、私は号泣した。その正義が本当に正しかったかはわからない。ただ、本書のタイトル通りの生きざまであることは確かだと思った。
いっしょに強くなる
『凜として灯る』では、米津の人生をとおして、1948年に成立した優生保護法(96年より母体保護法)をめぐる問題に焦点が当てられる。
同法の目的は、「不良な子孫」の出生を防ぐことだとされた。その下で、遺伝性疾患や障害を持つ人たちの同意がないまま、実に16,500件以上の強制不妊手術が行われたという。
8.五十嵐大『聴こえない母に訊きにいく』(柏書房)
五十嵐大『聴こえない母に訊きにいく』は、先天的に耳が聴こえない母の人生を振り返る。もしも彼女が同法の下で不妊手術を強いられていたら、著者はこの世に生まれていなかったことになる。
ともに耳が聴こえない父と母は、親族や近所に助けられ、自分たちで子どもを育てあげた。母は、ろう学校時代から、「いつもニコニコしていなさい」と教えられたという。そうすれば周りが助けてくれる。聴こえる人が多数を占める世界で生きるための、笑顔の戦術である。
むろん、人が笑顔を強いられる社会は、決して健全ではない。それでもなお、多くの人びとを引きつけてきた著者の母の人生に、笑顔は欠かせなかったはずだ。彼女は、周囲の笑顔を引き出すこともあっただろう。
笑顔をもって他者に助けられる人生は、他者に笑顔をもたらす人生でもある。笑顔の戦術は、笑顔の連鎖を生む。それは、強さというものが個人を越えてシェアされる局面につながってゆく。人びとが弱い部分を補いあい、相手はもちろん自分をも強くし、人間関係の網を細やかにする。
そんな局面が、この世にはある。
9.西加奈子『円卓』(文春文庫)
もしあなたにその心当たりがないとすれば、西加奈子『円卓』をとおして、自身の幼少時代を思い出してみてほしい。この小説の登場人物は、小3の「こっこ」をはじめ、みなキャラが立つ。ときに傷つけあい、意識せず補いあう。円卓にのっているかのように、愛がぐるぐる分かち合われる。
こっこの親友「ぽっさん」は吃音だ。大人はそれを勝手に哀れんだ。こっこはむしろ、彼の吃音を心から格好いいと思う。ぽっさんにとって、そんな彼女はかけがえのない友人だ。彼女もまた、小さな哲学者ぽっさんからさまざまな気づきの芽を分けてもらう。
ただ、かけがえのなさとは、取り替えがきかないということだ。こっこに大きな危機が迫った夏休みの日、ぽっさんは不在だった。こっこは情緒が乱れてゆく。後日、事件を知ったぽっさんは、そばにいてやれなかったことを悔い、謝り、涙を落とす。
ぽっさんは、「早く大人になりたいと願った」。そんな彼を見て、こっこは「死ぬことを寂しいと思った」。ふたりは、生まれて初めての感情をめいめい宿す。
あのころ、私たちは、ふたりのように強くはなかったか。生きることを肯定しあい、いっしょに成長していきたいと願う程度には――。
ただ、叫ぶ
これまで、筋肉や腕力とは別の強さの形をとらえようとしてきた。粘り強く考えること、かんたんに答えを出さずレッテルを貼らないこと、正義を更新しながらそれを実践すること、そして、いっしょに強くなること。
強く生きるって、かくも彩り豊かだし、かくも難儀である。とはいえ、完璧な強さを持つ人はこの世にいない。たいていは、たとえ顔で笑っていても、ひそやかに傷ついているし、そこそこ不幸だったりする。
私が日々斬り結ぶ高校生はといえば、ときに意味不明な叫び声をあげ、周りをぎょっとさせる。そんなあいつがちょっとうらやましい。心の底から湧く、不定形の思いのたけや不安は、文字にならない叫び声で発散するほかないのだから。
10.金城一紀『GO』(角川文庫)
金城一紀『GO』は、深みある強さを手探りするあなたに贈る最後の一冊だ。日本人の一部から差別される在日コリアンとして生きる高校生が、迷い、怒り、にらみつけ、友を殺され、ボクサーの父にケンカを挑み、歯を折られ、叫びながら、自分なりの強さを求める青春小説である。
「俺は《在日》でも、韓国人でも、朝鮮人でも、モンゴロイドでもねえんだ。俺を狭いところに押し込めるのはやめてくれ。俺は俺なんだ。いや、俺は俺であることも嫌なんだよ。俺は俺であることからも解放されたいんだ。〔……〕ちくしょう、俺はなんでこんなこと言ってんだ? ちくしょう、ちくしょう……」
メトロノームが左右に振り切れた瞬間のように、はっきりした答えを出してしまうことは容易だ。でも、結局それでは納得できず、左右の間をさまよう。対象や自分自身を、えいやと無理やり分類してレッテルを貼っても、とうてい満足できないのが人生である。
強さは、さまよい、迷い、とまどいの幕間からしか生まれない。
もやもやをどうしても言葉にできないときは、ただ、叫ぼう。川原や土手、部室、屋上、恥ずかしければカラオケボックスでもいいではないか。
そうしてまた、明日の朝を迎えよう。
この記事をシェアする
「たいせつな本 ―とっておきの10冊―」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥