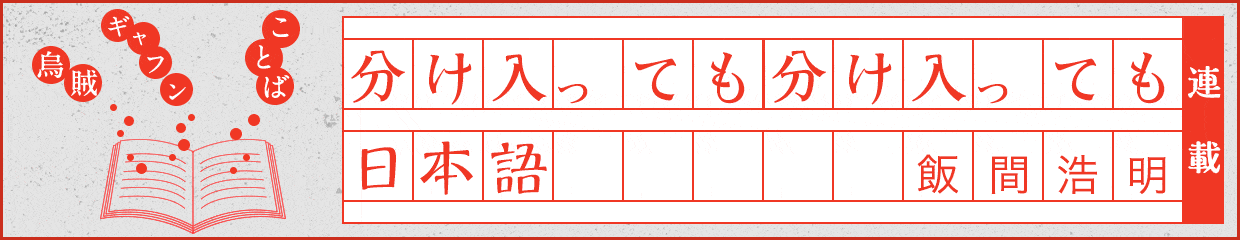高校時代、古文を勉強していて、ある文脈が順接(「だから」「それで」)か、逆接(「しかし」「それなのに」)か、判断に迷ったという経験を持つ人は多いでしょう。古文の順接・逆接というのは、本当に曖昧で分かりにくいのです。
たとえば、「伊勢物語」に出てくる、親しい友人同士の話の冒頭はこうです。
〈昔、男、いと麗しき友ありけり。片時さらず〔=少しの間も離れず〕あひ思ひけるを、人の国へ行きけるを、いとあはれと思ひて、別れにけり〉
「~を、~を」と「を」が続きます。このうち、〈あひ思ひけるを〉は「友人と互いに思い合っていたのに」と逆接に訳します。次の〈人の国へ行きけるを〉は、「その友人が地方に行ってしまったので」と順接に訳します。同じ「を」という接続助詞が、文脈によって、順接になったり逆接になったりします。面倒くさいですね。
「これだから古文は分かりにくい、論理関係ぐらいはっきり示せ」と、思わず文句を言いたくなります。「伊勢物語」の作者としては、どちらの「を」も順接とか逆接とかいう意識もないままに使用しているのでしょう。試みに、原文の雰囲気を現代語で再現すればこんな感じでしょうか。
「男は友人と互いに思い合っていて、で、友人が地方に行ってしまって、で、男は何だか悲しくなって、そのまま別れて来た」
まるで今の若い人の話し方のようです。原文では順接・逆接が未分化だったのを、現代人が読む際に訳し分けているだけだとも言えます。
今日、逆接の代表と言えば「しかし」です。ところが、歴史を遡ってみると、このことばもまた、逆接なのかどうか、曖昧なことばでした。
大元の形は「しかしながら」です。それが中世以降に省略されて「しかし」が生まれました。今では「しかし」はやや硬いことば、「しかしながら」はさらに硬いことばです。でも、中世~近世頃には、「しかし」はかなりくだけた会話に、「しかしながら」は格式張らない文章に使われたと言います(森田良行『基礎日本語』)。
では、「しかしながら」は、そもそもどんな意味だったか。「日本書紀」には、
〈又願はくは、普天の下の一切衆生、皆、解脱を蒙らむ〉
という難しい訓が出てきます。ここで、「一切衆生」(この世に生きているすべての生き物)の「一切」の部分に「しかしながら」と書いてあるのに注目してください。つまり、「しかしながら」は、もともと「一切」「そのまま全部」の意味でした。
「しかしながら」を分解してみると、「しか」の部分は、「しかも」などの「しか」と同じで、「そう、そのように」の意味です。「し」は、動詞「す」(する)の連用形。そして、「ながら」は「昔ながら」の「ながら」で、「~のまま」の意味を表します。全体では、「そのようにしたまま」「そのような状態のまま」ということです。
これが、後に「そっくりそのまま」→「言い換えれば」→「要するに」と、意味が変わっていきます。「しかしながら」が「要するに」を表した時代があったわけです。
また、中世~近世頃には、「そのような状態のまま、一方では」という意味から、逆接の用法が現れました。今の「しかしながら」「しかし」と同じ使い方です。
この頃の文献に「しかしながら」が出ているのを見ると、「要するに」の意味で使っているのか、今と同じく逆接の意味で使っているのか、分かりにくい例があります。
たとえば、中国のある皇帝が、国に繁栄をもたらす元となる吉夢を見た、という話を紹介した後に、「これは、しかしながら、短い夢であった」と説明する書物があります。この「しかしながら」はどう解釈すればいいのか。
「これは、要するに短い夢であった」という意味とも考えられるし、「(後々に繁栄をもたらしたが)しかし、元は短い夢であった」という逆接とも考えられます。
曖昧ですね。「しかしながら」は、もともとは逆接を示すことばではなかったのが、この例のように、逆接を表すような、そうでないような段階へと進みました。そこからだんだんと、現在のように逆接の接続詞へと発展していくことになります。
ちなみに、先に挙げた書物とは、16世紀に日本で書かれた『中華若木詩抄』という漢詩注釈書です。原文は、〈これは、しかしながら、一霎頃〔=短い間〕と云て、村雨の一通り降るほどの〔短い夢の〕ことなり〉というのです。
さて、現在では、「しかしながら」の省略形「しかし」が主流になりました。「しかし」はもちろん逆接を表しますが、そうではない使い方もあります。
漫才師の横山やすしさんの名ぜりふに「怒るで、しかし!」というのがありました。相方の西川きよしさんのツッコミに対して発するせりふです。インターネットを見ると、「この『しかし』はどういう意味か」と質問している人が少なくありません。
「怒るで、しかし!」の「しかし」は、逆接ではありません。「まったく」「本当に」などの意味を表す感動詞です。
やすしさんに限らず、私たちも逆接でない「しかし」を使っています。「今日は、しかし暑いねえ」というときの「しかし」がそう。こちらは「それにしても」と話題を転換する感じがあります。
これらの用法には、「しかし」が逆接の意味を持つようになった時期より前の意味が残存しているのかもしれません。
「しかし」ということばは、誕生した時から筋金入りの逆接の接続詞かと思ったら、そうではなく、また、現在も必ずしも逆接ばかりを表してはいません。他の類義語を見ても、もともと逆接でない語が逆接に転用された語がほとんどです。
-
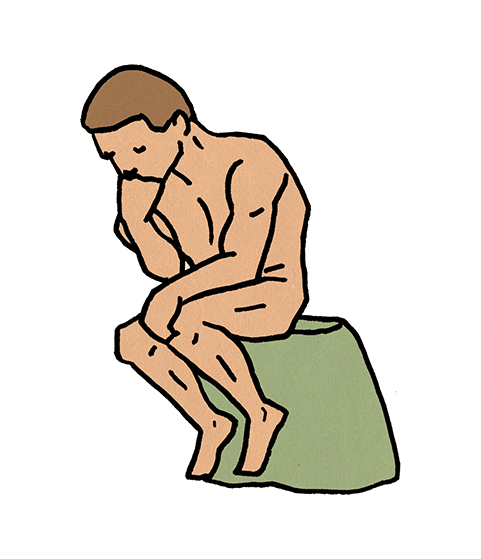
-
飯間浩明
国語辞典編纂者。1967(昭和42)年、香川県生れ。早稲田大学第一文学部卒。同大学院博士課程単位取得。『三省堂国語辞典』編集委員。新聞・雑誌・書籍・インターネット・街の中など、あらゆる所から現代語の用例を採集する日々を送る。著書に『辞書を編む』『辞書に載る言葉はどこから探してくるのか? ワードハンティングの現場から』『不採用語辞典』『辞書編纂者の、日本語を使いこなす技術』『三省堂国語辞典のひみつ―辞書を編む現場から―』など。
この記事をシェアする
「分け入っても分け入っても日本語」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-
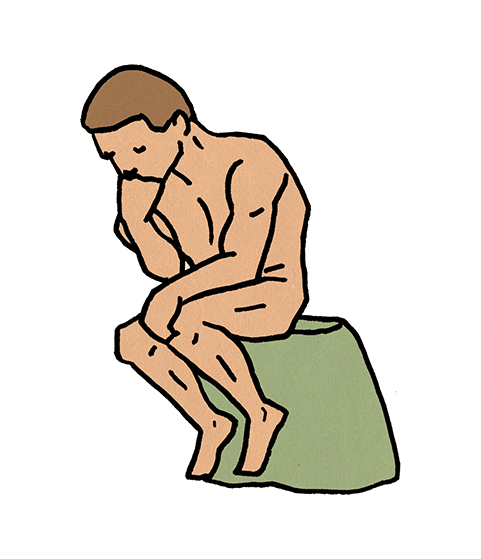
- 飯間浩明
-
国語辞典編纂者。1967(昭和42)年、香川県生れ。早稲田大学第一文学部卒。同大学院博士課程単位取得。『三省堂国語辞典』編集委員。新聞・雑誌・書籍・インターネット・街の中など、あらゆる所から現代語の用例を採集する日々を送る。著書に『辞書を編む』『辞書に載る言葉はどこから探してくるのか? ワードハンティングの現場から』『不採用語辞典』『辞書編纂者の、日本語を使いこなす技術』『三省堂国語辞典のひみつ―辞書を編む現場から―』など。
連載一覧

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら