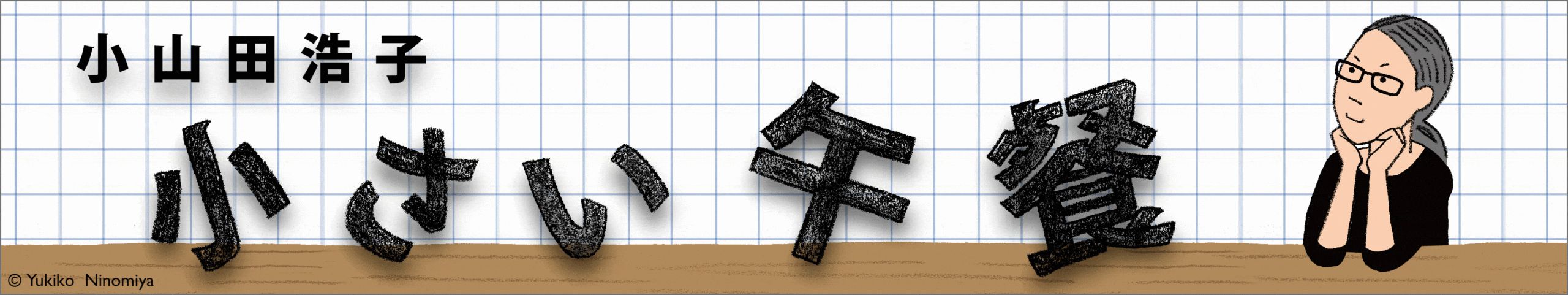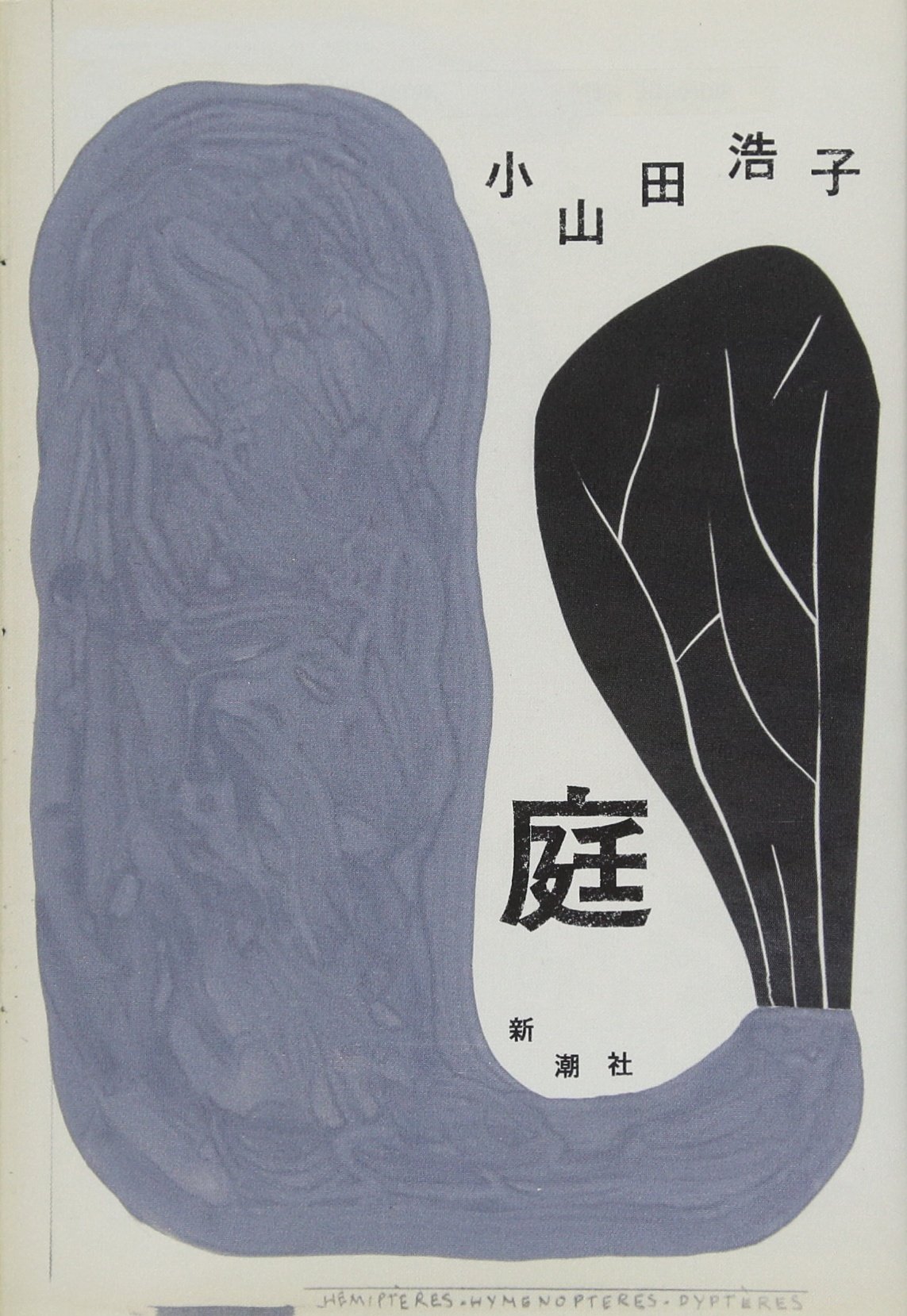年の瀬のばたばたした夕方、お好み焼きの出前を近所の店に頼むことにした。お好み焼きの出前は広島では一般的で宅配専門店もあるくらいだが、以前に東京の編集者の人にそう話すと「広島風のお好み焼きを?!」「出前で?!」「どうやって?」と驚かれた。もしかしたら広島以外では普通のことではないのかもしれない、それも新型コロナウイルス感染症の影響もあってデリバリーが増えたいまだとまた事情が違うのかもしれない、とにかくうちでは普通にしょっちゅう頼む。ホットプレートがないため家では作らないせいもあるが、疲れていて料理を作りたくないとき、でもある程度ちゃんと栄養があるものを食べたいし子供に食べさせたいとき、そしてそんなにお金がかけられないときお好み焼きは本当に助かる。夫に電話を頼む。初回注文を夫の携帯からしたためにその番号が向こうに登録されていて住所など言わなくて済む。「すいません、出前お願いします。肉玉そば3枚、で、1枚はそばダブル、1枚はそばハーフ野菜ダブル、もう1枚は普通でお願いします」間があり、「あ、そうです。あ、全然大丈夫です」多分住所の確認と、混んでいるから少し時間がかかるとか言われているのだろう。夫が言わないので私は夫の前で右手をチョキにして口元に持って行くジェスチャーをする。箸、箸。「あ、それと、割り箸いらないです。あと予備のソースもいりません。あー、いえいえ、はい、じゃ、よろしくお願いします」夫が電話を切り「40分はかかるって」と言う。じゃあ先に風呂済ませようか。私は風呂場へ行き湯を溜め始める。夫が電話し終わるのを待ち構えていた子供は夫に遊びの続きをせがんでいる。「わかったわかった」遊んでもいいけど、お風呂溜まったらすぐ入るんよ。「はーい」私はその隙にパソコンに向かって仕事をする。
子供のころは、お好み焼きはいつも母がホットプレートで焼いてくれるもので、出前も店で食べることも想像すらしなかった。月に1回多いときはそれ以上、食卓にホットプレートを出し小麦粉と水で作った生地のボウル、豚肉と卵のパック、焼きそば、生地のよりふたまわり大きい千切りキャベツが山盛り入ったボウル、もやしと青ネギ、ちぎったイカ天とソース、削り節や青のりなどが用意される。風呂から出た順に母が1枚ずつ焼いてくれる。ホットプレートの半分に生地を丸く広げ削り節を載せる。みるみる生地に透明感が出て縁が乾いてめくれたように立ち上がる。すぐにキャベツ、ちぎったイカ天、もやし、刻んだ青ネギを載せる。イカ天、おつまみやおやつ用に売っているサクサクした硬いのではなくしんなり柔らかいやつ、つまみ食いするとそれ高いんよと少しだけ叱られる。イカ天をちぎらず丸ごと1枚むしゃむしゃ食べるのが子供のころの夢だったが、大人になったいまやろうと思えば容易にできるはずなのにそういえばまだやったことがないな、テレビのカープ中継かクイズ番組か、曜日によってはアニメの音声の隙間に生地からはみ出てホットプレートに直に当たっている千切りキャベツがシーと鳴っているのが聞こえる。野菜の山の上に豚肉を広げながら載せ、ちょろっと生地を垂らしてひと呼吸置いて生地と野菜をひっくり返す。ヘラはないので普通のフライ返しを2本使う。生地が上、豚肉が下になりジュウウと音が立つ。生地は所々薄茶に焦げている。散ったキャベツなどをフライ返しでかき寄せる。もうキャベツのシーは聞こえない。ホットプレートの半分に焼きそばを入れソースを垂らして炒める。フライ返しで生地と野菜の山を軽く押さえる。かさが減っていく。ちょっと下をめくって豚肉が焼けていることを確認してから焼きそばを丸く整え、その上に2本のフライ返しで持ち上げた野菜と生地を載せる。いままで生地があった場所に卵を割り、フライ返しの角で黄身を潰して丸く広げ、その上に野菜と生地と焼きそばをまた2本のフライ返しで載せる。店だとここで再度ひっくり返す場合も多いがうちではいつもそれで完成、下から卵、焼きそば、豚肉、青ネギともやし、イカ天、キャベツ、1番上に生地、皿に移し、ソースは自分でかける。子供のころはマヨネーズが苦手だった。青のりと削り節を振る。母は次の分を焼き始める。お好み焼きの日はだからいつも家族で食べる時間がバラバラだったが団欒感があった。いつも自分の分を最後に焼く母は、生地がキャベツが余っちゃったとか足らんかったわなどと言いながら他のより大きかったり薄かったりするお好み焼きを食べていた。
高校生になったとき、違う県から広島にやってきた友達ができ、何人かで彼女の家でお好み焼きをやろう、ということになった。彼女は店では食べたことがあるが家では焼いたことがないと言う。「だって難しそうじゃない?」こちらのではないイントネーションで彼女は言い、「ひっくり返すのとかさー」いやそんなことないよ、全然難しくないよあんなの。私は母に生地の配合などを聞いて彼女の家に行った。母が家でやるのを見ていたし、生地を混ぜたりひっくり返したりする手伝いもしていたので余裕だろうと思い作り始めたのだが、焼き始めた途端、丸く広げようとした生地がおたまの背にくっついておかしな形になってしまった。修復しようとしてもさらにおたまにくっつきなんだかくしゃくしゃした立体になっていってしまう。あれ、おかしいな、その生地を捨てもう1度やったがそれもダメ、ごめんうち無理じゃ、なんでじゃろ、ちょっと代わりにやってや。「えー」別の子がやってもなんだかうまくいかず、作った生地が底をつきかけ追加で作ってもうまくいくとはかぎらないしもうそのまま行こうということになったが基盤となる生地がないためにキャベツも他の具材もとりとめがなく、それを無理やりひっくり返すと普段以上にキャベツが周囲に飛び散り、さらに強引にそばや卵と合わせ生地の不在を隠すようたっぷりソースをまぶしたものの食べたら全然お好み焼きの味ではなく、皆で笑い転げたが私はとても決まり悪かった。生地はあんなに薄いのにあれがないとお好み焼きにならないのだ。母はいつもこともなげにやっていたのに……「みんなが来るからきのう掃除したのに」と笑いながら友人は部屋のあっちこっちに飛び散った油まみれのキャベツをつまみ上げた。いま思えば卵を倍使って上下を挟んで生地代わりにでもすればよかったのだが、そのときは思いつかなかった。私たちはここにもある、嘘じゃろこんなとこにも飛んどる、と笑いながらキャベツを拾い集めた。
初めて店でお好み焼きを食べたのは多分大学生になってからだ。大学のそばにはいくつかお好み焼き屋があったが、大学の近くにあったその店はおいしくなくて、なんだか具が多い湿った焼きそばみたいで妙にもやし臭くて、よそから来てそこのを食べてなんだ全然おいしくないじゃんと思って広島のお好み焼き自体を軽んじたまま地元に帰る人もいるのだろうと想像するとややうっそりした。そして高校時代自分が作ったお好み焼きのことを思い、母が作ってくれていたお好み焼きがいかにおいしかったのかも知った。その後、就職してからはちょくちょく職場近くにある店で食べるようになった。当然ながらおいしい店もちゃんとあった、というか大半がおいしいのだ。普通かな、という店はあれどまずい方が珍しい、そうなれば、他の外食に比べてお好み焼きは値段に対してちゃんと栄養があるものを食べている感じがするしお腹も膨れる、仕事終わりに同僚とコンビニで買った缶ビールを飲みながら名店と言われる店の大行列に参戦したこともあったし、小さい、でも知る人ぞ知るなんよというような店を教えてもらったこともあった。ラードで荒々しく焼いたのや、ニンニクが効いているのや、糸のように細く切ったキャベツが甘く蒸されて柔らかいのやソースがひと味違うのや半熟に焼かれた卵がこれみよがしにとろっと垂れているのやいろいろなお好み焼きがあった。
あるとき、結婚前の夫と開店したばかりのお好み焼き屋へ行った。なんでも有名店の暖簾分けというか直弟子が独立して開いた的な店らしく、話題になっていたためオープン当初から行列ができていてその日もかなり待ってから鉄板前のカウンター席に案内された。カウンターの奥で、やや年配の男性が生地のボウルをかき混ぜていた。鋭い目つき、伸びた背筋、リズミカルながらどこか重厚なそのテンポ手の動きは熟練の職人感というか、あの人が店長というかこの厨房の主的な存在なのかなあと思って見ていたら厨房のステンレス製の壁からなぜか突然赤い丸いマグネットが落ちてきてそのボウルに入った。ひらっと、なにかが手書きされたメモも調理台に落ちた。マグネットが留めていたメモだった。値段だか分量だからしい数字がボールペンで書いてあった。男性は一瞬手を止めその生地まみれになったマグネットを素手で素早くつまみ出し、軽く振って生地をボウルに落とし(多分山芋とか隠し味とか入っているのだろう、粘りのある生地であまり落ちなかった)、シンクに投げ入れ(大きな音がした)、指先をボウル脇にあった布巾かなにかで拭いてそのままその生地をかき混ぜ続けそして鉄板前に陣取っていた若い男性に渡した。若い男性はその生地を鉄板に薄く丸く広げ焼き始めた。私はえええ、と思った。横目で見たが夫は全然あらぬ方向を向いていていまの所業には気づいていないようだった。まあ、マグネットったって厨房内のものなら全部うちは徹底的に清潔にしておりますんで汚くないんですよ、ということなのかもしれないけど、でも、やっぱりそれどうなんだ、そして出てきたお好み焼き(タイミングが違ったのでマグネットが入ったのとは違うボウルの生地で焼かれた)は仰天するくらいおいしくなくて、学生街のよりはるかにおいしくなくなんなら私が友人宅で失敗したやつより下なんじゃないか、生地が変に分厚くぼとぼとのごとごとで、全体が不快に湿っていて味もぼんやりしていて、いくらソースをかけてもその茫漠とした味は修復できなくて、夫の顔を見ると今度は夫もなにこれ、という顔をして私と目を合わせその後しきりにマヨネーズを絞りかけていた。二度と行くもんかと店を出たがその後もずっと行列は絶えなくて、多分、私たちが行った日は料理人の体調不良かなにかだったのだろうということになった。
その後、転職のたび転居のたびに近くの店へ行き、市内ならここ、近所ならここ、という店が定まった。市内、つまり広島の繁華街にある某店はおいしくて混んでいなくて立地が至便かつ全体の感じがいい。相席前提の細いテーブル、2人がけと4人がけのテーブル、という狭い店だ。鉄板前にもカウンター席があり一応椅子が置いてあるのだがそこに客が案内されるのを見たことがない。観光客らしい姿もときどき見るがだいたいが老人やサラリーマンなど近所の住人や労働者に見えるお客さんが多い。お好み焼きは1枚焼くのに時間がかかる。だいたい20分くらい、混んでいる店だとどうしても時間がかかってしまう。おそらくガイドブックに載っているような、観光客がたくさん行くような店が大行列になってしまうのもそのせいで、ようは回転率が悪いのだ。だがその店は席数が少ないのにどういうわけか満員で入れないようなこともなく、それでいておいしく、厚みはかなり押しつけられて平らになって、麺は鉄板に接していた部分がパリッと硬く焼けて、キャベツは太めのが歯切れよく、それが縁が膨らんだように高いクリーム色の平皿で出てくる。食べ終えると皿の中央のソースメーカーのロゴが見える。壁にはカープのカレンダーが貼ってある。壁と壁の角に小さいテレビがあってワイドショー的なものが放送されている。店は高齢の女性が1人、中年男性が1人、中年女性が1人の3人で運営されている。やりとりから、おそらく3人は家族、中年男性が高齢女性の息子、中年女性はその配偶者のような間柄に思われる。私がこの店に行きだしたころ、いまから10年くらい前には年配の女性が主に鉄板の前に立ってお好み焼きを焼いていた。小柄で笑顔が絶えない感じの女性が両手にヘラを持ってひょいひょいひょいとひっくり返していく。そばをヘラの角を使ってほぐしつつ焼く、キャベツやそばのかけらをヘラでこすって鉄板手前の溝に落とす、透明な油を鉄板に塗る、平たい大きなハケの先端にソースが絡まって粘って光っている。シャッ、とかチッとかシューとかジューとかいろいろな音がする。それが、最近行くと焼いているのはいつも中年男性で中年女性がお運び、高齢の女性は店の奥に置かれた丸椅子に座ってマグカップをかたわらに置いてにこにこ店内を見回している。彼女の仕事は、ごちそうさま、と立ち上がる客に向かってありがとうございました、と言うことのように見える。会計はソースメーカーのエプロンをして頭にバンダナを三角巾巻きした中年女性がしてくれる。
インターフォンが鳴り、今日の分、2020年12月某日のお好み焼きが配達されてきた。夫がまだ風呂から出ていなかったので私が出て、女性の配達員さんからほかほかしたビニール袋を受け取ってお金を渡す。届けてくれるのは女性だったり男性だったり、いつも若い人だ。今日の人も見ようによってはまだ高校生くらいに見える。分厚い上着を着ている。鼻の頭が赤くなっている。外は寒い。「ありがとうございましたー」ありがとうございました、お気をつけて。よいお年を、と言おうか迷い言いそびれる。袋には平たい丸い蓋つきの発泡スチロール容器が縦に3つ重なっている。蓋にそれぞれマジックで『ソW』『野菜Wソハーフ』と書いてある。1つにはなにも書いていなくて、これはつまり普通の肉玉そばだ。容器は輪ゴムで留めてあり、通常ならそこに小袋入りの追加用ソースと割り箸が挟んであるが注文時に断ったのでない。容器越しにもまだ十分熱い。子供、そしてちょうど風呂から出てきた夫を食卓に呼び麦茶と箸を配りそれぞれの蓋を取る。上からヘラでざっくり8分割してあるお好み焼きは完全には切れていなくて、上からその切れ目に箸を差しこんでつながっている生地やそばをちぎって持ち上げた断面から湯気が立つ。キャベツや麺が垂れ下がる。いままで何十回何百回と嗅いできた、1枚1枚全部違うけれど、やっぱり同じ、お好み焼きの匂いとしか言えない、ソースの、油の、生地の、そばの卵のキャベツのネギの青のりの、いろいろなものが重なり混じり合って熱せられたあのいつもの匂いの湯気が部屋に広がっていく。
-

-
小山田浩子
1983年広島県生まれ。2010年「工場」で新潮新人賞を受賞してデビュー。2013年、同作を収録した単行本『工場』が三島由紀夫賞候補となる。同書で織田作之助賞受賞。2014年「穴」で第150回芥川龍之介賞受賞。他の著書に『庭』『小島』『パイプの中のかえる』など。
この記事をシェアする
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥