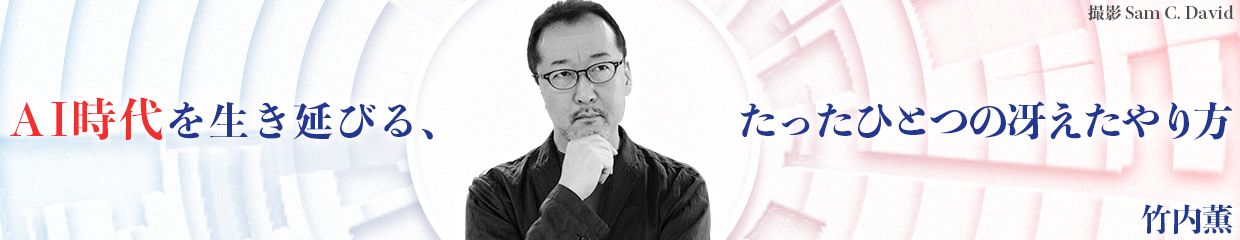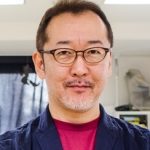さて、AI時代の人材育成の問題へと移ろう。「AIに勝つための教育」はどうあるべきか。ここまででAIの強みについて、いろいろと書いてきたが、弱点については、あまり触れてこなかった。だが、AIに勝つためには、まず、AIの弱点を知る必要がある。
そこで参考になるのが「東ロボくん」だ。国立情報学研究所が中心となって2011年に立ち上げられたAIプロジェクト。東大に合格できる人工知能を作りながら、AIの可能性と限界を探ろうというのである。過去問などの機械学習で東ロボくんはぐんぐんと成績を伸ばし、有名私立大学や国立大学にも合格できるような実力をつけた。だが、研究開発チームは、2016年11月に、突如、東ロボくんが東大受験を断念したと発表し、世間を驚かせた。いったい東ロボくんに何が起きたのか。
実は、いくら試験問題を機械学習しても、東ロボくんには解けない種類の問題があることが判明したのだ。それは、このような類の問題だ。
「A.彼はまた資料を忘れた」
「B.おまけにプレゼンにも遅刻した」
という文章のあとに、続く文はどれか?
(1)私は寝坊した。
(2)プレゼンには資料が必要だ。
(3)彼はもうすぐクビになるだろう。
(出典:竹内薫が勝手に作りました)
読者のほとんどは、すぐに(3)が自然な答えだとおわかりになったであろう。だが、驚くべきことに、人類の誰よりも「ガリ勉」の東ロボくんは、遅刻というワードに反応して短絡的に(1)を選んだり、資料というワードに反応して(2)を選んだりする。いったいなぜ、東ロボくんは(3)を選ぶことができないのか。
実は、東ロボくんの学習データには、(3)を選ぶための「社会常識」が欠けていた。われわれは皆、学校や会社でさまざまな失敗をくりかえしながら、やっていいことといけないこと、周囲から感謝されることと蔑まれることなどを学んでゆく。だが、ペーパードライバーがうまくクルマを運転できないのと同じで、いくら受験勉強をしても、生の体験が皆無の東ロボくんは、いつまでたっても、人間社会の常識が身につかない。東ロボくんは非常識で「空気が読めない奴」だったのだ!
東ロボくんの事例は、将来、AIと人間の役割分担をどうすべきかの良いヒントとなる。機械学習で効率よく学べる、パターン化された仕事はAIにまかせ、人間は、AIが苦手な分野で頑張ればいい。その分野を特徴づけるキーワードは、「創造力」と「人間コミュニケーション力」である。
東ロボくんには、なぜ、創造力や人間コミュニケーション力が欠けているのか。それは、東ロボくんには自意識や自我がないからだ。東ロボくんは好きで勉強していたわけではない。知的好奇心があるわけでもない。芸術や科学の創造につながるような、心の内から湧き上がる「動機」が東ロボくんには欠けている。東ロボくんは、他の人間に心があることすらわからない。自分に意識や自我がないのだから、他人の「中身」がどうなっているかを推測することもできないのだ。東ロボくんは「ゾンビ」なのだ!
ええと、ゾンビというのは、哲学者や脳科学者が普通に使っている表現であり、人間のように振る舞っていても、心がない状態を指すと思ってください。別にゾンビ映画みたいなホラーではない(いや、ホラーかもしれないが)。
近い将来、AIが会計作業をやったり、お役所の書類を処理したりするようになっても、そのAIは、自分勝手な「マニュアル人間」みたいに見えるはずだ。あるいは、慇懃無礼な執事、あんちょこにだけ頼っている学校の先生、興味なさそうに仕事をしている市役所の人……みたいなイメージである。マニュアル人間も慇懃無礼な執事もあんちょこ先生も能面みたいな市役所職員も、みな、本当は心を持っているが、やっている仕事がつまらないから、ロボットみたいに見えるわけだ。AIロボットの場合、本当に心がないので、究極のマニュアル人間になってしまう。
では、逆に、われわれの回りで、活き活きと仕事をしていて、みんなから好かれる人々は、どのような特徴があるだろう。たとえば、温情判決で、ぐれたティーンエイジャーを更生させる裁判官、思いやりがあり、いつも授業を工夫している先生、仕事ができるけれど喧嘩ばかりしている二人の部下の間をうまくとりもつ上司、それから、詩人、即興演奏で観客を楽しませるミュージシャン、フォトグラファー、エトセトラ、エトセトラ。
いかがだろう。社会には、東ロボくんに似た人間も多いが、その対極に位置する人々も多い。そして、ポイントは、AIが人間の仕事の半分を奪う場合、奪われるのは、前者の仕事であり、後者の仕事は末永く人間の領域に留まり続けると予想されることなのだ。
東ロボくんの東大挑戦は頓挫したが、おかげで大きな教訓が残された。人間が取るべきAIとの共存戦略は、「創造」や「人間コミュニケーション」の分野で頑張ること。それがわかっただけでも、きわめて有益な研究プロジェクトだったといえるのではないか。