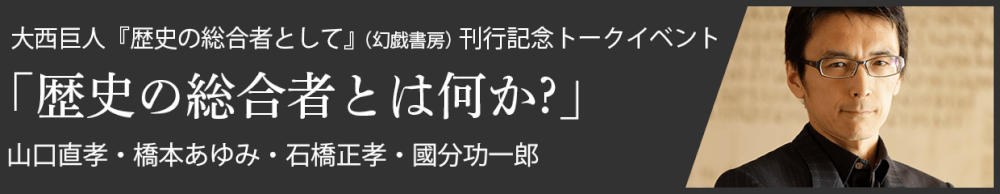山口 ここで少し話を変えます。『歴史の総合者として』には書評がたくさん収められています。大西巨人は、編集者として優れた能力を持っていた人ですが、書評子としても素晴らしい書き手であったことが、本書を読むとよくわかります。文章を読むと、どれも読みたくなります。実際、私は、今回何点か新たに買って読み、感動しました。ただ残念なことに、紹介されている本の多くは、現在新刊で入手することができません。ジョルジュ・アルノオの『恐怖の報酬』などは、生田耕作訳の単行本があるだけです。文庫になっていないせいか、古書価が結構します。
紹介書の中には、外国の小説、あるいはノンフィクションの類がかなりあります。時間がないので書名を挙げることしかできませんが、例えばフランスのクロード・モルガン『人間のしるし』やチェコのヤン・ドルダ『高遠なる徳義』などの対独レジスタンス活動を描いた小説、アルジェリア解放闘争に取材したアンリ・アレッグ『尋問』、アメリカ人による対日戦争と中国革命運動とのルポルタージュ『中国の歌ごえ』などです。乱暴に括ってしまうと、これらの作品は、ファシズムや帝国主義に対する抵抗や蜂起を描いたレジスタンス文学、革命の文学ということで共通します。大西巨人は、1950年代にそのような作品を読んで感動し、推奨しているわけです。
実際それらは、心理的な圧力や物理的な暴力に屈することなく解放や独立のためにたたかった人たちの物語であり、感動的です。かっこいい人が出てきて、かっこいいことを言う。どの作品にも、決めのせりふがあって、それが読者に忘れがたい印象を残します。ヤン・ドルダの『高遠なる徳義』を例にとると、ナチス支配下のチェコにおいて暴政を布いたハイドリッヒ総督が暗殺されるという事件が起こります。当局は血眼になって実行者を探そうとして、容疑者や関係者と目したものを片っ端から捕まえて拷問にかけ、見せしめのために殺していきます。また、チェコの人民に容疑者逮捕のために協力することを強制します。小説の舞台は、ある学校、主人公は、老いたラテン語・ギリシャ語の教師で、「高遠なる徳義の見地よりしますと……」という口癖で普段は生徒に笑われています。教師が勤める学校にも総督暗殺の捜査の手が及び、生徒3人が関係者として拘引されていきます。翌日、教室で拘引された生徒を非難し、残った生徒たちを戒める役割を振られた教師は、ためらった末「高遠なる徳義の見地よりしますと」、「暴君を殺すことは罪ではありません!」と言い放ちます。教師の勇気ある発言に、生徒たちは「ぎらぎら光る眼をして、『気をつけ』の姿勢で立」って応えます。これが『高遠なる徳義』のあらましで、クライマックスは教師が「暴君を殺すことは罪ではありません!」と言うところになります。巨人が推奨する作品は、いずれも同様の劇的な場面、クライマックスを持っている作品です。巨人は小説家であるので、感動的な作品に出会った場合は、当然それを一つのお手本と考えるはずです。『人間のしるし』や『高遠なる徳義』など推奨している作品については、とりわけ意識することになるでしょう。しかし、1950年代にすぐれた抵抗の文学、革命の文学に触れながら、直ちに巨人はそれに連なる作品を書こうとしませんでした。そこに考えるべきところがあるようです。
書評で紹介されているものではありませんが、やはりかっこいいせりふを主人公が言う作品としてシーモノフ『ロシア問題』(新世界文学研究会、1950年5月)という戯曲があります。シーモノフは、ロシアの戯曲家で、今は忘れられた作家になっているようですが(私もよく知りません)、巨人は高く評価しています。例えば、『たたかいの犠牲』には『ロシヤの人々』(八住利雄訳、協同出版社、1946年9月)からの共感的な引用があり、『プラーグの栗並木の下で』(土方敬太訳、昭森社、1946年8月)のロシア軍曹長マーシャの「『君も地球に生れたんだね。僕も地球生れだ。お互ひに地球の人間だから同郷人だね』つて云ひ合へる時がいつたい来るやうにならないものかしらつて。」という発言は、平等の理念を表した言葉として、エッセイなどでくり返し取り上げられています。
『ロシア問題』は、3幕の戯曲で、舞台は1946年のアメリカです。反動的な言論を売りにする新聞社で働いている記者スミスは、会社の方針に従わず、自分の目で見たありのままのソ連の姿を伝えようとします。しかし、彼の書いたルポルタージュは、社主の妨害によって出版ができなくなってしまいます。さらにスミスは、職を失い、妻にも去られるなどの苦境に陥ります。それでもスミスは志を曲げず、「まったく幸福なことに、ハーストのアメリカに身を置くことができないとしても、彼はかならず、もう一つのアメリカ――すなわちリンカーンのアメリカ、ルーズヴェルトのアメリカに身を置くことであろう。」と最後に語ります。二つのアメリカがあり、一つから疎んじられても、もう一つのアメリカの可能性に自分は賭ける、ということをスミスは言うんですね。「二つのアメリカ」を少し言い換えると、一つは、資本主義の先進国であり、反共産主義の拠点としてマスコミが独占資本と結託して民衆を支配しているアメリカ、もう一つは民主的で進取の気象に富み、平等の社会の実現を理想としているアメリカになるでしょう。
このスミスのせりふを巨人は銘記したようで、『歴史の総合者として』に収録した二つの文章で言及しています。一つは、ゲオルギウ『二十五時』という反共色の濃い現代小説の観念性を徹底的に暴いた「寓話風=牧歌的な様式の秘密」という長編評論において(133ページ)、もう一つは、「アグネス・スメドレー著、高杉一郎訳『中国の歌ごえ』」(233ページ)においてです。後者において、巨人は、中国の特派員として抗日戦争と革命運動との実像を見届けたスメドレーを「『リンカーンのアメリカ、ルーズヴェルトのアメリカ』に属する一人である」と位置づけています。アメリカを一つの国として簡単にとらえず、否定的な部分と肯定的な部分との両方を見てきちんと評価していく、という発想は、『神聖喜劇』の東堂太郎にも見られるものです。当たり前と言えば当たり前の態度ですが、ともすれば人は、国と国との対立で国際情勢を考えがちです。ナショナリズム的な思考に知らない内に染まってしまっている。それではいけないので、一つのものの中の対立・葛藤を見て、肯定的なものを生かして高次の発展を目指すことを考えなければいけません。弁証法的な意識というものを大西巨人は創作方法として常に保持していたと思われます。「リンカーンのアメリカ、ルーズヴェルトのアメリカ」という文言への注目は、弁証法的な意識の持続の一つの現われと言えます。
巨人は、かっこいい話、すなわち抵抗の文学、革命の文学を紹介するだけでなく、自身で書くことも志していました。しかし、置かれた環境が異なります。ドイツに侵略されたフランスやチェコ、あるいは植民地として支配されているアルジェリアではなく、巨人が所属するのは、ファシズム体制の一翼を担った日本でした。自由を抑圧していた国の一員が簡単に解放の文学を書くことはできません。書こうとするならば、過去を真摯に反省し、自分の力で止めることができなかった暴政が生まれたゆえんを徹底的に解明することから始めなければならない。決意表明である「歴史の縮図」で巨人は二つの具体的な目標を掲げています。一つは、「反動的・ブルジョア的・ファッショ的文化=文学の危険と頽廃との戦いとそれの克服」です。ファシズム体制は、敗戦によってひとまず占領軍の手で解体されるわけですが、主体的に成し遂げられた変革ではないだけに、反動的な言説が常に息を吹き返す危険性がある。そのような言説とたたかっていかなければならない。もう一つは、「日本文学=文化を世界的規模にまで、真の近代の精神に立脚した場所にまで展開しようと思うこと」です。世界文学としての日本文学を自分が書く、ということですね。当時の文学者は、西洋の小説をお手本として強く意識していましたが、それと肩を並べる、あるいは超えることを本気で考えていた人は少なかったと思いますが、巨人は真面目に考えていたんですね。ちなみに、この時の巨人は、まだ一編の小説も発表していません(笑)。
二つの目標のうち、前者は、後者の前提になります。あるいは前者を遂行することが後者の創作を体現していくことになります。敗戦後の巨人にとって、絶えず再帰的に現われる反動的あるいは反共的な言説を丹念に掘り起こし、それを批判する手続きは、日本において革命の文学を実現していくために必要なものでした。また、それは敵対する陣営に対してだけではなく、巨人が関わった民主主義文学運動の内部においても行われなければなりませんでした。「二つの日本」のうち、可能性の日本によって反動性の日本を撃つ作業に巨人は敗戦直後から取り組んでいきます。
時間がないので詳しい説明は省きますが、反動的な言説を対象化し、理想的なマルクス主義の言説によって批判して、可能性の日本を見出すために、あるいは生成させるための道筋として、批評活動が必要とされたという事情があったのではないかと考えています。1950年前後、小説を書くことを目指しながら、なかなか書けず、結果的には批評が書かれている。しかし、それは代替の行為ではなく、新しい小説言説を生み出すための跳躍台の役割を果たすものでした。あるべき小説を書くための必然的な迂回路として批評があった、とも言えるでしょう。
二つのものの対決は、一国の中においてだけでなく、一人の人間の中においても行われる必要のあるものです。ニヒリズムの極限にまで追いつめられた、あるいは自己を追いつめた水村宏紀を描いた『精神の氷点』は、負の自分を対象化する試みでした。『精神の氷点』を発表第一作の小説として選んだ巨人の意識の内には、容赦ない自己剔抉がなければ革命の文学はありえない、という直感があったのだろうと思います。かっこいいせりふが出てくるかっこいい抵抗の文学、革命の文学は、海外で生み出されており、読むことができる。しかし、日本でそれを実現するためには同じやり方では駄目で、足元を見つめる作業から始めて、絶えず自らと社会とを問い続ける遠回りをしていかなければならなかった。『神聖喜劇』は、意識的な遠回りの積み重ねの上に構築された作品です。
『神聖喜劇』には決めのせりふがたくさん出てきます。一つだけ選ぶのは難しいですが、「第八部 永劫の章」の「模擬死刑の午後」における冬木二等兵の表明は、代表的なものでしょう。新兵の過ちを大げさに取り立て、死刑に処すると脅して慰み物にする上官たちのいじめに、東堂と冬木とが「人のいのちを玩具にするのは、止めて下さい」と抗議の声を上げる。その際、上官から「人のいのち」が大切だというお前は、戦場で銃を持たされた時にどうするのかと問われます。それに対して、冬木は、「上向けて、天向けて、そりゃ、撃たれます」と答えます。冬木の言葉は、武器を敵にも味方にも使用しないという、非暴力の思想の宣言です。冬木の表明は、巨人が推奨した抵抗の文学、革命の文学の到達のさらに先を示したもので、『神聖喜劇』の世界文学としての水準の高さは、例えばそこに求めることができるのではないでしょうか。「上向けて、天向けて、そりゃ、撃たれます」という言葉が生み出されるために、東堂たち新兵たち、いわゆる食卓末席組の地道な話の積み重ねがあり、冬木に対する東堂の根気強い働きかけがあり、東堂の内面における過去の緻密な検証作業がありました。大西巨人がたどった遠回りの道を、東堂(たち)もまた作品の中でたどっています。そして、『歴史の総合者として』も革命の文学のための必然的な迂回を体現している書物であると言えます。
今日の政治情勢は、例えば朝鮮民主主義人民共和国の脅威を過剰に煽り、国際緊張を無理に作り出そうとしています。独占資本とマスコミとが癒着したアメリカは、利益追求のためになりふり構わず他国に干渉し、同盟国の日本はただ追従するのみです。今日のアメリカには、いよいよ「リンカーンのアメリカ、ルーズヴェルトのアメリカ」が求められなければいけません。むろん、アメリカだけでなく、日本においても同様です。「安倍晋三の日本」、「保守反動の日本」ではなく、「大西巨人の日本」、「人民共和の日本」を打ち立てていかなければなりません。有志の人と「もう一つの日本」作りに取り組んでいきたいと考えていますが、そのためにはまず『歴史の総合者として』を熟読していただかなければなりません。みなさん、ぜひお買い求めください(笑)。
以上で私の話を終わります。ありがとうございました。
國分 山口先生どうもありがとうございました。非常に明確な図式を出していただき、この本の位置づけも非常にはっきりしたと思います。
-

-
考える人編集部
2002年7月創刊。“シンプルな暮らし、自分の頭で考える力”をモットーに、知の楽しみにあふれたコンテンツをお届けします。
この記事をシェアする
「大西巨人『歴史の総合者として』(幻戯書房)刊行記念トークイベント「歴史の総合者とは何か?」」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 考える人編集部
-
2002年7月創刊。“シンプルな暮らし、自分の頭で考える力”をモットーに、知の楽しみにあふれたコンテンツをお届けします。

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら