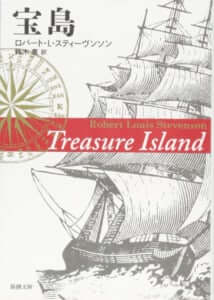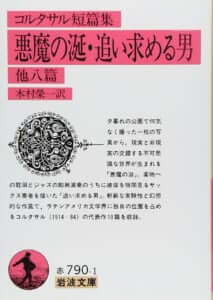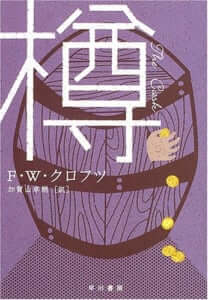2022年10月15日
岸本佐知子×津村記久子「世界文学に関するあれこれをゆる~く語ります」
後篇 「ギャツビーて誰?」から始まった
『華麗なるギャツビー』『ゴドーを待ちながら』『ボヴァリー夫人』……名前は聞いたことあるけど、実は読んだことのない名作と真っ向から向き合った津村記久子さん。時にはツッコミを入れながら、古今東西92作の物語のうまみと面白みを引き出した世界文学案内『やりなおし世界文学』の刊行を記念して、翻訳家・岸本佐知子さんと対談。後篇では作品論から作家論まで話が広がりました。二人が選んだ「Zoomイベントに一緒に出たくない作家」は誰?
(前回の記事へ)

ギャツビーとYRP野比
岸本 そもそも、この『やりなおし世界文学』の企画はどうやってはじまったんですか?
津村 毎日新聞社の「本の時間」から連載しませんか?とお話をいただいて、最初は自分が行ったことのない街のことを想像して書く、という企画で、わたしはエストニアには行ったことがないけど、調べたり想像して書いてみるという話だったんだけど、実際にやろうと思うとけっこう難しくて、それで、読んだことない本を読んで書く、というのに変えて、「ギャツビーて誰?」という仮タイトルで始まって、最終的には「やりなおし世界文学」になりました。
岸本 そんな経緯があったんですね。
津村 結局、行ったことはない土地と同じように、読んだことのない本をとりあげて、自分で行ってきて読むというスタイルになりました。『カラマーゾフの兄弟』は有名だけど、実際は読んでない人も多いし、だから研究者がその土地にずっと住んで書いている人だとしたら、わたしは旅行者みたいに、カラマーゾフに行ってきたんですけど、って土産話をしているような感覚なんです。降りたことない駅に降りるのとか、たのしいじゃないですか。
岸本 じつはいまわたし、「MONKEY」という雑誌でまさにそういう趣旨の連載をやっているんです。たとえば京急線に「YRP野比」という駅があるんですよ。「YRP」と「野比」の組み合わせの絶妙に変な感じが京急で通り過ぎるたびに気になっていて、それでついに降りてみたんです。
津村 どんなでした?
岸本 事前に検索したくなかったので、知らないままに行ったんですが、YRPとはYokosuka Research Parkの略で、ハイテク企業が集まった研究都市みたいなところだったんです。駅を降りると、まずはいかにも「野比」!って感じののどかな風景が広がっていて、それがバスに乗ってしばらく行くと、突然「YRP」部分が現れる。道のこちら側はすごくのどかな「野比」なんだけど、あちら側にはNTTとかIT系のビルがずらっと並んでいて、でも人の姿はまったく見えないという、なんともシュールなところでした。
津村 それは、すばらしい連載ですね。
岸本 このあいだは五本木というところに行ってきました。てっきり六本木の隣なのかと思っていたら、港区ではなく目黒区にある普通の住宅街で、場所もイメージも六本木とはまったくかけ離れていて、気持ち的には二本木くらいの感じでした。
津村 会社勤めをしていたときに通勤電車の終着駅が「大日」という駅で、もうこのまま降りずに大日まで行きたいと思いながら乗っていたんですけど、仕事を辞めたあとに行く機会があって、いざ行ってみたら、巨大なイオンモールと住宅地があるだけで。そう聞くとなんだと思われるかもしれないけれど、ずっと執着を持っていた場所に行くと何もなくても、やっぱりすごい充実感があるんですよね。
岸本 そうそう、何もなくても楽しい。
津村 本を読むのもそれに近いものを感じていて。だから、何かを学ぼうという気持ちはさらさらなくて、なんか行ってきたで……という気持ちで連載していました。それなので、作品によっては怒られるものもあるんじゃないか、と思っていて。
岸本 『日々の泡』なんかは、もはや神格化されている作品だけれど、読んでいてずっと辛かったと書いていらっしゃいましたよね。
津村 合う人は合うんでしょうけど、もう最初の13ページくらいで、すでにしんどかったです。部屋の家具の描写がずっと続いて、働きたくないということを全身で言っているような小説でしたね。でも最後は働くはめになるから、そういう意味でも現実感あるなあ、と思いながら読んでいました。
年齢を重ねて面白くなってくる小説
岸本 次に何を読むのか、ある程度リストがあるんですか? 今回、本の帯を書かせてもらうために事前にゲラで読ませていただいたんですが、ラファティの『九百人のお祖母さん』の回で、「もう疲れたんで、ラファティ読ませてもらってもいいですか」って編集者に聞いたというくだりがあって、そうか、津村さんはラファティを読んで癒されるのか、と面白かったのに、本ではそこの文章は削られていました。
津村 その回は2020年6月で、ウイルスのこととかもあっていろいろ疲れていた時で、慣れ親しんだおもしろいものを読みたいな、と思ってラファティにしたんですけど、ただ本では、それがいつ書かれたかは読者にわからないから、急に何を言い出すんだこの人は?と思われるかなと思って、ゲラの途中で外しました。
岸本 なるほどそうだったんだ。再読っていいですよね。
津村 年齢を重ねてから読むと、また理解力が深まっていたりするし、当時はわからなくても今読んだら、おもしろいかもよ、と言いたい気持ちはあります。ウィリアム・ギブスンの『クローム襲撃』もそうでしたけど、大学生の時は、ギブスンの小説はヤクばっかりやってるなあ、ついていけないなあ、と思いながら読んでいたんですけど、大人になると、それはそうなるよなって理解できるから、30代後半くらいからが本の読み時なのかもしれないな、という気もしています。
岸本 同時に、若くてよくわからないなりに読んでいるときのよさもありますよね。
津村 今回発見だったのはスティーヴンソンの『宝島』で、子供の頃はあんまり好きな本じゃなかったんですけど、大人になって読んだらとてもおもしろかったんです。人の心の斟酌みたいなものが実感をもって書かれていて。あと、スティーヴンソンは文章がめちゃくちゃうまい。
岸本 そういう意味では、子供向けにやさしくリライトした世界文学ってどうなんでしょうね。それで読んだ気になってしまって大人になってから読み返さないのはもったいないな、と思うことはありますよね。今回津村さんの原稿を読んで、『宝島』はわたしも改めて読んでみようと思いました。
Zoomイベントに一緒に出るとしたら……
津村 『やりなおし世界文学』でとりあげた本のなかで、岸本さんにぜひ読んでもらいたかったのがコルタサルの『悪魔の涎・追い求める男 他八篇』なんですけど、もう読まれてますか?
岸本 はい、わたしはもうコルタサル先生に一生ついていくって決めているんで(笑)。
津村 読んだ時から、これは岸本さんと話したいって思っていて。さっきの降りたことのない駅の話とも通じるんですが、「正午の島」という収録作があって、スチュワードの男性が自分の乗っている飛行機の上空から毎日正午に見える島にすごく執着していて、彼は耐えきれずに実際にその島に行ってしまうんです。隣の島から漁船をチャーターしないと行けないようなところなのに。これを読んで、岸本さんがエッセイで書かれていた塔にいく話のことを思い出して。ありましたよね?
岸本 ありましたありました(笑)。そういうあこがれって、ずっとあるんですよね。小学生の時に駅のそばの塾に通っていて、線路沿いの背の高いマンションにオレンジ色のカーテンがいつも掛かっている窓があって、そこにずっと行ってみたくてしかたなかったり、小田急線の東北沢という駅の、ホームのすぐ向こうに小さなかわいい扉のある洋裁屋さんがあって、中に入ってみたくてみたくて、どうやったら子ども一人でそこに入れるかシナリオを何通りも考えたり……。たぶん自分の手の届かないところにあるファンシーな世界へのあこがれがずっとあって、それが解消されないままに今も続いているんだと思うんです。
津村 目の前を通り過ぎていくもののなかで、気になったものの中に入ってみたいという夢がずっとあるんですよね。百万円もらえるのと、好きなビルに入り放題の券をもらえるのの、どっちをとる? と聞かれたら、わたしは絶対ビル入り放題券が欲しいです。
岸本 津村さんも入ってみたいところってあるんですか?
津村 わたしは中に入りたいのもあるんだけど、その中にいる人の気持ちをすごい想像するんです。かつて南港の埋立地にZepp大阪というライブハウスがあって、その帰り道に大阪港の近くを通るんですけど、港湾関係の仕事が多いから深夜でも煌々と明かりがついていて、あの人たちは何の仕事してるんだろうって、いつも考えていました。コルタサルの小説はそれを実現しちゃうのがすごくて、コルタサル先生とわたしたちは何も接点も共通点もないのに、見ず知らずのおじさんが自分の願望そのままみたいな小説を書いているということに驚きと羨望が入り混じる思いでした。
岸本 コルタサル先生、あらすじだけだと単なる馬鹿っ話みたいなのに、細部がエレガントですばらしい。ほんとうに尊敬しています。きっとわたしたちと気が合ったんじゃないかと恐れ多くも思ってしまいます。
津村 コルタサルのまわりには、こういう話できる友達がいたんですかね?
岸本 いや、いなかったんじゃないかな。話すとドン引きされるから、言わずにひとりで書いていたんじゃないですか。
津村 そうだとしたら、『やりなおし世界文学』に出てくる作家のなかで一緒にZoomイベントしてもよい人はコルタサルでいいですかね?
岸本 はい、それでお願いします(笑)。今回『やりなおし世界文学』を読んでいちばん読みたくなったのがクロフツの『樽』でした。この小説、まったく知らなかったんだけど、“主人公が樽そのものとも言える樽萌え小説”って、それどういうことですか?
津村 病気の療養中に書いていた小説らしいんですけど、本当に楽しそうに樽のことを書いていて、クロフツもコルタサル先生とのトークに入ってもらっても一緒に話せたんじゃないかと思うんですよね。実は、自分も気になる場所があって……と口を挟んできそうな気がする(笑)。
岸本 食い気味にね(笑)。むしろ、わたしたちは聞いていたいね。コルタサル先生とクロフツさんのトークを。
津村 ほんとですね。逆に、一緒にイベントに出たくない作家は誰ですか?
岸本 まあ、案の定と言うか、アンブロース・ビアスでしょうかね。読んでいてビアスのことが嫌いになりすぎて、会社員時代にすごく苦手だった同僚のおじさんの声と顔で脳内再現されるようになったくらい(笑)。津村さんは、だれが嫌でしたか?
津村 ぶっちぎりで、ラディゲです。性格悪すぎると思って。こんなにうまい小説を書くのに、こんなに性格が悪いことに想像力がある人、怖いですよ。『肉体の悪魔』のことを思い出すたびに、トーマス・マンの『トニオ・クレーゲル』が頭をよぎって、トニオはあんなにわかりやすいのに、なんでこの子は……って思ってました。
岸本 連載中に津村さんが本を読みながらつけていたメモを事前に見せていただいたんですけど、本を読み終わったあとすぐに原稿を書いていたんですか?
津村 メモのとり方もやりながら変わっていったんですけど、たいてい2、3日、長くて1週間くらいでまず読んで、そこから週末を挟んで原稿を書き始めることが多かったような気がします。
岸本 わたし、津村さんの小説も大好きなんですけど、『やりなおし世界文学』の文章がほんとうにかっこよくて、こうした所感の表現はどのようにして生まれるんだろうとすごく知りたかった。たとえば、ウィラ・キャザーの『マイ・アントニーア』の「神話的なほどの力強さ」という表現に思わず線を引いたんですが、見せていただいたメモにはその言葉はなかった。となると、原稿を書いている段階でそういう表現が生まれてくるということ?
津村 『マイ・アントニーア』はもう、この小説のなかで生きている人たちの人生が壮絶なんですよね。まったく知らないネブラスカの移民の人たちの生きている姿がほとんどおとぎ話みたいで、すごい力があって、それに圧倒されながら書いていたのもあるんだと思います。
岸本 メモを読み返しながら原稿を書く?
津村 メモのここを書こうというところに印をつけて、それを並べていきながら、これで記事にできるかなと考えて流れをつくっていく感じでしたね。だから、メモは内容のインデックスであると同時に、読んでいるときの感情のインデックスでもあるんです。カフカの『城』なんて、ただただ仕事が終わらない、という小説だとも言えるじゃないですか。岸本さんも会社勤めをされていたからわかると思うんですけど、たらい回しにされ続けて、なにをやっても怒られる、みたいな状況ってあるじゃないですか。その仕事のリアリティがすごいあるな、と思いながら読んでいました。
岸本 “出向先で勝手がわからない小説”って書かれていましたよね(笑)。あの回もすごく力が入っていました。しかも『城』は未完だという……。
津村 サイゼリヤで読んでいたんですけど、『城』があまりに長すぎて、最後にレジの人に長居しすぎてすみません、ってあやまりました(笑)。
岸本 そういえば、『百年の孤独』を読もうとは思わなかったんですか?
津村 あまりに分厚すぎたり、あまりに多くの人が読んでいる本は、もう誰かに聞いたらいいやん、と思ってしまうところがあって。
岸本 わかります。わたしもその感覚がすごく強いから、古典をあまり読まずにきてしまったところがあります。みんな読んでいるから、もういいやって。
津村 その姿勢が、岸本さんの『「罪と罰」を読まない』(三浦しをん、吉田篤弘、吉田浩美各氏との共著)につながっているんだと思うんですけど、ほんとは読む以前にその本について想像しているだけで、もう充分おもしろいんですよね。
岸本 そう、だから想像をすること自体がもう読書の一部だと言ってもいいんじゃないか、という暴論をつい吐きたくなってしまうんです(笑)。
津村 きっと、コルタサル先生は理解してくれると思いますよ。
(おわり)
(協力:本屋B&B、構成:加藤木礼)

津村記久子『やりなおし世界文学』(新潮社)
-

-
津村記久子
1978(昭和53)年大阪市生まれ。2005(平成17)年「マンイーター」(のちに『君は永遠にそいつらより若い』に改題)で太宰治賞を受賞してデビュー。2008年『ミュージック・ブレス・ユー!!』で野間文芸新人賞、2009年「ポトスライムの舟」で芥川賞、2011年『ワーカーズ・ダイジェスト』で織田作之助賞、2013年「給水塔と亀」で川端康成文学賞、2016年『この世にたやすい仕事はない』で芸術選奨新人賞、2017年『浮遊霊ブラジル』で紫式部文学賞を受賞。他の作品に『アレグリアとは仕事はできない』『カソウスキの行方』『八番筋カウンシル』『まともな家の子供はいない』『エヴリシング・フロウズ』『ディス・イズ・ザ・デイ』『やりなおし世界文学』など。
-

-
岸本佐知子
翻訳家。訳書にルシア・ベルリン『掃除婦のための手引き書 』『すべての月、すべての年』、リディア・デイヴィス『話の終わり』『ほとんど記憶のない女』、ミランダ・ジュライ『最初の悪い男』、スティーブン・ミルハウザー『エドウィン・マルハウス』、ジャネット・ウィンターソン『灯台守の話』、ジョージ・ソーンダーズ『短くて恐ろしいフィルの時代』『十二月の十日』など多数。編訳書に『変愛小説集』『楽しい夜』『居心地の悪い部屋』ほか、著書に『なんらかの事情』ほか。2007年、『ねにもつタイプ』で講談社エッセイ賞を受賞。
この記事をシェアする
「岸本佐知子×津村記久子「世界文学に関するあれこれをゆる~く語ります」」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 津村記久子
-
1978(昭和53)年大阪市生まれ。2005(平成17)年「マンイーター」(のちに『君は永遠にそいつらより若い』に改題)で太宰治賞を受賞してデビュー。2008年『ミュージック・ブレス・ユー!!』で野間文芸新人賞、2009年「ポトスライムの舟」で芥川賞、2011年『ワーカーズ・ダイジェスト』で織田作之助賞、2013年「給水塔と亀」で川端康成文学賞、2016年『この世にたやすい仕事はない』で芸術選奨新人賞、2017年『浮遊霊ブラジル』で紫式部文学賞を受賞。他の作品に『アレグリアとは仕事はできない』『カソウスキの行方』『八番筋カウンシル』『まともな家の子供はいない』『エヴリシング・フロウズ』『ディス・イズ・ザ・デイ』『やりなおし世界文学』など。
連載一覧
対談・インタビュー一覧
著者の本
-

- 岸本佐知子
-
翻訳家。訳書にルシア・ベルリン『掃除婦のための手引き書 』『すべての月、すべての年』、リディア・デイヴィス『話の終わり』『ほとんど記憶のない女』、ミランダ・ジュライ『最初の悪い男』、スティーブン・ミルハウザー『エドウィン・マルハウス』、ジャネット・ウィンターソン『灯台守の話』、ジョージ・ソーンダーズ『短くて恐ろしいフィルの時代』『十二月の十日』など多数。編訳書に『変愛小説集』『楽しい夜』『居心地の悪い部屋』ほか、著書に『なんらかの事情』ほか。2007年、『ねにもつタイプ』で講談社エッセイ賞を受賞。

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら