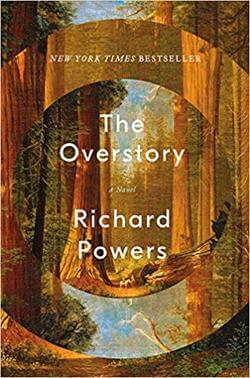(2)木の讃歌――リチャード・パワーズの新作
The Overstory by Richard Powers
著者: 柴田元幸
柴田元幸です。この場では主として海外文学について、新しく読んだ本や仕入れた情報などを紹介していきます。で、なぜ「亀」かとゆうと、MONKEYなぞという雑誌の責任編集を務めてはいるものの、前世は亀だったと確信しているからです。
誰も聞いたことのない音楽を作ろうとした男の話である前作『オルフェオ』(2014、邦訳新潮社)が素晴らしかったので、もちろん本格的でない作品など一冊もない作家ではあるけれど、やはりリチャード・パワーズの代表作となると、バッハの『ゴルトベルク変奏曲』とポーの「黄金虫」を霊感源に進化の問題を考えた『黄金虫変奏曲』(The Gold Bug Variations, 1991; 未訳)、歌の絆で結ばれたユダヤ人の父と黒人の母を持つ家族をめぐる『われらが歌う時』(2003、新潮社)、そして『オルフェオ』という「音楽小説群」ではないか、と2014年の段階では思ったものだった。が、今年出たThe Overstory(W. W. Norton)を読んで、いやいやそう簡単に決めつけてはいけない、と思い直した。
「オーバーストーリー」とは森の一番高い層を形成する木々のこと。むろんそこはパワーズだから、それだけではなく、あらゆる物語の上に立つ物語、いわば「超物語」(over-story)という意味も込めていることは間違いないが、この小説、まずは本当に木の話である。切られた木材(wood)の話ではなく、あるいは文明と対比されて癒しを提供したり魔が棲んでいたりする場でありつづけてきた森(woods)の話でもそれほどなく、何よりも一本一本の木(tree)の話。いや、「一本一本の」と言ってしまうと、中身を歪めてしまう。木と木がつながって、いわば個を超えたより大きな個を形成しているという認識が、この小説が差し出している叡智の一環だからだ。
小説は元々、小さな個(たとえば個人)の都合と、大きな個(たとえば社会)の都合との対立と和解(あるいは破綻)を主要なテーマとしてきた。社会の都合に合わせられなかったためにアンナ・カレーニナは破滅し、首尾よく合わせられたデイヴィッド・コパフィールドは幸福な晩年を迎えた。だがパワーズはデビュー作『舞踏会へ向かう三人の農夫』(1985、河出文庫)以来、一貫して対立よりも関係に重きを置いてきた。より小さな個が結び合わさってより大きな個が作られる仕組み、あるいはより大きな個からより小さな個が産出される仕組みを、写真、音楽、遺伝子、戦争、経済等々をモチーフに、意表をつくアナロジーと愉快な言語的曲芸に満ちた文章を通してパワーズは考察してきた。今回の、500ページを超える、訳すと原稿用紙1500枚くらい行きそうな新作では探求の場を木々に求め、木々同士のつながり、さらには木々同士が交わすコミュニケーションに焦点を当て、そこから世界全体のありよう――特に世界のなかでの人間の位置――を考えようとしているのである。
日本の本でいえば奥付にあたるコピーライトページの一番上には、こう書かれている。
The Overstory is printed on 100 percent recycled paper. By using recycled paper in place of paper made with 100 percent virgin fiber, the first printing has saved:
408 trees
393,576 gallons of water
132,288 pounds of greenhouse gas emissions
40,272 pounds of solid waste
Totals quantified using the Eco-Calculator at https://rollandinc.com/.
『オーバーストーリー』は100%再生紙で印刷されています。100%バージンパルプの代わりに100%再生紙を使うことで、初版では以下の量が節約されました:
木 408本
水 1,489,847リットル
温暖化ガス放出 60,005キロ
固形廃棄物 18,267キロ
計算値はhttps://rollandinc.com/のEco-Calculator(エコ計算機)による
これを引用するのは、実はあまり得策でないかもしれない。具体的な数字が並んでわかりやすくはあるが、だからこそかえって、読む人が環境保護主義の独善のようなものを予想しかねないからだ(僕だったらする)。だが、本文が始まると、環境保護主義的な考えが打ち出されるとしても、それはつねに、特定の文脈のなかで生きる個人の発言・意見として提示され、一定の説得力が与えられてはいても、作品・作者が露骨にそれを是認するような印象はない。パワーズは元々、小説を通して読者に「教える」ことを恐れない作家だが、教える手段はあくまで、データを提示することではなく、物語を語ること、誘惑的な文章で読者を魅了することである。
The redwoods knock all words out of them. Nick drives in silence. Even the young trunks are like angels. And when, after a few miles, they pass a monster, sprouting a first upward-swooping branch forty feet in the air, as thick as most eastern trees, he knows: the word tree must grow up, get real. It’s not the size that throws him, or not just the size. It’s the grooved, Doric perfection of the red-brown columns, shooting upward from the shoulder-high ferns and moss-swarmed floor—straight up, with no taper, like a russet, leathery apotheosis. And when the columns do start to crown, it happens so high, so removed from the pillars’ base, that it might as well be a second world up there, up nearer eternity.
セコイアを前にして二人は言葉を失う。ニックは黙って運転を続ける。若い幹ですら天使のようだ。そして、何キロか走った時点で、二人は怪物の前を通り過ぎる。垂直に空中12メートルまで突き出ている第一枝は、東部のたいていの木ぐらい太い。それを見てニックは知る――「木」という言葉じゃ足りない、言葉が成長しなきゃいけない、本気になってくれなきゃ困る。彼が仰天するのは大きさではない。大きさだけではない。赤茶色の円柱の、溝が刻まれたドーリス様式の完璧さ、それが肩の高さのシダや苔に覆われた地面からまっすぐ上に突き出ている姿。一直線の、先細りもない、小豆色の革のごとくしなやかな、神への変容。円柱がついに冠に達するとき、それはあまりに高い、柱の土台からあまりに離れた所で起きるので、もうそこは第二の、永遠により近い別の世界みたいなものだ。(The Overstory第二部“Trunk”〔幹〕から)
『オーバーストーリー』はこうした、木をめぐる印象的な描写に満ちている。とはいえパワーズは、物語を木の視点から語ったり、木の「考え」を言語化したりすることは決してしない。木の擬人化は徹底して避けている(この小説を読みながら、谷崎由依の新作『鏡のなかのアジア』〔集英社〕に収められた傑作中篇「天蓋歩行」を何度か思い起こした――こっちは木が人に変身する話で、文字どおりの擬人化であり、『オーバーストーリー』とは正反対だが、どちらも伝統的な、人が木に変わる変身譚や、木に人間的感情を読み込むロマン主義から新鮮に逸脱している点で共通の魅力がある)。パワーズはあくまで、木と深く関わる何人かの物語を並行して語るのである。で、その何人かの部分的紹介を試みると――
クリ胴枯病の流行(20世紀前半に実際に起きて、アメリカ中のクリをほぼ絶滅させた)にもかかわらず一本だけ生きつづけたクリの木を庭に持つ家系の子孫。
ミミ・マ(Mimi Ma)
賢者を描いた不思議な絵を携えて中国からアメリカに渡ってきた父親を持つ女性。
アダム・アピッチ(Adam Appich)
環境保護運動に携わる人々の精神的傾向を研究テーマに選んだ心理学者の卵。
レイ・ブリンクマンとドロシー・キャゼイリー(Ray Brinkman and Dorothy Cazaly)
冷えきった夫婦関係が夫の卒中を契機に、木を通して劇的に変化する夫婦。
ダグラス・パヴリチェク(Douglas Pavlicek)
帰還兵。非人間的な心理学実験の被験者にされた経験などを経て、木の魅力を発見する。
ニーレイ・メータ(Neelay Mehta)
子供のとき木から落ちて車椅子生活となるが、現実世界に限りなく近いきわめて複雑なゲームを発明してゲーム業界の花形になる。
パトリシア・ウェスタフォード(Patricia Westerford)
聞く・喋ることに障害があるが早くから木に親しみ、木と木がコミュニケートしていることを研究者として実証する。
オリヴィア・ヴァンダグリフ(Olivia Vandergriff)
感電死したのち蘇り、木の声(のようなもの)を聞くようになってカリスマ的魅力を獲得する。
――このうち何人かは、紆余曲折を経て環境保護グループに加わり、やがてグループは先鋭化して過激な運動を展開するに至る。作者は彼らのエコテロリズム的行為を支持しているわけではないが、さりとて彼らの愚かしさを糾弾しているわけでもない。成り行きによって、誰も本当に望んだのではない方向に事態が否応なしに進んでいく流れが説得力をもって描かれ、このあたりは小説的に見事である。
パトリシア・ウェスタフォードだけははっきりモデルがいる。ドイツ語原書が2015年に刊行された『樹木たちの知られざる生活』(早川書房)の著者ペーター・ヴォールレーベンである(もっとも、研究の成果を年長の男性学者たちに嘲笑され、一時は学界から追放同然となるも、やがて若い学者たちに「再発見」されるというドラマはパトリシア独自のものである)。
何年か前スタンフォードで教えていたときに、コンピュータ産業のメッカの只中で巨大なセコイアの木に出会って衝撃を受けたパワーズは、人間を中心に世界を考える姿勢から抜け出る必要性を感じたとインタビューで述べている(たとえばhttps://www.theguardian.com/books/2018/jun/16/richard-powers-interview-overstory)。その意味で、この本はひとつの大きな変化を示していると言えるかもしれない。が、木と木の空間的・時間的つながりをコミュニケーションの問題として捉える姿勢は、いままでのパワーズの思考の一番刺激的な部分とつながっている。たとえば1991年刊の『黄金虫変奏曲』のなかの次のような一節は、『オーバーストーリー』のどこかにあってもおかしくない。
Now I find that evolution is not about competition or squeezing out, not a master plan of increasing efficiency. It is a deluge, a cascade of mistaken, tentative, branching, brocaded experiment, secrets seemingly dormant, shouted down from the past, wills and depositions hidden in the attic, how-to treasure maps reading “Tried this; it worked for a while; hang on to it,” program-palimpsests reworked beyond recognition, churches renovated so often in a procession of styles that it’s impossible to label them Romanesque, gothic, or baroque. It is about one instruction: “Make another similar something; insert this command; run; repeat.” It is about the resultant runaway seed-spreading arabesques, unrelated except in all being variations on that theme.
いまの私にはわかる。進化とは、競争とか敵を追い出すとかいう問題ではなく、どんどん効率を上げていくためのマスタープランでもない。それは洪水であり、滝である。誤った、仮の、枝分かれする、ブロケード状に錯綜した実験や、過去から叫ばれた一見眠っているように見える秘密や、屋根裏に隠された遺書や預託証券や、「これを試した。しばらくはうまく行った。捨てずに持っているべし」と書かれた宝の地図ハウツー版や、それとわからぬほど徹底的に作り直されたプログラム兼重ね書き文書や、次々違ったスタイルで再三されたものだからロマネスクともゴシックともバロックとも呼びがたい教会等々から成る怒濤である。肝腎なのはひとつの指示だ――「もうひとつこれと似た何かを作れ。このコマンドを挿入せよ。実行せよ。リピートせよ」。肝要なのはその結果生じる、暴走する、種子を散布するいくつものアラベスクであり、それらが唯一たがいに関連しているのは、どれもその主題の変奏曲だということだけだ。(The Gold Bug Variations, XII, “The National Kingdom”〔自然の王国〕から)
ここでは「暴走」「変化」の創造性が謳い上げられ、「変奏」の重要性が説かれていて、たしかにその点は『オーバーストーリー』の木にあってはそこまで顕著ではないだろう。だがパワーズは代わりに、木というものの、想像を絶する気の長さをたびたび強調している。悠久の時間のなかで、いずれ世界は木の根気強さに屈するのではないか……そういう畏怖の念に近いものがこの小説を貫いている。むろん気になるのは、現在アメリカをはじめ世界各地で進行している、目先の効率を重視した伐採や森林破壊(これについては作品はいかなる賛意も示していない)にも木は耐えられるのか?という現実的問いだろうが、この問いに答えるのは小説の役割ではあるまい。それに関しては、祈りのようなものが聞こえてくるのみであっても、この小説に共感する理由にこそなれ、責める理由にはならないだろう。
最新情報
エドワード・ゴーリー『失敬な招喚』(河出書房新社)が刊行されました。ポール・オースター『インヴィジブル』(新潮社)は9月27日に発売予定。9月29日(土)、30日(日)には世田谷美術館にて朗読劇『銀河鉄道の夜』に出演します(満席・当日立見席若干あり)。
-

-
柴田元幸
1954年生まれ。翻訳家。文芸誌『MONKEY』編集長。『生半可な學者』で講談社 エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。2017年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。
この記事をシェアする
「亀のみぞ知る―海外文学定期便―」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 柴田元幸
-
1954年生まれ。翻訳家。文芸誌『MONKEY』編集長。『生半可な學者』で講談社 エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。2017年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。
連載一覧
対談・インタビュー一覧

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら