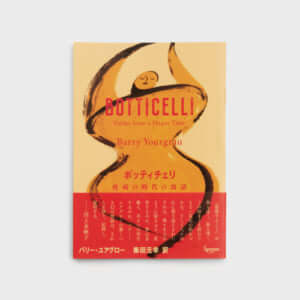(番外篇その1)バリー・ユアグロー、『ボッティチェリ 疫病の時代の寓話』を語る
Barry Yourgrau on the Story Behind His Pandemic Collection Botticelli
著者: バリー・ユアグロー , 柴田元幸
『一人の男が飛行機から飛び降りる』などで知られる、アメリカの作家バリー・ユアグローさん。日本では柴田元幸さんの翻訳で親しまれています。
バリー・ユアグローさんは、ニューヨークがロックダウンされている間、正気を保つために掌編小説を書き、柴田さん宛てに一篇ずつ送っていました。
目の前で起こっている事実そのままではなく、寓話というかたちを借り、何かにすがるようにして書かれた12篇の物語が、英語圏に先んじて、2020年5月に日本の ignition gallery から『ボッティチェリ 疫病の時代の寓話』として発売。44ページの小さな本は評判を呼んで、現在4刷にまでなっています。
『ボッティチェリ 疫病の時代の寓話』が生まれた背景、そしてなぜNYで生まれたこの掌編小説が、とりわけ日本の読者の心をつかんだのか――バリー・ユアグローさん本人がLITERARY HUBに寄稿した文章を、柴田元幸さんの訳でお届けします。
それから、寒さに唇も青ざめた女が〔……〕私の耳許でささやいた(私たちはそこでは皆ささやいていたのだ)――
「あなた、これを言葉にできます?」
私は答えた。「できます!」――アンナ・アフマトーヴァ
私はシュールな色合いの超短篇を専門とする作家である。四月以来、ロックダウンされたニューヨークで、窓の外ではサイレンが鳴り響くなか、寓話のような物語を書いては、トラウマのただなかにある都市からの心の緊急レポートとして、東京に住む、長年私の作品を邦訳してくれている柴田元幸に送るようになった。さっそく小冊子にまとめられたこれらのレポートは、世界の反対側にいる人たちの心の琴線に触れたように思える。
誰もが知るとおり、ニューヨークはこの春、コロナウイルスの世界的中心地となった。私が住んでいる、人種的に多様なジャクソン・ハイツと、その周囲の、人口密度は高く収入は低いクイーンズ一帯は、その中心地の中心地だった。私の住まいからわずか六ブロック、歩いて十数分のところにある、長年気楽に利用してきたエルムハースト病院は、ニューヨークに広がっている地獄絵の代表として世界中に知られるに至った。検査を受けようと、雨でびしょ濡れの姿で病院前に群がる人々。待機中の、死体運搬用冷凍トラック。ぎっしり人で一杯の病院の廊下。ニューヨークは三月後半ロックダウンに入り、生活は一転して、一瞬も安らがぬ、激しい恐怖に包まれた閉鎖状態に陥った。霊界のような街路。突然、必死の形相でマスクを着用しはじめた人々(マスク、どこで手に入れたのか?)。混乱した、というかほとんど存在しない地域安全ガイドライン。加えてホワイトハウスの、啞然とさせられる無関心と狂気。何もかもが不足していた――検査、消毒薬、食料品。
街全体に広がるトラウマが、私個人のトラウマを呼び覚ました。病状が呼吸器系であるせいで、肺ガンで死にかけた母が、息をしようと空しく喘ぐのを私自身なすすべもなく見守ったときの記憶がよみがえった。人はコロナによってそういうふうに死んでいく――ただし、つねに一人で。何日かのあいだ、私は妙な風邪をひいていた。本当に「風邪」だろうか? 息が切れて、胸に痛みがあった。心配に身を焼かれる思いで何晩かを過ごした。
サイレンは二十四時間ずっと、方々からエルムハースト病院に集まっていった。ブルックリンで緊急治療室に勤務する友人がフェイスブックに投稿した文章を私は読んだ。ウイルスで死に瀕した年配の女性のそばに友人が自分のスマホを立てかけて、必死に訴えてくる息子が、意識もなく横たわる母親に向かって、涙ながらに別れの祈りの言葉を送れるようにしたという話が、短い、胸を刺す文章で綴られていた。私はそれを読んで、コンピュータの画面を前にして泣いた。
ボストン近郊に住む、私の双子の片割れの義理の父親も、病に屈した。ケアテイカーの親切さ、優しさのおかげで、家族はフェイスタイムを使って別れを告げることができた。私はまた泣いた。
何もかもが耐えがたかった。世界は終わろうとしている。苦悩に包まれた私は、感染率、死者数、防護具の不足を報じるニュースを遮断し、ツイッターを遮断し、ホワイトハウスが垂れ流す破壊的な噓とたわごとを遮断した。
その沈黙の中から、最初の物語が飛び出してきた。街なかではモクレンが満開だった。マスクと手袋で武装したロックダウンの散歩に私は日々出かけ、甘美なピンクと白の花の前を通り過ぎながら、心も頭も恐怖と不安で真っ暗だった。このグロテスクな不調和から突然、荒々しいインスピレーションが訪れたのである――すべてを裏返すのだ。病に罹った者が、病が重くなればなるほど魅惑的な美しさで包まれる、そういう病気に仕立て直す(あとで気づいたことだが、これはポーの「赤死病の仮面」の世界を襲うのと反対の運命だ)。「集中治療室では美人コンテストが行なわれた」と私は書いた。醜さこそが誇り高き健康のしるしとなった。私はその病を、そしてその物語を「ボッティチェリ」と名づけた。
以前からよくそうしているように、私は書いたものをすぐさま、東京にいる柴田元幸に送った。「正気を保つため」に書いた、と書きそえた。村上春樹の知人で仕事仲間のモトは、たぶん日本で一番傑出した現代アメリカ文学翻訳者だ。私の本もずっと前から訳してくれていて、中には日本だけで出たものもある。モトはただちに「ボッティチェリ」を訳し、翌日ラジオで朗読した。もっと送れ、と彼は言ってきた。
「いま僕たちは、ものすごく奇妙な文脈の中にいる」とモトは書いていた。「文学的な価値に加えて、何か別のものが、読者に対して奇跡のようにはたらきかけることもありうる」
こうして、ほとんど毎日のレポートのように、物語があふれ出てきた。ウイルスが猛威をふるい、ニューヨークのロックダウンが延長されるなか、四月から五月にかけての二週間、さらに十一本の物語が生まれた。私としても、トラウマについて書くのは初めてではない。両親の死について、辛い失恋についていままでも書いてきた。でも、経験のただなかで書いたことはない。今回も、事実を直接書く気はなかった(もともと私はそういうふうには書かない)。生々しい実感は欲しかったが、ある種、詩的な隔たりも必要だった。「ボッティチェリ」のように寓話的に語って、寓話が与えてくれる無垢と、闇と、カフカ的な不運を取り込むのだ。パンデミックの途方もないスケールゆえに、一種フォークロア的な声を私は求めた。古くから使われてきた響きのある“plague”(疫病)という言葉を私は用いた。「コロナウイルス」「コーヴィッド」といった言い方はいっさい使わなかった。
二番目の物語は、街を駆け抜けていく救急車を扱っている。救急車の姿はひどく恐ろしくもあり、かつ不思議と慰められもした。サイレンによってはその音が不気味に、ほとんど海のような響きで脈打つ。私は救急車を鯨として思い描いた。その広々とした背中に病人を乗せて運搬すべく海から連れてこられた、頭に赤いランプを縛りつけられた、大きな、厳めしく英雄的な優しい生き物。疲れはてて、息絶えるまで彼らは働いてくれる。「知恵も言葉もない自然が、無責任で無力な、苦しむ人間たちを精いっぱい助けてくれている」と私は書いた。むろん私は看護師、医師、ケアテイカーの人々のことも考えていた。
買い物からまたひとつレポートが生まれもした。ある時点では、ジャクソン・ハイツで営業しているスーパーマーケットはほんの一握りだった。小さな食料雑貨店すら閉まっていた。ガールフレンドとともに敢行した、初めての、不安に満ちたスーパーマーケット行きは惨憺たる結果に終わった。性急に店内に二人で入ることで、自分たちを危険にさらした疚しさを抱えて私は帰宅した。ガールフレンドはもともと、まだ早すぎると反対したのだ。それまで買い物はすべて彼女が一人で担当していた。一人でなら安全の確保もやり方がわかっている。でも二人で行くと彼女は半狂乱になった。そして私は、小さな女の子がパニックと恐怖に打ちのめされて路上に座り込んでいるところに出会う話を書いた。慰めようもない――女の子は影をなくしたのだ(あとで、アンデルセンにも影をなくす話があることを私は知った)。私は女の子を励まそうとするが、彼女の状態がどれほど危険かも私は知っている。どうやって助けてあげられるのか、私にはわからない。
いまになって気づくが、私は深い涙がもたらす解放感を始動させるために、いろんなイメージやつながりを呼び寄せていたのだ。人々を失い世界を失い、悲しみと恐怖に包まれ、混乱に覆いつくされるなかで、そういうものが私には必要だった。量販文具店で買ったボールペンで組み立てた幻を前に涙することで、私は精いっぱいパンデミックに対処しようとしていたのだ。テレビで放映されつづける耐えがたいビデオを止めるよう当局に訴える話を私は書いた。ビデオはくり返し、単純素朴な家族のピクニックの情景を映し出す――かつてやっていたとおり、マスクもせず手袋もせず、皿が回され、カップに飲み物が注がれ、みんなで毛布に座って一緒に歌を歌っている。感染した都市から逃走途中に溺れ死んだ老人について私は書いた。彼につつましく仕える幽霊が私の夢に現われ、帰れと私に言われるまで夢をかき乱す(これが私の姉の義父が亡くなったときや、ずっと前に私自身の父が亡くなったときの記憶につながっていることがいまはわかる)。健康維持のために、鏡をめぐる訳のわからない条例が出される話を私は書いた。安全な丘の上の村で、みんなが無邪気に凧代わりに雲を上げ、眼下の、閉鎖された陰惨な町を見下ろす話を書いた。最後の方では、笑いすら狙うようになった(私はもともとコミカルな書き手なのだ)。十八世紀に書かれた、監禁された日々をめぐるメモワール『わが部屋の旅』に着想を得て、私自身のロックダウンされた仕事部屋を舞台とする散々な旅を書いたのだ。
私が一番ヒントを求めた本は、カミュでもボッカチオでもデフォーでもなかった。それは、1972年にソ連のストルガツキー兄弟が書いたSF小説『路傍のピクニック』である。エイリアンが訪れ、残骸が散らばった恐ろしいエリア「ゾーン」では物理の法則も無茶苦茶に狂ってしまっている。タルコフスキーの映画『ストーカー』はこれに緩く基づいている。脚本もストルガツキー兄弟が書き、SF的要素をすべて取り除いてタルコフスキーを喜ばせたが、ゾーンのような場は残っている。
『ストーカー』(ストルガツキー兄弟は「スタルカー」と発音する)という映画は、心酔する人もいるし(たとえばジェフ・ダイヤー)、死ぬほど退屈する人もいる(たとえば私)。『路傍のピクニック』はハードコアSFならではの不気味さがあって、私は前々からこの原作に惹かれてきた。そしていま、自分たちがまさにこの小説の「ゾーン」に閉じ込められていることを私は感じた。孤立した、私たちの住むクイーンズの界隈が「ゾーン」だ。いかなる悪意の運命によってか、この惑星で最悪の感染地帯は、もうとっくに武漢などではなく、いまやこの一か所に縮んでいる――いま私たちがいるところに。
『路傍のピクニック』へのオマージュとして、誰もその恐ろしさを知らない致死的な輝きを帯びた、異星からの人工物をめぐる小さな物語を私は作った。ストルガツキー兄弟が描く、放置された「ゾーン」のガレージの薄闇に光る、異星から来た悪意ある蜘蛛の巣をイメージしたのだ。私のバージョンでは「ゾーン」は山奥のジャングルだ。だが私の物語は一種の前奏曲であり、それが終わった時点から本当の物語が始まる。まさに「ストーカー」的な、残骸を漁って回る密猟人が、ジャングルの奥でそのピカピカの人工物を盗み出す――彼を待つ、そして世界を待つ恐ろしい事態もつゆ知らずに。その「ストーカー」的人物は私だ〔この作品「スプーン」は番外編その2として全文掲載〕。
英語圏では未発表のこれらの短篇を、日本で五月末に緊急出版すべくモト・シバタが手はずを整えてくれた。日本からの郵便が復活すると、私は片手に、我々が『ボッティチェリ 疫病の時代の寓話』と名づけた葉書大の冊子を持っていた。日本ではいみじくも、超短篇を「掌の小説」と呼ぶ。いまでは赤い帯も付いたこの小さな本は、わがマスクのコレクションや手指消毒剤ピュレルの壜に交じって棚に収まっている。表紙に横山雄がフリーハンドで描いてくれた女性は、寝床に入っているようであり踊っているようでもある。裏表紙には、マティスが作った微生物のカットアウトのごときものが浮かんでいる。その表紙と裏表紙とのあいだで、私が苦しみを切り抜けるよすがとなってくれた、現実を変容させた言葉たちが、私には理解できない日本語へと変容している。美しい、異国の物体――と同時に、私の心底親密なお守り。
出版元のignition galleryは、アマゾンを避けているインディーのアート組織だが、『ボッティチェリ』は日本の主要新聞すべてに紹介記事が載り、一か月で三刷まで行き、現在は四刷に達している。
「『想像すること』が最も速く、最も深く、この始まりも終わりもない災厄の根をつかむ」と、いまをときめく作家、川上未映子が『ボッティチェリ』を評してくれた。
なぜ『ボッティチェリ』が日本の読者の心に響いたか、私はモトにも訊いてみた。「僕ら日本人にとって、これらの物語は、自分たちがくぐり抜けてきた経験を美しく誇張した鏡だったのだと――いまでもそうなのだと――思う」と彼は書いてきた。「精妙に歪められた、僕たち自身の経験。新聞や雑誌を見れば、パンデミックを語った日記調の文章はいくらでもあるけれど、寓話に仕立てるということはあまり考えられていなかったんじゃないか」とモトは言う。そうして最後に一言、「いまになってわかるけれど、日々起きていることにつぶされないために、僕自身、あなたの物語に頼っていたんだと思う」。
四月から五月にかけて、東京都民は律儀に外出を控え、息をひそめて一日一日を迎えていた、とモトは言う。「でも僕たちはまだ、くたびれていなかった。いま感じているような疲労があのころにはなかった」
これが何か月も、何年も続くかもしれないと思うと……。
それでも。夏の終わり、ニューヨークの感染率は全米でも指折りの低さだった。エルムハースト病院の周りの街路にも生活が戻ってきた。
この秋がどんな寓話をもたらすか、私は固唾を吞んで待っている。
-

-
バリー・ユアグロー
南アフリカ生まれ。10歳のときアメリカへ移住。シュールな設定ながら、思いつきのおかしさだけで終わるのではなく、妙にリアルで、時に切なく、笑えて、深みのある超短篇で人気を博す。敬愛する作家・アーティストはロアルド・ダール、北野武ほか、また「ヒッチコック劇場」「トワイライトゾーン」などのTV番組にも大きな影響を受けたという。著書に『一人の男が飛行機から飛び降りる』『セックスの哀しみ』『憑かれた旅人』『ケータイ・ストーリーズ』(以上、柴田元幸訳)『ぼくの不思議なダドリーおじさん』(坂野由紀子訳)などがある。現在、「波」で「オヤジギャグの華」を連載中。公式サイト
-

-
柴田元幸
1954年生まれ。翻訳家。文芸誌『MONKEY』編集長。『生半可な學者』で講談社 エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。2017年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。
この記事をシェアする
「亀のみぞ知る―海外文学定期便―」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- バリー・ユアグロー
-
南アフリカ生まれ。10歳のときアメリカへ移住。シュールな設定ながら、思いつきのおかしさだけで終わるのではなく、妙にリアルで、時に切なく、笑えて、深みのある超短篇で人気を博す。敬愛する作家・アーティストはロアルド・ダール、北野武ほか、また「ヒッチコック劇場」「トワイライトゾーン」などのTV番組にも大きな影響を受けたという。著書に『一人の男が飛行機から飛び降りる』『セックスの哀しみ』『憑かれた旅人』『ケータイ・ストーリーズ』(以上、柴田元幸訳)『ぼくの不思議なダドリーおじさん』(坂野由紀子訳)などがある。現在、「波」で「オヤジギャグの華」を連載中。公式サイト
-

- 柴田元幸
-
1954年生まれ。翻訳家。文芸誌『MONKEY』編集長。『生半可な學者』で講談社 エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。2017年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。
連載一覧
対談・インタビュー一覧

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら