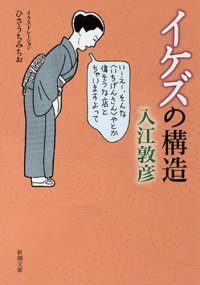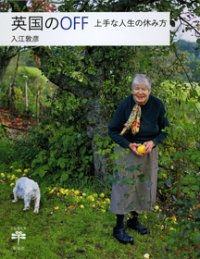わたしのお正月準備は10月に始まります。
その年の気候によって前後しますが、イタリア産クラスAグレード(上等のマロングラッセになるやつ)の栗が地元の八百屋に出回ると、なにをおいても渋皮煮を拵えるのです。お裾分けで味をしめたご近所さんたちが増え、季節になるとカフェで顔を合わせるたび口々に「今年はいつ?」と催促されるので、もはややらないわけにもいきません。かなり大量になるので若干面倒な仕事ですが年に一度と決めているので気は楽。
もちろん瓶詰めされた栗たちは新年の本番を待つわけですが、シロップ漬けしてから約一ヶ月後、取り分けておいた〝割れ栗〟の味見をします。もしかしたら、これはお節の晴れ舞台以上にテンションがアガる家庭内行事かもしれません。手間がかかるだけで失敗することは少なく、美味しいことはわかっているのでテイスティング当日は朝からそわそわ。お茶の準備をいたします。
渋皮煮に合わせるのはお煎茶でも中国茶でも、珈琲、紅茶でも構わないし、なんにでも寄り添ってくれる味わいですがやはりお抹茶。お薄をいただきます。とりわけここ数年、割れ栗にはこれ! という茶盌が定まってからというもの、ほかに選択肢はなくなりました。
銘は「拾喰」。DQNネーム(笑)でしょ。すいません。名づけ親はわたし。御つくりおきのお盌です。へんこな名前をつける親ほど――その育て方が正しいか否かは別にして――子供に執着する傾向がありますが、ここでもそれは例外ではありません。私的な区別として茶陶の碗には敬いを込めて【盌】の字を宛てていますが、茶席のために作陶されてもいないのに拾喰を盌と呼んでいる。お茶のセンセに怒られそう。でもわたしはもう、この茶盌が可愛くて可愛くて。掌に包むたびにいつも相好を崩してしまいます。

器を注文するというと普通は陶芸家さんや食器屋さんにお願いするんでしょうが、拾喰の来歴はちょいと変わっております。産声を上げたのは骨董屋さん。「北野天満宮」の側、京都で最も古く格式ある花街上七軒に近い「こっとう画餠洞」が産院なのです。
いわゆる町屋を改装した小態な間口は、なにやら老舗めいたムードを漂わせていますが、まだオープンして十数年。店主の服部元昭くんも、相棒の朝日久恵ちゃんも若い。おふたりとも地元民なのでたぶんその嗜好や雰囲気が店の【しつらい】に滲んでいるのでしょう。つまり〝あり得べき西陣の骨董店〟なのです。こうなると実際にどれだけ長く商売をやっているかは関係ありません。
わたしは彼が現在の場所にオープンする前からの知人です。毎月25日に骨董市が立つ天満宮の例祭「天神さん」の帰り道、仕舞屋の玄関を入ってすぐにある通称「店の間」の畳の上におもちゃ箱をひっくり返したようにものを並べている服部くんの店ともいえぬ店を覗いたのが始まり。はっきりいってなんの期待もせずの冷やかしでしたが、これが存外いい品揃え。

当時はまだ月一、天神さんの日に露店感覚でやってるだけだと聞いて「ああ、きっと次はないんだろうな」と失礼なことを考えていたら、あにはからんや屋形を構えられたので驚きました。売られているものにも服部くんらしい個性が光るようになり、かつクオリティもめきめき向上。しかし、なによりちょくちょく顔を出すうちに知った彼のある技能ゆえ、わたしは画餠洞に撞着と敬意を抱くようになったのです。――それは金継ぎ。
金繕い、金直しともいいます。ごく単純に説明すると、割れたり欠けたり皹がいったりした焼き物を漆で接いだり繋いだり埋めたりして、修理あとに金彩を施すことで〝景色〟を創る仕事。そうした修繕を生業としたプロもいて超絶技巧を有する職人たちは骨董や古美術の世界では深い尊敬を集めています。なかには完品を購入するのと変わらない値段が依頼にかかることすらある。
現在は英語圏でも新たな【美意識】として Kintsugi という言葉が広く知られるようになっています。
わたしはむかしから金継ぎされた器が好きで、完品と繕われたものが並んでいたらそちらに手が伸びました。それは自分にとってはただの修理ではなく個性の付加なのです。また、それゆえにかつて所有していた人たちの愛情を垣間見ることも。
服部くんは技術的にも見事な腕を持っているのですが、テクニック以上に繕う対象への思い入れ、というか共鳴かな、みたいなものが「ならでは」なのです。名職人が和装の着付け名人だとしたら、彼はセンス抜群のスタイリスト。画餠洞の奥で繕われる金継ぎの器はどれも本当に洒脱な媚態を備えるのです。


先日、日本に帰国したときも天神さんで買った李朝中期の碗を直してもらいました。目に見えないヘアークラックからお茶が漏れるのです。服部くんはそりゃあもう乙に仕上げてくれました。針のように細い一筋の金が碗の内側に燻る暗い焼きむらをかすめ、まるで雷を孕んだ黒雲で一天俄かに搔き曇ったかのような景色。彼の技量に改めて感動しました(写真左)。撮影に使う予定があったので大急ぎ、しかも突然のお願いだったにもかかわらずですから尚のことです。
けれど無茶ぶり、無理難題という点では前述した拾喰の比ではありません。はっきりいって、あれは不可能を形にしていただいたようなものだから。だって半分に割れた茶碗を持ち込んで「これ、なんか継いで使えるようにしてくれへん」なんて頼んじゃったんですから。
それは画餠洞と並んでしょっちゅう出入りさせてもらっている骨董店「大吉」のご主人、杉本理くんがくれた【くらわんか】。唐竹を割ったがごとく真っ二つになった半碗。高瀬川の川底浚をしたとき出てきたという話でした。「ツマミのせたり小物容れにでもしてください」とにやにや。もちろんわたしが大のくらわんか好きと知ってのプレゼントです。
かつては交通手段として輸送方法としていまでは考えられないくらい河川を大型船が往来していました。くらわんかというのはそれらに向けて飲食品を流し売りしていた小舟が利用していた安価な陶器類。安価で、けれど日常雑器ならではのざっかけない良さがある〝手〟です。船舶販売業の中心だった淀川だけでなく京都をふくめ全国で用いられてきました。
船頭さんの「くらわんかぁ~」という物売り声から名前がついたとされるそれらは安さゆえ粗雑に扱われ、まだ使えるようなものでも景気よく廃棄もされました。けれど水底で地中で永く睡るうちにしっとりした味わいが染みてゆき、やがて民藝運動によって下手の魅力としてディスカバーされるのです。
なにしろ大量生産ですから欠けのない完品だってそこそこ見つけることはできます。が、わたしは発掘陶片により惹かれる。ので、理くんのプレゼントに舞い上がりました。その挙句どうも思考能力を失ってしまったらしい。早い話がハイになっちゃった。
そうでもなければいくら付き合いが長いといっても「これの片割れにでけるようなん見っけて継いだってくれへん?」なんて、さすがにお願いできません。「こんどの帰国まで2年あるし。ほな、よろしゅう!」
もちろん金継ぎを得意とする服部くんは常日頃から陶片を沢山蒐集しているし仕入れで目にする機会も多いというヨミはありました。それにここまで難易度が高い注文だとギブアップもしやすかろうとも考えたのです。はっきりいってダメ元の御つくりおきでした。
ところがですねえ。服部くんはやっちゃったですよ。盌を仕立て上げてしまった。
ガラスの靴を携えてシンデレラを尋ね歩くように服部チャーミング王子はかなりの間わたしの半碗と径の合う陶片を探してくれたようです。が、大衆的なくらわんかには無限の型があり、どうもそれは不可能だと判った。普通の人はそこで諦めるでしょう。ところが彼は「では残る半分を作ってしまおう」なんていうトンでもないアイデアを思いついてしまった。
拾喰というのは、そんなわけで半分が陶器、半分が木のお椀なのです。本来いっしょになるはずのない素材を漆で接合させてある。しかもただの二分割ではつまらないと、もうひとつ時代は同じだけれど丹波の山奥の畑から掘り出された印判のくらわんか陶片を入手して嵌め込むなんて芸当をやってのけたのです。

これで名前の由来も理解していただけたでしょう。拾得くらわんかを繋いでいるので「拾喰」ってわけ。
かくなる難産を経て誕生した玉のような御つくりおきですから、わたしがめろめろになってしまった理由もなんとなく納得してくださるのではないかと存じます。こちらにいるときこそ〝割れもの〟繋がりで破れ渋皮煮の相手役を務めていますが日本では贅沢のし放題でした。
まず、デビューがこともあろうか「草喰なかひがし」さんですよ。おくどさんで炊かれた、あの世界一のごはんを、いの一番によそってもらったのです。およそこんなラッキーな器はございますまい。続いては「オオヤコーヒ焙煎所」の大宅稔さん。なんと、この器のためのオリジナル珈琲をブレンドしてもらいました。大宅さんは拾喰を「ブラックジャック」と呼び、わたしのリクエストを面白がってくれたものです。天神さんの出店で御自ら淹れてくださいました。


そのほかにも嵯峨の名割烹「おきな」では若主人の井上洋平くんに麹の香気高い別格に旨い蕪寿司をどっさり盛りこんでもらいましたし、桂の老舗菓子舗「中村軒」の女将さんにはお薄を点てていただきました。「この器にはこれが似合いますやろ」と選んで下さったのはお店の名代の麦代餅で感激でしたね。
かくのごとく仲良くしていただいている店にはとりあえず拾喰を連れてゆき、お披露目し、無理をいってそこの美味を充たしていただくという贅沢をさせていただいてます。お見せするたびにお褒めの言葉を無理やりもぎ取って、そうでしょうそうでしょうと頬ずりしているのですから、これを親馬鹿と言わずしてなんと申しましょう。しかしここまで猫可愛がりできる器を持てたこと、有り難く思わずにはいられません。
拾喰以降もわたしは画餠洞に無理難題を持ち込み続けています。前回お願いした山茶碗(平安末から室町にかけて生産された無釉の陶器)5客もかなり苦労していただいたようです。今回は仕入れられたばかりの文殊菩薩騎獅を店に出る前に我がものとしたうえで、これを載せる敷板の調達を依頼して帰ってきました。満足できる結果が待っているのは間違いないとして、どれだけの驚きを服部くんが用意してくれるのかが楽しみです。


画餠洞は金継ぎ屋ではありません。骨董店です。だから壊れた器をいきなり持ち込んで、だしぬけに修理を頼んでも引き受けてくださるわけではない。ただ、ここには個性的な繕い技術を持ったご主人がいて、彼の直した端正な器が売られている。なのでそういうものの好きな人々が集まってくる。だから通っているうちに場合によっては手を貸してもらえることもある……。どうか、そのあたりの極めて京都的なニュアンスをわきまえてお店を訪ねていただきたい。
拾喰はこの世にひとつですが、長く付き合ってゆけばいつか服部くんはあなたが親馬鹿ちゃんりん蕎麦屋の風鈴鳴らせるようなものを見つけ出してくれるでしょう。
こっとう画餠洞HP http://www.wahindo.jp/
「拾喰」制作記
http://papindo.seesaa.net/article/393038242.html
メンテ記
http://papindo.seesaa.net/article/438986451.html#more
-

-
入江敦彦
いりえあつひこ 1961年京都市西陣生まれ。多摩美術大学染織デザイン科卒業。ロンドン在住。作家、エッセイスト。主な著書に、生粋の京都人の視点で都の深層を描く『京都人だけが知っている』、『イケズの構造』『怖いこわい京都』『イケズ花咲く古典文学』や小説『京都松原 テ・鉄輪』など。『秘密のロンドン』『英国のOFF』など、英国の文化に関する著作も多数。最新刊は『読む京都』。(Photo by James Beresford)
この記事をシェアする
「御つくりおき――京都のひととモノとのつきあいかた――」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら