インタビュー 山田太一
自分のことをただ書くのではむき出しすぎると思った
初めての連載が9年つづき、
これまで書かずにきた記憶の残像が
降り積もって一冊の本となった。
――受賞作『月日の残像』は、足かけ九年のあいだ「考える人」に連載していただいたエッセイです。七十代のほとんどにわたって書いてくださったことになりますね。
山田 テーマも枚数も自由に決めてくれていいと当時の編集長の松家仁之さんに言われたとき、それまでエッセイでは書いたことのなかった一回が少し長いもの、四百字十枚でやってみようと思ったんです。連載というのも初めてのことでした。
――授賞理由のなかに、「自ら回想を戒める人の回想」という言葉がありました。
山田 自己顕示欲は人並みにあるのだけれど、いざ書くとなると、自分についてただしゃべるなんて格好悪いというか、いまさら恥じらってもしょうがないんだけれどなにか工夫が要るような気がして、引用を入れたり、ぜんぜん違う話から入って最後にちょっとだけ自分のことを話すとか、そんなふうにしながら、これまで書いたことのなかったことをいろいろと書くことになりました。
――「抜き書きのノートから」という章が二つあります。そのほかにも折りにふれさまざまな本からの引用が出てきます。大学時代から松竹撮影所で助監督をなさっていたころまで、十年ほどのあいだにかなりの数の抜き書きノートをつくられたそうですね。
山田 数えたことはありませんが、十五冊か二十冊くらいでしょうか。図書館や友人から借りた本を読んで感動しても返せば手元になくなってしまうから、これは書いておかなくちゃと思ってせっせと書き写しました。当時はコピーなんかありませんからね。筆跡を見ると、この頃はちょっと荒れてるなとか、何ページも引用して、こんなつまらない文章にずいぶん感服興奮していたんだなとか、見返すといろいろ思いますね。
でももっともっとセンチメンタルな詩や恋物語の抜き書きなんかは、とても引用できません(笑)。日記はつけていなかったから、引用がその代わりになるようなつもりもあったのですが、今となると年月日が書いてなくて役に立ちません。
湯河原で読んだ小林秀雄
山田 『月日の残像』が本になって何度か版を重ね、案外読んでくださる方がいることを喜んでいました。そのうえ小林秀雄賞をいただいて、じつに思いがけなく、うれしいです。
昭和二十五年九月、高校一年のときに、第一次の小林秀雄全集全八巻が創元社から出はじめました。そのときはまだ小林秀雄のことをほとんど知らなかったはずなんですが、なにかで読んで、とても凄い人だという思いだけがあって、この全集を買おう、と思ったんですね。いまでも本棚のいちばんいいところに置いてあります。
はっきり覚えているのですが、第一回の配本は『ドストエフスキイ』でした。ちょっと昨日ひらいたらこれが四百ページ近くあって二百円。『Xへの手紙』は百ページほど少くて百九十円。当時は湯河原に住んでいて、田舎の本屋さんには全集なんて予約しないと届きませんから、予約して毎月届くのを楽しみにしていました。そのわりに難しくてよく覚えていないんですけど。主にエッセイみたいなものを読みましたね。ずいぶん長いこと、遠くに偉い人がいるという感覚があった。なにか書いていても、あの人に叩かれるぞ、なんて思ったりして(笑)。
ある言葉について―たとえば「天」、「自由」、「神仏」、「個」とか―小林さんは、ふつうはこういうものだと言われているけれど、本当は違うだろうとおっしゃる。常識をひっくり返すというか、それが推理小説を読むように面白いんですよ。揺さぶられるのが楽しくて読んでいたところがありますね。
――予断や常識的な見方をひっくりかえすというのは、山田さんのテレビドラマとも通じますね。
山田 影響を受けているのかも知れませんね。小林さんは、『考えるヒント』のなかでエリオットを引きながら、ヒューマニズムについて書いています。ヒューマニズムというのは人の善意を信じるとか、寛容であるとかそういうことではなくて、理念でものが言われているときに、「ヒューマン」の立場から、つまり社会生活や個人生活の視点でその理念を批評する力だと書いていらっしゃる。そして、生きた人間はかならず矛盾するものだから、その理念はすっきりうまくいくわけがないとおっしゃっていたと思うんです。
手前味噌ですが、テレビドラマで、ある理念を根拠にして書こうとして、実際に人物を動かしていくと、そうはいかなくなってくる。ふりかえってみると、小林さんの「ヒューマニズム」をいくらか基準にして生きてきたという思いがいたしますね。小林さんのお考えを、神さまみたいに崇めているわけではないし、しょっちゅう引用できるほど読んでもいないんだけれど、高校生ごろに植えつけられた考え方の文法みたいなものをずっと引きずっているんだなと思います。
生活している生身の人間が、理念とかイデオロギーをどういうふうに生きるかをドラマでシミュレーションすると、そうはいかないよ、ということになる。とてもおこがましいけれど、うまくいった時のテレビドラマにもそういう役割が担えると思っています。
『ドストエフスキイの生活』の冒頭に、パスカルの「最後に、土くれが少しばかり、頭の上にばら撒かれ、凡ては永久に過ぎ去る」という引用があります。人生には意味がない、死ねば土くれがぱらぱらまかれて終わりだと。これは近代がぶつかった大テーマですよね。神はいない、死んだら終わりよ、という話。
その引用の言葉はなんとなくずっと頭にあった。ガルシア=マルケスの『百年の孤独』でも、いろいろなことがあったって、百年もたてばいずれみんな忘れ去られると、同じようなことを言っている。それは厳然たる現実だけれど、でもそんなニヒリズムだけでは僕らは生きていけないでしょう。
自然をよく見ると、動物、たとえばペンギンなんかも大変な苦労をして子どもを育てるじゃないですか。そうしなければ維持できないところで生命を維持している。それにまったく意味がないということはないと思う。感嘆する他はない精緻な花の美しさだって、何の意味もない、ということはないんじゃないか。芸術家がいて、花をデザインしたわけじゃない。じゃあ誰がデザインしたのか。人間がこうして生きて、ある年月が経つと死んでゆく。何者か、超越的な存在がいるかもしれないという発想は、そんなに突飛ではないと思っています。
小林秀雄さんは、終戦の翌年にお母様が亡くなったあと、夕暮れに蛍が飛んでいるのを見て、お母さんは蛍になったんだと思ったと書いていますね(『感想』)。この世にあるものに何の意味もないとすれば、どう考えたっていいとも言えるでしょう。蛍を母だと思う。フィクションとはそういうものだと思います。ある人にとってそれはシロクマかもしれない。
つまり、僕らは意味を欲しているんだと思うんです。自分を安定させる、心を安定させるようなフィクションを必要としている。そのフィクションは現実によって否定される。否定されることでフィクションも力をつける。よきフィクションは宝だと思います。
脚本と小説、エッセイ
――『月日の残像』では、冒頭の「武蔵溝ノ口の家」がまず印象的です。
山田 もう四十年近く暮らしていますが、なんだかここから動く気にはなれなかった。めんどうだったせいもありますけどね。溝の口自体は古くからある町ですが、田園都市線沿線は新興住宅が一気に増えた地域です。多摩川に近い溝ノ口に僕が越してきたころは、田園都市線のたまプラーザの駅の前なんて、荒野みたいでした。風が吹くと砂があたりじゅうに舞って、西部劇みたいだった。奥から開発していって、デパートなどは場所を確保しておいてあとからつくる。いわゆる小市民が一戸建てやマンションを買えるようになってきた時期ですね。
――「岸辺のアルバム」や「沿線地図」、「丘の上の向日葵」などいくつも
のドラマが思い浮かびますが、この沿線で暮らす人たちをお書きになっています。
山田 そうですね。ふだんまわりにいる人たちがおもしろいと思った。近くにいる人については、学問的な視点とか理念では書けませんね。書きながらシミュレーションしてみるところがありました。たとえば、この奥さんがいまこの時代のこの土地で浮気をしたらどうなるだろうか。ドラマではあらゆることが具体的です。喫茶店では何の音楽が流れているとか、そういうことに立ち入っていくと、最初に企画書に書いたような人生なんて書けないとわかってくる。
――脚本は俳優さんが決まってから、その方を思い浮かべながら書くそうですね。
山田 メインの数人の方についてはそうです。オリジナルでシナリオを書くときには、その役を誰がやってくれるかということはとても重大です。俳優さんが変わると、話が変わってしまう。この人だったらこうなるけれど、この人だとちがうなとか。むろん俳優さんだから、いろいろな役をなさるけれど、でも似合うキャラクターの限度がありますよね。あえていつもとは違うことをやっていただくのも面白いけれど。
――先日放映された「よろしくな。息子」(TBS日曜劇場「おやじの背中」)では、渡辺謙さんが靴職人の役をなさっていましたね。「おやじの背中」というシリーズの一話ですが、山田さんの回は、渡辺謙さん演じる父親の世代の人物が、若い人のふるまいを見てすっかり感心してしまいます。
山田 若い人に深みを求めるのは無理かもしれないけれど、時には私たちのころよりずっと社会性もあり、柔らかな知性の持ち主もいる。いたらない息子と寡黙な父という物語は描きたくなかった。先ほどの小林秀雄さんじゃないけれど、ひっくり返すことをいつも考えているようなところがありますね。
――俳優の身体を通して表現する脚本と、文章だけで完結する小説やエッセイはずいぶん違うものですか。
山田 違いますね。他者と一緒にする仕事も嫌いではないです。相手の顔ぶれを見て、演出家や俳優さんが、やってよかったと感じてもらえるように書こうと思う。うまくいかないこともあるから、あまり大きな声では言えませんけど。
俳優さんが演じて、演出家がいて、はじめて世界が実現するというのと、自分の文章だけというのでは、両方にプラスとマイナスがありますね。ドラマや舞台の予算とか日程とか役者の制約への気配りをあれこれしていると、小説で勝手放題のありえないような嘘の話を書きたくなる。
なにを書いていても、行き詰まるのはしょっちゅうです。だからといって、あらかじめプランを考えていると、活力がわかない。かならず行き詰まるけれど、そこからだよなといつも思います。この連載もずいぶん行き詰まって、苦し紛れに思わぬ方向に行ってしまったりもしました。
章の終わりにとつぜん出てくる、三島由紀夫さんご夫妻と遭遇したときの話とか、父の後妻だった二度目の母と十数年ぶりに電車で向かいあわせに坐った話とか。ああいうのは、書きすぎちゃいけない。説明したり描写したりしないで、ぱっと一瞬だけ見せて終わりにしたい。そこからはじめて、前振りをあれこれ書いたということもありました。
――子どもの頃からお身内がたくさん亡くなっていますね。八人きょうだいのうち、お兄さまが四人亡くなっている。お母さまも戦時中にご病気で亡くなっておられます。
山田 姉と兄と妹がひとりずつ残りました。父は浅草のころは食堂をやって、湯河原にいってからは指圧だとかパチンコ屋だとかとにかくなんでもやって、子どもたちを養ってくれました。父が働いている姿を、僕は毎日なにかしら見ていた。このあいだ、長年の友だちが、高校のころ僕の家に来たとき、父が外で働いている姿を二階の窓から見て、あっ、お父さんが働いている、と思ったと言うんですね。彼はそれまで父上が働く姿を見たことがなかった、と。うちの父はパチンコ屋の店の表回りの拭き掃除をしていたらしい。親というのは、こんなふうに働いているものなんだと思ったと。ついこの間、その友人とめずらしく長くしゃべって、そんな話を初めて聞きました。僕には当たり前でも、環境が違うと新鮮だったんでしょう。
父はどうしろこうしろと日常の具体的な指示は言うけれど、人間はこういうもんだというようなことはめったにしか言わない人でした。湯河原での仕事がちょっとうまくいって、少し余裕ができて、これで大学に行かせてやれるぞ、と言ってもらった。昔の人ですから、言葉ではあんまり言わないんですが、俺のことを考えてくれていたんだなとありがたかった。
息子たちが肺結核で死んでいるから、煙草を吸うなとはずいぶん言われましたね。たくさん家族がいたのに、きょうだいが半分いなくなってしまった。僕は生き残った人間だから、過度に酒を飲むとか、自分をあまり粗末に扱っちゃだめだという思いはいつの間にかありました。父の悲しみを見ていましたから。
――そういう経験が、山田さんという人と作品をつくられたのですね。
山田 それが僕の限界でもあり、色合いでもあるのだろうと今は思っています。
1934年、東京浅草生まれ。
早稲田大学卒業後、松竹大船撮影所入社。演出部で木下恵介監督の助監督に。65年独立。以後およそ半世紀にわたって、「岸辺のアルバム」「早春スケッチブック」「ふぞろいの林檎たち」「時は立ちどまらない」など、数多くの名作テレビドラマを手がける。
88年『異人たちとの夏』で山本周五郎賞受賞。主な小説作品に『飛ぶ夢をしばらく見ない』『冬の蜃気楼』『終りに見た街』『空也上人がいた』ほか、エッセイに『親ができるのは「ほんの少しばかり」のこと』など。(受賞当時)
● ● ●
選評
奥ゆかしく、それでいて強靭な意志
関川夏央
山田太一『月日の残像』の冒頭章は「武蔵溝ノ口の家」と題した一章である。浅草育ちの著者なのに、多摩川を西に渡ったそこに長年住んでいる。山田太一のドラマには鉄橋を渡る私鉄電車の映像が必ずといっていいほど入るが、そのわけが著者の生き方とともにそくそくと読者につたわる。
最終章「この先の楽しみ」は、つくられた記憶と現実を混同してしまったエピソードだ。それはたしかに「老い」のもたらした現象には違いないだろうが、著者はそんな事態にもあわてなかった。悲しみもせず、むしろ心をなごませた。それは「あたらしいもの」に際会して、驚きながらおもしろがる態度であった。
『月日の残像』は「考える人」に八年半にわたって連載された。「老い」に甘えて回想に身をゆだねてはならないという強い自戒と、回想のかたちでいうべきことはまだあると思う「穏やかな野心」とのバランスが絶妙なのは、山田太一の叙述のリズム(ためらいの波長)と季刊誌のスタイルが融和したからだろう。この本は冒頭と末尾の章のみ連載の順番をかえて「編集」されている。そのこともこの書きものの意味と味わいを増すべく作用した。
もうひとつは「引用」である。
〈(他人が興味を持つのは)私の弱点だけだといふことも、たしかな事実であるが、ふしぎな己惚れが(……)もう一つの同じ程度にたしかな事実、「他人にとつて私の問題などは何ものでもない」といふ事実のはうを忘れさせてしまふことが、往々にしてある。〉
これは三島由紀夫『小説家の休暇』からの引用で、二十代から三十代にかけて「抜き書き依存症」であった著者が、自分の古いノートから再び抜いた。ほかにも都合四度、三島の発言があらわれるが、それらはみな私たちの通俗な三島像を裏切るもので、著者は「引用」によって自分の三島由紀夫像を語ろうとする。
そしてそれらは、三島だけではなく松竹助監督時代の師匠木下恵介を悼む文章、「人は否応なくそれぞれの外的内的な余儀なさを生きてしまうのだろう。まるごと尊ぶしか死者との向き合いようはないのだろう」という諦念と並列される。温顔のゆかしい書きぶり、その下にある著者の本質的な勁さを私たちに伝えるのに、「編集」と「引用」はたぐいまれな力量を発揮した。
破れ目を破りきらないこと
堀江敏幸
脚本や小説、もしくは単発の短い随想の集合体には収まりきらない「感情」がここにはある。情動の過度な強さも感懐の脆さも否定せず、しかしそれらを自然に取りのけて残った未定形の感情が、一篇のなかだけでなく全体でひとつの浮遊体となってただよう。
親兄弟、とくに父親のこと、仕事で知り合った人たちや友人のこと、最大の友人とも言える書物のこと。テレビや映画の世界の裏面に触れた興味深い逸話もならんでいて内容はとても具体的だし、喜怒哀楽に分類しようとすればできなくはない反応がたしかに記されている。とまどい、うろたえる姿もある。
にもかかわらず、ひとつ読み終えるたびに、大切なのはそこではないとの思いにとらわれる。記憶というものが持っている本質的なとげとげしさを、書き手は深く理解している。かつての「溝の口」的な、便利ではあるけれど少しはずれた土地のにおいと、下町育ちの生理感覚をむりなく融合させた平凡への意志をかたくなに守ることによって、平凡でないエピソードをしずかに押さえつける恰好になってはいるのだが、そういう道筋をたどらなければ出てこない「感情」が不意に湧き出てくる破れ目もあちこちに見られる。
たとえば、助監督時代に現場でいっしょだったOさんという古参の先輩について語った章。《その仕事のあと、Oさんの友人がお宅へ訪ねると、狭いアパートの一室で、掛け蒲団の皮をはいで中の綿だけにくるまって寝ていたという。どうしてこんなことを、ときくと、これだと綿をちぎって首の回りを囲めるからあたたかくていいのだ、といったという》。その後まもなくOさんは亡くなる。自死の噂もあった。著者はそこで、《いくらか「普遍」をはみ出すものに触れたという気持になった》と記す。
破れ目とはつまり、「普遍」をはみ出すものだが、それに触れる感性があり、実際に触れてもいるのに、向こう側へ身体を入れてしまうことはしない。かならず戻って来るのだ。つとめて穏やかに、人を傷つける前に自分が傷つくようことを運ぼうとする配慮と、いきなり「殺意」(「映画の周りで」)といった言葉を書き付ける最低限の攻撃性が共存しているところに、深く心を動かされた。
いい本にあまり理屈はいらない
橋本治
山田太一さんの『月日の残像』を読んで、「いい本だな」と思いました。読み終わった後でそう思ったのではなく、読み始めてすぐ「いい本だな」と思いました。「いい本」には「いい本の香気」があります。それが強く立ち上るのではなく、気がつくと穏やかな香気の中にいるという感じです。
『月日の残像』というタイトルで、本のカバーは夕焼けの光景なのに、読み終わると夜明けの青空を見上げるような新鮮な感じがします。山田さん特有の「毒」もこの中に書かれてはいるのに、「毒」は毒としてあって、そのままなにかに昇華されて行きます。そこには人のリアルな営みが描かれているのに、読めばきれいな透明感を感じます。
『月日の残像』を「いい本だな」と思って、どのように「いい本」かを書くことが出来ません。「いい本だから読んで」と言われて手渡されるだけの本はちゃんとあって、『月日の残像』はその一冊です。過不足なく、なんのへんてつもありません。作者の姿だけが浮かび上がるというわけではありません。作者の姿が見えないまま、文章だけが浮かび上がるというわけでもありません。作者の姿があって、文章があって、どちらが強いというわけではなく、等分に存在しているそのところが美しいのです。
書き手ばかりが前に出るわけではなく、書かれた文章の中に作者が見事に収まっている、その按配のよさが文章の美しさを作り出していて、「書き手というものはどうあってしかるべきか」ということを静かに教えてくれているところが、凡百の随筆とは違うところだと思い、その姿勢こそが小林秀雄賞にふさわしいのではないかと思います。
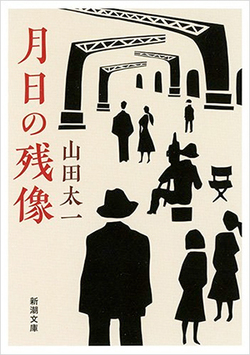
2016/06/01発売
この記事をシェアする
「小林秀雄賞」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら





