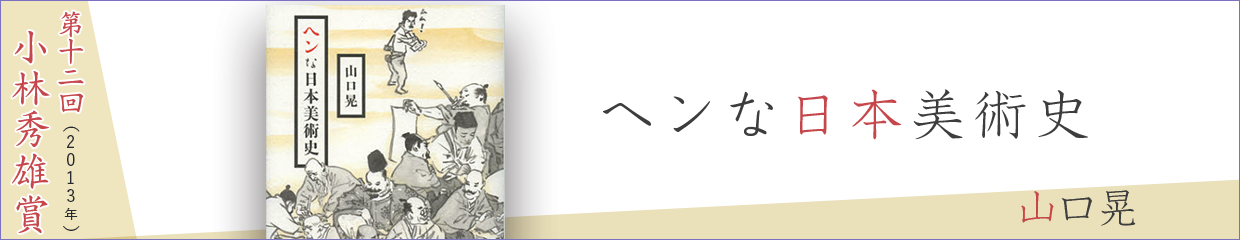インタビュー 山口晃
大きな流れの中で日本美術の異なる見方を紹介したい
美大での西洋偏重の疑問から、落書きに
立ち戻り、見つめた日本美術。現れたのは、明治期に
とりこぼされた大きな断絶と、「ヘン」な魅力だった。
雪舟のどこがヘン?
「ヘン」な部分に限らず日本美術に目が向きだしたのは、大学での古美術研修で奈良・京都を二週間ばかり回って見始めた頃からでしょうか。以来、ぽつりぽつりと思いためてきたことをまとめました。
日本の美術が「ヘン」というのは、まずは中国から見た部分があります。それに、日本の中での正統派から見ての「ヘン」もある。他にも現代の私達から見て、西洋から見て、というのもありますが、「ヘン=悪い」ではなく、中心から距離があるという感じです。
この本は、ひたすら古い絵の感想を述べていく「私見 にっぽんの古い絵」と題したカルチャースクールでの講義が元になっています。日本の古い美術について、雑誌などに単発で寄稿することはあっても、まとめて振り返る機会は、この時が初めてでした。
絵のスライドを映しながら「ヌルッとしていいでしょう」とか、「バシッと決まっているんですよ」と講義している分にはよかったのですが、その「ヌルッ」はなんだ、というのを文章にすることから始まりまして。けっこう削ったり書き直したりを繰り返し、四年ほどかかっています。これでもまだ、表現が感覚的すぎるという注意はいただきますけれど。作品を前にしてお話をしても、半分伝わるかどうか。ましてやそれが字になると、なかなか手に余る作業でした。
まとめるうちに、とくに熱が入ったのは雪舟です。
奈良の大和文華館に来ていた秋冬山水図が、雪舟を見た初めですが、外光の入る明るい展示室のせいか、なんだこのペラペラの絵は、とまったくひっかからなかった。それがずいぶん後になって、美術館のなかの暗いところで見たときに衝撃を受けまして。彼にはいろいろなタイプの絵があり、正統派のうまい作品があるかと思うと、外連味たっぷりな「慧可断臂図」みたいなものも書く。落ち着かない人だな、走り続けた人だな、とにわかに興味がわいて、なんとか一端でも感じとることができはしないかと近寄って行ったという次第です。
本家である中国の山水画を見ますと、雪舟のおかしさといいますか、ヘンさが見えてきます。さらには中国の人が日本の山水画はヘンだ、と言う理由が見えてくる。
中国の山水画は少々くどく感じる程に手が入っており、それに比べると、雪舟はいかにもガサッとやりっぱなしで、かといって米芾のように妙にボテッとしたものとも違う。出がらしのようにも見えるけれども、いやいやこれは干からびている様で鰹節みたいな旨みの詰まったものではないだろうか、という「ヘン」なのです。
日本の山水画は中国の山水画をまねるところから始まりますが、写しているうちにどうしても変わってしまい、人となりが出てきます。本物を志向しているのに、とんでもなくぶれる。そこが面白いですね。いかにも日本です。まじめに写すんですけれどもぶれてきて、そのうちぶれている方が面白くなって、そっちでお祭りをはじめちゃう。これだけ画聖と言われている人ですらそうなんですから、こういうことは雪舟のころも、その前もあったんでしょう。とても日本的な部分が現れているといえます。
逆転の発想
オーソドックスなものとは何なのか。過ぎ去った時代のオーソドックスを考えてみても、確かめようのない部分があります。何かの理由で人気が出た作品があったとして、それが必ずしもいいものではないということもあります。作品の良し悪しの他に政治力や時の運、当時の観る人とのマッチングにも関係していますから。
残っていないものはどういうものだったのかは言いようがないし、残っているものが必ずしも優れているとは限らない。後の時代の再評価や再忘却もおこりうる。
そんなことから、当然のごとくに良く言われていることに関しては、逆のことを考えてみるようにしています。悪く言われていることに対しても。世の中のことは、たいていはどっちもありなんですね。弘法にも筆の誤りと弘法筆を選ばず、と、対になることわざが必ずあるように。大きな流れの中で、「日本美術」の異なる見方を提供したいと思っています。
明治が生んだ断絶
この本で取り上げた「日本美術」と、現代を生きる画家との間には、いくつかの断絶があります。
まず、大きな要因となったのは明治期に西洋絵画が入ってきたことです。このとき、日本美術には断絶が生じました。一般的にはあまり言及されませんけれども、私からするとこれはたいへんな断絶で、ここでとりこぼしたことを拾っていきたいというのが、この本の主題のひとつです。
一つ目の断絶はパース(遠近法)の登場です。それまでの日本には、パースを取るという技法はなかった。なので、僭越ながら私は、河鍋暁斎よりはパースが取れると思うんです。ただ、人は、誰かがやっているのを見れば、真似をしてできるようになります。ひとりが膨大な情報の中からコツをつかんだら、前の世代までできなかったことが、次の世代からは苦も無く軽くできるようになる。
その他の技法にしても、西洋から講師と共に入ってくると、その途端、意味が伝わります。バルールや色味、陰の部分があること。そうやって日本の画家たちがパースをとれるようになったことで、むしろ「とれない」ことがどんどん許されなくなっていく。その結果「パースをとれない」ことが出来なくなるのです。絵を勉強すればするほど、そういう部分でのものの見方が去勢されてくるといえましょうか。
でもこれを避けるのは難しいことで、まっとうな神経の持ち主ならほかの文明圏でどういう表現がされているのか、気になります。見れば見るほど無視できなくなってくる。だから、日本画は西洋画のルールに吸い込まれていき、下書きに形を遠近法で写すというデッサンがどんどん入りこんでいく。
もうひとつの断絶は筆です。筆を使わなくなったことの断絶は大きいです。
筆を使える時代の人たちは、運筆をするときに、意識せずとも自在に筆を操ることができます。どう力を入れて身体を動かすかがしっかり身についている。
しかし、私たちが古めかしくやろうと思って筆を使うと、筆の抑揚を調節しようとするだけでカツカツになってしまいまして。筆が死ぬといいますか、筆致が精彩のないものになります。鉛筆なら、しんが硬いので1でも10の力でも濃淡の差になるだけで、抑揚にあんまり差は出ません。でも筆はとんでもなく差が出る。1と2のちょっとした力の差ですら違いが出るんです。西洋絵画は、色彩の濃淡による質感表現に優れますが、日本絵画は線の抑揚でそれをやろうとする。更にそこに画家の気宇みたいなものまでのせてくる。線に依る事で、表現しうる領域がかわってくるんですね。
明治期、京都画壇の竹内栖鳳は、修業時代はとにかく筆だったと回顧していますね。来る日も来る日も書道で、まっとうな筆遣いができるようになってようやく絵を描かせてもらえる。暁斎も、筆を扱えるようになる前からものを描かせると筆が縮こまる、と言っている。明治の初期は、画家たちは筆を思う存分使えたことがわかります。
ただ、ある頃から、絵描きさんが鉛筆でデッサンをし始めます。描いてしっくりくるのが鉛筆か筆かということが分水嶺だったのでしょう。そこで鉛筆が選ばれ、どんどん日本画は厚塗りになって、油絵のタブローみたいな質感表現になった。薄いと筆の抑揚がばれますが、厚塗りだと、とてもじゃないけれど線の抑揚を見るような楽しみ方はできません。
こうした、とりこぼされたままの断絶にスポットライトを当てることは、この本の大きな意義だと思っています。
なるべく明解な表現で、できうる限り考えていることを正直に書いて、怒られちゃうかなというようなことも、言い回しを柔らかくして出したつもりです。
全く日本美術に興味のない方がこの本を読んで美術作品に目を向けてくれたり、美術館に足を運んでくれたらうれしいです。すでに日本美術好きな方も、「こういう見方をしていいんだ」と、新たな意識を向けてもらえたら。展覧会に行きますと、みなさん解説ばかりを読みふけっています。解説をじっと三十秒ぐらい読んで、絵は五秒ぐらい。ああ、もったいない。企画展の時に黒山の人だかりだった作品が、東博(東京国立博物館)の常設展に出ていると誰も見ていないことも多いですし。
もう少し、絵自体が醸し出している香りや味、匂いみたいなものを味わう事に目を向けていただくには、どういうことを書けばいいんだろう。本書では、その点にも腐心しました。
わたしは電柱をよく描きますが、電柱はびっくりするぐらい嫌われています。景観の邪魔者で、とにかく地下に埋めるのがいい、と。これは新鮮な驚きでした。でもそう言っている人たちは電柱をちゃんと見ているわけでもない。電柱の運動性、空間への干渉の仕方みたいなものを全く見ていない。例えば、青空をバックに冬枯れの木があると、真っ黒いシルエットが出現します。それを景観の邪魔と言う人はあまりいないでしょう。あのシルエットの黒は、空間を分割したうえで青空を一番きれいに見せる仕掛けの一つで、電柱電線はその木の在り方に一番近い。これは文明の作った、なかなか大したものの一つではないでしょうか。そういうことを文章でも伝えられないかなと思っています。
画家になる
幼いころから、あんまり積極的な子どもではありませんでした。ただ、クラスの真ん中に躍り出て面白いことをいうことはなくても、たま~に回ってきたお鉢はぜったいに逃さない。自分から行くのは浅ましいと思いつつ、人様にアピールするのは嫌いじゃない。それが大人になっても続いております。
子どものころは、画家になりたいとは思っていませんでした。私の勝手な画家のイメージは、ベレー帽姿で結核で三十歳前に死ぬというものでしたから。乱歩が好きでしたので、ああいったドキドキするものを書いて暮らせたら楽しいなと思っていました。画家という事ではなく、イマジネーションを形にする、字なり、絵に関する職業につけたらなあと。
作文は得意ではないけれど、好きで書いていました。弁論大会があると張り切ってみたり。ちょっと物申すというところは、その頃からありました。
絵は自分の内々のものに近かったです。学校で絵を描くと、手を抜いたり仕上がらないと怒られますが、家で広告の裏に描く分には飽きたらやめられますし、誰からも怒られない。その気楽な絵でよかった。
でも、ひっそり好きで描いていた絵ですが、手の方がだんだんイマジネーションに追いつかなくなるんです。それで、とにかくこの技量不足をなんとかしたいと浪人を経て美大に進みました。
その頃は、ドガやミュシャのような、わかりやすくデッサンでみせる、生真面目なものが好きでした。作家自身というよりはデッサン力への憧れです。思うままに描いてみたい。でも、予備校でもそうでしたが、大学では出来て当たり前なので、昔はここで褒めてもらえたのにというところで、褒められません。むしろ出来ない部分をつつかれる。さらに「美術」が自分の絵に入ってくることに対しての違和感と言いますか。なんで絵をうまくなりたいだけなのに、西洋美術史を学んだうえで描かなければいけないのか、という違和感が大きくて葛藤していました。
自分の中の日本
中村光夫の「『移動』の時代」という随筆があります。高校生の時に読み、大いにアテられました。文化の内発性について問題提起をした内容で、明治期以降の外来文化を受容してそれを消費するサイクルというのはおかしくないですか、と言っています。はじめは様式の踏襲でも、やがてはそれを消化吸収してゆくのではなく、様式を踏襲しているうちに西洋で次の様式が生まれたら、またそれを踏襲する。踏襲の繰り返しだけでは、内発性が全くないじゃないか、どうなんだ、と。油画科で絵をやりだすと、まさにその通りの図式でした。
本にも書きましたが、日本の洋画には西洋絵画、西洋美術界という「宗家」があります。その「宗家」の様式を踏襲し続けるんですね。私が学生時代の芸大は、ボイスというドイツ人の芸術家にご執心で、ボイスが来日して講演したときに何かを描いた黒板が、そのまま後生大事にとってあるくらいでした。それを消すところからだ、と憤りながらも、先生には口では全然歯が立ちませんので、もんもんとしておりまして。どうやって抜け出せるだろう、やり直ししかない、ということで、無理やり古い日本の絵柄を試します。大学一年ぐらいです。
ところが一年二年とやったところで、自分の中の伝統的日本がびっくりするほど少ないことに気が付きました。桂離宮を背負っているつもりが2×4住宅がせいぜい。薄い自分に気が付きました。自分にとっての日本とは何だろう。辿り着いたのは子供の頃からの広告の裏のお絵かきでした。
西洋ではないけど、純日本なのかというとそうでもない。ボールペンや鉛筆で、ちまちまと細かく宇宙戦艦やカブトムシを描いていたあれだと思い、一度油絵を置きまして、三年生のときから落書きに戻ります。その落書きの世界からですと、反発していた西洋美術も素直に見ることができるようになりました。一方の日本美術にもこんなご先祖様がいたんだ、と学びだすようになりまして。
その頃から、いまの自分の絵柄になったような気がします。無理に日本美術めかして筆の味わいをと言うのではなくて、鉛筆しか使えないから鉛筆を使おう。ご先祖様に興味があるから雲など描いてみよう。絵柄を作ろうと思った事は一度も無いのですが、やるべき事をするうちに、こうなりました。
最近は、描き方では雪舟がどう引き継がれていったのかに関心があります。それから水墨画の本家の中国、あるいはもうちょっと遡ってインド、そこら辺のアジアに対してはかなりお留守でしたので、細かく見て行きたいですね。漠然としたイメージしかないのですが、ひょっとしたらそれがポリネシアに流れて、そこから北上したものがまた違う系統で入ったりしやしないのか。視界を広げていきたいです。
昨年平等院に襖絵を奉納致しましたが、もう一部屋手掛けさせて頂けることになりそうです。昨年納めたのは文化財と同じ棟の指定外の部屋でしたので、あまりしばりはありませんでした。でも、今度話をいただいているお部屋は文化財部分なので、ちょっと困っております。私は日本画材は不得手なので、かといって油絵で許可が出るのかどうか。これが目下、迫っている大きな挑戦です。
油絵と現代美術の位置から日本の美術を手がける。きちんとやってらっしゃる方は大勢いらっしゃるので僕一人ぐらい、こういう変なポジションでやっていてもいいのかな、と思っています。もののサイクルが速くなりますと、会派のような運動が起こりにくくなります。そうなってくると、これからは正当に後を継ぐというよりは、私淑という形で個人が継いでゆく流れになっていくのではないでしょうか。会派を立ち上げなくとも、死んで十年、二十年経った後に誰かが継いでくれるかもしれない。そんなことを期待しつつ、自分もいいなと思う人に私淑して、現代ならではの絵を作っていきたいですね。
1969年東京生まれ。群馬県桐生市に育つ。
96年東京芸術大学大学院美術研究科絵画専攻
(油画)修士課程修了。
2001年第4回岡本太郎記念現代芸術大賞優秀賞。著書に『すゞしろ日記』(羽鳥書店)、『山口晃 大画面作品集』(青幻舎)、『日本建築集中講義』(藤森照信氏との共著、淡交社)など。10月12日より「山口晃展 画業ほぼ総覧−お絵描きから現在まで」が開催される(群馬県立館林美術館、2014年1月13日まで)。(受賞当時)
● ● ●
選評
節度ある芸
養老孟司
久しぶりに読後の爽快感を味わったように思う。実作者が美術を批評する。そこには自ずから節度が生まれてくる。どのような批評をするにしても、所詮は自分に戻って来ざるを得ない。その批評が成功裡に終わっているということは、同時に著者の実作者としての力量を示す。若い頃に生意気をいうと「そんなにいうなら、お前がやってみな」といわれたのを思い出す。しかも筆致が明るい。ネット社会になって、他人の難癖を気にするせいか、表現がハキハキしなくなったような気がする。歯に衣を着せて羽二重でくるむ。それがないから気持がいい。なんだか軽いなあ。そういう感もあるが、そもそも日本美術というのは、軽いのではないか。それを重くしたら、かえって嘘になりかねない。貧乏人は絵画がなくたって生きていく。その意味で美術は社会の余技であろう。美術商はそれをお金にする。そこを考えたら、実作者が美術を本音で批評する、その芸を買う。
考えている人
加藤典洋
やはり実際にものを作っている人は強いと思った。
受賞作のことである。
著者は、明治の反骨の人河鍋暁斎がじつに堅固な技倆の持ち主だったことに触れて大きな絵が小さく見えてしまう、といっている。ふつうの技倆だと、縦一メートル弱の大きさでも人物像が歪むということが多々ある。それなのに暁斎の「龍頭観音像」は縦が三・五メートルもあるのに歪みがない。図版などではもっと小ぶりにみえる。小ぶりにみえるというのは、「手首から先を使って出す精度を、腕を使って出せる」からだ。手を浮かして大きな文字を描く難しさを想ってごらんなさい、するとわかるヨ、とおっしゃっている。
モノが生き生きしているというのは、「ちょろまかす」というか「一手間抜く」ということがそこに起こっているということで、そのため解像度が一段階落ちる。これは「鳥獣戯画」の面白さにふれてのお言葉だが、昔、ある人が飛んでいるゴムまりは歪んでいるといった。また、若い人がSFX映画の映像を念頭に(だろう)、過視的、と面白いことをいった。そういう指摘を思い出させる。
4×4のボードの上で15の駒を動かすパズルでは、一手間抜いて、解像度を落とすと、動きが生まれる。アキがないと私たちは、過視的に感じる。しかしそれは、一段と低い解像度が私たちの生の地べただからである。
中でも私は、明治時代になってみんなが「写生」を学びパースをとれるようになったら、モチーフと背景を一緒に描くことができなくなってしまったのは、一度、自転車に「乗れる」ようになってしまうと、「乗れない」ことができなくなるのと同じだというのに、そうだ! と思ってしまった。批評も同じである。
批評家ではないのに、書くものが批評。そういうことがあるのが批評の面白さだが、批評の精度を「腕を使って出せる」人。そのため、この本は小さく見える。でもひとつひとつの本の細胞が、押すとプチプチと音を立てて潰れる。油画科出身の日本画家? 考えてみればこういう人が、「考えない」わけはないのである。
ということで今年の受賞作は画家山口晃さんの画論『ヘンな日本美術史』になった。受賞が決まってから帰宅して、画像検索で山口さんの絵を見た。ああ、この人だったのか、と思った。すばらしい画家に、おりよく、よい賞がいったのではないか。
「ヘン」に気がつけばなにかが見える
橋本治
その気になって見れば、日本の美術史はヘンな絵だらけです。ヘンな絵だらけだけど、しかし普段はあまりそう思わない。「自分にゃ分からないけれども、きっと立派な作品なんだろうな」と思わされていて、その「ヘンさ」にあまり気がつかない。「ここがこうヘン」と言われて、初めて「ホントだ、確かにヘンだ」と気がついたりするのは、この本にも書かれていますが、近代以前の日本の絵というのは、「言われてみればヘンだが、言われなきゃ気にならないところを、隠し持ったり、平然と丸出しにしているようなもの」です。昔の日本人ばかりでなく、今の日本人にとってもこのことは当たり前のようなことで、だとすると、そういうものをわざわざ「ヘン」と言わなくちゃいけない理由はなんだろう?
早い話、「ヘンだ」と感じてしまうのは知性のなせるわざで、知性がなければ「ヘンだ」と言われても、ただ「どこが?」で、そのことに気がつかない。知性の目で見ると、その「ヘンなもの」は魅力的に見えるけれども、それを「ヘン」と思う知性を持ってしまった頭では、その「魅力的なもの」を創り出すことが出来ない。
山口晃さんの『ヘンな日本美術史』は、そのもどかしいようなジレンマを具体的に解きほぐしてくれます。
本文を開けるといきなり飛び出して来る、《鳥獣戯画》に対する《「上手でございます」ぶりがやや退屈に感じられてしまう》という評語に、山口さんの「複雑な状況を踏まえた明快さ」が凝縮されていて、「いかにもいかにも、その通り」とうなずきっ放しです。
おだやかな口調でどんどん過激なことを言ってしまえるのは、実作者である山口さんの強みで、おだやかだからこそ、この「過激」は本質的で、深い破壊力を持っています。その気づかれないこわさが魅力です。素直になれない日本人は、この本を読んでいろんなことを納得した方がよいと思います。
自転車に乗れないことが「できる」ことがわかる人
関川夏央
河鍋暁斎は天保初年に生まれ、明治も二十年あまり生きて東京美術学校開校の年、一八八九年に死んだ画家だ。
近代日本画は「(岡倉)天心の危機意識と同志フェノロサの理想の押し付けが生み出した外発性の高い人工的な代物に見える」という『ヘンな日本美術史』の著者山口晃さんには、河鍋暁斎の作品は、パース(遠近)が「とれない」のではなく、「とれない事ができる」絵と映った。
自転車は一度乗れるようになると「どうやっても乗れてしま」うが、そのあとは「むしろ乗れない事ができなくなる」のだと彼はいう。そうして「ムリに乗れない風をやろうとすると、とてもワザとらしく」なり、近代日本画にはその度合が痛々しいほどだ、ともいう。日本画のみにとどまらず、現代日本人と現代日本文化への批評であろう。
中国・西洋・現代日本人から見て「変わっている」「ヘンな」日本美術を、山口晃は「やあ、色んな絵が在って面白いぞ、先達は凄いなぁ」とわくわくしつつ、「鳥獣戯画」を始点に明治までを、ちょっと「ヘン」な口調で明るく批評した。
そうか、こういうジャンルがあるのか。こういう書き方があるのか。『ヘンな日本美術史』を「発見」したとき、私はまさに虚を衝かれた。
フィクションと詩歌以外のすべてのシーンで、日本語表現の可能性を広げる果敢な試みを顕彰するのが小林秀雄賞である。その受賞者ラインナップに、山口晃さんが加わってくださることの意味は大きい。
私は山口さんが、今後もこのような「ヘンな」、また「さわやかにおもしろい」批評をつづけられることを強く望むが、かりにそうはならず、ご自身の本業である絵画の制作にその情熱が向けられたとしても、このユーモアに満ちた才能を激励できるなら十分に報われた思いである。
切迫したなにか
堀江敏幸
軽くはない。肩の力が抜けているというのでもない。カルチャースクールでの語りを基に構成したものだから当たりはやわらかいのだが、一読して、少し息が詰まるような、切迫したなにかが感じられた。日本美術史における創見や新知見を披瀝するのではなく、これまで絵を描いてきて、現在も描いていて、これからも描いていくことになる人が、徐々に襲ってきた金縛りに似たものを振り払うために、否応なく言葉の力を借りていると、そんなふうに思われてならなかった。
実作者の立場を特権化しようとしているわけではないけれど、作品を観ることと描くことのあいだの身体的な感覚の隔たりは、どうしようもなく大きい。その隔たりを山口氏は縮めようとしているのだ。
子どもや初心者だけが持っている、先入観のない「前のめり」の朗らかさ。破綻の面白さ。一通りの技法を習得したのちに、それらを厭味なく回復することは可能なのか? 自転車に乗れるようになる前と後の不可逆性の譬喩は、他の芸術分野でも考えざるをえない、とても厄介な問題である。
上手が下手を装う嫌らしさは、どんな世界にもある。しかし、下手を安易に模倣しない決意と覚悟がなければ、先には進めないのだ。雪舟はその難しい一点をクリアしている、と著者は言う。雪舟の「非常に前のめりにこけつまろびつしている精神」のあり方、「途中で一息つきながら『よいしょ』という感じで描」く感覚。ここにはまぎれもない表現の喜びがある。先の切迫した想いが、その喜びにうまく覆い隠されたとき、余計なものをそぎ落とした明るい批評が立ち上がったのではないか。
かつて小林秀雄は雪舟の「慧可断臂図」について、「曖昧な空気はない。文学や哲学と馴れ合い、或る雰囲気などを出そうとしている様なものはない」と語った。画家にはこのあと、「こけつまろびつ」している様を「或る雰囲気」に頼らない絵として表現する大仕事が控えている。その成果を当然のこととして待ちながら、同時に、言葉の洛中洛外図の制作にも励んでいただきたいと、この場を借りてお願いしておきたい。
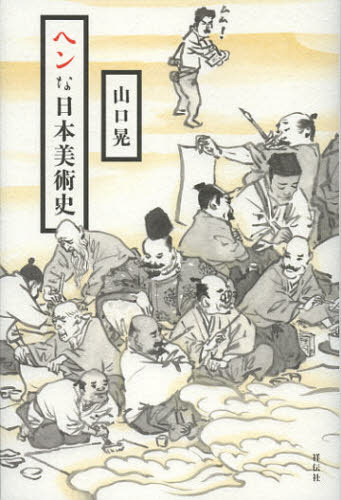
2012/11/1発売
この記事をシェアする
「小林秀雄賞」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら