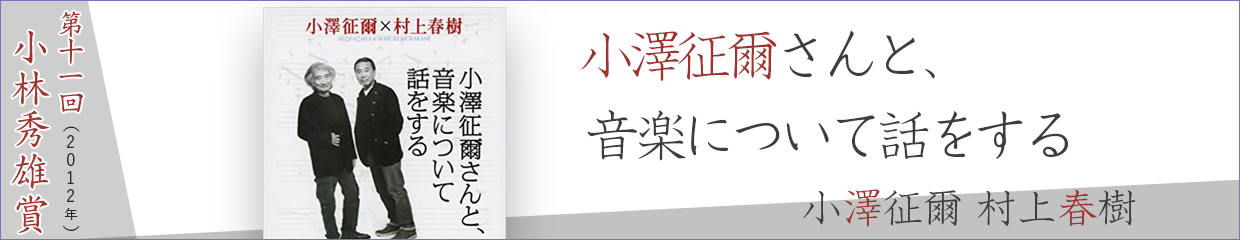インタビュー 小澤征爾
小林秀雄さん、春樹さん。
小林秀雄は「モオツァルト」という随筆を書いたから、僕にとって有名な人なんだけど、考えてみたら一度会ったことがあるんです。
一九六三年にベルリン・フィルを指揮したあと、アメリカに帰る前にパリへ寄った時に、成城学園中学の同窓生である白洲チコさん夫妻から夕食に呼ばれた。そこにいたのが小林秀雄さんで、一晩いろいろ話をしました。それで翌日、彼が泊まっているベルファストっていう感じのいいホテルで朝飯を食わしてもらった時、会うなり小林さんが「小澤君、僕はあんたの親父と友達だったんだよ」と言ってくれたんです。親父(小澤開作)は戦前、北京の小澤公館で民族宥和みたいなことをやっていたんですが、そこに何週間か泊まっていたと。「親父さんには北京でお世話になったんだ」って。そのパリでの印象が強く残っています。
もう一つ、親父は終戦直後の食糧がない時期に飴を行商していたことがあったんです、金がなくて。その飴を一缶担いで、親父が小林さんの住む鎌倉の家に届けに行ったってお袋から聞いたこともあった。だから今回の賞は遠回りの縁だなあと感じます。うれしい因縁みたいなもんだと。
この賞をいただいて、本をもう一回ゆっくり読み直してみました。いちばん良かったのが「始めに―小澤征爾さんと過ごした午後のひととき」という春樹さんが書いた長い文章。読んでるはずなのに、あわててたのか前はあんまり気がつかなかったんだけど、ちょっと衝撃的に感動しました。こんなに深く見られていたんだなと。この本に対する態度がはっきり書かれているし、もし僕がこれを読んでから話をしていれば、もっといろんなことを真面目に言えたかもしれない(笑)。
春樹さんは異常なくらいの音楽好きで、ジャズもクラシックもいろんな聴き方をうんとしてるけども、いい音楽を聴いたっていう時の聴き方が非常に緻密で、非常に細かいところまで聴き分けをしている。これは僕から見ると驚きでした。音楽家でも気がつかないようなところに彼が気がついて話題にして、そこから僕自身も一緒に聴いて掘り下げていったら、普段は考えたこともない、無意識にやっていることが僕から言葉になって表れてきました。そこが面白かった。
音楽は言葉で表すことができない、だから音楽は大事なんだというのが僕の生き方です。人間にとって音楽は何で大事かというと、言葉では表せないいろんなものがあるから。音楽じゃなきゃ表せない感情とか、雰囲気とか、精神とか意志がある。でも、春樹さんの質問にかかると、そういう言葉じゃ言えないっていうやつ、自分でも思ったことのないようなものが引き出されて、口に出していた。僕は外国に住んでいるのが長くて、おそらく音楽について話すチャンスがなかったからじゃないかと思うんです。最初のうちはめちゃ外国語が下手で、忙しくて音楽の勉強ばっかりで、どこにいても音楽だけを使ってコミュニケーションしてるようなところがありました。それに慣れていたのかも知れない。だから、春樹さんとこうして喋って、なるほどこんなことってあったのか、喋るってのはこういうことなのかと発見させられました。
話している時は、「これ、誰かが読んでも、我々が聴いてるレコードなりテープなりがないと分かんないんじゃないの?」って春樹さんに何回か言っていた(笑)。本が出てから、出てきた音源をまとめてCDにしようという話もあったんだけど、それをやる必要はないんじゃないかとも今は思っています。音がなくても、こういう聴き方があるんだっていうところは分かる。この本はあくまでも春樹さんの言葉の魔術みたいなもので、それを味わってもらえればいいんじゃないか。実際に音を聴かなくても、音楽家がこういうことを考えて、こういうことを言ってるんだと、そこだけで面白いのかなと思うようになりました。気楽に読んで、ちょっとだけ肌で感じて分かっていただければいい。音楽とはそういうものなんじゃないかな。
一つ話し足りなかったのは、あとがきにも書いたけど奥志賀高原(小澤国際室内楽アカデミー奥志賀)のこと。去年のスイスには来てくれたんだけど、奥志賀も見てくれれば、演奏家が西洋人中心のスイスと、東洋人中心の奥志賀との違いが春樹さんの中で見つけられるんじゃないかな。今年は残念なことに春樹さんのスケジュールが合わなくて、僕も体調を崩して奥志賀までは行けたのにレッスンに参加できなかったから、来年こそはぜひ来てほしいんです。
1935年9月1日、奉天(中国・現瀋陽)生まれ。桐朋学園で齋藤秀雄に指揮を学ぶ。1959年、仏・ブザンソンのオーケストラ指揮者国際コンクールで第一位を獲得。ヘルベルト・フォン・カラヤン、レナード・バーンスタインに師事。1973年からボストン交響楽団の音楽監督を29年にわたり務め、2002年にはウィーン国立歌劇場の音楽監督に就任した。2008年、文化勲章を受章。現在、サイトウ・キネン・フェスティバル松本総監督、小澤征爾音楽塾塾長、水戸室内管弦楽団顧問などを務めるほか、小澤国際室内楽アカデミー奥志賀、スイス国際音楽アカデミーを主宰。 (受賞当時)
インタビュー 村上春樹
優れた音楽と耳の精度
─村上さんとクラシック音楽の出会いについて教えてください。
村上 僕はまずジャズに取りつかれたのですが、高校時代にそれと並行してクラシック音楽をよく聴くようになりました。どうしてそうなったのか、よく思い出せないんだけど、とにかくジャズとクラシック音楽の間を行ったり来たりして、十代の日々を忙しく送っていました。レコードもよく聴きましたが、できるだけコンサートにも足を運ぶようにしました。今でも記憶している当時の公演は、まだ西側デビューしたばかりのウラジミール・アシュケナージの初々しい演奏と、クラウディオ・アラウの重厚なブラームスです。ジャズの場合もそうだけど、素晴らしい生の演奏は時間を超えてしっかり耳に残ります。とくに十代の頃は、音楽にせよ文学にせよ、良いものはいくらでも心に深く率直に染み込んでいきます。そういう意味では僕は若いときに、いろんなジャンルの音楽を分け隔てなく吸収することができて、それは幸運だったかもしれない。
─インタビューは、日本だけでなく世界のさまざまな場所で行われました。お二人の「セッション」の中で、印象に残っていることは何でしょうか。
村上 やはり小澤さんが何かあると、すぐに歌い出したことですね。そのことがいちばん印象に残っています。話の流れの中で自然にメロディーが出てきて、リズムが出てくる。こればかりはうまく文章で再現することができなくて、苦労しました。小澤さんがどのように音楽を捉え、こしらえていくかというのは、彼が歌うメロディーや、彼の足が刻むリズムを実際に聞かないと、なかなか説明しきれないところがあります。そういう意味では、全身が音楽でできているような人です。言葉や論理はあくまで補助手段に過ぎません。たとえばベートーヴェンの五番のシンフォニーの冒頭部分がどのようなリズムで成り立っているかというのを、僕は実地に身体を使って説明されて、「はあ、なるほど、そういうことだったのか」とすとんと納得できたんですが、それは文章ではとても説明できません。そういうところは他の表現手段を持ってくることで、少しでもカバーしようとは試みましたが。
─レコードを用意することに始まり、村上さんは周到な準備で小澤さんへのインタビューに臨まれ、テープ起こしや原稿構成、編集作業のすべてをご自身が手がけられました。その際、最も留意されたことは何でしょうか。
村上 最も留意したのは、僕が僕自身の意見を持って、それを小澤さんに率直にぶつけていこうということでした。僕は一介のアマチュア愛好家で、小澤さんは超一流のプロなので、二人で音楽について語るときに、僕にできることと言えば「できるだけ正直になる」ということくらいしかありません。わからないことはわからないと言う、自分がこう感じる、こう思うということは、はっきりそう口に出す。知ったかぶりもできないし、いい加減なことも言えません。だから「この次はこういうテーマでいこう」と決めたら、そのテーマに沿っていろんな音楽をできるだけたくさん聴き、それについて自分なりの考えを固めました。それにはもちろんずいぶん時間がかかります。何度も何度も同じ演奏を集中して聴き直します。でも音楽を聴くのはもともと大好きですから、そういうのはまったく苦痛ではありませんでした。むしろとても楽しかった。すごく勉強にもなりましたし。
─一年にわたる小澤征爾さんとの対話を通じて、村上さんの音楽への思い、聴き方に何か新しい変化は生まれましたか。
村上 音楽を創るのは、小説を書くのと基本的には変わりないんだと、あらためて実感したことですね。優れた音楽を創るには、まず自分の耳の精度を高め、本当に僅かな音の違いや、リズムの違いを聴き取れるようにならなくてはなりません。それが第一歩です。文章を書くときにも、それと同じ作業が必要です。僕は思うんですが、文章のメロディーやリズムは、本質的には音楽のそれと変わりありません。僕自身はキャリアの最初の段階から、文章を書く際にいつも耳を意識してきました。そこにリズムがあるか、メロディーがあるか、ハーモニーがあるか、自由な楽想があるか? そして何度も何度も納得がいくまで、耳で推敲を重ねます。
スイスのワークショップで、オーケストラを相手に小澤さんがやっていることを間近に見て、音楽を創るのも文章を書くのも、本質的なところではほとんど変わらないんだなと強く実感しました。意識を集中し、耳の精度を上げ、文体を徹底的に磨き上げていく。小澤さんの手がけるそのようなプロセスは、本当にため息が出るほど見事なものでした。分野は違いますが、同じ創造に携わるものとして、学ぶところはとても多かったですね。
1949年1月12日京都市生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。1979年、『風の歌を聴け』(群像新人文学賞)でデビュー。『羊をめぐる冒険』、『ダンス・ダンス・ダンス』、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』(谷崎潤一郎賞)、『ノルウェイの森』、『ねじまき鳥クロニクル』(読売文学賞)、『1Q84』(毎日出版文化賞)をはじめ、多くの長編小説・短編小説・エッセイを刊行。作品は世界四十数言語に翻訳されている。海外での文学的評価も高く、フランツ・カフカ賞、エルサレム賞、カタルーニャ国際賞などを受賞している。 (受賞当時)
● ● ●
選評
大病あけの、弱い風
加藤典洋
『小澤征爾さんと、音楽について話をする』。
この作品を受賞作とするのに選考委員会はひととき悩んだ。そもそも授賞とは顕彰、そして名誉の授与である。書き手(たち)はともに国際的に名高いマエストロ、ノーベル賞候補とも言われている小説家と「外形」の大きな人たち。今回は、そういうケースかどうかが、問われたのである。
しかし、この「聞き書き」の本では、こうした「外形」がきれいさっぱり、洗い流されている。それぞれに自分の仕事に精魂を傾けてきた音楽好きな二人がふつうの人になり、ふつうの言葉で、「はははは」、「うーん」(しばらく黙考)、音楽をめぐって話している。
そしてそれがこの本の味わいなのだった。
以下、私の選考に臨んでのメモから。
「大病あけの小澤の音楽をめぐる談論の風合いがよい。聴き手村上の音楽の素養の異様な広さと深さが、こういう形で―効率悪く―活用されたのは、とてもよいことで、この本を贅沢なものにしている」。
マエストロのひとときの休暇を奇貨として、六十歳をすぎてなお年少の国際的な小説家が、尊敬と友愛の心持ちに、ひかえめに切実な感情を加え、この本を作っている。その動機が、この本に、ある意味で奇跡のごとく、朝露のひとしずくの「小ささ」、「はかなさ」を与えている。大病あけの、弱い風。それには、修善寺の大患という前例もあった。
この本は、村上春樹さんの仕事である。しかし、氏にこういう仕事をさせたのは、小澤征爾さんである。最後、村上さんがスイスに行ってセミナーに参加する。その後の、教育論議で、小澤さんが、師の方法に反抗して、メソッドをもたず、その場で出たとこ勝負、教える、という個所が、いい。「でも僕はね、音楽ってのはそういうものだけじゃないんじゃないかと、ずっとそう思ってやってきたんです」「何にも用意しない」「その場で相手を見て決める」。マエストロの言葉は元巨人軍のスーパーヒーローに似ている、そういう話が出た。でも、このあたりはどこか小林秀雄とも似ている。
今回のインタビュー、対話の本は、「外形」大きな当事者の一人が自ら「企画・構成」している。これもあまり前例がないことだ。村上さんにとっても、『アンダーグラウンド』に続く一つの新しいジャンル開拓の試みだろう。表現の質、構成の妙。本の軽さ。達成度が極めて高く、新ジャンルの日本語の表現として時を得て顕彰できたことは、ラッキーだった。
演奏のような「間」
堀江敏幸
取材の速記録や録音をそのまま文字に起こすのは、難しい作業ではない。しかし、起こした文字を読むに耐える文章にしながら、我を消して対話者の言葉の色艶と現場の空気を再現し、そのうえで全体を見通しよく構成するには、相当な技術と年季を要する。
村上春樹氏は、それを極めて高いレベルで実践した。本書には、過不足のない「まとめ」を超える熱く冷静な言葉が動いている。言語にできないものをいかにして言語化するか。外からの説明や解説とはちがう現場のリズムをいかに再現するか。対話者を架空の登場人物に仕立てず、単なる取材の「対象」にもしない、ぎりぎりのところで保たれた均衡は、小説家の繊細な耳と目にすぐれたジャーナリストの嗅覚と編集の術が加わってはじめて可能になったものだ。
とはいえ、どれほどみごとな編集術があっても、聞き手の問いを受け入れる対話者の度量しだいで、言葉の色調はまるでちがってくる。村上氏の手柄のひとつは、小澤征爾という稀有な人物と向き合う機会を得て、それを素直に生かし切ったことにあるだろう。多忙な世界的指揮者が、休養のために思わぬ時間を与えられていた偶然も幸いした。無尽蔵と思われる活力を誇った人物が抑制を強いられたときの身体と言語の反応を、小説家は音楽の話に向き合うときとおなじ精度で観察し、一書に脚本のような流れを与えている。
オーケストラという複数の他者を用いつつ自分だけの声を表現する指揮者の存在は、心に巣くう他者を単独で動かす小説家からすれば、巨大な謎でもある。小説家が自然体と見せながらさまざまな角度から問いを発すると、マエストロはそれに対して少しもひねったところのない、ざっくばらんで構えの大きな受け答えをする。紹介される興味深い逸話はもとより、繰り出される「小澤語」の採取じたいがみごとな達成だが、マエストロの身振り手振りは、饒舌なようでかならずしもそうではない。
この対話集の白眉は、指揮者が小説家との思考回路の相違に気づき、それを否定するのではなく真正面から受け止めるために、しばし言葉を止める場面だろう。自分と音楽とのあいだにあるものだけを感覚的に信じるというマエストロから明確な回答が得られない瞬間の、演奏の「間」のような重さ。そこに強く惹かれた。
日常日本語の表現力と編集力
関川夏央
「小説家はマエストロを聴き尽くす」と帯にあるが、対話はこの言葉を裏切らない。
二〇〇九年暮れにマエストロは食道癌を発見され、手術を受けた。
もともと小澤征爾の娘さんと村上春樹の奥さんが友だちだった。手術後の回復期に「ひまをもてあまして居た」マエストロが村上家へ招かれ、小説家と「とっておきのレコード」グレン・グールドと内田光子を聴きながら話した。すると不思議なことにマエストロの脳裡に「想い出がどんどん出てきた」。
それが、二〇一〇年十一月に神奈川県で始まり、二〇一一年七月のスイスとパリで区切られる長いインタビューの、または長い回想と点検の、幸運な始点となった。
帯の言葉はもうひとつある。
「そういえば、俺これまで、こういう話をきちんとしたことなかったねえ」
というマエストロの発言である。小説家が「会話を録音し、自分でテープ起こしをして原稿のかたちにまとめ」たものを読んだときに発せられた。
音楽には、ほとんど徹底した無知で、話題に応じた音楽が頭の中に響くことのない私なのに、いっさいの滞りなしに最後まで読みきった。そして小説家の、年季の入った音楽との接し方に感じ入った。
だがそれ以上に、節度を保ちながらも相手を刺激して回想と点検を誘い出す日常日本語の表現力に驚いた。同時に、それを際立たせる編集力に深く魅了された。
小説家に問いかけられたマエストロは、「考え」「かなり長く考え込」んで言葉を口にした。ときに「あははははは」と「楽しそうに笑」い、またときに「時間をかけて深く考え」た末にしかし答えなかった。そうしながらも音楽について、スコアを読むということについて、一九六〇年代について、「きちんと」話そうとつとめるのだった。それは、すがすがしい態度だった。
ゆったりとしていて、その実スリリングな日本語対話を記述したこの本こそ「共著」の理想形ではないかと考えた私は、おふたりに小林秀雄賞をもらっていただければ幸せなのだが、と発想したのである。
この件で私は選考委員失格ですの弁
橋本治
私は西洋のクラシック音楽というものがさっぱり分かりません。分かろうとして分かれないものがあって、それはなんだろうと思っていましたが、この本の中で村上春樹さんの引いているシェーンベルクの言葉―「音楽とは音ではなく、観念だ」というのに出合って、いきなり「あ、そうだ」と腑に落ちてしまいました。音を聴いていても「観念」だから、なんだかよく分からない―その「観念」を具体化する能力がありません。自分はそのように西洋のクラシック音楽が分からないのだということを理解しましたが、そんなことが分かってもどうしようもありません。なにしろ、「観念」が具体化された音を聴いても、私にはさっぱり分からないのですから。
そんな私ですが、この本の中で小澤征爾さんの語っていることに耳を傾けると、「これは西洋音楽だけの話じゃないな」という気がして来ます。小澤征爾さんの身体の中には、「観念」を肉化して具現化してしまう回路が存在しているのだなと思いました。面白いと言えば、「観念」を具体化するプロセスがそこにあることで、それは洋の東西を問わず、また「音楽」というジャンルに限定されることでもないと思いました。
私が出来るのはそういう分かり方、あるいは感じ方だけで、この本の中に登場する音楽がまったく想像出来ません。クラシック音楽の好きな人が読めば、この本の中からいくらでも音楽が聴こえて来るのでしょうが、私にはその能力がなく、だからこそ、この本に対してもっと突っ込んだ感想を持つことが出来ません。もしかしたら選考委員失格かもしれませんが、それが哀しくもあります。
「別格」の輝く一冊
養老孟司
今年はとくに問題がなかった。そう言うしかないと思う。
似たような本が集まると、意見が割れてしまうが、今回は似た本がなかったから、この本が小林秀雄賞として適切かどうか、そこだけが問題だった。
でもそこにも明瞭な線引きがあるわけではない。テーマとしての音楽も問題はないし、文章表現としては絶賛する意見もあったから、そこはそれでよろしいとなると、ダメだという根拠がない。問題ないどころか、確かにその通りなのだ。主題は音楽だし、形式は対談だから、ふつうに選考に出てくるタイプの本ではない。しかも著者はお二人ともにいまさらなにを、という方たちである。
じつは私は選考の前段階で、本書だけは別に分けておいた。もともと別格なんだから、と理解していたからである。小林賞としてこういう本も結構ですよ、ということがはっきりしたというのが今回の結論である。

小澤征爾さんと、音楽について話をする / 小澤征爾 村上春樹
2011/11/30発売
この記事をシェアする
「小林秀雄賞」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら