インタビュー 橋本治
「始まり」のための「鎮魂」
思想する三島由紀夫には、ぜんぜん関心がなかった。市谷の自衛隊で彼が自決した時も、部屋で本棚にはたきをかけてて、母親が「あんた、三島さんが死んだよ」って言うから、「『三島さん』って、知り合いなの?」って答えたぐらい。その時私は二十二歳で東大生。大学闘争の時代だから自分の行く学校がなくなっちゃうことに比べれば、三島由紀夫が何を言っても、遠い他人の話でしょ。
なぜ関心がなかったかというと、直感的に「へんな芝居をしている人だな」と思ったから。芝居をせざるをえない三島由紀夫その人の内面については、考えるなにかがあるかもしれないと思ったけど、へたな芝居に付き合う必要は全然ないだろうと。耽美的と言われていた人が右傾化するなら、そこにはなにか大きな飛躍があるはずで、そこを抜かすのはへんだと思っちゃう。
私は思想に反応しない人なんですよ。他人の思想は他人の思想としてあって、思想が逆立ちしてなんとかなるとか、思想が世を覆うということにリアリティを感じないんです。十代、二十代の頃に評論や思想書を読むというのが、ある時期の通過儀礼のようなものだったけど、私にはその経験がないんです。自分が生きるというのは、自分の問題でしょう。あとは、自分以外の生きている他人と、どういった共生関係を結べるのかを考えるのが必要であって、ナマの思想に対応するという考え方自体がへんだと思っちゃう。思想書を読むんだとしても、思想の中にある自分に役立つ部分はなんだろうという、実際的なとらえ方しか私にはできない。私は物語にしか反応しないんですよ。思想する三島由紀夫には「わかんないよ、こんなもん」でしかなくて、物語をする「三島由紀夫」のなにかに反応したのが、そもそもの始まりかな。
いわゆる文芸評論を書いたのは今回が初めてだけど、他人の書いたテキストを読み込むというのは、他人のものとしてある具体的なディテールを、自分の中に組み込むということでしょう。それに対して、私は基本的に小説家だから、普通は具体的なディテールを一から全部作るんです。でも作業としては、小説を書くことと今回のような評論を書くことと、そんなに変わらない。私の場合、小説以外のものもみんな小説だと思ってもらって構わない。意味があることを人に語るということは、それ自体に意味があることだとある時期に達観しちゃったんで。だから小説だろうと評論だろうと関係なくって、それが整合性を持っていて美しい形になっていれば、それはそれでいいんじゃないかと思ってる。
何のために書いたかというと、三島由紀夫の「鎮魂」をしてあげたかったから。「可哀想な人だから『鎮魂』してあげよう」と。もしかしたら文学の目的って「鎮魂」なのかもしれない。今『平家物語』をやっているんだけど、これは「王朝」という時代のものすごく大きな「鎮魂」なんです。『平家物語』にしろ『源氏物語』にしろ『日本書紀』にしろ、歴史の体系を作っていた「王朝社会」というものが滅んでしまって、その滅んだというのをはっきりさせないと、次の時代は生まれないから、同じように「鎮魂」が必要だと思っているんです。前に行きたがるくせに、後ろに戻るというへんなことをやっているというのは、たぶんそういうことなのかなって。
私は『本居宣長』しか小林秀雄の本を読んだことがないんです。なぜ読んだのかというと、それもまたシュールな話で。その時はもう作家になっていて、別に本居宣長のことは興味ないし知りたいとも思っていなかったんだけど、「日本で一番難しい本」らしいので読んでみようかなと。作家になって頭良くなったから今なら読めるだろうと(笑)。そうしたら、それまで自分が思っていたのと全然違う構図が見えちゃったんです。
本居宣長って桜になりたがった人なんですよ。墓を二つ作って、一つに桜を植えて、そこに死骸はないけれどそこが自分の本当の墓だって。人間には実生活に即している自分と「こっちが本当だ」と言いたがる本来的な自分という二種類があって、江戸時代の実生活に即した本居宣長は実生活に殉じちゃった形だから、「死んだ後ぐらいは自由にさせてくれ」だと思ったのね。小林秀雄がそういうことを言っているから、この人もやっぱり実生活に即している自分とそうじゃない自分という分け方をする人なんだなと。でも、全集に原稿を書くために読み直したら、「あっ、実生活と自分を分けるという方法があるんだなというのを、『本居宣長』の中で言っていたんだな」と、以前と若干違うことを感じちゃった。そうなってくると、小林秀雄の言うところの「無私」というのは、それに関係することなのかなあと。
『本居宣長』の構造ってすごい不思議で、周到な迂回なんです。墓の話から始まって、「本居宣長がやっていた思想というのはこういうことであって」と言いながら、同時に「私にとっても必要なことを本居宣長はちゃんとやっているんだ」と、展開していくんだけど、結局また墓の話に戻るしかないっていう形になっている。ぐるっと回りながら、肝心なところは空白にして終らせるんですよね。もしかしたら、これが小林秀雄という人の論理構造というか批評活動なのかもしれない。そして、その空白の中に入るのは読者なんです。つまり読者を存在させるために、冷静に空白を設定させなければいけないという、美的な「沈黙」ですよね。
書き手が空白部分を「自分」で埋めてしまって、「私を崇めろ」というのはとても簡単なんですよ、ある意味で。周到に空白を残しておいて、そこに読者というものを存在させるべく、他人のための席を真ん中に空けている人っていうのはそうそういないんじゃないかな。それが小林秀雄という人の特殊な在り方なんだろうね。だから、三島由紀夫の「沈黙」を語ると「三島由紀夫とはなにものだったのか」になるけれど、小林秀雄の「沈黙」を語ると、どうしても「小林秀雄を必要とした日本人とはなにものだったのか」という方向に行っちゃうんです。
それにしても、なんで私は、突然そんなことを言い出すのかなあ(笑)。別に深く考えてたわけじゃないんだけどさ。私は口からでまかせを言うのが先だから、論理的な裏付けはその後。「書け」って言われたら困っちゃうけど(笑)。この賞をもらうという厄介さというのは、そういうこともやらなければいけないのかなと思っちゃうことだよね。だから、私は賞をもらうのは「小林秀雄賞」を最後にしたいですよ。賞をもらうというのは、責任を背負うということですから。小林秀雄というのはそれを人に要求するような名前なんだと思う。私と小林秀雄がなんか関係があるとは思っていなかったけど、突然やって来られると、「小林秀雄がして来たことをある部分で受け継ぐという責任があなたにはあります」と言われたようなもんでしょう。なんか、明日の日本を創る人材をつくるために、働きなさいって言われているような気がしないでもないですね(笑)。
1948年、東京生まれ。東京大学文学部卒業。作家・批評家。小説・評論・戯曲・エッセイ・古典の現代語訳など多彩な執筆活動を行う。著書に『生きる歓び』『宗教なんかこわくない!』『窯変源氏物語』『ひらがな日本美術史』『二十世紀』ほか。『双調平家物語』全十四巻を刊行中。(受賞当時)
インタビュー 斎藤美奈子
夏休みの自由研究みたいなものですから
ちょ、ちょっとそれは、まずいんじゃないの?——受賞の連絡を受けたときの、それが率直な感想でした。保守本流に対して横から茶々を入れるのが斎藤の役目なのに、そんな不逞のヤカラの本が小林秀雄賞なんて、文化の在りようとして間違っている。シャレにならない、と(笑)。私がそう考えるのを見越していたのか、親しい担当編集者の一人は「ここはシニカルにならず、素直に喜ぶのが得策かと」なんていうメールをくれました。
小林秀雄という人に関しては、記者会見では「こわいオジさんだと思う」なんて適当に答えてしまいましたが、私に限らず、多くの人にとっては、教科書や入試問題に出てくるコワモテの批評家というイメージでしょう。高校生くらいのときに、新潮文庫の『モオツァルト・無常という事』なんかを、でもみんな読んじゃったりするんだよね、私ぐらいの世代だと。もっと下の世代になると、名前も知らない人もいるかもしれない。それでも文芸評論を書きたいと思うような変人の間では「批評の神様」という認識はいまも根強くある。「小林秀雄論」で群像新人賞の評論部門に応募してくるような人、という言い方を私はしてるんですけど(笑)。
小林秀雄賞は、創作以外のすべての文章を対象にしているのだと理解しています。今回の受賞作はたまたま二本とも文芸批評ですが、第一回は本当ならば科学評論みたいなものが一本入るとおもしろかったよね。日本に科学ジャーナリズムってないじゃない? 小林秀雄賞がサイエンスも視野に入れた賞だということが定着したら、科学ジャーナリストを志す人が増えるかもれない。そういう賞ってほかにないでしょ。せいぜい大佛次郎賞くらいかしら。私には踏破できない分野ですけれど、若い人が張り切ってくれるといいなと。
私自身は大学も経済学部だし、文芸批評家を目指していたわけでは全然ありません。そもそもいま私がやっていることが文芸批評かどうかもわからない。文の芸を評論するのだから文芸評論家でいいかって、そのくらいの気持ちです。八〇年代は編集者として子供向けの本や実用書——図鑑や料理の本などを主に作っていました。八五年ころに、評論家の芹沢俊介さんが主宰する社会風俗批評の同人誌に誘われて、二年間ほど署名原稿を書いてたことがあります。それを読んだ筑摩書房の編集者から「もっと何か書きなさい」と言われ、「はい」って返事をしたんですけど、そんなことはすぐ忘れ、一〇年間、仕事に忙殺されていました。それ自体、とても楽しかったですし。ところが九〇年代に入ってバブルが弾け、仕事が少し減ったので、できた時間で書き進めて完成したのが初めての本『妊娠小説』です。ドラマチックな裏話は何もない。
私は文学少女でもなかったし、小説をまあまあ読むようになったのも大人になってからです。ちょうど構造主義批評とか、新しい批評理論が出てきたころで、そっち経由で小説も読めるようになったという感じです。「妊娠小説」というテーマも、テレビドラマなんかでもこういう話が多いよなあって、たまたま思いついただけ。アイディアは自分の中にもともとあるわけではなく、何かの対象に出会って「これって何?」と感じる、その疑問がすべての出発点ですね。まあ、やり方としては、夏休みの自由研究と同じです(笑)。疑問を起点にいろいろ調べていくと、思いがけない発見があって「こいつは面白い」と感じる。その面白さを読者にも伝えたい……それが仕事になってしまったようなものです。一冊で謎がすべて解けるような資料は当然ないし、それがあったら私が出しゃばる必要もない。未知の領域に分け入って、ほらほら、こんなの見つけちゃった、と言いたいんだと思いますよ。だからプロセスごと読者に開示して、臨場感を読者と共有するしか手がない。読者をノセるには、自分もノッていないとダメです。
『文章読本さん江』は、思いつきの時点から八年ぐらいかかっていますが、実質的に書いていたのは三年ぐらいかな。でも、テーマが念頭にあるとないとでは大違い。頭の中にアイディアの片鱗があれば、資料も蓄積していきます。あとは調べて書いて考える——この繰り返し。書き始めてやっと「何がわからないか」が明確になる。かなり思考が進んだ段階で、一度捨てた文献を改めて読み直したりすると、また別のものが見えてくる。構成には苦心惨憺しました。先が見えなくなって、途中で何度も暗礁に乗り上げた。そういうときは原点に戻る。と、新しい糸口が見つかって、それがもう一度、推進力になるわけです。文体模写をしてみたり、サービス精神を発揮していると言われるんですけど、それは子供むけの本を編集していたなごりですね。子供ってものすごーーーーく面白くないとついてこない。これ以上、厄介な客はありません(笑)。我慢しながら読んでなんかくれませんからね。その癖がついているから、もっと淡々と書くのがカッコイイんだなとわかっていても、ついつい過剰なサービスをしたくなる。
調べものをするときは、図書館も使うし、古書店にも通うし、ありとあらゆる手段を使います。
『文章読本さん江』に関して言えば、引用した本は百冊ぐらいですけれど、当たった資料を数えたら何百冊の単位ではきかないかも。大変じゃないとは言いませんが、私にとってはむしろ、資料なしで無から有を生み出すことのほうが百倍難しい。もともと教養のある人は、放っておいても知識の泉が湧き出てくるのでしょうけれど、なにせこっちは夏休みの自由研究だから、いちいち仕込みから始めるわけですよ。積み上げた資料からこれぞというものを発見したときは「やった!」です。取捨選択して、分類して、という作業自体は大変ですが、でも、教養の蓄積のない人は他人のフンドシに頼りなさいって言いたいです(笑)。「労働」でなんとかなるよ、って。何かアイディアを思いついたら、とにかく片っ端から資料を集める。着想から資料に向かい、資料からまた構想がふくらんでゆく——循環していくんですね。まあ当たり前のことですが。
私の書き方について、よく「バッサリ斬って捨てる」とか「舌鋒鋭く」なんて言われますが、本人はあんまり斬って捨てているつもりはない。というか、根っこにあるのは案外「自虐」かもしれないと、最近思うようになりました。他人事なら放っときゃいいのに、ツッコミを入れずにいられないのは、対象の中の変てこな部分を私自身も共有していて、じつはそこに一撃を食らわせたいんじゃないかなと。明治以来の日本の女性像を辿った『モダンガール論』も、自分の内なる欲望を拡大鏡で探っていたようなところがある。具体的に私自身のことを書く気はまったくありませんけれど、それではなぜ文章読本だの女性史だのにこだわっているのかというと、やっぱりそれは自分に関係のある分野だからとしか考えられません。だいたい、人の頬っぺたを叩いたときは、叩いた自分の手も痛いんですよ(笑)。
『文章読本さん江』を出してから思ったのは、文章読本はまだ過去にはなっていないということでした。文章、あるいは文学でもいいですが、それらが文化の中心的存在だった時代の権威は、もう残っていない。ただ、権威の形骸だけはまだ辛うじて生きています。権威なんて崩壊してしまえとも思う半面、私みたいにそれをつつきたい向きにとっては、権威の方がどっしりと構えていてくれないと困るんです。斎藤ごときがチョッカイを出したくらいでガタガタするなと切にお願いしたいです(笑)。
1956年、新潟市生まれ。成城大学経済学部卒業。文芸評論家。受賞作の他、著書に『妊娠小説』(筑摩書房、ちくま文庫)、『紅一点論』(ビレッジセンター出版局、ちくま文庫)、『読者は踊る』(マガジンハウス、文春文庫)、『あほらし屋の鐘が鳴る』(朝日新聞社)、『モダンガール論』(マガジンハウス)、『文壇アイドル論』(岩波書店)、『戦下のレシピ』(岩波アクティブ新書)がある。(受賞当時)
● ● ●
選評
ここには批評が無償の行為として敢行されている
加藤典洋
橋本治さんの『「三島由紀夫」とはなにものだったのか』は、「橋本治」が「三島由紀夫」について、ふいに「その気」になって試みた、一場の考察の記録である。
「ちょいと一杯」のつもりではじめたが、後を引き、数ヶ月の間、それにのめりこんだ。何があったのか、橋本さん自身にもよくわからなかったはずだが、察するところ、彼はそこで、誰もが登攀していない未踏峰を発見し、誰もが見ていないところでこれを踏破し、誰にも見られないまま、そこから、下山している。この本が透明人間のように誰からも見えないのはそのためだ。わたしはこの本を読んで、一人の文芸評論の徒として、居ずまいを正させられる気がした。そこでは、批評が無償の行為として敢行されていたからである。
この本の特徴は、何と言っても新しさが強靱だということだ。三島論としてこの本は、『仮面の告白』から『豊饒の海』までの約二十年間三島が自分の前に置いた問題とは何だったか、そこでのカギは何か、またそのこととわたし達の関係は何かを、普通の人のぶつかる問題として考察している。パブロ・カザルスの弾くバッハの無伴奏チェロ組曲を聴くと、バッハがけっして大バッハと聞こえない。バッハというただの人の曲に聞こえる。そういうバッハとのつきあいを可能とするために、カザルスは数十年間毎日、曜日ごと六つの組曲を日課として練習したのだが、この本での橋本さんと三島の関係は、なぜか、この逸話を思い出させる。ここでも三島はまったく橋本さんに怖がられていない。これだけ深い、未曾有と言ってもよい、三島理解を橋本さんに促したものは、何だったのだろうか。
また、思考する散文として、この橋本さんの文章は、小林秀雄以来の批評とまったく無縁である。これもホント言えば、信じられないくらい、新しい。その証拠に小林の行文とは違い、彼の文章には、名言として取り出せるような一行はどこにもない。これは、小林が何かそれまでにないものを彼の批評で作ったように、ここで、これまでにない何かがやはり橋本さんの手で作られているということである。この本を読むとけっして収斂しない思考の強さというものがあることがわかる。この本は批評として柄が大きい。竹ではない、ハイテク・セラミックの感触。わたしは、小林秀雄にはじまった文芸批評と切断されたところから、新しくまったく別種の批評が生まれ出る瞬間に立ち会っている気がして、もしこういうものに小林の名前を冠した賞が授与されるなら、この賞にとって、幸運なことだと思ったのである。
この二作を選ぶことで、この賞の間口の広さも示せた
河合隼雄
小林秀雄賞の第一回ということで、受賞作がなければどうするか、という心配がまずあった。ところが、ふさわしい作品が二作あって、有難いことであった。小林秀雄の名を冠する賞にふさわしいと私が感じるのは、何らかの意味で新しい世界を切り拓く、切れ味のよい論法である。その点で受賞作は二作とも申し分なく、この二作を選ぶことで、この賞の間口の広さも示せたのではないか、と思う。
心理療法家というものは、どんな人に会っても、「うん、わかるその気持」というレベルで対話ができないといけない。私がこの仕事をはじめて、一番それができ難いのが、男性の同性愛者であった。スイスで訓練を受けていたとき、同性愛のクライアントを受けもち——しかもドイツ語で——、困ったあげくに、三島由紀夫の作品をあれこれ読んだが、なかなか決定打が得られなかった。今回、橋本治氏の三島由紀夫論を読み、「同性愛の才能」という語を見て、うーんとうなってしまった。
音楽の才能のない者は、いくら練習しても駄目である。当時の私は同性愛の才能が無さすぎた。音楽の才能の無い者は音楽家にはなれないが、音楽の鑑賞は相当にできる。私も年齢と共に、同性愛の人とも大分会えるようになったのも、鑑賞力が相当な努力で身について来たからなのだろう。
橋本治氏の本書における論の立て方も面白い。俗に「入れ子構造」などというが、この場合、入れ子から箱を取り出すと、取り出した途端に前の箱より大きくなる、という仕掛けになっている。入れ子の箱がだんだん小さくなって終り、とはならず、どんどん大きくなって、「じゃこのへんで」というところで一応おしまいにするような、面白い本である。続けようとするなら、また続くだろう。
斎藤美奈子氏の本は、大の男たちを女剣士がバタバタと斬り倒すところが、何とも勇ましい。もっとも「文章読本」を書く女性もいるが、その数の少ないことは驚くべきである。
ところで、剣士の用いる剣に男ぶりと女ぶりはあるのだろうか。このあたりはよくわからないが、この書物に関しては、剣は男ぶりだが、それによる斬り方というよりは舞い方が女ぶりのような気もする。もっとも、このような、男と女による分類を試みること自体がオジンくさいと言われそうである。
バサリバサリと大男を斬って捨て、返す刀で、この女剣士は何を斬るのかな、と思ったりする。
個性的意志的かつ明朗な作品
関川夏央
「文章読本」というジャンルへの着眼が、まず水際立っている。存在さえ忘れていたが、たしかにそれはあった。そうして、いまだひそかに繁栄している。
「文章読本」群が時代をつらぬいて共有する、いわば棒のごときものは、文章(書き言葉)が一番、印刷された言語がエラい、作家と文学作品が頂点に立つという、「文芸至上主義」ならぬ「文芸最上位主義」だ、と斎藤美奈子さんは見てとった。一九三〇年代、五〇年代末、七〇年代末が「文章読本」の画期で、この時期にいくつかの「名作」が書かれた。それはいずれも、書き言葉の君臨が新しいメディア(三〇年代のラジオ、五〇年代末のテレビ)によって、また近代青年につきものの教養主義が落日すること(七〇年代末)でおびやかされた時期であった、という指摘は肯綮にあたっている。
「文章読本」は「文芸政権」の危機意識の産物であったのだな。文芸を無前提的に信頼しているのに、同時にその先行きに不安を禁じ得ない読者がそれを読み、一定の安心を得て、しかるにその文章作法の影響を受けなかったわけがよくわかった。文芸的であることをおおっぴらに自慢してはばからないベテラン新聞記者(社内では敬遠されつつ保護される)が、昨今これをしきりに書きたがる理由がよくわかった。
生まれながらに「文芸最上位主義」の呪縛から自由な斎藤美奈子さんの実証は周到だが、文体は軽快で平易だ。それでいて決して下品の側に転落しないのは、知性の技である。その自己相対化を怠らない知性は、おのずとユーモアを呼び、読者を元気づける。評論もまた娯楽たり得るのだとあざやかに印象させる。
元気づけられた私は、斎藤さんにさらに元気でいてもらいたいと思う。そして、「こう言われたら、こう返す」などと備える批評家の習性(男のディスクール)を忘れ、鋭敏な明るさで読者を刺激しつづけてもらいたいと願う。明朗さこそが、批評という物語を書くときの十分条件だと考えるからだ。
小林秀雄賞は文芸評論の賞ではない。フィクションとドキュメントを除く、すべての言語表現を対象としている。今回は橋本治さんと斎藤美奈子さんの作品、いずれもが文芸評論のかたちをとって、かつその枠を破る、というか、枠などにハナからとらわれない、個性的意志的かつ明朗な仕事が私たちの前にあった。喜ばしいことだ。
艶のある論理、そして速度とリズム
堀江敏幸
橋本治氏の『「三島由紀夫」とはなにものだったのか』は、博引旁証にたよらず、作品を徹底的に読み込み、考え抜いて、その軌跡を自分の言葉で運んでいく作業にほかならない「思考」の、最も基本的な喜びを感じさせてくれる力作だと思う。「三島由紀夫が最も拒絶した作家は、他ならぬ三島由紀夫自身だった」という逆説を必要としていた時代の奇妙さ、そしてその奇妙さの必然性が、ねばりづよい論理展開のなかで、はっきりと見えてくる。虚偽を虚偽として生きた作家の寂しさが、読後、生々しく伝わってくる。
語義矛盾を怖れずに言えば、ここにあるのはじつにアクロバティックな直線だ。しかも線上には、語り手の言葉の使い方に潜む感情のよじれを解きほぐすきめ細かな観察が、ほとんどミクロ単位で刻まれている。だから、文章にではなく、論理に艶が出る。艶のある論理に支えられた『豊饒の海』の読解は、三島由紀夫がスターだった時代を知らない、橋本氏より若い世代の読者にとって、今後ひとつの指標となるだろう。
斎藤美奈子氏の『文章読本さん江』も、橋本氏とは別種の直線に貫かれた作品である。「文章読本」と呼ばれる指南書のジャンルがどのように誕生したのかを、膨大な資料を参照しながら、その重みを少しも感じさせない速度感あふれる文体で明らかにしていく。とくに生彩を放つのは、「文章に実用的と芸術的の区別はない」とした谷崎潤一郎の『文章読本』に、両者の区別を謳った明治期の作文教育に対する反撥を読み、戦前の「綴り方」に「私小説」の匂いを嗅ぐあたりだ。例文の捌き方、揶揄やパロディをまじえての読解のリズムは、「文章読本さん」を主人公にした一篇の小説を思わせる。また、そういう書き方でなければ、突っ込んだ剣先が自分に跳ね返ってくる危険を回避するのは困難だったろう。「文章読本」そのものを語ろうとする発想が、すでにして新しい。
批評には、公平・客観・中立なんて要らない
養老盂司
橋本治氏の作品は、全員にまったく異論なく推されたと思う。こういうことは、わりあい珍しい。すでに『宗教なんかこわくない!』で新潮学芸賞を受賞されていることが話題にはなった。しかし、だから授賞しないという意見はなかった。それにこの二つの作品は、性格と内容がかなり違う。『宗教』のほうは橋本氏が読者をより意識した、いわば啓蒙とでもいうべき作品だが、今度の『三島由紀夫』はより独白に近い。読者の説得よりは、自分の説得である。当然だが、橋本氏の三島理解なのである。だから力が入っている。私は文芸批評の素人だが、批評はそれでいいと昔から思っている。NHKじゃあるまいし、公平・客観・中立なんか要らない。
斎藤氏の『文章読本』はすっと読めて、笑えた。これは大切なことである。真面目な主題を扱って笑える本は、この国には少ない。文章読本を扱うのだから、文章に工夫がなければ、推しようがない。口語体が出来上がる頃の、明治の先人たちによる語尾の文体模写は、パロディーの傑作である。本当は内容の吟味を述べるべきであろうが、せっかく笑わせてもらえる本を、真面目に評論するのは野暮である。だからこれ以上いうことはない。気になったのは、選考委員に女性のいないことである。女性独自の視点は、やっぱりあるはずである。女性が不在である以上、著者を除く女性の視点が、最終選考に反映されていないことを注記しておく。

2005/10/28発売
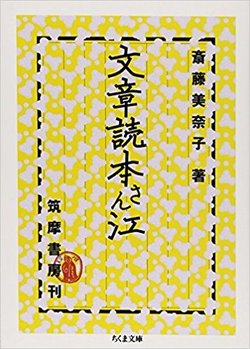
2007/12/10発売
この記事をシェアする
「小林秀雄賞」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら





