インタビュー 岩井克人
「現実」が「抽象」に追いついたんです
私の書いたものが小林秀雄の名を冠した賞をもらえるとは思ってもみなかったので、驚いたというのが正直な感想です。私にも文学青年だった時期があって、当時の文学青年のすべてがそうしたように、小林秀雄の著作は読んでいます。中でも『様々なる意匠』にある一節、「世捨て人とは世を捨てた人ではない、世が捨てた人である」というような逆説的な言い回しが印象に残っています。
小林秀雄は、個別性とか人々の生活実感に価値があると思っていて、言葉は最終的には負けてしまうというようなことを書いていたのではないでしょうか。私が小林秀雄にイカレずに、アカデミックな道を選んだのは、資質の違いもありますけれども、志向性の違いが大きな理由だったと今になって思っています。私は、生活実感の裏にある言葉や言語、つまり個別性の背後にある普遍性を探りたいと思っていましたから。矛盾や対立の背後にこそ論理があるんだという私の見方と、小林秀雄の見方はちょっと違うんですね。
ただ、私と小林秀雄の共通点は、ジャーナリズムに対する見方にあるのかもしれません。私は学問をやっているけれども、一番怖い読者がいる場、つまり最も知的で強い批評のある場は、近代の日本においてはジャーナリズムだと思っているんです。その点、小林秀雄も同じだったのではないでしょうか。彼の批評は常にパブリックに向けて書かれていたし、そのことがまさに彼の批評を批評たらしめていたと思うのです。アカデミックな論文を発表する場というのももちろんそれなりに怖いのだけれども、それでもやっぱり、日本で一番怖い場はジャーナリズム、つまりパブリックな場であって、そこでこそ知的な勝負ができると思っています。そういう意味で、この賞を受賞できたことは非常に嬉しいですね。
受賞作は、三十年以上研究してきた資本主義論と十五年以上研究してきた法人論が、編集者によるインタビューを通してハッピーな形で結びつき、できたものだと思っています。私としてはもっと学問的な本にしたかったのですが、平凡社の担当編集者、西田さんの「サラリーマン、サラリーウーマンにこそ読ませたい」という上手なおだてに乗ってしまいました(笑)。そのおかげで、それまでの本と違って、現実の社会にコミットした内容のものになりましたね。
今回初めて話し言葉で本を書いたのですが、これまで私が書いてきたものは、抽象的で独り善がりで、よく水村(編集部註・小説家の水村美苗氏)に「独りで踊りを踊っている」と言われるぐらいで、極く限られた読者しか意識していなかったかもしれません。ところが今回は話し言葉で書き、かつインタビューが基になったということもあって、これまでと違って、より多くの人に読んでもらおうという意識、現実に責任を持とうという意識が表れたのかもしれません。
元々私は科学少年で、それから文学青年になったのですが、研究対象を決めるときにそのどちらもやりたいと思っていて、結果、足して二で割って、社会科学の道を選んだのです。そして、研究を進めるうちに、抽象的な論理の面白さに突き動かされてしまいました。でも歳をとってくると、現実に対する興味が湧いてきて、同時に自分が生きている社会に対して、責任感を感じるようになるんですね。自分としては籠って好きなことを書いている方が好きなのですけれど、その一方で現実とつながっていなければいけないという意識もどこかで持っているんです。たまには抽象的なものから離れて、ものを考えてみようかなと。
不思議なもので、私が抽象的に考えていたことが、実際に現実で起きたりするんです。私はずっと抽象的な形で貨幣とか資本主義について考えてきました。そもそも資本主義というのは、収入から支出を引いた差異が利潤であるという単純な原理で動いていて、それ自体が非常に形式的なものです。その現在形であるポスト産業資本主義になると、差異を作って利潤を生むという純粋に形式的なものになります。それまで私の考えていたことは、まったく現実と遊離していると思っていたのに、現実の方がより純粋で形式的なものになってしまった。私が現実へのコミットメントを意識した理由には、そういったこともあると思っています。
受賞作のテーマである会社と法人について研究を始めたのは、一九八〇年代の終りにプリンストン大学で日本経済を教えることになったのがきっかけです。向うの英文科の人に文学批評の論文が評価され大学に招かれた水村に「婦唱夫随」でついていって、私も職を得るため、大学にアプローチをしました。そこで出された条件が「日本の経済について教えてくれ」というものでした。それまで私は抽象的なことばっかりで、日本経済の実態なんてさっぱり。それで慌ててにわか勉強を始めて(笑)。
そこの学生に、日本的な資本主義を説明しようとして、日本の会社について調べたんです。すると、「法人」という普遍的な概念に行き当たりました。何だかおもしろそうだなと、どんどん調べていくうちに、「法人」というのは、「ヒトでもモノでもある」という形而上学的なナゾに満ちた非常に不思議なものであることがわかったんです。そして、この、法人の「ヒトでもモノでもある」という二重性が、日本の会社システムとアメリカの会社システムの違いをよく表していることに気づいたんです。
ちょうどその頃、日本はバブル経済の最盛期で、「日本的経営バンザイ」とさかんに喧伝されていました。しかしバブルが崩壊すると、いつのまにか「アメリカ型の経営こそがグローバル標準だ」に変っていて、気づいたら周りに日本の会社について調べている人がいなくなってしまいました。そういった状況の中、それまでの「法人」の研究が、あるアクチュアリティをもって、日本経済が陥っている苦境の構造的問題の解明につながったんです。同時に、礼賛されているアメリカ型の株主主権論は、私の研究からすると、理論的誤謬に過ぎないということもわかってきました。
その一方で、以前から研究をしていた資本主義論からも、アメリカ型経営の限界にアプローチできたんです。差異からしか利潤が生まれないという資本主義の純粋形であるポスト産業資本主義では、ヒトにしかその差異は作り出せません。機械をもっているだけでは利潤を生み出せないのです。しかも機械はおカネで買えますが、ヒトはおカネでは買えない、ということは、おカネの価値が相対的に下がります。この二つ、つまり「法人」の話と、おカネが資本主義の中で弱まってきたということをうまく結びつけたら、おカネが一番強いという株主主権的なアメリカ型経営は、これからの時代にフィットしないのは明らかなんです。
そうしたいくつかの偶然の重なりによってこの本が生み出されたと思うのですが、日本の経済や会社の未来を危惧している社会人や学生の不安を拭うことができれば嬉しいですし、彼らにこれからの見取り図を提示できればと思っています。かといって盲目的に「日本的経営の復活だ!」というふうにとられるのも、ちょっと違いますけれどもね(笑)。
1947年生まれ。東京大学経済学部卒業後、マサチューセッツ工科大学大学院にて博士号を取得。イェール大学助教授、プリンストン大学客員準教授などを経て、89年より東京大学経済学部教授。03年9月まで同大学経済学部長を務める。著書に『ヴェニスの商人の資本論』『貨幣論』(1992年度サントリー学芸賞を受賞)『二十一世紀の資本主義論』(以上すべて筑摩書房)、『不均衡動学の理論』(岩波書店)、共著に『資本主義を語る』(講談社)など。(受賞当時)
インタビュー 吉本隆明
沈黙しないという原則を作ってくれた人
賞というのは、これから新しい仕事をしていく人への励みになるものだと思うんです。ところが僕は今、半年ぐらい先のことしか考えられない。だから今回の賞は、香典がわりじゃないかって思ってるんです(笑)。
ただ、小林秀雄という人は僕にとって特別に大きな存在で、旧制米沢高等工業学校時代には「追っかけ」のようにして読んでいました。どこの雑誌に何かを書いた、と聞けばすべて探し出して読んでいました。その小林さんの名前を冠した賞ですから、これは大変ありがたい。これ以上に望むものはありません。ですから躊躇することなく、ありがたく頂戴することにしました。
旧制高工では、一年生は全寮制でした。寮生には台湾からの留学生もいて、その中に台湾の留学生で湯さんという人がいました。彼が小林さんの『ドストエフスキイの生活』を持っていたんですね。まだ一年生の時です。「いい本持ってるじゃないか、読みたいから貸してくれないか?」と僕が言ったら「あげるよ」って、くれたんです。それがきっかけで小林さんの本を集め始めました。東京に帰ってくるたびに神田の神保町の古本屋を探し歩いて揃えていった。
旧制高工に入るとすぐ戦争が始りました。戦争中に小林さんが書いていたものは古典論が多かった。「実朝」「徒然草」「平家物語」「無常といふ事」。読むたびにびっくりさせられました。国文学者の古典論とはまったく違う。中世の人間を、目の前の生身の人間のように描き出す。この文章の力は凄いとしか言いようがなかった。
戦争が終わると今度は「モオツァルト」でしょう。あの頃の小林さんは、文学というよりも音楽や絵画のほうに行ってしまって、もう文芸批評はやめてしまうのかなと思ったりもしました。保田與重郎もあまり物を言わなくなるし、横光利一も亡くなってしまうし、僕が追っかけていた人たちは、皆一様に口が重かった。戦中戦後の小林さんの姿は、そういう意味でも強い印象があります。
漱石を読み始めたのも旧制高工時代からです。つまり、だいたい僕は文学書を読むような男じゃなかったんですよ。漱石すら読んだことがなかった。ある日、学校で仲のいい奴と言い争いをしていたら「おまえは赤シャツだ」と言う。「赤シャツって何だ?」って聞いたら「漱石の『坊っちゃん』に出てくる嫌なヤツだよ」。癪だから読んでやろうと思って、東京に帰ったとき神保町で漱石の『坊っちゃん』を探したんです。そうしたらたまたま店になくて、そのかわり『硝子戸の中』があった。これを買って最初に読みました。
重たい文章でしたね。でもどこか資質が自分に似た人だという印象を持った。それから岩波の全集を集めてきて、すべての作品を読んでいきました。
そうやって読み進めるうちに偉大な作家だとわかっていったんですが、ますます、スケールは違うけど資質が自分によく似ているという印象が深くなりました。考えてみると、自分の仕事には細かいところで漱石の発想を借りているなと思うところが少なくありません。
いちばん好きなのは『門』です。最初に読んだときから今にいたるまで変わりません。
漱石を論じたもので言えば、まずは小宮豊隆とか森田草平のものがありますが、これは遠慮もあるし、持ち上げすぎのところもあるし、言い足りない部分もあって、どこか断片的なものになっている。戦後では平野謙、荒正人といった近代文学の人たちの仕事もあった。これにも教わるところはありました。でも江藤淳という人が出てきて、『夏目漱石』を書いた。これを読んだら、見事に漱石が総合的に論じられていて、「あ、こういう本が出てきたら、もうオレはこの本があれば充分だ」と思っちゃったんですね。続いて『漱石とその時代』も書かれていったし、漱石について書く気持ちは起こらなかった。
江藤さんの後にもいろんな漱石論は現れましたけど、これはと思ったのは蓮實重彦さんの『夏目漱石論』ぐらいですね。「雨と遭遇の予兆」とか「横たわる漱石」とか、よくこういうことに気がつくなあ、と感心しました。やっぱり映画的な視点というか、あれほど特異な漱石論は他にはありません。ますます僕の出番なんかない。
ところが、筑摩書房の編集者が「漱石についておしゃべりをしてくれませんか?」と言ってきたんです。書くんじゃなくてね。漱石については繰り返し読んできたからしゃべることはいくらでもあるよ、すぐにでもできるよ、とパッと引き受けたんです。作品論をしゃべるのなら自分でもできるだろうと。
だけど誤解されると困るんだけど、僕はおしゃべりは苦手なんです。だから準備はする。漱石の個々の作品のどの山場を重点に話せば、細かく論じなくてもその作品について充分伝えることができたに等しいか、とよくよく考えて、ポイントだけをノートに書いて講演に臨むという方法です。しゃべるのなら楽、というのではなくて、自分としては大変な緊張感があった。
本にまとめる段になると、書き言葉と話し言葉の中間にある文体を作れないか、とかなり意識的に考えて、削ったり書き加えたりしました。全面的に書き直すのではなくて、話し言葉の緊迫度は残して、単なるおしゃべりの癖みたいなものは整理する、というやり方です。これで通してみたら、僕としては新しい文体を会得したと思うぐらいの成果があった。これは自分のなかで新しい方法論にもなって、そのやり方でもずいぶん本を出しました。だけど古くからの僕の読者のなかには、「あいつ、つまんねえことをしゃべって本にするようになっちまった」と否定的にとる人もいて、熱心だった読者を失う契機にもなったですね。
ただ、しゃべることについては僕なりの理屈があるんです。それは小林さんの話に戻るんですが、僕の旧制高工時代、つまり戦争が激しくなっていって、自分はこれからどうやって生きていったらいいのかがわからない時に、小林さんでも横光さんでも太宰さんでも、自分が追っかけていた人たちが、何でもいいから発言してほしいという気持ちが強かった。もし何かしゃべってくれたら一言一句聞き漏らすまいと待っていた。しかし彼らは黙っていたんです。そのいっぽうで戦争に負けた途端「これからは平和国家だ」なんて新聞にサッサカ書いている連中もいた。ああいうのにはなりたくねえしな、とも思った。
つまり優れた文学者というのは、そういうときには沈黙する、とわかるんです。だから小林さんに不服があるわけじゃない。だけどその頃の自分を思い出すと、しゃべりにくければしゃべりにくいほど、そのことについて何か言ってくれたらこっちはどんなに助かったかわからない、という気持ちは残った。それならばオレがもしそういう場所に立つことがあったら、遠慮せずに言うことにする、嫌だな億劫だな、という時はなおさらしゃべることにする。これを自分の原則にしよう、と決めたんです。
そのきっかけを作ってくれたという意味でも、小林秀雄という人は、僕にとって今も大きな存在であり続けていると思っています。
1924年東京生まれ。東京工業大学電気化学科卒業。詩人、批評家、思想家。主著に『固有時との対話』、『マチウ書試論』、『擬制の終焉』、『高村光太郎』、『丸山真男論』、『言語にとって美とはなにか』、『共同幻想論』、『源実朝』、『心的現象論序説』、『最後の親鸞』、『初期歌謡論』、『悲劇の解読』、『マス・イメージ論』、『重層的な非決定へ』などがある。著作集としては、『吉本隆明全著作集』全15巻(勁草書房)がある。2012年没。
● ● ●
選評
今年も二作
加藤典洋
吉本隆明さんの『夏目漱石を読む』は、一九九〇年から九三年にかけて行われた四回の漱石作品をめぐる講演記録を、おそらくは二〇〇二年の弓立社による音声記録のCD盤の刊行をきっかけとして、新しい観点から再編成し、書き改めている。内容は、『吾輩は猫である』から『明暗』まで、主要十二作を通観する。読んでみると、一九九六年の水難事故以後、一部視覚的な不自由に見舞われることになった著者にとってのこの総まとめの作業が、内心深く期するところある、渾身の試みであったとわかる。なぜこの時期、このような本が生まれたかは、わたしの読後感からは明らかであって、集中の白眉は、一九九三年、この一連の漱石講演の掉尾を飾る、『門』『彼岸過迄』『行人』の三作を扱う「不安な漱石」である。この講演での、独り相撲にこそ漱石の文学の本質があり、そのことに漱石が自覚的だったという『彼岸過迄』の取り出し方が、鮮やか。解決が偶然を交え、偶然に助けられてやってくるという『門』の指摘も、深い。この講演は、上記弓立社の音声版刊行でようやく記録にとどまった。たぶんは編集者の手で活字化された講演記録を示されて、著者は、そこでの自分の説を面白く感じ、長年自分の岸辺に横たわっていた大きな舟が、ぽっかりと離礁する、気持の高まりをおぼえたのではないか。江藤淳氏の『夏目漱石』以来、近年のわたし達もまた、数多くの漱石像をもつが、本書の提示する独り相撲をとる漱石、独我論的な漱石という像が、わたし自身の現在の漱石観には、一番ぴったりとくる。読み手であるわたしが、静かに励まされる本だった。
岩井克人さんの『会社はこれからどうなるのか』も、一見すると、語り下ろしの軽い本のようだが、大変な野心をひめた作品である。ハイスピード、ハイテンションの時間を生きる経済学の最突端の知見が、こうした深い、ゆったりした流れの中にしか棲息しない一般の生活人の生き方への配慮をともなうことは珍しい。読んでみると、現在のように経済的な事象が深く人々の生の基盤を腐蝕し、傾かせている時だから、「会社」という現代日本人にとって重大な意味をもつ“場”を、純粋に学的な考究の対象にすえつつ、そこに生きる普通の人間の問題に目を向ける本書のような経済学を内側から揺るがす試みが生まれてきたのだとわかる。経済の論としてユニークであるほか、これが日本論、生き方の論ともなっているところに、一歩踏み出た本書の特長がある。選考委員の一人から出た、日本はかつての場たる“家”を失い、次に掴んだ“会社”をも失いつつある、この本から一つのシンポジウムが構想できる、という指摘が、本書とわたし達の接点をよく示している。語りは平明。経済学が、ここでは経済の雲の外に突き出た頭部から見下ろされている。ここにもインタビュー記録からはじめて、これを書き直してなったという本書の方法的な堅固さが、光っている。面白い、意欲的。画期的、と言ってもよい。わたしはこの経済書を、文学的作品として読んだことを断っておきたい。
日本人の生き方に対して異なる角度から照射した二作
河合隼雄
第一回の二作に続いて、今回の二作を選ぶことによって、小林秀雄賞の幅の広さ、奥行きの深さがよく認識されたと思う。
両書とも話し言葉で書かれており、平明で解りやすいが、内容は決して軽くはない。その言葉の端々から、いろいろな連想を誘い出す力があり、どちらも読んでいて楽しかった。関西風に言えば、「どっちもオモロイ」本であった。
吉本隆明さんの書物は、実は私も漱石の作品を再読して何か書こうかな、などと思っていたので、「先を越されてしまった」と思いつつ読んだが、もう私の仕事はなくなったと感じた。漱石は「書かざるをえないモチーフが先にあって、それをなんとかするために」作品を書くので、日本の小説好きの「玄人受け」しない、という指摘は納得がゆく。私が漱石を好きなのは、やっぱり「素人」だからなのだと了解。
漱石の好きなモチーフ、三角関係の本質を西洋の文明開化、西洋の個人主義に触れた漱石の内面の苦悩に結びつけて解釈するところは卓見。それと漱石の「偶然を重くみる」ことの指摘も素晴らしい。全体を通じて、漱石がなぜ現在も日本人によく読まれるのか、という問いに満足する答を与えている。
何か書くなんて気持は弱くなってしまったが、これを読むと、もう一度、漱石をじっくりと読み直したくなってくる。
岩井克人さんの本は、経済や法律のことなどまるでわからぬ私にも、すらすら読めて、よく納得がゆくので嬉しくなっていたら、「中学生でもわかる」と帯に書かれていて、ますます成程と納得。「会社という不思議な存在」について説明しつつ、日本型の会社の姿が実にわかりやすく鮮明に示される。そして、短絡的な結論として、日本型がいいとか悪いとか言うのではなく、過去と未来を見渡すなかで、会社の在り方そのものについて考え、そこに日本型の特質を適切に述べている。
「カイシャ」は日本人にとって「イエ」の代用として、アイデンティティの支えともなっていたので、このような会社論に、日本人の今後の生き方についての示唆まで読みとれるように感じた。これは今後とも大いに追求してゆく課題だと思った。
私は日本人の生き方ということに常にこだわってきているので、それに対してまったく異なる角度から照射した二作を得て、実に参考になることが多く有難かった。
言語と文学の力量
関川夏央
小林秀雄賞選考委員五名の年齢は幅広い。もとより考えも異なっている。しかし選考にあたっては、作品の毛を吹いて疵をもとめるようなことはせず、作品の長所を探し、それが日本社会にどんな意味を持つかを考えようとする態度は共有されている。
したがって、選考会はおのずと「なごやかな争い」となる。それは、小林秀雄という人が持っていた言語への信頼の遠い響きであるだろう。またこの賞の源流ともいうべき新潮学芸賞、その選考委員に司馬遼太郎、安部公房両氏がおられた時代の、辛辣でいてさわやかな座談の風を、はるかに受け継いでいるともいえるだろう。
選考会に臨むまでの準備は重い。だがそれは、すでに一家をなした書き手に対する礼儀であるのみならず、ユーモアを存分にまぶしたはげしい議論というオトナの現場に連なる幸せを味わうための条件である。
吉本隆明さんの『夏目漱石を読む』が発するものは、まず著者の誠実さである。つぎに漱石作品への深い愛着と、漱石への同情である。漱石のいだいた(苦しんだ)宿命観を、吉本さんはひとごととは思っておられない。
西洋文学では不倫小説や浮気小説として出現するはずの三角関係が、なぜあのようなぬきさしならぬものとして設定されるのか、吉本さんの分析はスリリングである。同時に、著者が若年の頃から読み返しつづけて、しかるについに飽きることのなかった漱石の仕事から受けた恩徳に報いようとされる気持は、読者にそくそくとつたわってくる。
『夏目漱石を読む』はたんなる文芸評論ではない。漱石とその作品を介した著者の自己表出であり、整頓への試みである。その意味で吉本さんがどうしても書かなければ済まされなかった本である。「日本社会の頑張り方と、漱石の頑張り方は似ており、そのために漱石はいまだによく読まれ」る、と本文中にある。それは吉本隆明という表現者にも通じることなのだ。
岩井克人さんの『会社はこれからどうなるのか』と小林秀雄賞の組合わせに意外の念を持たれた人がいるかも知れない。しかし岩井さんの基本的姿勢は、経済をとおして人間とは何かを考えることにあり、それは一貫して揺るぎがない。
『ヴェニスの商人の資本論』は八〇年代の衝撃としていまも記憶に新しい。一方、『会社はこれからどうなるのか』はそれとは違った方法をとる。すなわち、平易でいて堅牢な言葉の積み重ねによって普通の人々(読者)を説得し、勇気づけようと試みたこの本のありかたこそが文学ではないか。文学の仕事ではないか。
選考委員はみな、話すべきは話し、聞くべきは聞いた。譲るべきは譲り、頑張るべきは頑張った。その末に上記二作に賞をさしあげると決した際には、もはや誰にも異論はなかった。昨年の橋本治、斎藤美奈子両氏、このたびの吉本隆明、岩井克人両氏、四人の方々の名前を並べるとき、私はそこに日本語表現の広がりと文学の力量とを、ともに見るのである。小林秀雄賞の基点は定まった。そう自信を持っていう。
「語りかける言葉」の必然
堀江敏幸
吉本隆明氏の『夏目漱石を読む』は、十年以上前の講演録がもとになっている。漱石にたいする愛と執着が、やわらかい言葉に乗せてみごとに表現されていくのだが、ところどころで、読者自身の思考を刺激する固い石が、無造作を装って投げつけられる。『道草』の描写における作者の身の乗り出し方、『門』におけるありきたりの日常の、アンチクライマックスの大切さ、そして漱石作品ぜんたいに見られる男女の区別がない均質な人間観のありよう、といった指摘の数々は、執筆順に作品をもう一度たどり直してみたいと読者を誘う、魅力あふれる言葉のつぶてだ。国文学の研究とも文芸批評ともちがう微妙ななにかが、ここにはあると思う。
岩井克人氏の『会社はこれからどうなるのか』は、昨年度の橋本治氏の作品に似て、余計な参照物をできるかぎり排除し、よく咀嚼した素材だけを、反復を恐れず丁寧に使い切った、いさぎよい作品だ。資本主義の歴史のなかに、机上の空論ではない「実体論的な」会社組織としての日本企業を位置づけ、その限界と可能性を見きわめるという誰もが望んでいた交通整理を、しかし誰とも異なる徹底ぶりで岩井氏は語りおろした。当節はやりの、男たちの物語ふうの挿話は、ひとつも登場しない。そうでありながら、厳密な論理の展開のなかに、会社人のみならず二十一世紀の日本人にむけられた、あたたかいまなざしが透けて見えてくる。そこにこそ本書の新味があるのではないか。
書き言葉から話し言葉への移行は、語るべき内容を何度も何度もかみ砕き、いつわりない自分の表現にまで鍛えあげておかないかぎり、安易の風にあおられてたちまち失墜する。今回の受賞作は、いずれもながいあいだあたためてきた核があって、そのうえで語りかける言葉を選んだという経緯の必然が、おのずと理解できる点で、思考のありかたの、すぐれた手本となるものだった。
新しい口語文への要求
養老盂司
二人の著者は、それぞれすでに定評ある著名な方たちであり、あえて作品の内容にまで細かく言及する必要もないと思う。むしろ小林秀雄賞がどうあるべきか、それを考えながら、この二作が選ばれた。今回の選考を私はそう解釈している。
私にとって興味深かったのは、受賞作が二作ともに、著者の話を書き起こしたものになったことである。むろん意図的にそういう作品を選んだわけではなく、結果的にそうなったのだが、じつはだからこそ、それがきわめて印象的だった。お二人ともに、自身の筆で書かれた著作が多数ある。
自分のことをいう場ではないが、私自身の著書『バカの壁』が同じ「語り起こし」であり、それがよく売れている。その背景には、「新しい口語文」への読者の要求があるのではないかと疑う。ケータイやメールの普及が万人に文章を書かせるようになったことも、大きな背景であろう。一方が明治以来の言文一致体の模範を創った夏目漱石、他方が経済学というわかりにくい社会科学、両者が題材であったことも、たいへん興味深い。当然ながら、文章という形式が書き手のものだけでなく、読者のものでもあることを痛感する。

2009/9/11発売
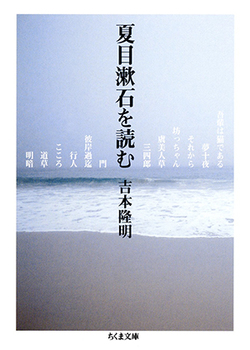
2009/9/9発売
この記事をシェアする
「小林秀雄賞」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら





