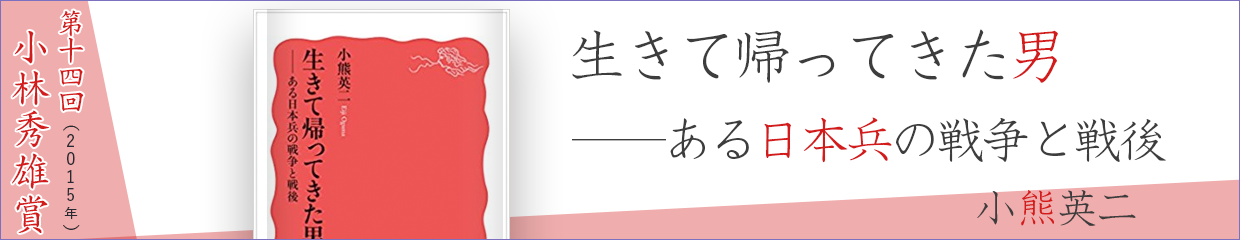インタビュー 小熊英二
目の前に転がっている、身近な話にこそ実りが多いと気づいた
「普通の人」とは何だろう―
戦前・戦中・戦後の父の生き方に、
息子が真摯に耳を傾けた。
――書名の『生きて帰ってきた男』とは、小熊さんの実父・謙二さんのことです。一九二五年生まれで、シベリア抑留体験者であるお父さまの話を聞き書きしようと思ったきっかけは何でしょうか。
戦争体験と戦後思想を扱った『〈民主〉と〈愛国〉』を二〇〇二年に出版したあと、一度は父の戦争体験も聞きました。しかしそのときは、数ある戦争体験記と比べて、特筆すべき発掘はないとしか思わなかった。あくまで、父だから個人的に聞いておこうというだけで、三時間一回きりで終わりました。文章にまとめてもいません。
その後、『1968』を書く際に高度成長期の社会や経済状況を調べた。さらに現代日本の危機的状況を理解するために、経済史、住宅政策史、金融史、社会保障史の本を読んで、『平成史』を書いた。そのようにして、私の側の関心と知見が広がっていきました。
そして二〇一二年ごろから、父は余生が長くないと思ったのか、自分から過去の話をするようになった。ただそれは、「酒田や岡山にこういう親戚がいるから、俺が死んだら連絡しろ」といった、実務的な話でした。しかしそういう話のついでに出てくる、昔の生活の話が興味深いと思った。これはきちんと記録すると貴重な生活史になるのではないのかと思って、改めて聞き書きすることになったのです。
しかし話の大部分は、どこにでもあるような内容です。それを「面白い」と思えるようになったのは、私自身の関心が広がっていたからでしょう。
――シベリア抑留時代の話などは、小さい頃からお話を聞いてらっしゃったのですか?
そういう話をまとまって聞くことはありませんでした。その点は、戦争体験者のいるどこの家庭でも同じでしょう。それは一つには、話しても背景がわからなければ理解できないし、理解してもらえそうもないと思ったら話さない。そしてもう一つは、父も含めて多くの戦争体験者は、自分の経験はありふれたもので、話すほどの価値はないと思っていたからでしょう。
いまの社会に流布している戦争体験物語は、実はかなり偏ったものです。例えば、軍全体では極めて少数にすぎない戦闘機操縦者の話が、戦争体験の典型のように扱われている。ガダルカナルやニューギニアの戦闘に参加した人も、それよりはずっと多いですが、全体からみれば少数です。単純に数的な多数派は、中国大陸や日本本土にいて、あまり悲惨な経験はない、といった兵士かもしれません。そういう人は、「私はたいした経験をしていないから話すことはない」と考えてしまう。
また民衆の戦争経験の典型とされやすい「集団疎開」や「空襲」も、都市部に限られた経験です。農村部はあまり空襲を受けていない。しかし都市中産層は文字を書き残す確率が高いので、それが典型のように流布しやすい。
ある時代の体験というのは多様であって、「これが典型」というものはない。いろいろな経験を総合し、社会科学的な知見で補強して、全体を推し量るしかない。しかし往々にして、極端に劇的な経験か、中上層の経験が、支配的な物語になってしまう。そうなると、それにあてはまらない物語は、語るに値しない、あるいは語っても受け入れられない物語になってしまう。
戦争体験を残す活動をしている方々と話すと、沖縄戦や特攻パイロットの体験談は聞いて歩いているわりに、自分の親の話は聞いたことがないという人がいる。自分の親は特別な体験をしていないから、詳しく聞こうと思わなかったと話した人もいました。
身近なものを「発見」する
今回、この本を書いていちばん思ったのは、「身近なものほど目に入りにくい」ということです。
私は最初、アメリカの研究から始めました。そのあと日本の明治期の研究、そして朝鮮・台湾・沖縄の研究をしました。それから日本の戦争体験と戦後思想、さらに日本の60年代の研究を経て、『平成史』を上梓するに至っています。つまり私自身が、だんだん「身近なものを発見できるようになった」のだと思います。「青い鳥」の話ではないですが、蓄積がない時期は、遠い時代や遠い地域のことの方が、書くに値すると考えていたんでしょう。
今年公表した仕事は、父の聞き取りと、福島原発事故後の脱原発運動の記録映画です。あの運動も、人々の目の前で起こっていたのに、その歴史的意義に気づいている人は少なかった。
――一九七八年に謙二さんは八王子市の新興住宅地に一家で引越し、以来ずっと住んでらっしゃいます。郊外の新興住宅地で暮らすうちに、環境に関する住民運動にかかわるようになります。さらに時を経て、今ではその一帯は住民の平均年齢があがり、〝限界集落〟のようになっている―日本中のそこかしこで見られる現象ですが、確かに「生活史」としてこれらの変遷がきちんと記録されてはいないかもしれません。そういった意味でも、本書は〈けっして書かれたことのない〉一冊です。
そういう読み方は歓迎です。この本は戦争体験に焦点が当たりがちだと思いますが、戦前から現代まで続く生活史を書いています。読者の目の前にある、気にも留められないようなできごとに注目し、背景を探り、意味づけをしていくきっかけにしてほしい。
語り手と聞き手の相互作用
またこの本は、介護関係や地方自治体の方々にぜひ読んでいただきたい。身近にいる高齢者たち一人一人が、じつは貴重な経験と記憶の持ち主かもしれない。聞く側が想像力と聞く気を持てば、それを引き出せる。そのことに気付くきっかけになればと思います。
その場合、本にしようとか、まとまった聞き書きをしようとか考える必要は、必ずしもありません。私は父から話を聞いて、研究としても成果がありましたが、単純に関係がよくなりました。父の話をよく理解できるようになったし、共通の話題も増えた。父の方も自分の話を熱心に聞いてもらえたことは、いい経験だったでしょう。介護の現場などでは、そういう効果のほうが重要です。成果を上げようと考えると、効率よく史実を尋問するという態度になりがちですが、それはよくない。行ったり来たりする話をゆっくり聞き、「それどういうこと?」と膝を乗り出しながら耳を傾ける姿勢が大切です。最終的に本の形になっているとわからないと思いますが、私の父への聞き取りもそういうものでしたから。
――従来のオーラルヒストリーと差異化を意識したところはありますか。
「差異化」ということは考えていませんでした。結果的には、高学歴中産層でもなく、民俗学が対象にする農民や漁民でもない、「その他大勢」の経験を記録したことでしょうか。しかしそれより、目の前にあるのに、誰も見向きもしないような事柄が、聞き手のありようによっては、実り多いものになることに気付いてほしいですね。
――自分のお話が一冊の本にまとまったということに対して、お父さまご自身はどのような反応でしたか。
「自分のことが本になった」ことより、私が話を聞いて、それが形になったことを喜んでいたと思います。あとは、通読してみて、自分の体験を位置づけ直せたと言っていました。
――この本を読んで、自分の親に話を聞いてみようと考える方も多そうです。
それはぜひやってみたほうがよいと思います。ほぼ確実に関係がよくなりますよ。極端な経験でなくても、戦争体験でなくてもいい。人はそれぞれ、固有の経験をしているはずです。
たとえば、父は高度成長期以後に、立川で小さなスポーツ用品店を経営していた。私は経済史の観点から、当時の中小商店がどういう経営をして、どんな人が雇われていて、公共施設への納入などが実際にはどのように決まっていたのかを聞きました。そういったことがわかる資料は、じつは非常に少ない。最近になって「中小商店の経営史」の聞き取り研究が出てきましたが、新しい分野です。これまでは身近過ぎて、注目されていなかった。しかしそういう話ならできる、という高齢者は身近にたくさんいるでしょう。
――最後に、小林秀雄についてどういう印象をお持ちでしょうか。小熊さんの読書史の中で、思い出深いエピソードなどがありましたら、ご紹介下さい。
私は読書家ではありませんし、小林秀雄を研究対象として読み込んだこともないので、コメントはできないです。そもそも、楽しみとして読書するという習慣がない。本より音や映像や現場の方が好きで、活字はもっぱら研究として読みます。だから、そういうご質問にはうまくお答えできません。
1962年、東京都生まれ。
慶應義塾大学総合政策学部教授。
東京大学農学部卒業、同大学大学院総合文化研究科国際社会科学専攻博士課程修了。『単一民族神話の起源―〈日本人〉の自画像の系譜』でサントリー学芸賞、『〈民主〉と〈愛国〉―戦後日本のナショナリズムと公共性』で毎日出版文化賞・大佛次郎論壇賞・日本社会学会奨励賞、『1968』で角川財団学芸賞、『社会を変えるには』で新書大賞を受賞。(受賞当時)
● ● ●
選評
父のことを書くこと
加藤典洋
みみずが土を肥沃にするメカニズムがどのようなものであるかは知らないのだが、みみずが土を食べる。それを排泄する。すると、みみずの身体を通過した土は、肥沃なものとなっている。
この本を読んで、私は、何だかみみずの身体を通過するその土になったような気がした。読みはじめるまえよりも、読み終えた後のほうが、心身がしなやかで、世界がより静まって見えた。たしかに自分は何かチューブのような異空間を通過したと感じたのである。
最初見たときにはタイトルも、惹句も、帯裏の引用も、なんということのないコトバだった。不覚にも(?)読み終わったら、それらがまったく違ったように読めた。
何がこの父への聞き書きである本の力なのだろうか。
ほかの家族はもういない。死んでいる。父と子が二人、この世界に残されているとも、私は感じた。
こういう異空間を作るのに、この書き手はひとりの若い著作家に助けを求めているが、そのはじまりに向かうときの緊張が、この本の最後まで、とぎれることなく続いている。
読後、私に浮かび、選考の場でもついもらした感想は、「これまでにない、いままで日本ではけっして書かれたことのない本がここにある」というものだった。大仰ないい方だとは思う。けれども、文学を専門とする人間としてはこういうほかない。この父との対し方のうちに一つの達成がある。「父と子」にはじまった近代の文学が、とうとうここまできた、というような。またフィクション、ノンフィクションの「零度」(ロラン・バルト)の針が、ここでぴたりと止まっている、というような。
去年、『HHhH』という若いフランス人の小説家の作品を読み、そこでフィクションを極力排除して自分の経験していない過去を蘇らせようとする企てが敢行されているのを見て、なぜ、最近の若い日本の小説家の作品は小ぶりなのか、教えられた気がした。そこに欠けているのは「歴史」である。この小熊さんの父上への聞き書きは、遠く、彼らの頭越しの、海外の文学への一つの回答になっていると思う。
ただ父のことを書くということが、いま、批評の行為なのである。
批評の積極性
養老孟司
今回の受賞作は選考委員の点数評価がいちばん高かったから、その意味では順当というべきであろう。私自身も異論があったわけではない。「父の語りを語る」という形が批評であると見做せば、小林賞としても問題はない。そう納得した。ただいつものことだが、厳選された複数の候補作から選ぶので、優れた作品が多く、「どれでもいい」というのは無責任だし、最終の判断に難儀をする。その時々ということもあるし、特に原則論があるわけではない。その点で今回感じたことをメモしておこうと思う。
人文系の学問が大学の組織上でも問題にされ、具体的にもいわば消されようとしている感がある。重要だといわれつつ、そうなるのだから、時代の趨勢ということであろうか。「批評」は典型的に人文系の作業であって、「書かれたこと」「言われたこと」を扱うものだと思う。いまは歴史が盛んだが、これは「書かれた事実」に基づく。微妙な点だが、この事実の重みが問題である。端的にいうが、本来の人文系の学問が安易に「事実」に寄りかかりすぎる傾向がないか。それなら人文学はいらない。
逆に理科系では、人文的な思想がほとんど排除されてきている。STAP細胞の事件はその典型ではないのか。生物の歴史性への考察が皆無というしかない。それが現実に研究者の自殺という悲劇を生む。
おびただしい「言説」があらわれる時代だからこそ、言説そのものに関する深い思いを担う学問があっていい。あるべきであろう。別な候補作中の人物の行動が「軽い」という評があった。まことにその通りと思うと同時に、この軽さが日本であり、それを救う、深めるのが批評の積極的な面ではないのか、と感じる。
「普通の人」の得がたい歴史
関川夏央
小熊英二『生きて帰ってきた男—ある日本兵の戦争と戦後』は、その主題と副題にあるとおり、「生きて帰ってきた男」の「戦争」と「戦後」を等価に記録する。この本の「重さ」と「おもしろさ」を保証するのは、そのような態度である。
戦争・抑留の体験記は、あまた書かれた。しかし、いわゆるインテリが残した記録がほとんどで、「普通の人」あるいは「多数派」のものはまれだった。かりにあっても、なかばやむを得ないことであるにしろ、その悲惨な体験や劇的な経過は「ロマンティシズムで色付け」される傾向があった。この本が、そのような誇張や自己憐憫から自由なのは、多く語り手(小熊謙二)の「淡々とした性格」によるだろう。さらに肉親だからこそ、つとめて語り手との「距離」を保とうとした記録者(小熊英二)の姿勢が、個人史から修飾を去らしめるべく機能したのでもあるだろう。
戦争末期に十九歳で入営。満洲に送られてシベリア・チタに三年間抑留。帰国して転々と職をかえるうち、肺結核を発病して五年間の療養所生活。手に一物も持たずに社会復帰すると折しも高度経済成長の時代で、語り手は勤め人として、また小企業の社長として生き抜いた。彼の戦後の頻繁な転居の仕方と転居先もまた「戦後史」そのものであろう。
語り手は「インテリ」ではないと書いたが、それは彼が高等教育を受けなかったことより、むしろ「文学の影響下になかった」ことを意味する。語り手の記憶力、つぶさな観察力はただごとではない。やはり昭和戦前が生んだ「市井のインテリ」というべきである。
この本は「平均的な人生」などはないのだといっている。逆に「多数派」の人生こそ限りなく多様なのであって、そういう人たちが生きた「昭和」という時代は、戦前・戦中・戦後が地続きなのだと実証的に語られる。
災難と困難に淡々と身を処しながら生きた九十歳に近い父親、その人生を記録した五十代の息子、その両者によって、この「親孝行文学」はすぐれた歴史記述として完成した。
ふつうを研ぎ澄ますこと
堀江敏幸
記憶は単体で生き残ることができない。聞き出す人、あるいは語らせる人がいなければ、外から見えるものにはならない。過去の凹凸に光が当たって、現在に影がのびる。記憶が他者に共有されるのは、その影を通じてのことだ。
ここに記録されているのは、一九二五年に生まれたひとりの日本人男性の、徹底した現場の感覚である。生い立ち、応召、シベリア抑留、帰国後の流浪と過酷な結核療養。二十代のすべてを愚かな戦とサナトリウムに奪われた男が、なぜ後の高度経済成長のなかで絶望もせず、高ぶりもせず、流れに任せながらもつねに自分の頭で考えて行動できたのか。それが淡々と語られていく。
もちろん、男の声は、聞き手であり書き手である作者、つまり息子にあたる人物によって再現されたものだが、それゆえにこそ語り手の特殊性がきわだつ。身のまわりの出来事を、ふつうの感覚で、ふつうに、しかし正確に観察しつづけ、ふつうと呼ばれるものを研ぎ澄ませることによって、男はそうと意識することなくそのふつうを超えていく。ふつうではないふつうさの静かな力を受け止めているうち、聞き手の、そして読者の胸に、男にとっては戦中も戦後もなく、あるのは日々の持続だけだという事実が染みてくる。軍隊の愚かさを認め、天皇の戦争責任をあたりまえのこととして口にする。会社の金に手を出したと打ち明け、捕虜時代にいっしょだった朝鮮系中国人の戦後補償に力を貸す。既成の価値観に頼らず、顧みるべき事象に優劣をつけない姿勢は、まっとうであるだけに、いまの日本においてはいっそう貴重なものと映るだろう。
実の父親を扱いながら、その話をとりまとめ、整序の役を担う著者は、あくまで語り手の視線に寄り添っている。息子として見知っている過去に介入せず、自身を三人称として描くこの距離感が、父親が社会に対して、また自分自身に対して保ちつづけた距離感を無傷で残す力になった。「未来がまったく見えないとき、人間にとって何がいちばん大切だと思ったか」という最後の問いに対する一九二五年生まれの男の回答が、素のままで響く。「希望だ。それがあれば、人間は生きていける」。ふつうを超えたふつうを活かすために求められる聞き手の側の理知と抑制が、聞き書きとも評伝とも異なる形での、他者の記憶の解放を可能にしたと言えるだろう。
日本人でよかった
橋本治
小熊英二さんの『生きて帰ってきた男—ある日本兵の戦争と戦後』は、タイトルだけ見ると今までにいくらでもあったような本の一つかとも思えますが、読み始めるとすぐにそうではないことが分かります。いたって当たり前の「市井の人」が、「市井の人」のままその当たり前さを貫いて行くとどれほどすごいことになるのかという、なんの色もつかない等身大の「市井の人」基点の昭和史で、これは『—ある日本兵の戦争と戦後』ではなく、『—ある日本人の戦争と戦後』ではないかと思いました。
一番すごいのは、対象となった小熊英二さんの父謙二さんの「淡々たる普通さ」と、その「勁さ」です。ただ「生きる」ということを考えて率直になれば、生きるのに必要なしなやかな勁さが表れる。厳寒の大地に立って「あ—」と思いながら、「立ちすくむ」という意識を持たずにただ立っていれば、残酷な運命の横風になぶられながらも、生きて行くことは出来る。「生きて行ける」と「生きて行けない」は紙一重で、その境を分けるものは、実のところなにもない。その中を歩み続ける勁さを持つことこそが、「名もない普通さの持つ力」でしょう。
それでも、ただのオーラルヒストリーであれば、そこに自慢が入ります。それは一人称語りの持つ悲しき必然のようなものですが、父謙二の語る言葉を子の英二が受け止めながら、その語りを聞き流すように、その時の父のいた「周辺」を記述して行くという展開が、語り手の持つ素晴らしさを引き出していることは忘れることが出来ません。
そして最後、「名もなき市井の人」が、偶然のような「あってしかるべきプロセス」によって、突如立ち上がってしまうという、小説のような展開。「名もなき市井の人」の持つ潜在的な力の見事さが表れて、「日本人でよかった」と思わされてしまいます。

生きて帰ってきた男 ――ある日本兵の戦争と戦後 / 小熊英二
2015/6/20発売
この記事をシェアする
「小林秀雄賞」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら