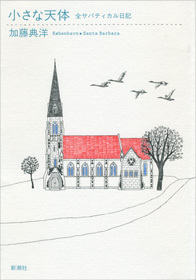加藤 僕は高校二年生のときに偶然、大江さんの『日常生活の冒険』を家で読んで「日本の小説家はこんなにおもしろい小説を書いているのか!」そう思って、日本の現代小説に目覚めた口です。
そのときから完全に大江健三郎にハマってしまい、それからしばらくの間、ずっと追っかけだった。高校の頃は大江さんの書いたものは全部、スクラップして持っていました。
そうしたら国立大の受験のときに、一時限目が国語だった。見ると問題文が大江健三郎の文章なんですよ。一九六四年のオリンピックについて書かれた文で、問いには、いつ書かれたか、オリンピックの前か、後か、最中か、なんてものまである。僕は全部スクラップを取っているから、掲載された日にちまでわかるわけです。その勢いで試験に受かってしまった。大江さんには、そんな形でもお世話になっている(笑)。
上岡 『敗者の想像力』では『水死』の前に、「人間の羊」を取り上げていますね。占領下の文学が、日本では占領を描いて来なかった。つまり、占領が意識化されていなかったなかで大江さんだけは、そういうものを書いていたと。
加藤 大江さんのノーベル賞受賞時に、この受賞にどういう意味があるか、ということでどこかに書いた覚えがあるのですが、僕は、特に大江の作品の初期のものに、その独自さがはっきり現れているという考えです。たとえば、アジアの後進国といわれているような国の若い小説家が、非常にヨーロッパ的な新しい手法を駆使して、それでヨーロッパ人をギョッとさせるようなものを書く。そういう面白さを大江は体現しています。『人間の羊』はそういうものの代表的な作品の一つですが、僕は、大江がもしノーベル文学賞を貰うことに意義があるとしたら、それは、そういうところではないかと思う。開高健がベトナム戦争について書いたもののなかに、戦争の最中、ベトナムの若い知識人が地下のバーに集まり、そこでシモーヌ・ヴェイユを読んでいるという話が紹介されています。そういう話を読んで、僕らはギョッとするわけですが、大江のノーベル文学賞受賞には、そういう新鮮な驚きをもたらす要素があったのではないでしょうか。
二〇一〇年、カリフォルニア大学サンタバーバラ校に半年間いたのですが、そこで、ジョン・ネイスンの日本戦後文学の授業に顔を出しました。彼は三島の『午後の曳航』や大江の『個人的な体験』の翻訳者で、大江のノーベル賞受賞時にはストックホルムに同行しています。学者、翻訳者というだけでなく、ドキュメンタリー映画でもエミー賞を受賞しているという博学多才なエネルギッシュな人物ですが、教室で、「大江というのはもう本当に完全な超天才だ」というんです。七〇人くらいいる多様な出自をもつ受講のアメリカ人学生、留学生にむかって「考えてごらん。戦争中にアジアの、ちっぽけな国の山中に米軍の飛行機が墜落して、乗っていた黒人の飛行士が落下傘で降下して村人に捕まる。彼はその後、檻に入れられるんだが、そこで『飼育』されるんだ。そんな話を1950年代にアジアの一角で、日本の若い小説家が書いた。信じられるか?」。学生はみんなギョッとして一瞬おいてから笑うんですけど、その笑いがちょっと引きつっている(笑)。そのインパクトたるや、想像を絶する。こういうと、その感じがわかってもらえるのではないでしょうか。

-
大江健三郎/著
1959/09/29発売
上岡 あの「人間の羊」のグロテスクさにしたって、大江さんの想像力には本当に驚かされますよね。占領する側とされる側、つまりアメリカと日本の関係がものすごく誇張され、恐ろしいくらいです。と同時に、できるだけ占領されていることを意識したくない人たちの姿もグロテスクと言える。そして、彼はずっと「戦後民主主義とは何だったのか」ということにこだわってきたわけです。
加藤 僕が小学校六年生のときに、勤務評定反対運動というのがありました。学校の先生を文部省が勤務評定し、管理しようとすることに反対して教員がデモをしていたんです。そこに自分の担任がいるのを見つけて、すごく不思議な感じがしたのを強烈に覚えています。そういう意味で僕も、戦後民主主義の教育を受けてきた人間だと思うんですけれども、大学に入ったあたりで、それが変わる。日本で平和と民主主義なんていっているあいだに、ベトナムでは普通の人間がたくさん米国による「空爆」や傀儡政権による圧政のもとに死んでいる。この社会の成り立ちを抜本的に変えなきゃならないんじゃないか、という考えに動かされ、全共闘運動にのめり込むようになるのですが、すると、戦後民主主義というのは、生ぬるいんじゃないか、と思えてくるわけです。それで学生の運動や三里塚の運動などにはっきりとした態度を示さないで戦後民主主義だけを言い募る大江健三郎の姿勢に対しても、当時は違和感を覚えるようになりました。
それともう一人、大学生のころまでに小林秀雄の影響を強く受けていたんですが、その小林が何かのおりに学生運動などをさして「今の若い奴はなんともならん」みたいなふうなことを言っているのを読んで、このときもショックを受けました(笑)。小林秀雄からは突き放され、大江健三郎にも違和感を覚え、これから先は、先行者なしに自分一人の考えでやっていくしかないと思い知った。だから僕自身は戦後民主主義にあんまりいい印象はないんですが(笑)、しかしやはり、戦後民主主義が自分の血のなかを流れているという感覚は消えない。これとの間にも僕なりの「忠誠と反逆」が生きているわけです。

上岡 加藤さんの仕事で、『敗者の想像力』と合わせてぜひ読んでいただきたいのは『戦後入門』です。様々な思想家が戦後をどう捉えたか、追っていきながら、最後は加藤さんの「九条の精神を生かした改憲」案に結実します。「これはすごい!」と僕は思ったのですが。
加藤 あの本については、様々な批判を覚悟していました。当初の理想を手放さなかったら、どういう主張をしなければならないのか、という見本を示したかったのと、でもそれだけではもうやれそうにないとしたらどう考えていくべきか、というのと、その両方を示し、考えたかったし、考えてもらいたかったのです。いまやずいぶんと歳をとってしまった戦後民主主義は、ある種の急流を乗り越えて、また別のところに行く。そういうことが必要なのと、もうひとつは様々な異論がありうるなかで、もっともっとそれを容認しながら全体として力強くなっていくという流儀を持たなければ、今のリベラルな思想というのは、もうダメになってしまう、その二つの危機感に背中を押されて書きました。
上岡 「憲法を一言一句でも変えないぞ」と言っている先には、どうしてもリベラルの限界があると思います。では、そこをどう乗り越えればいいのか……。
加藤 今のような政治情勢にあっては「一言一句変えるな!」という主張もあり得ると思いますが、その主張を貫くとしたら、どのような責任を引き受けなければならないか。その覚悟が足りないと思うのです。では対米従属をどうするんだ! そういおう沖縄からの声に、この「一言一句変えるな!」の護憲論の憲法学者たちは論の地平でどう答えるのか、ということです。全体として戦後民主主義はどこに向かうのがよいのか、いまの当面の目標は何なのか。そのあたりをよりダイナミックに把握できていなければ、ダメだな、というふうに個人的には思っています。
上岡 少なくとも戦後民主主義の行き先を考えて改憲論議を行うには、「戦争の苦い部分」に関する認識がもっと必要ですよね。戦争が始まるときはいろいろと大義が謳われるわけですけど、実際は大義とも言えないことで動き出し、動き出したら止まらない。こうして犠牲者が増えていくわけですが、自分たちは犠牲者にもなり得るけど加害者にもなり得るということに目を背けてはいけないと思うんです。
加藤 上岡さんが書かれた『テロと文学』に登場するティム・オブライエンとフィル・クレイは自身の戦争体験に根ざしてこの「苦い部分」を書いています。これに対して『ビリー・リン』のベン・ファウンテンは戦争を経験していないんですが、今度はその経験なしという空白の事実に根ざして、やはり戦争の「苦い部分」を描き出している。いまはその両者が共闘できる。戦争自体がそういうものに変わっています。そしてこのことと通底していると思うのですが、『戦艦大和ノ最期』で吉田満が、「大和」が沈んだあと、自分たちの上をずうっと旋回しているアメリカの飛行機が攻撃してこなかった、ということを書いています。彼はそこに、戦った人間同士、ある種の敬意、共生感のようなものを感じた、そういうものがあるのだ、と述べています。これについてはのちに江藤淳さんが、アメリカへの迎合がここにある、と批判したのですが、それは違うだろうと思います。事実、そういうことがあるのだと思います。山本七平も、自分たちが激戦ののち捕虜になったあと、実際に戦火を交えた連中が捕虜収容所の管理にあたっているあいだ、相手は非常に親切だった。でも、クリスマス休暇でその兵士たちが皆いなくなり、戦争を経験していない兵士が代わりにやってきたら、今度はアジア人に対する差別意識が剥き出しになったと、全くおんなじことをいっています。
戦争を経験した人は、仮に立場が勝者と敗者に分かれたとしても、相手に対してある種の想像力を抱くことができる。そしていまは、その戦争の経験と非経験の差が紙一重くらいになってきている。そういうことだと思うんです。そこで「戦争の苦い部分」というのはつまり、戦争・戦場に本当の勝者はいない、ということです。そして、それは言葉をかえれば、戦争ではみなが敗者なのだ、ということでもある。『戦後入門』に書いたことはそう簡単にはいかないと思っています。しかし、一方、上岡さんが『テロと文学』で書かれたことと、僕が『敗者の想像力』で書いたものなら、実は強くつながっている。敗者の経験は勝者の経験よりも、どう考えても、誰にも通じる。普遍性をもっているからです。そのあたりを足場に、今後、『戦後入門』、さらに『敗者の想像力』の続きを考えていきたいというふうに思っています。今日はありがとうございました。

(平成29年7月11日 下北沢「B&B」にて)
書籍紹介

-
加藤 典洋/著
2017/5/17発売

-
上岡 伸雄/著
2016/1/15発売
-

-
加藤典洋
かとうのりひろ 1948年、山形県生まれ。文芸評論家。東京大学文学部卒業。著書に『アメリカの影―戦後再見―』、『言語表現法講義』(新潮学芸賞)、『敗戦後論』(伊藤整文学賞)、『テクストから遠く離れて』『小説の未来』(桑原武夫学芸賞)、『村上春樹の短編を英語で読む1979~2011』『3.11死に神に突き飛ばされる』『小さな天体―全サバティカル日記―』『人類が永遠に続くのではないとしたら』ほか多数。共著に鶴見俊輔・黒川創との『日米交換船』、高橋源一郎との『吉本隆明がぼくたちに遺したもの』ほか。
-

-
上岡伸雄
かみおかのぶお 1958年、東京生まれ。学習院大学文学部教授。訳書にドン・デリーロ『墜ちてゆく男』、フィル・クレイ『一時帰還』、ハーパー・リー『さあ、見張りを立てよ』、ジョン・ル・カレ『われらが背きし者』(共訳)、グレアム・グリーン『情事の終り』など多数。著書に『テロと文学 9・11後のアメリカと世界』など。
この記事をシェアする
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 加藤典洋
-
かとうのりひろ 1948年、山形県生まれ。文芸評論家。東京大学文学部卒業。著書に『アメリカの影―戦後再見―』、『言語表現法講義』(新潮学芸賞)、『敗戦後論』(伊藤整文学賞)、『テクストから遠く離れて』『小説の未来』(桑原武夫学芸賞)、『村上春樹の短編を英語で読む1979~2011』『3.11死に神に突き飛ばされる』『小さな天体―全サバティカル日記―』『人類が永遠に続くのではないとしたら』ほか多数。共著に鶴見俊輔・黒川創との『日米交換船』、高橋源一郎との『吉本隆明がぼくたちに遺したもの』ほか。
著者の本
-

- 上岡伸雄
-
かみおかのぶお 1958年、東京生まれ。学習院大学文学部教授。訳書にドン・デリーロ『墜ちてゆく男』、フィル・クレイ『一時帰還』、ハーパー・リー『さあ、見張りを立てよ』、ジョン・ル・カレ『われらが背きし者』(共訳)、グレアム・グリーン『情事の終り』など多数。著書に『テロと文学 9・11後のアメリカと世界』など。

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら