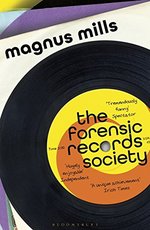(7)遍在するブライアン・ウィルソン
Beatlebone by Kevin Barry The Forensic Records Society by Magnus Mills
著者: 柴田元幸
無茶振りというのも時には有難いものである。昨年11月に東京で開かれたヨーロッパ文芸フェスティバルで、アイルランド人作家ケヴィン・バリーの朗読会に飛び入りで参加すべし、と敬愛するHMV BooksのMさんから振られたので、まあ新しい作家を知る機会かと思って引き受け、まずは手元にあった文芸誌Grantaに載っていたエッセイ(“The Raingod’s Green, Dark as Passion,” Granta135)と、The New Yorkerに載っていた短篇(“The Coast of Leitrim,” The New Yorker, Oct. 15, 2018)を読んでみたらなかなか面白かった。で、実際人前で一緒に話してみたら期待以上に面白い人で、訳していったアイルランド・コミックノベルの傑作フラン・オブライエン『第三の警官』の一節を練習もなしで一緒に英日バイリンガル朗読したところこれがけっこう上手く行き、読み終わったとたんケヴィンに「我々はツアーに出るべきだ!」と言ってもらったのだった。
というわけで、これだけでも大満足だったのだが、ケヴィンの本当の真価がわかったのは、その後に彼の長篇Beatleboneを読んだときである。短篇とエッセイも十分よかったが、この長篇を読んで、この作家の志の高さ、達成度の高さを知った。
Beatlebone。タイトルからして、そうかな?と思うし、どこかの田舎にいてどこかの島に行こうとしているらしい人物も“John”と呼ばれているので、これはビートルズの話だろうかと思って読んでいくと、始まって10ページ目くらいで、たとえばこんな一節が――
Good morning, John says.
The dog raises an eye in wariness—he is careful, an old-stager. He comes across but cautiously and he looks soul-deep into John’s eyes and groans.
I know exactly how you feel, John says.
And now the fat old dog rests its chin on his knee, and he places a palm on the breathing warmth of the dog’s flank, and they share a moment’s sighing grace.
Never name the moment for happiness or it will pass by.
The dog lies down to settle by his feet and sets a drooly chin on the toe of a fresh purple sneaker.
Those are not long from the bloody box, John says.
He reaches down and lifts the dog’s chin with a finger and he finds such a sweet sadness there and a very particular handsomeness, a kind of gooey handsomeness, and at once he names the dog—
Brian Wilson, he says.
At which the dog wags a weary tail, and apparently grins, and John laughs now and he begins to sing a bit in high pitch—
Oh it’s been buildin’ up inside o’ me
For oh, I don’t know, how long . . .The dog comes in to moan softly and tunefully, in perfect counterpoint to him—this morning’s duet—and John is thinking:
This escapade is getting out of hand right off the fucking bat.
おはよう、とジョンが言う。
犬は慎重に片目を持ち上げる。百戦錬磨の油断なき犬なのだ。こっちへやって来るが、足取りは用心深い。犬は魂をのぞき込むようにジョンの目に見入り、うなり声を上げる。
わかるよ、お前の気持ち、とジョンは言う。
そしていま、老いたデブの犬はあごをジョンの膝に載せ、ジョンは暖かく息づく犬の横腹に手のひらを当て、彼らは一瞬の、ため息に彩られた恩寵の瞬間を分かちあう。
幸せの瞬間を名指してはいけない、名指すと去ってしまうから。
犬は横たわってジョンの足もとに身を落着け、よだれに濡れたあごを真新しい紫のスニーカーの足先に載せる。
その靴、おろしたてなんだぜ、とジョンが言う。
ジョンは手をのばし、指で犬のあごを持ち上げ、ひどく感じのよい哀しさと、独特の、湿っぽいハンサムさを見てとり、瞬時にして犬を命名する――
ブライアン・ウィルソン。
そう呼ばれて犬はくたびれた尻尾を振り、ニヤッと笑ったように見え、ジョンも声を上げて笑い、高いピッチで少し歌う――
いつごろからだろう
胸のうちに思いが募って……犬も仲間入りして、柔らかくメロディアスに、完璧な対位旋律を加える。けさのデュエット。そしてジョンは考える――
このドタバタ、しょっぱなからムチャクチャだな。
――ビーチ・ボーイズのリーダーの顔が思い浮かぶくらいのポップス・ファンであれば、「ひどく感じのよい哀しさと、独特の、湿っぽいハンサムさ」というのがいかにもブライアン・ウィルソンに相応しいことがわかるだろうし、「いつごろからだろう……」というのがビーチ・ボーイズ初期の佳曲“Don’t Worry Baby”のリフレインであることもわかるかもしれない(「高いピッチ」というのはもちろんブライアンの裏声を真似ている)。
というわけで、この時点で多くの読み手は予想するだろう。この本、ポピュラー音楽トリヴィアがそこらじゅうにちりばめてあって、ポップス・ファンにはたまらない本かもしれないぞ、と。
そしてその期待は、ものの見事に外れる。
たしかにこれは、ジョン・レノンをめぐる長篇小説ではあるのだが、240ページくらいあるなかで、言及されるミュージシャンはせいぜい5、6人にすぎない。ケイト・ブッシュ(作品の時代当時に大ヒットしていたシンガー)、レイ・ライナム(舞台であるアイルランドの地元カントリー・シンガー)、スコット・ウォーカー……何しろポールもジョージもリンゴも出てこないし、ヨーコ・オノの名も2度ばかり出てくるだけだし、そもそも「ジョン」はつねに出てきても「レノン」は一度も出てこない。曲名への言及もほとんどなし。時にビートルズの歌詞を想起させるフレーズ(たとえば‘Honey Pie’を思い出させる‘North-of-England’とか)が随所にひっそり埋め込まれているだけである。
つまりこれは、「ポップス・ファンにはたまらない本」をまったくめざしていない。そして、そういうものをめざさないことによって、間違いなく、全然別の、とてもいい本になっている。
物語はひとつの歴史的事実から出発している。1970年代、ジョン・レノンはそこに隠遁するつもりでアイルランドに小さな島を買った(結局、実際にはほとんどそこを訪れることなく他人に譲った)。小説は、コーネリアスという男に連れられて、ジョンがその島へ行こうとするのだけれど、追いかけてくるマスコミに邪魔されたりしてなかなかたどり着けないという設定である。そのなかで、ジョン・レノンをめぐる何らかの謎が解明されるわけでもないし、ジョンの内面の意外な事実が暴かれたりもしない。小説の大半は、ジョンとコーネリアスの、どこへもたどり着かないように思える会話から成っている。たとえば――
After a while, Cornelius, do you get to wondering?
About, John?
What’s it we’re here for?
You mean in the middle of Clew Bay on as miserable a fucken Sunday as you’d meet?
Or more generally.
Ah Jesus, John. Are you having feelings again?
I know.
These large sad warmish feelings, John? The best thing you can do is ignore the fucken things.
しばらくするとさ、なあコーネリアス、どうなんだろうって思わないか?
何をだい、ジョン?
俺たちがなんでここにいるのか。
って、最低最悪の日曜にクルー湾にいるってことかい?
てゆうか、もっと一般的に。
おいおい、ジョン。あんたまた、感情湧いてるのか?
わかってんだけどさ。
でっかくて哀しくって温かっぽい感情かい、ジョン? そんなもん、無視するに越したこたぁないぜ。
――作者はこの手の会話が自然に響くようにすることにもっとも心を砕いたという。僕もそこがこの小説の一番素晴らしいところだと思う。‘About what, John?’と言うべきところを‘About, John?’で済ませていたり、わかってるよ、そういうつまんない感情抱いたって意味ないのはわかってんだけどさ、を‘I know’だけに凝縮していたり、実に芸が細かい。
ジョンをより高い次元に導いているようでもあり、ただのペテン師のようでもあるコーネリアスの人物造形も見事である。ふだんはインチキ臭く飄々としている彼が、父親のことを思い出していくうちに取り乱していくところなどは異様にテンションが高まる。で、彼とのやりとりを通してジョンは何か叡智を達成するわけでもないし、逆に大いなる幻滅を経験するわけでもない。小説はいわばなんとなく始まって、なんとなく終わる。けれど、わかりやすい物語に落とし込んでしまう多くの小説とは全然違った、一行一行の、滑稽だったり緊迫していたりする息づかいの実感は格別である。まあ翻訳は至難の業だろうが……。
音楽がらみの小説をもう一冊。こちらはイングランド発である。デビューしたときは「ブッカー賞候補の現役バス運転手」として話題になった異色作家マグナス・ミルズの長篇第9作。ミルズの登場人物たちは、自分たちが抱えている問題(柵作り、物流、住宅問題等々)を人生一般の真理に高めたりは決してしない人物たちであり、今回もそれは同じだが、そもそも彼らの抱えている問題は、人生一般の真理を引き出そうにも引き出せそうにないたぐいの問題である。
‘The perfect pop song is precisely three minutes in length,’ he announced. ‘Do you agree?’
‘It depends,’ I said. ‘Would you like to sit down and discuss it?’
‘Thank you.’
It soon transpired that the spiky haircut matched the newcomer’s personality exactly. He appeared to think that a conversation comprised a series of questions and answers fired back and forth like some frantic game of ping-pong. Moreover, he was seemingly fixated by the duration of records as expressed in minutes and seconds.
‘Mike,’ he said by way of introduction, harshly scraping a chair into position. ‘“God Save the Queen”. How long?’
‘Not sure,’ I replied. ‘Three minutes?’
‘Three twenty,’ he snapped back. ‘“Smash It Up”. How long?’
‘Don’t know.’
‘Two fifty. “Stand Down Margaret”. How long?’
‘You tell me.’
‘Three thirty-two. “Complete Control”. How long?’
‘Three ten,’ said James.
‘Oh ... er ... yes.’
James’s sudden interjection briefly knocked the wind out of Mike’s sails. Or perhaps he’d simply run out of energy. Either way, his response to this evidently correct answer was to cease his cross-examination and fall silent. He sat back in his chair and stared at the pint glass he’d brought with him.
「完璧なポップスはきっちり3分の長さだ」とそいつは宣言した。「賛成するか?」
「見方によるな」と私は言った。「座って話すかい?」
「ありがとう」
じき判明したことに、尖った髪型はこの来たばかりの男の性格に完璧にマッチしていた。どうやらこいつは、会話とは必死の卓球の試合みたいに質問と答えを次々投げつけあうものだと思ってるみたいだった。おまけに、分と秒で表わされたレコードの持続時間に執着しているらしい。
「マイク」とそいつは自己紹介し、耳障りな音を立てて椅子を引きずった。「『ゴッド・セイヴ・ザ・クイーン』。何分何秒?」
「どうだろうなあ」と私は答えた。「3分?」
「3分20秒」とマイクはピシッと言い返した。「『スマッシュ・イット・アップ』。何分何秒?」
「わからない」
「2分50秒。『スタンド・ダウン・マーガレット』。何分何秒?」
「教えてくれよ」
「3分32秒。『コンプリート・コントロール』。何分何秒?」
「3分10秒」とジェームズが言った。
「え……う……そうだ」
ジェームズがいきなり口をはさんだことで、マイクはしばし虚をつかれたみたいだった。それとも、単に息が切れたのか。どっちにしろ、この明らかに正しいらしい答えに応えて、マイクは詰問をやめ、黙り込んだ。そして深々と座り直し、持ってきた一パイントのグラスをじっと見た。
――一軒のパブを舞台とするこの小説の登場人物の大半は、ポピュラーソングのこと以外いっさい頭にない。そんな彼らが、タイトルにもなっている‘The Forensic Records Society’(訳しにくいが、強いて訳せば「鑑識的レコード協会」)を結成し、パブの奥の部屋を借りて集会を開き、持ち寄ったレコード(シングル盤のみ。この宇宙にLPはどうやら存在しない)をかける。ルールは、レコードが終わったときに誰もコメントしてはならない。つまり、ただレコードをかけて聴き、またレコードをかけて聴き、またレコードをかけて聴くのである。だがやがて、それに飽き足らないメンバーが出てきて、終わったあとにコメントを許す別の協会が結成され、そのうちに、このパブのウェートレスがかつて一枚だけシングル盤を作った伝説的シンガーであることが判明し、神話的なる一枚を誰もが探し求め……
馬鹿馬鹿しいと言えばこれほど馬鹿馬鹿しい話もないのだが、マグナス・ミルズ作品の常として、しょうもない問題が人生全般のメタファーに転じることもなく、とことん即物的に語られることで、独特の現実感――正確に言えば、独特の非現実感を伴った現実感――が生まれる。そこは相変わらず見事である。そしてその独特の非現実感/現実感は、上の引用でもわかるように、曲名は次から次へと言及されるのにミュージシャンの名前はまったく出てこないことからも生まれている。唯一の例外が、ほぼ書き出しで語り手がシングル盤のレーベルに書かれた言葉をそのまま口にしている箇所である――PRODUCED BY BRIAN & MURRY WILSON。何とここでもブライアン・ウィルソン!(この親子プロデュースのシングルは1969年のビーチ・ボーイズ・シングル「ブレイク・アウェイ」ですね)
というわけで、全然違った二冊だが、音楽ネタを用いながら音楽について書かないことで大きな効果を挙げている点は同じ。書き込めばいいというものじゃないんですね。
最新情報
2月1日(金)は東急大井町線尾山台駅近くのFlussで3日満月(音楽)、林青那(ライブドローイング)と一緒に朗読をやります。題して『失われた詩を求めて』(19:30-)。2月9日(土)は神戸市外国語大学で絵本作家(てゆうか、シバタ専属絵師)きたむらさとしさんと講演会「絵は語り、言葉は描く-絵本作家と翻訳家の対話―」(14:00-)。2月10日(日)昼は枚方蔦屋書店で、谷崎由依さん(作家・翻訳家)に聞き手になってもらって翻訳について喋ります(13:00-)。2月10日(日)晩は京都恵文社一乗寺店できたむら、青木隼人(ギター)、柴田の絵と音楽と朗読のパフォーマンス「『アイスクリームの皇帝』at COTTAGE」(18:15-)。2月14日(木)は「樟まつり」の一環として調布市文化会館たづくりで講演「アメリカ文学の面白さ 『ハックルベリー・フィンの冒けん』を中心に」(14:00-)。2月16日(土)はMONKEY17号刊行記念イベントをRainy Day Bookstore & Caféで(15:00-)。2月23日(土)は奈良市fangleで内田輝さん(クラヴィコード、ソプラノサックス)と「言葉と音楽の対話」(17:00-)。2月24日(日)は四日市市〈子どもの本屋 メリーゴーランド〉で講演(14:00-)。
-

-
柴田元幸
1954年生まれ。翻訳家。文芸誌『MONKEY』編集長。『生半可な學者』で講談社 エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。2017年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。
この記事をシェアする
「亀のみぞ知る―海外文学定期便―」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 柴田元幸
-
1954年生まれ。翻訳家。文芸誌『MONKEY』編集長。『生半可な學者』で講談社 エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。2017年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。
連載一覧
対談・インタビュー一覧

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら