(17)中国史家・岡本隆司の10冊
通史の味わい方を教えてくれる10冊
著者: 岡本隆司
宮崎市定著/礪波護編『東風西雅抄』(岩波現代文庫)
原勝郎『東山時代に於ける一縉紳の生活』(講談社学術文庫)
竹越与三郎著/中村哲校閲『二千五百年史』(講談社学術文庫)
司馬遼太郎『この国のかたち 全6巻』(文春文庫)
川北稔『砂糖の世界史』(岩波ジュニア新書)
藤沢道郎『物語 イタリアの歴史――解体から統一まで』(中公新書)
間野英二『中央アジアの歴史――草原とオアシスの世界』(講談社現代新書)
宮崎市定『東洋における素朴主義の民族と文明主義の社会』(東洋文庫)
杉山正明『遊牧民から見た世界史 増補版』(日経ビジネス人文庫)
梅棹忠夫『文明の生態史観ほか』(中公クラシックス)
昨年『明代とは何か』(名古屋大学出版会)という書物を著した。一地域の一時代に焦点をあてた著述ながら、全体を視野に入れたつもり、世界史上の「明代」を問いなおす通史である。
 そんな拙著に明代史を専門とする研究者の方々から、種々学会誌上で批評を忝くし、無知な門外漢の誤り偏りを正していただいた。自身あきれる間違いもあって、増刷の機会に最低限の訂正をほどこせたのは幸いである。
そんな拙著に明代史を専門とする研究者の方々から、種々学会誌上で批評を忝くし、無知な門外漢の誤り偏りを正していただいた。自身あきれる間違いもあって、増刷の機会に最低限の訂正をほどこせたのは幸いである。
それにしても考えさせられた。偏向・誤謬が出るのは、菲才を棚に上げれば、あながち理由のないことでもなさそうではある。
著述は読んでもらわないと、無きにひとしい。通史の論著なら、通史・概説なりにおもしろさが必要である。自ら筋が通っておもしろいと思えないことに、他人様がおもしろいと感じ関心をもってくれるはずもない。
そこで武断的独断的な素材・論旨・表現の取捨選択が不可欠となる。勢い余って、ケアレス・ミスのみならず、「過言」「極論」「捨象」「断定」と評される余地も生じかねない。どうやら通史・概説の宿命である。
学界・アカデミズムでもジャーナリズム・一般でも、どうもそこに対する意識と理解が乏しい。通史にはとかく、あれがない、これも誤り的な批判ばかり、これでは執筆意欲が減退するのも、いたしかたない。個性的で読み応えのある通史が少なくなったのは、こうしたところに原因があるのだろう。
通史が担うべき任務は、別にあってよい。歴史の流れを一望し、史実を体系的に解釈したいのは、専門であるかどうかを問わず、誰しも抱く願望である。だから世上、通史に対する渇望は、実は少なくない。
そこであらためて、往年の見るべき著述を紹介しながら、通史の筆法と現代の歴史叙述のかかえる問題を考えてみよう。ひいては、世上・学界の意識の高まりを望みたい。
宮崎市定著/礪波護編『東風西雅抄』岩波現代文庫、2001年(初出1978年)
 若年時オリジナル版を読んで、いたく感銘を受けた東洋史学の巨匠のエッセイ集。当時はわからなかった文脈も、長じて合点がいくようになった。
若年時オリジナル版を読んで、いたく感銘を受けた東洋史学の巨匠のエッセイ集。当時はわからなかった文脈も、長じて合点がいくようになった。
往年の文豪・横光利一と道連れになった旅程をふりかえって漏らす「実感と明晰」こそ「歴史学の立場」であるとのテーゼ、また自身の執筆を論じて「読むための本にはリズムが必要」、「人類の歴史にはリズムがあ」って「思考の流を文章のリズムに写す」には、「速度が必要である」との心得は、斯学の鉄案・通史の骨法にほかならない。
そして圧巻は、原勝郎のエピソードである。
原勝郎教授がその名著、英文『日本歴史』を書いていたときのこと、三浦周行教授の部屋へいきなりとびこんできて、応仁の乱の東軍、兵力何万、西軍の兵力何万、すぐ言ってくれ、と尋ねる。三浦教授が、ちょっと待って、いま調べるから、と答えると、
見込みでいい、見込みでいい、
とせきたてたのは有名な話だが、この気持はよくわかる。本当はブランクにしておいて後でうずめればよいのだが、やはり実数をいれておかぬと書く気分がのらない。
つづけて「あとで直すつもりでも、時間が経つとそれを忘れてしまって、つい大きなまちがいをしでかすことがよくある」という。通史にミスの生じるゆえんであって、「書いてはやめ、書いてはやめ」「調べては書き、調べては書き」したような作品は、「読みものにはならない」。実際に通史を書いてみれば、身にしみて「よくわかる」。
原勝郎『東山時代に於ける一縉紳の生活』講談社学術文庫、1978年(初出1917年)
 上に登場した原勝郎の通史としては、「英文『日本歴史』」のほか、和文で名著の誉れ高い『日本中世史』があって、美しいその文章は、史書といわず著述の規範とまでいわれてきた。しかし今や入手も難しく、手軽には繙けない装丁・内容なので、専著ながら文庫本100頁の手頃な本書をあげる。文体のみならず趣旨もほぼかわらない。
上に登場した原勝郎の通史としては、「英文『日本歴史』」のほか、和文で名著の誉れ高い『日本中世史』があって、美しいその文章は、史書といわず著述の規範とまでいわれてきた。しかし今や入手も難しく、手軽には繙けない装丁・内容なので、専著ながら文庫本100頁の手頃な本書をあげる。文体のみならず趣旨もほぼかわらない。
足利時代を日本のルネサンスだとみて全体史を体系づけ、社会史・生活史の論述を創出し、それまでの日本史の見方を180度転換させた。さすがに一世紀以上も前の作品だから、やや古めかしい文章である。けれども宮崎のいう「実感と明晰」を地で行く歴史叙述で、彼我の時間差を感じさせない。
竹越与三郎著/中村哲校閲『二千五百年史 上』『二千五百年史 下』講談社学術文庫、新装版(2冊)、1990年(初出1896年)

 神武紀元の「二千五百年」というタイトルだけで、かつては敬遠する向きもあっただろうし、今ではこの数字の意味すら知らない向きが多いかもしれない。しかし少なくとも本書では、含意にイデオロギー色はごく希薄、単に日本の通史だというにひとしい。
神武紀元の「二千五百年」というタイトルだけで、かつては敬遠する向きもあっただろうし、今ではこの数字の意味すら知らない向きが多いかもしれない。しかし少なくとも本書では、含意にイデオロギー色はごく希薄、単に日本の通史だというにひとしい。
筆者も恐る恐る繙くと、みるみる引き込まれて一気に読了した。「リズム」に溢れる躍動の文体は、日本史上の英雄を語るくだりに多い。けれども本書は同時に、日本の「時代の精神」を論じた社会史でもある。「北方特有の武断的民主政」の普及や名主・庄屋の「自治制」という論断は、当時の民権思想という著者自身の主張、いな偏見なくしては、とてもおぼつかない。いまなら「極論」といわれそうな概念ばかり、だからこそ痛快である。
司馬遼太郎『この国のかたち 全6巻』文春文庫、1993年~2000年
 原にしても竹越にしても、文明開化の明治の史論であるから、西洋近代の歴史学の影響が色濃い。そんな近代主義にもとづき歴史小説を紡いだ昭和の作家が、司馬遼太郎である。それこそ「実感と明晰」を文字どおり実践する「読みもの」として、大多数の日本人の支持を獲得した。一方でその作品には、事実認定の誤謬や記事・史観の偏向など、歴史学界の批判が絶えなかったのも事実である。アカデミズムに帰属する筆者も、親しく見聞してきた。
原にしても竹越にしても、文明開化の明治の史論であるから、西洋近代の歴史学の影響が色濃い。そんな近代主義にもとづき歴史小説を紡いだ昭和の作家が、司馬遼太郎である。それこそ「実感と明晰」を文字どおり実践する「読みもの」として、大多数の日本人の支持を獲得した。一方でその作品には、事実認定の誤謬や記事・史観の偏向など、歴史学界の批判が絶えなかったのも事実である。アカデミズムに帰属する筆者も、親しく見聞してきた。
しかし通史を手がけて、司馬の作風のゆえんやそこに批判が出るメカニズムが、いっそう「よくわかる」ようになった。およそ通史に対する批判と重なるからである。だとすれば、司馬の文体や作話に学ぶところは、同じ歴史家として少なくない。もちろん菲才なれば及びがたい境地、とても近づけないけれども、まずは持ち重りのする話題を平易に扱った、達意な短文の読み切り型エッセイから入門したい。
川北稔『砂糖の世界史』岩波ジュニア新書、1996年
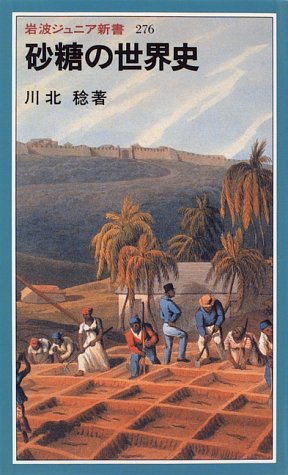 西洋の近代史・近代主義の源は、西洋近代にある。あたりまえながら、ではその近代は、どうやって生まれたか。それは必ずしもあたりまえではない。そのため学問的に研究と論争が続いてきた。経済学としてその歴史を描いたのがマルクスであって、その所説をいっそう周到に洗煉したのが、ウォーラーステインの「世界システム」理論だった。いまや斯界であたりまえ、グローバルな近代世界の構造を一目瞭然ならしめた不朽の達成といってよい。
西洋の近代史・近代主義の源は、西洋近代にある。あたりまえながら、ではその近代は、どうやって生まれたか。それは必ずしもあたりまえではない。そのため学問的に研究と論争が続いてきた。経済学としてその歴史を描いたのがマルクスであって、その所説をいっそう周到に洗煉したのが、ウォーラーステインの「世界システム」理論だった。いまや斯界であたりまえ、グローバルな近代世界の構造を一目瞭然ならしめた不朽の達成といってよい。
それを社会史・生活史にまでひろげつつ日本に定着させた川北の厖大な仕事のうち、最も「世界システム」に偏り、最も平明達意で「実感と明晰」をそなえた通史が、おそらく本書である。これで西洋近代のしくみがわかるといえば、言い過ぎかもしれない。しかし通史には、やはり「過言」がつきものではあろう。
藤沢道郎『物語 イタリアの歴史――解体から統一まで』中公新書、1991年
 そんな「世界システム」は大航海時代にはじまる。それなら大航海時代の起源は、といえば、航海術にしても地球球体説にしても、イタリア・ルネサンスにあった。それなら世界史をみるには、イタリア史は欠かせない。そして本書を読めば、地中海世界と西欧世界は歴史的本質的に異なっていたことがわかる。イタリア史とはローマの崩潰からはじまったからである。
そんな「世界システム」は大航海時代にはじまる。それなら大航海時代の起源は、といえば、航海術にしても地球球体説にしても、イタリア・ルネサンスにあった。それなら世界史をみるには、イタリア史は欠かせない。そして本書を読めば、地中海世界と西欧世界は歴史的本質的に異なっていたことがわかる。イタリア史とはローマの崩潰からはじまったからである。
イタリアは地中海とヨーロッパのはざまにあって、前者で繁栄し後者で衰弱した。西欧流の国民国家になかなかなれなかったその体質は、どこに由来するのか。中国史と同じく、列伝体をとらざるをえない通史の論述が、それを暗示している。
間野英二『中央アジアの歴史――草原とオアシスの世界』講談社現代新書、1977年
 地中海をヨーロッパ・西洋ととらえる向きは多い。けれども愚見・持論では、それは誤解でなければ錯覚である。いまでも東岸・南岸はすべてイスラム圏だし、歴史的にもオリエントの派生とみなしてよい。いわゆるシルクロード西端のフェニキア、つまり現在のシリア・レバノンの拡張として、ギリシア・ローマは出発した。それならシルクロードの正体が、地中海世界理解の鍵になる。
地中海をヨーロッパ・西洋ととらえる向きは多い。けれども愚見・持論では、それは誤解でなければ錯覚である。いまでも東岸・南岸はすべてイスラム圏だし、歴史的にもオリエントの派生とみなしてよい。いわゆるシルクロード西端のフェニキア、つまり現在のシリア・レバノンの拡張として、ギリシア・ローマは出発した。それならシルクロードの正体が、地中海世界理解の鍵になる。
シルクロードの中核は「中央アジア」、本書はそこで主役を演じた「トルコ系」諸族の通史にほかならない。シルクロード・中央アジアはかねて、東西交渉の通路とみなされがちだった。ところがその文明は、じつに草原の遊牧民とオアシスの農民・商人との対峙・交流・相剋という南北関係でできあがっていたととなえたのが、本書である。そんな創見、つまり偏見は衝撃的刺戟的だったがゆえに、批判を受けたのもまた当然ではあった。
宮崎市定『東洋における素朴主義の民族と文明主義の社会』平凡社・東洋文庫、1989年(初出1940年)
中央アジア史・ティムール帝国史の権威だった間野は、上で引用した宮崎市定の高弟である。その宮崎はつとに間野のいう南北関係で、東洋史全体を再構成していた。数え40歳の時その視座から書き下ろした処女作の通史が、本書である。
初出から80年以上経つ文体は、もちろん文語体ながら雄渾無比な筆致、王朝交代・正統史観・中華主義の中国史をあざやかに塗り替えた。世界史・中国史の大半を遊牧世界と農耕世界との対峙交渉とみなし、前者に由来する「素朴主義」の存在と役割を重んじる史観こそ、日本人のつくった東洋史学の精髄なのである。
杉山正明『遊牧民から見た世界史 増補版』日経ビジネス人文庫、2011年(初出1997年)
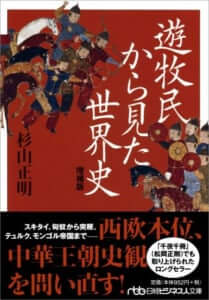 上に紹介した宮崎の通史は、あくまで漢文・漢人・農耕民・「文明主義」の側からみた叙述だった。本書はおよそ半世紀のち、その志を承けて「素朴主義」・遊牧世界の立場・視点から、「ユーラシアを見つめなお」し、世界史の書き換えを試みた通史である。
上に紹介した宮崎の通史は、あくまで漢文・漢人・農耕民・「文明主義」の側からみた叙述だった。本書はおよそ半世紀のち、その志を承けて「素朴主義」・遊牧世界の立場・視点から、「ユーラシアを見つめなお」し、世界史の書き換えを試みた通史である。
遊牧民の側にたつ「ユーラシア世界史」から、「近現代史の枠組みを問う」視座は、まだまだ少数派にすぎない。つまりは西欧本位の歴史像・世界観が、なお支配的だという現状でもある。その自覚・意識のないことが最も恐ろしい。四半世紀も前の本書の所説が、いまだ正鵠を射ていると感じるのは、筆者だけではないはずである。
梅棹忠夫『文明の生態史観ほか』中公クラシックス、2002年
マルクスからウォーラーステインにおよぶ西洋流世界史観は、すでに半世紀以上前、この一篇が覆していた。ユーラシアと世界史の見方を一目瞭然に示した「生態史観」は、しかしあくまで民族学・人類学の成果である。歴史学ではない。
そのためか長く歴史家から批判はあっても回答はなく、対応する歴史叙述もなかった。なかんづく「暴力の巣」遊牧世界の役割をいかにとらえなおすか。そこはわが東洋史学の範疇であったはず。この卓抜な見取図をどうすれば歴史に、通史の叙述に昇華できるか。数十年考えつづけて、いまも試案を書きつづっている。
-

-
岡本隆司
1965年、京都市生まれ。京都府立大学教授。京都大学大学院文学研究科博士後期課程満期退学。博士(文学)。宮崎大学助教授を経て、現職。専攻は東洋史・近代アジア史。著書に『近代中国と海関』(大平正芳記念賞受賞)、『属国と自主のあいだ』(サントリー学芸賞受賞)、『中国の誕生』(樫山純三賞、アジア・太平洋賞特別賞受賞)、『李鴻章』『袁世凱』『曾国藩』『中国の論理』『明代とは何か』『君主号の世界史』など多数。最新刊は『悪党たちの中華帝国』。
この記事をシェアする
「たいせつな本 ―とっておきの10冊―」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら








