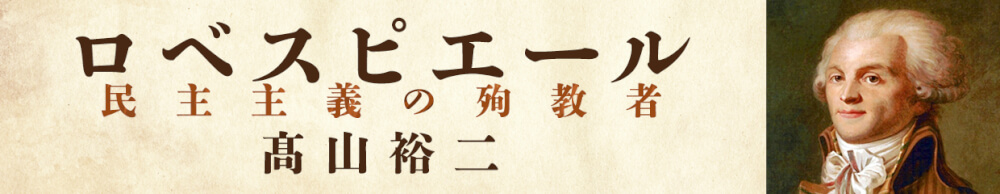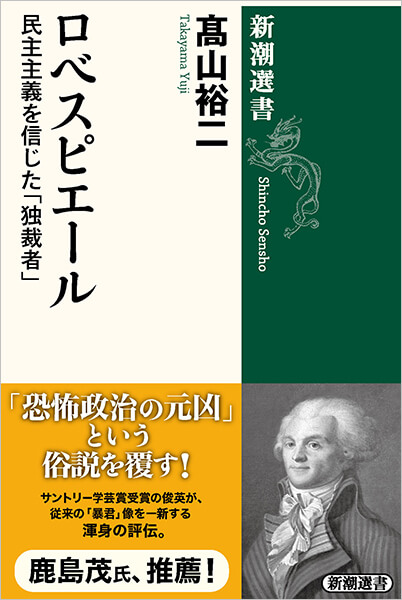第1回 真の民主主義を求めて
著者: 高山裕二
フランス革命において「真の民主主義」を追求したがゆえに、次々と政敵を処刑する「恐怖政治」の権化となり、自らもまたギロチン台の露と消えたロベスピエール。その生涯を辿り直し、民主主義に内在する「魔性」を浮き彫りにする。
「ポピュリスト」以後
トランプ前アメリカ合衆国大統領がワシントンを去って1年と半年が経つ。在任中は、社会を敵と味方に分断し、議会やマスメディアに代表される既成権益層(エスタブリッシュメント)を腐敗していると言って罵倒する一方、司法の独立を攻撃しながら最高裁に自身に近い裁判官を3名送り込んだ。その政治手法は国内外で「ポピュリズム」と批判された。

そのトランプ氏がとりあえず退いた後のアメリカ、そして世界の政治は今後どう変わるのか、変わらないのか。それを予測することは難しいが、ひとつだけ確かなことは、民主制度(≒普通選挙制)を採用する国々において「専制化」――端的に言えば執政府への権力集中――がますます進む傾向にあるということである。現に普通選挙、複数政党による競争型選挙が一応でも実施されている国々でそうした傾向が見られる。1970年代に始まる「第3の波」によって民主化された南欧、ラテンアメリカ諸国(ブラジル等)やアジア(フィリピン等)、それが波及した旧ソ連・共産主義諸国(ロシアやハンガリー等)はもとより、英米のような旧来の民主国家でも、そうした傾向が明らかに進んでいる。
むしろ、民主主義だからこそ、そのような傾向が現出するのかもしれない。そうだとすれば、それはトランプ氏の突飛な言動によってもたらされた一時的な現象として片づけられるような種類の問題ではない、ということになるだろう。
これに対して、いや、民主主義とは人民の多数派の支配だとしても、個人や少数派の権利を尊重するものでもあり、それを保障するのが司法の独立や報道の自由だ、というような反論がありうる。しかし、それが仮に民主政治を支えるものだとしても、それはまた別の理念であって、民主主義それ自体ではない。原理的に言えば、デモクラシーとは古代ギリシアに由来する「デモス(民衆/人民)」の支配であって、それ以上でも以下でもない。マイノリティの権利を擁護し多様な意見を尊重すること、また多数決を採用することでさえ、それは民主政治のひとつの手法であってその目的ではない。
その点で、多様な意見の代表ないし政党による討議に基づく代議制=議会主義も、民主主義そのものとは別物である。かつてそう喝破したのは、ドイツの思想家・法学者のカール・シュミット(1888-1985年)である(『現代議会主義の精神史的地位』1923年)。シュミットによれば、民主主義は国民の平等(=同質性)に基づいて治者と被治者の同一性を前提とした統治である。これに対して、議会主義は国民の不平等と個人主義に基づいて治者と被治者の差異性を前提とした統治であって、これは民主主義というよりも自由主義の一種と言うべきである。したがって両者、要するに民主主義と自由主義とは明確に区別されなければならない。
問題は、民主主義がその原理からして、「デモス」の一体性を求め、そうでないものを排除しうるところにある。人民の支配と言っても、まずは「人民」とは何かが問題となり、人民とそうでないものとが分類される。確かに全員が「人民」ということはありうる。そこに表向きは、外部(敵)はないのかもしれない。しかし、小規模でよほど同質的なコミュニティでもないかぎり、そうあることは難しい。まして、現下のグローバル化する世界においては、そのような同質性を民主国家内で維持することが不可能であることは明らかだろう。逆に、それが国民には移民の増加によって毀損されていると感じられるがゆえに、一体性を強く求め、そのために強い権力が求められているようにも見える。そのことは、国民の同質性が比較的高いと言われてきた日本にとっても、情況の激変(移民国家化?)によって無縁ではなくなっている。
もうひとつの問題は、民主化と世俗化(脱魔術化)が急速に進んだ結果として、民主主義自体が「宗教的」様相を帯びるようになったということである。つまり、人びとのアイデンティティ、あるいは生きる意味のようなものを確証してくれる宗教ないしは〈信じるもの〉の力が弱まるなか、私や私たちの存在証明が民主政治に託されるようになったということである。特に冷戦体制の崩壊で、「世俗宗教」としての共産主義への信用も衰微して以降、その傾向がますます強まっているのではないか。現代フランスの政治思想史家、マルセル・ゴーシェはこれを「代替宗教の破綻」と評した(『民主主義のなかの宗教:脱宗教化の軌跡』[伊達聖伸・藤田尚志訳『民主主義と宗教』]、1998年)。
民主化=宗教化の原点
2年ほど前、トランプ大統領(当時)は弾劾裁判の渦中にあった。2019年12月18日、アメリカの下院本会議は、ウクライナ疑惑[米国大統領がウクライナ大統領に対して軍事支援を取引材料にして民主党の大統領予備選で有力候補だったバイデン氏に関する不利な情報を得ようとしたとされる疑惑]によってトランプ大統領を弾劾訴追する決議を可決したのである。だが、与党共和党が多数を占める上院の弾劾裁判では無罪評決が下された(2020年2月5日)。翌日、トランプ大統領はホワイトハウスで1時間あまりの演説を行い、弾劾につながった捜査について「それは邪悪(evil)だった」と非難した。「それは腐敗した(corrupt)、汚れた(dirty)警官だった。それは密告者であり嘘つきだ」、と。
さらに、その演説に先立って行われた恒例(毎年2月の第1木曜日に開催)の全米祈祷朝食会(National Prayer Breakfast)の席上で、民主党のペロシ下院議長と共和党で唯一造反した元共和党大統領候補のロムニー氏を念頭に置きながらこう言い放った。「周知のように、我が家族と我が偉大な祖国、そしてあなた方の大統領は、幾人かのきわめて不誠実で汚れた(very dishonest and corrupt)連中によって恐ろしい試練を受けたのだ」。
こうして〈敵〉と〈味方〉に選別し、それを「正」と「邪」に置き換えるようなレトリックの政治は、確かに「ポピュリスト」のそれだと考えられる。しかし、問題はやはりそれが「民主的」でもありうるということだろう。というのも、人民に代表されている(少なくとも選挙で選ばれた)〈我々〉に歯向かう〈彼ら〉は「人民の敵だ」という指摘は、理屈の上では一応成り立つからだ。しかも、それがいまや妥協を許さない「神々の闘争」の様相を呈している。そのなかで、近代化(=脱魔術化?)したはずの時代には信じられないような偏見や迷信、陰謀が大きな力を恢復しつつある。
もちろん、その種の闘争は今に始まったわけではない。民主化=宗教化の原点を求めて歴史をひもとくと、私たちはひとつの歴史的事件に出くわす。1789年、フランスで勃発した大革命である。その原理は、フランス革命のなかで初めて典型的なかたちで現出した。よく考えてみれば、先ほど述べた民主主義の手法、民主政治を維持するための条件や理念(=自由主義)というのはそれ以後、19世紀と20世紀を通じて人類がさまざまな挑戦を経て「権利」として勝ち取ってきたものである。フランス革命に立ち返って考えることは、それらのヴェールをとりあえず剥ぎ取って、民主主義をある意味で原初状態のもとで理解するに等しい。
フランス革命は、人民の主権を宣言することで、現代民主主義の礎を築いたと言われる。しかし、同時にそれは宗教(カトリック)に代わる信仰であるかのように唱えられ、人民の〈友〉と〈敵〉に分かれて妥協なき闘争を繰り広げたことを思い出そう。この革命、とりわけその後半期は世界史ではしばしば「恐怖政治」として切り捨てられるのが定石である。そのため、その中心にいた「独裁者」とみなされるロベスピエールへの評価も他に比肩するものがないほど厳しい。しかし、良かれ悪しかれ、この人物こそ民主主義の原理を体現していたのではないか。
ロベスピエールと民主主義のレッスン
マクシミリアン・ロベスピエール(1758 - 94年)は、フランス革命において普通選挙制のために戦い、死刑制度廃止を含む人民の権利保障を熱心に訴えた人物である。それにもかかわらず、「清廉の人」の思想と行動は今まで正当に評価されてきたとは言い難い。テルミドールのクーデタで彼を失墜させた者たちによって恐怖政治の「独裁者」というイメージが吹聴され、それがのちに定着したためである(歴史的業績を讃えて通りなどに人物名をつける慣行のあるフランスの首都パリには、今までに彼の名を冠した通りはない。2011年にある市議からそうした提案があったが議会で否決された。同じくフランス革命の志士であるダントンやサン=ジュストでさえその名の通りがあり、またナポレオンを讃えたモニュメントが山ほどあるのとは対照的である)。一方で、彼を礼賛する者も一部いたが、彼らを含めロベスピエールの思想、その民主主義の理念の真価は十分に語られてこなかったのではないか。

20世紀に入って、ロベスピエールの名誉回復に先鞭をつけた高名なフランス革命史家のアルベール・マチエは、彼を「怪物として憎む者もあれば〔革命の〕殉教者として崇める者もある」が、どちらも革命をめぐる利害・情熱にとらわれており、今こそそこから離れて真実を明らかにしなければならないと訴えた。だが、そのプロジェクトは依然として未完である。
その人と思想を理解するためには、さしあたり革命期の評価を一旦離れて、ロベスピエール個人の精神史に着目する必要があるだろう。というのも、もともと彼にとって真の自己(私)の存在の探求と真の政治(共和国)の探求はオーバーラップするものだったからだ。ロベスピエールによれば、市民は「仮面」を剥ぎ合い、その意志は他の市民、そして社会や国家の意志と一直線に結びつく、結びつくべきであり、その一体性によって初めて真の共和国=《民主主義》が実現する。逆に言えば、民主主義は〈私〉同士が一致し――皆が純粋に〈私〉を告白すれば必ず意志が一致するということを前提にして――、そうでない者を取り除くことで成り立つ政治である。そもそも民主主義とは、一体としての人民の意志の支配のはずではないか。
ところが、ロベスピエールもその犠牲者となる。いや、《民主主義》=真の民主主義を追求したからこそ、彼自身もギロチン台で〈敵〉として露と消えなければならない運命だったのではないか。一体としての人民の支配としての民主主義はひとつの特権も、ひとりの独裁者も許さないはずだから。ここに浮かび上がるのは、革命の殉教者というよりも、あくまで《民主主義》の殉教者としてのロベスピエールの姿である。
では、「ポピュリスト」と呼ばれる現代の政治家に、民主主義それ自体のために殉教する覚悟はあるだろうか。むしろ、ロシアをはじめ東欧や南米の一部の政治指導者によって私益のために民主主義は利用=偽装され、各地で「専制化」しつつある。しかし問題がより深刻なのは、すでに述べたように、そのような傾向が「西側」でも進んでいることである。なるほど、「東側」の指導者は西欧の民主主義は偽善だと主張するが、その主張を暗に讃える有権者が欧米諸国のなかにも多く存在していることはその証左だろう(アメリカ合衆国ではプーチン大統領を英雄視する人びとも少なからず存在するという)。その事実は、民主主義を利用した権威主義体制が世界中に拡散した未来を予感させる(イワン・クラステフ、スティーヴン・ホームズ『消えゆく光』[立石洋子訳『模倣の罠――自由主義の没落』]、2019年)。
いや、実のところ、民主主義には権威主義的政治に利用されやすい面があるのではないか。そうだとすれば、私たちが民主主義の「専制化」とは異なる未来を描くことはそもそも不可能なのだろうか。それは、民主主義それ自体を知解しなければわからないのではないか。
本連載では、真の民主主義を探求したロベスピエールの精神の軌跡をたどりながら、それが悲劇に終わったときに立ち顕れるその魔性を含め、民主主義そのものへの接近を試みてみたい。
*この連載では、参考にする文献の紹介は最低限にとどめ、仔細は書誌情報を含め後日予定のある書籍化の際にまとめて記す予定である。なお、ロベスピエールの口頭弁論やパンフレット、演説や書簡等の言説はすべて、彼の全集(全10巻)Œuvres complètes de Maximilien Robespierre, 10 volumes, Société des études robespierristes, (Paris: Ernest Leroux, 1912-1967)、および近年公刊されたその補巻(第11巻)Tome 11, Compléments (1784-1794), édition présentée et annotée par Florence Gauthier, (Paris: Société des études robespierristes, 2007)を参照する。
この連載が単行本になりました
髙山裕二『ロベスピエール 民主主義を信じた「独裁者」 』
「恐怖政治」という理解だけでは見えない政治家の真実とは?
フランス革命で政敵を次々と粛清、最後は自らも断頭台で葬られたロベスピエール。「私は人民の一員である」と言い続けた元祖〈ポピュリスト〉は、なぜ冷酷な暴君に堕したのか。誰よりも民主主義を信じ、それを実現しようとした政治家の矛盾に満ちた姿から、現代の代議制民主主義が抱える問題の核心を鋭く問う画期的評伝。
-

-
高山裕二
明治大学政治経済学部准教授。博士(政治学)。専攻は政治学・政治思想史。著書に『トクヴィルの憂鬱』(白水社、サントリー学芸賞受賞)、共著に『社会統合と宗教的なもの 十九世紀フランスの経験』(白水社)、『近代の変容(岩波講座 政治哲学 第3巻)』(岩波書店)などがある。
この記事をシェアする
「ロベスピエール 民主主義の殉教者」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 高山裕二
-
明治大学政治経済学部准教授。博士(政治学)。専攻は政治学・政治思想史。著書に『トクヴィルの憂鬱』(白水社、サントリー学芸賞受賞)、共著に『社会統合と宗教的なもの 十九世紀フランスの経験』(白水社)、『近代の変容(岩波講座 政治哲学 第3巻)』(岩波書店)などがある。
連載一覧
著者の本

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら