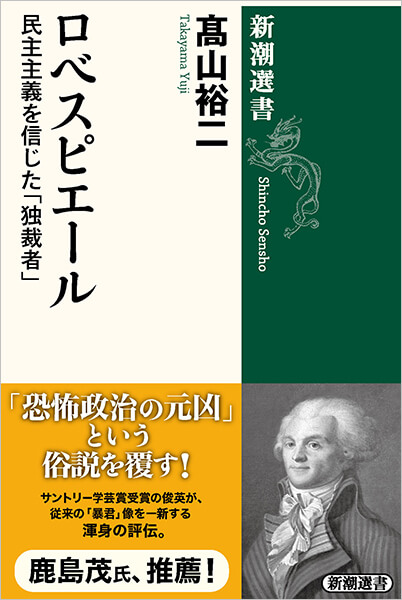髙山裕二『ロベスピエール――民主主義を信じた「独裁者」』刊行記念エッセイ
トランプとロベスピエール――狂気に通ずる民主主義に寄せて
著者: 高山裕二
稀代の〈ポピュリスト〉、ドナルド・トランプ氏がアメリカ大統領に返り咲くことが決まりました。そして、奇しくもこのタイミングで、フランス革命で活躍した元祖〈ポピュリスト〉の評伝『ロベスピエール――民主主義を信じた「独裁者」』(新潮選書)が刊行されます。はたして2人の〈ポピュリスト〉には、どのような共通点と相違点があるのでしょうか。著者の髙山裕二さんに刊行記念エッセイを寄せていただきました。
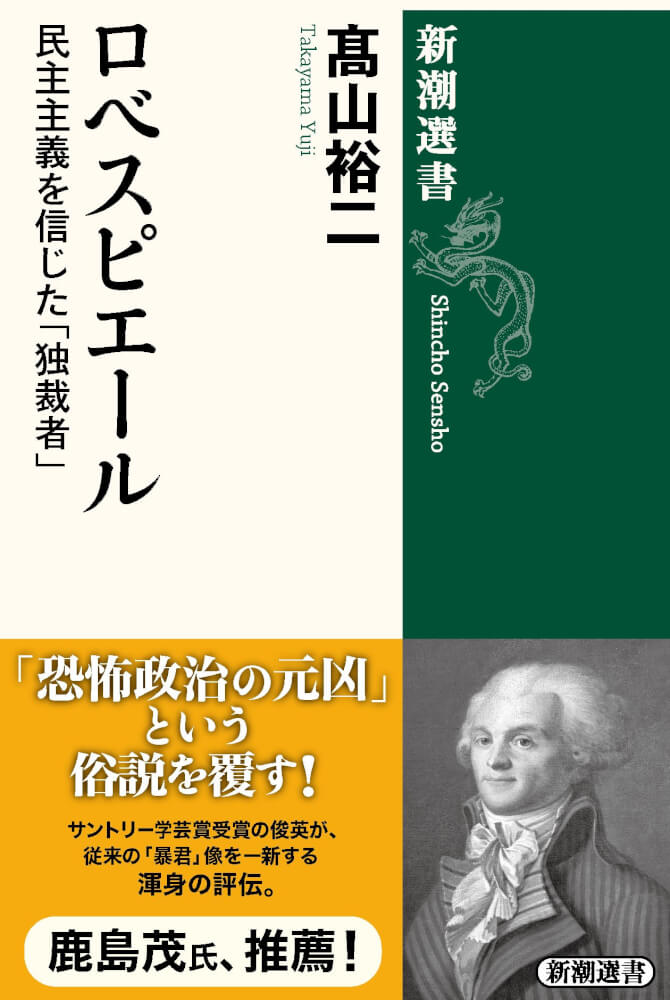
現代世界の「専制化」の傾向
2022年5月、本サイトの連載「ロスベピエール 民主主義の殉教者」、第1回「真の民主主義を求めて」の冒頭で、わたしは次のように書いている。
そのトランプ氏がとりあえず退いた後のアメリカ、そして世界の政治は今後どう変わるのか、変わらないのか。それを予測することは難しいが、ひとつだけ確かなことは、民主制度(≒普通選挙制)を採用する国々において「専制化」――端的に言えば執政府への権力集中――がますます進む傾向にあるということである。現に普通選挙、複数政党による競争型選挙が一応でも実施されている国々でそうした傾向が見られる。
2年半余り、このような「専制化」の傾向は衰えていない(その後、世界の「権威主義化」については優れた研究も公刊された。東島雅昌『民主主義を装う権威主義――世界化する選挙独裁とその論理』千倉書房、2023年)。そして先日、ドナルド・トランプ氏がアメリカ合衆国大統領に再選された。「とりあえず退いた」というのは、もちろん再選を意識した上での表現だったが、これほど選挙人数上大差で再選されるとは筆者も予想外だった。その要因はともかく、先の大統領選で選挙結果を受け入れず、またそれを不服として連邦議事堂に乱入した暴徒を煽動するかのような発言をした人物が、再び大統領に「民主的」に選出されたのである。
上下両院でも共和党が多数を獲得する、いわゆるトリプルレッドになる見通しである。このことは、大統領の再選それ自体よりも政治的な影響は甚大である。なぜなら、同党大統領への権限が確実に集中しうるからだ。さらに、アメリカ合衆国憲法は大統領の3選を禁じるが(修正22条)、憲法改正によって3選を「合法的」にすることも理論上は可能である(改正には両院の3分の2による発議に加えて、州議会の4分の3の承認が必要で、現実的には難しい)。
こうして、かつて民主国家のモデルとされ、今でも経済・軍事両面で最大の国家であるアメリカ合衆国でも、「専制化」(=権力集中)の傾向が見られる。それでも、それは驚くべきことではないかもしれない。先ほどの引用箇所に続けて、わたしはこうも書いている。
むしろ、民主主義だからこそ、そのような傾向が現出するのかもしれない。そうだとすれば、それはトランプ氏の突飛な言動によってもたらされた一時的な現象として片づけられるような種類の問題ではない、ということになるだろう。
民主主義にもかかわらずではなく、民主主義だからこそ生じる「専制化」。なぜか?
民主主義はもともと「デモス」(人民)の支配を意味し、その一体性を前提とするが、実際には「人民」なる主体は存在しない。そのため、「人民」の名の下に、その声を体現すると称する指導者が現れ、彼とその周辺に権力が集中する傾向がある。また、真の人民(国民)ではないとされる者を排除することで、その一体性を強化しようとする傾向が生まれる。
こうして、自分は真の人民(国民)の代表者であると主張し、人民の真の利益に反する主張をしているとされる者を「敵」として攻撃する指導者のことを「ポピュリスト」と呼ぶ。その元祖の一人はロベスピエールだろう。では、彼は現代の「ポピュリスト」と同じだろうか。


このエッセイでは、トランプ氏が再選された政治状況を念頭におきながら、拙著『ロベスピエール――民主主義を信じた「独裁者」』(新潮選書)をもとに元祖〈ポピュリスト〉の特徴を瞥見することで、トランプ以後の民主主義の課題について少し考えてみたい。
元祖〈ポピュリスト〉の矜持
青年時代、ロベスピエールは古代ローマの歴史から善悪二元論的なレトリックを学び、また田舎に戻って弁護士業をする中で友敵の論理を鍛えあげた。人民の〈友と敵〉という対立の構図を作り、敵を糾弾する様子は、まさに現代の「ポピュリスト」のそれである。
しかも、バスティーユ監獄襲撃から始まるフランス革命の過程でロベスピエールは何度か民衆の「蜂起」を正当化した。1793年5月、ブリソ派(ジロンド派)が民衆に人気があったマラを不当に逮捕した際にも人民の蜂起を正当化し、それを勧告するような言動さえ行なった。「あらゆる法が犯されたとき、専制が絶頂に達したとき、誠意や貞節が踏みにじられたとき、人民は蜂起しなければならない」(本書第10章)。
それはトランプ前大統領と同じだろうか。しかし、違いをあえて強調すれば、ロベスピエールの場合は、民主的選挙の結果を覆すような蜂起を正当化したわけではない。しかも、彼の言動は自分(たち)の立場や利害を擁護するために民衆を煽動するようなものではなかった。そこでロベスピエールが正当化したのは――為政者によって法が犯されたあとに起こる――民衆主導の蜂起である。彼が人民の蜂起権を主張したのはその証左だろう。
また、ロベスピエールは蜂起権とともに人民の請願権を「不可欠の権利」と呼んで重視した(本書第7章)。それは、「民衆が人民主権を定期的に行使する機会を開くためだった。彼は、議員が〈人民=民衆〉の声から逸脱した場合は、その声に耳を傾けるようにさせる仕組みが必要であると考えていた」。

この点に現代の「ポピュリスト」との大きな違いがあるように見える。彼らは人民の代表であると自称しながら国民を煽動する反面、国民の主体的な政治参加を期待しているわけでは必ずしもない。対してロベスピエールは、それが人民の意思(=一般意思)に基づく政治=民主主義には必要だと考えた。だからこそ彼は「私は人民の一員である」と繰り返す一方、自分は――人々が言うような――人民の「守護聖人」(=彼らの意思の体現者)ではないと言明した。
元祖〈ポピュリスト〉が信じた民主主義は、一般意思に基づく政治で、それは人民と代表者が透明な関係性を構築する場合に可能となる。だが、ロベスピエールに独自なのは人民の主体的な行動への期待とは裏腹に、代表者の役割と責任は大きいと考えたところにある。つまり、「人民」は代表される必要があるのであり、そのためには政治家が特殊(=個人的)利害に拘泥しない、その意味で腐敗していないことが求められた。彼はそれを《美徳》と呼んだ。
確かに、《美徳》は人民(民衆)には自然に備わっているはずだと想定されたが、それはしばしば曇らされているため、彼らは啓蒙される必要がある。だからこそ、代表者の役割と責任はあまりに大きい。政治家みずからが《美徳》ある存在たることが求められたのである。
したがって、ロベスピエールは直接民主主義を否定する。人民の意思(一般意思)に基づく政治が展望されたが、それには政治指導者の存在、彼らの《美徳》が不可欠なのだ。それが「清廉の人」、元祖〈ポピュリスト〉の矜持でもあった。もっとも、《美徳》が失われつつある時代にその成就は困難であることも、彼自身がおそらく誰よりも自覚していたはずだ。
それを踏まえると、現代の民主主義にとって深刻なのは、政治イデオロギーの相違よりも、《美徳》なき時代の特殊利益の支配、政治経済におけるオリガーキの再来のように思えてくる。
《美徳》なき時代のゆくえ
戦後日本のロベスピエール研究に先鞭をつけたのは、ナポレオン研究でも知られる歴史家井上幸治の『ロベスピエール――ルソーの血ぬられた手 (歴史の人間像) 』(誠文堂新光社、1962年)である(再版された際に『ロベスピエールとフランス革命』(1981年)とタイトルを変更)。
同書では、タイトルにあるように、ロベスピエールが「ルソーの血ぬられた手」と表されている。ただ、これは井上のオリジナルではない。「まえがき」(初版)によれば、それはドイツの詩人ハインリヒ・ハイネ(1797-1856年)の表現だという。
フランス革命のさなかでも、そののちの時期でも、ロベスピエールを「吸血鬼」、「虎」と呼んだし、ハイネのような自由主義の詩人でも、彼の名を革命テロルと直接結びつけていたのであろう、「ルソーの血ぬられた手」と詠んでいる。
ここに出典は明記されていないが、ハイネは実際そう言っているのだろうか。『ドイツの宗教と哲学との歴史のために』(1834年刊。岩波文庫のタイトルは『ドイツ古典哲学の本質』1951年)をひもとくと、ロベスピエールはルソーの思想を「時代の母体からひっぱりだした血まみれの助産婦」だと書かれている。続けて、「血みどろの両手」という表現も出てくる。
サン・トノレ町に住んでいた偉大な俗物マキシミリアン・ロベスピエールは王政を倒すとなれば、もちろん、例の「破壊的」狂犬病の発作におそわれ、つづいて「国王首切り」の癲癇をおこして、ものすごくひきつけたものだ。けれどもお寺参り〔最高存在の祭典〕をするとなると、すぐさま癲癇の白い泡を口からふきとり、血みどろの両手をあらってから、ぴかぴかひかるボタンのついた青色の晴れ着をきて、おまけに幅広の胸着に花束をさして出かけたのである(伊東勉訳。表記を一部変更)。
この引用では、ロベスピエールの「吸血鬼」のような残忍性があらゆる表現を使って強調されている。井上自身、旧制中学の歴史の教科書か参考書でロベスピエールのことが「性、残忍酷薄にして」と書かれてあったというエピソードを紹介しているが、その種のイメージは今日も日本国内ではさほど変わっていないだろう(井上も触れているように、フランスではその時すでに「ロベスピエール復権」の兆しがあり、今も再評価が進む。「暴君」や「怪物」というイメージが彼の失脚前後にいかに作られたかを論じた研究が最近翻訳された。ジャン=クレマン・マルタン『ロベスピエール――創られた怪物』田中正人訳、法政大学出版局、2024年)。
もっとも、負のイメージが誇張されているとはいえ、ロベスピエールには残忍な面があり、その面が強調される歴史的理由は十分にある。狂気(=恐怖政治)へと至るフランス革命において、彼が枢要な役割を果たしたのは事実である。しかし、ルソー思想の実践者として残忍さばかりが刮目されるあまり、彼がただルソーの「思想の助産婦」だったのではなく、その実践者として苦悩しながら師とは異なる民主主義を構想し、信じたことが見落とされてはならない。
拙著『ロベスピエール――民主主義を信じた「独裁者」』で描かれるように、ロベスピエール自身、ルソーの神話的な立法者像の影響を受け、おそらくそれに憧れた面があるにせよ、彼にとって立法者はあくまで目の前にいる「代表者」だった。それは彼がルソーとは違い、現実の政治家だったことと無縁ではない。伝説的な指導者、あるいは理想的な人民(民衆)に政治を委ねるのではなく、しばしば無知な人民(民衆)を導く現実の政治家と議会の責任の重さをロベスピエールは主張した。この点は、トランプ氏が再選されたこの時期に改めて注目されていい。革命指導者が求めたような責任は重すぎるとはいえ、政治家に《美徳》をまったく期待できなければ、代表制(=議会制民主主義)の存続は危ういと考えられるからだ。
加えて、民主主義には「人民」の一体性が必要とされる、ロベスピエールはそう主張した。そこで彼が考案したのが、「最高存在の祭典」だった。そこにも、ルソーの「市民宗教」の影響を見るのは容易い。しかし、ロベスピエールは単なる理論家ではなく実践家として、その宗教の祭典を主宰し、「独裁者」という批判を浴びながらも、各宗教の自由を認めながら国家を超える価値を基調とした信仰と、それに基づく国民の一体性を求めた。
では、トランプ氏が「アメリカを再び偉大に」と言うとき、一体性の回復は目指されているだろうか。ロベスピエールの視点からすれば、民主国家に求められるのは社会の分断を超えた一体性である。だが、メディアを通じて聞こえてくるのはアメリカ社会の分断を煽る言動ばかりである。
他方、今日のアメリカで一体性を回復する手段がないわけではない。それはフランシス・フクヤマによれば、合衆国憲法の理念の保守であり、建国の記憶の想起であるという(この点については、『IDENTITY――尊厳の欲求と憤りの政治』山田文訳、 朝日新聞出版、2019年を参照)。ただその場合、たとえば独立革命については伝統的な理解ではなく、多様なアクターに目配せしたような今日的な理解に基づく「一体性」が必要となるだろう(そのような革命の理解についてはさしあたり、上村剛『アメリカ革命――独立戦争から憲法制定、民主主義の拡大まで』中公新書、2024年を参照)。国民の「一体性」とは、アイデンティティの「同一性」ではないのだから。
いまや問題はトランプのアメリカではない。トランプ後のアメリカで、そのような一体性が保たれるか、言いかえればポストトランプの世界を見据えて一体性の回復に向けた取り組みが今できるかどうかだろう。それが、フランス革命の友敵の論理が至った狂気に陥らないためには必要である。少なくともアメリカ有権者の多数の不満をトランプ氏が受け止め、支持されたという事実を反対者も受け入れることから始めなければならない。彼を非難するばかりで、彼を支持した人々の意思に目を向けなければ、「一体性」を前提とした民主主義の未来は暗い。
-
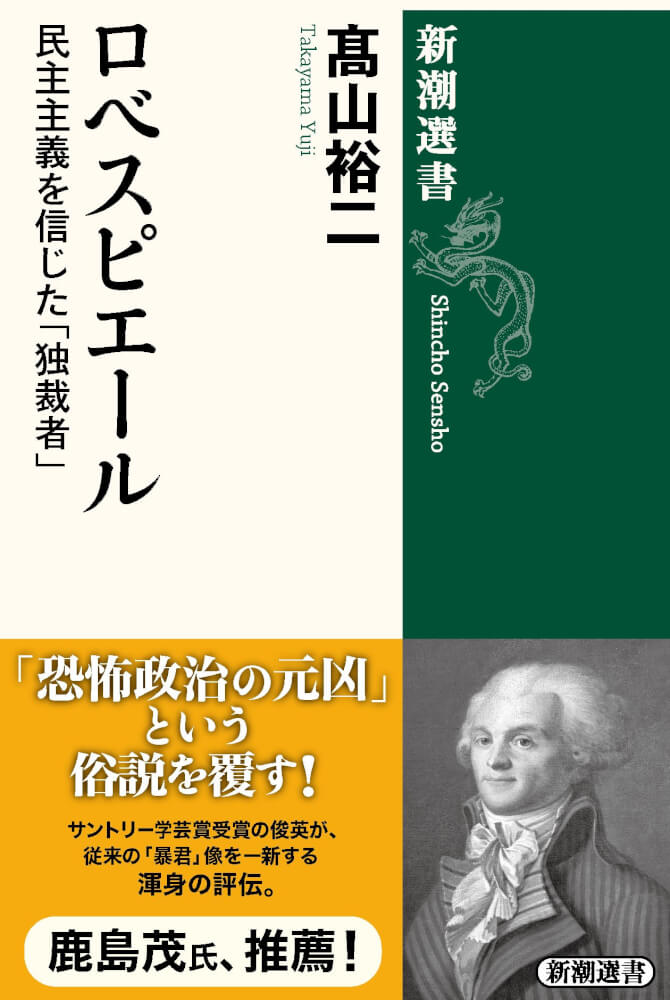
-
髙山裕二『ロベスピエール――民主主義を信じた「独裁者」』
2024/11/20
公式HPはこちら。
この連載が単行本になりました
髙山裕二『ロベスピエール 民主主義を信じた「独裁者」 』
「恐怖政治」という理解だけでは見えない政治家の真実とは?
フランス革命で政敵を次々と粛清、最後は自らも断頭台で葬られたロベスピエール。「私は人民の一員である」と言い続けた元祖〈ポピュリスト〉は、なぜ冷酷な暴君に堕したのか。誰よりも民主主義を信じ、それを実現しようとした政治家の矛盾に満ちた姿から、現代の代議制民主主義が抱える問題の核心を鋭く問う画期的評伝。
-

-
高山裕二
明治大学政治経済学部准教授。博士(政治学)。専攻は政治学・政治思想史。著書に『トクヴィルの憂鬱』(白水社、サントリー学芸賞受賞)、共著に『社会統合と宗教的なもの 十九世紀フランスの経験』(白水社)、『近代の変容(岩波講座 政治哲学 第3巻)』(岩波書店)などがある。
この記事をシェアする
「ロベスピエール 民主主義の殉教者」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 高山裕二
-
明治大学政治経済学部准教授。博士(政治学)。専攻は政治学・政治思想史。著書に『トクヴィルの憂鬱』(白水社、サントリー学芸賞受賞)、共著に『社会統合と宗教的なもの 十九世紀フランスの経験』(白水社)、『近代の変容(岩波講座 政治哲学 第3巻)』(岩波書店)などがある。
連載一覧
著者の本

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら