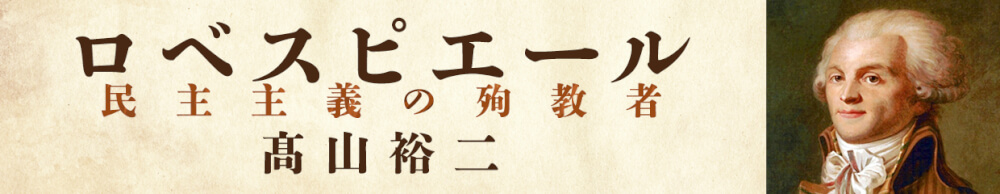「抑圧された人々」のために
当時、アラスは2万2千人ほどの住民が暮らす地方の中心都市だった。それでも、長引く不況で繊維産業は衰退し、伝統的な穀物取引に多くを依存していた。政治も、アルトワ州三部会からして貴族によって占められ、また高位聖職者が行政権力に食い込み、同州司教コンズィエを中心に「特権階級」が大きな影響力をなお誇示する世界だった。そこでロベスピエールは、父や祖父と同様、王国の四つの州にある州上級評定院つきの弁護士として登録されるが(1781年11月)、みずから個人的なネットワークを構築してゆかなければならなかった。

「一着の服と穴のあいた靴しか持っておらず」、社交的でなかったパリの大学の給費生が、帰郷した地方の世界で生き抜いてゆくのはそれほど簡単ではなかっただろう。だが、彼はここでもその能力によって頭角を現すことになる。半年後、普通は10年待つとされた司教管区裁判所[アラスとその周辺にある30ほどの教区を管轄する裁判所]の5人の裁判官の1人に抜擢されたのである。その能力と人格は、周囲にも強い印象を残したという。裁判デビューを果たしたロベスピエール氏は話ぶりやその明晰さの点で彼に及ぶものは皆無というじゃないか――アラスのある弁護士は手紙にそう書いている。これに対する返事で、当時パリ法科の学生だった同郷のエティエンヌ・ラングレはこう賞賛した。
事実、このド・ロベスピエール氏という人物は、君が言うように恐ろしい人だ。付け加えて言うなら、彼の優秀さに喝采を送り、このような才気溢れる人物を生んだわが故郷を祝福したい気持ちを抑えられないよ。(マクフィー『ロベスピエール』)
ここでも日課は厳格に守られた。シャルロットの回想によれば、早朝に起きると、8時に鬘職人がやってくるまで仕事をし、パンと牛乳で朝食をすませ、仕事を再開、10時までには裁判所に出勤した。午後は軽食ですませるが、コーヒーを愛飲し、果物、特にオレンジがお気に入りだった。帰宅後は、散歩をした後に仕事を再開し、夜遅くに食事をとったが、作業に夢中になるあまり食事をとるのを忘れることもしばしばだったという。ロベスピエールの伝記作家ルース・スカーが書いているように、革命がなければ、このままルーティンを厳格にこなしながら生を全うしたのだろう。コーヒーを飲む量からすると、胃か腸の癌で亡くなったのかもしれない。しかし、時代は勤勉な青年を平凡な生には留めておかなかった。
上級評定院では、1年目から13件の裁判の弁護を担当し、2年目は28件で法廷に立ち、3年目は13件と数こそ減ったが、そのうち10件で勝訴した。仕事は順調だったが、苦い経験もした。司教管区裁判所の裁判官でもあったため、殺人者に死刑判決を出さねばならなかったのである。しかも当時は、ギロチンが発明される前で、庶民には車裂きの刑が処されていた。妹の回想によれば、その判決の夜、帰宅すると兄は絶望した様子で、「彼が有罪であり、悪党であることはわかる、それでも1人の男に死を宣告せねばならぬとは……」と繰り返したという。こうした伝統的な慣習・因習と彼の「良心」との間の葛藤は日に日に大きくなってゆく。
シャルロットによれば、兄が法曹の道に進んだのは「抑圧された人々」を擁護するためだった。1783年に始まるドトフ事件裁判はその一例である。それはある修道士(会計係)が修道院の若い女中クレマンス・ドトフの兄を窃盗容疑で告発した事件だった。兄フランソワによれば、修道士は自身の窃盗を隠すため、また妹を口説いたが断られたその腹いせのために告発したのだ。地方の有力な地主でもあったアンシャン修道院に対して「質の悪いパンすら家族に供給することも難しい」庶民は泣き寝入りせざるをえないところ、ロベスピエールは彼を果敢に弁護し、3年に及んだ裁判で勝利した。このとき、既存の法秩序に対する「常軌を逸した見解」を表明したと弁護士会から叱責を受けたが、ロベスピエールがそれを意に介した様子はない。彼は「抑圧者に対して抑圧された人々を守ること」を義務だと信じていたからにほかならない。
「科学」の勝利
ロベスピエールの弁護士活動でもっとも有名な訴訟として、「避雷針事件」(1783年5月)がある。ある法曹家の建てた巨大な避雷針を不安に思った――先入観のためにその装置に落雷して爆発や地震が起こると思い込んだ――住民たちの訴えを認めるかたちで、裁判所はその取り壊しを命じた事件である。これに対して、訴えられた側は上級評定院に上告、富裕な弁護士でアマチュア科学者でもあったアントワーヌ=ジョゼフ・ビュイサールに弁護を依頼した。するとビュイサールは、当初はその教育係を務めていたロベスピエールにその仕事を任せたのである。そこでロベスピエールは、この20歳以上離れた友人が所蔵する膨大な啓蒙書を参照しながら、本件で逆転勝訴を勝ち取った。その弁論は彼の「哲学」を開示する機会ともなった。
新米の弁護士は口頭弁論冒頭、アリストテレスからデカルトまでの哲学の歩みや、医学の発見について触れた後、次のように言って〈光の世紀〉を謳いあげる。「今後は才能がその活動のすべてを自由に行うことが許され、科学は完成に向けて急速にその歩みを進めます。われわれの世紀を特徴づけるのはこの理性という特性であり、そのために人間精神がこれまで思いついたなかでもおそらくもっとも大胆でもっとも驚くべきアイデアが、普遍的な熱意を持って迎えられてきたのです」。ここには、個別の事件の弁護を超えて、彼の時代認識とそのうえでの自己主張を見てとることができよう。それは、今は理性の時代であり、人類は誤謬や偏見のためにその歩みを止めてはならず、その進歩にむしろ奉仕すべきだという理念である。
第2回口頭弁論でも、冒頭でこう述べる。「前回の弁論であなた方に提出された反対意見に対し、今日も応答する勇気を私に与えるのは同じ動機です。私はできるかぎり全力で、それと思い切って戦いさえするでしょう」。ヨーロッパ中の支配者や国民がこの戦いに加わってきたし加わるべきであり、フランス人もそれに倣うべきだと呼びかけ、一地方の「避雷針事件」を、ヨーロッパに残るあらゆる旧弊に挑むという普遍的な問題にしてしまう。そして、「すべての科学者の側に味方する」かどうかは、わが祖国の名誉の問題であるとさえ言って憚らない。
この事件に注がれるヨーロッパ中の眼差しによって、あなた方の判決が受けるべきあらゆる評判は確実なものとなるでしょう。この狭い地方内部に視野を制限しないでください。首都を見てください、フランス全土を、他の諸外国を見てください、あなた方の判決を待ちかねています。……パリ、ロンドン、ベルリン、ストックホルム、トリノ、サンクト・ペテルブルグはアラスとほとんど時を同じくして、この科学の進歩に対するあなた方の英知と熱意の金字塔をすぐに知ることでしょう。
こうしてロベスピエールは弁論を通して、みずからの科学(=学問)そして啓蒙への信仰を吐露している。そして、このために「科学」という分野を超えた〈戦い〉が必要であることを示唆している。ただ、それがどこまで「政治的」問題であると意識されていたかは定かではない。言い換えると、この時点で彼にとって自己主張が政治(改革)と必然的に結びつくと意識されていたかは判然としない。いずれにしても、その弁舌が評判を呼び、「彼はもうムッツリした青年ではなく、社交を求め」る大人になっていた――ある研究者はそう描写している(マルク・ブゥロワゾォ『ロベスピエール』[遅塚忠躬訳]1957年)。
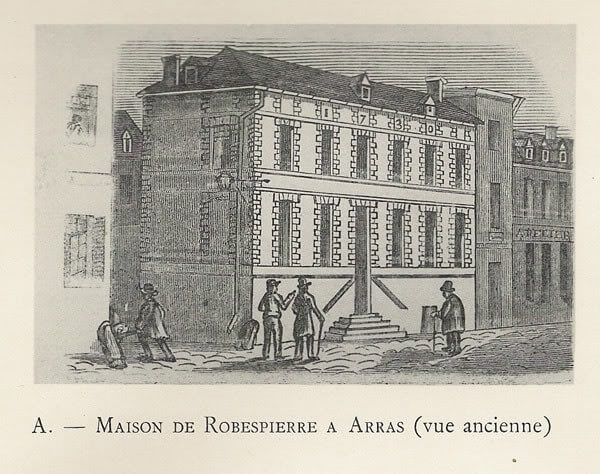
デビュー演説と「名誉」
「避雷針事件」で科学を勝利に導いたロベスピエールは同年11月15日、ビュイサールが院長を務めるアラス王立アカデミー(学士院)会員に選出される。そして翌年の4月に行った入会演説は、彼の政治観を初めて披瀝したという点で事実上のデビュー作といえる。
その演説でも偏見と不正義の不利益を訴えるが、そこで選ばれたテーマはいわゆる加辱論、すなわち「市民権の喪失を伴う処罰」によって罪人の家族全員もその不名誉を背負うべきかどうかというテーマだった。これは実は、メッス(フランス北東部にある都市)の王立アカデミーが公募した懸賞論文の論題に由来し、加辱は有害か、そうだとすればその対処法は何かを問うたものだ。演説後、ロベスピエールは原稿をいくらか手直しして懸賞論文に応募し落選するも、選考委員会が感銘を受けて特別賞(入選と同等の報賞400リーブル)が授与されることになった。同年、彼は報賞金を使ってパリで同論を自費出版する。
主にモンテスキューの『法の精神』(1748年)を引き合いに出しながら語られるその入会演説は、未来の政治指導者にとって事実上のデビュー作といえる。その理由は、政治・社会の基礎には〈美徳〉がなければならないという、彼の根本思想が語られているからにほかならない。これに対して批判されるのは、モンテスキューが君主政の原理と規定した「名誉」である。
演説冒頭、アカデミーないし科学者は「公共の利益」に尽力するものであると述べ、自分もあなた方(アカデミシャン=科学者/研究者)には遠く及ばないとしても、その役に立ちたいと語る。その観点から加辱の原因である「偏見」は有害であると断じる。彼によれば、偏見はある国民や人類の名誉をある個人の行為に帰すことから始まったもので、ある時代の意見(opinion)にすぎないが、統治の形態次第で大きな影響力を有することになったという。
たとえば、「専制国家においては、法は君主の意思でしかありません」。それは、刑罰が君主の怒りの表徴でしかなく、不名誉が君主の意見によって決まることを意味する。これに対して、「各人が政治に参加でき、主権の構成員であるとすれば」、その種の偏見が力を持つことはない。つまり「共和政の自由は、この意見の専制に反抗するでしょう」。ここでは、君主政が直接批判されているわけではないが、それに対して共和政の利点が語られているのは明らかである。
モンテスキューが言明したように、共和政の原理は〈美徳〉だが、共和政において偏見が追放されてきたことは古代ローマの歴史が証明している。また、ロベスピエールは現代の近くにある模範としてイギリス国制に注目する。この弁護士によれば、イギリスは君主国でありながら国制としては「真の共和政」をなし、それゆえ「意見の軛」を払い除けることができたのだ。ここでは、『法の精神』の著者のようにイギリスの政治体制を評価することよりも、同じく君主政をなす同国と母国フランスの政治を対照させることで、君主政の革新を主張することを慎重に避けながらも、その問題点をあぶり出すという意図があったのだろう。
実際、モンテスキューがイギリス君主政の原理として評価した〈政治的〉名誉(=「名誉」)の問題点が指摘される。ロベスピエールは、名誉を政治的と哲学的なそれに区分し、君主政の原理と考えられる前者を批判する。彼によれば、「政治における名誉の本質は、〔人が〕好まれ区別されることを切望するところにあります。そして尊敬に値するというだけでは満足せず、特に評価されたいと望み、行動において正義より偉大さを、理性より華々しさや威厳を優先したいと思わせるものです。この名誉は少なくとも美徳と同じくらい虚栄心と結びつくものです。ただ、政治秩序のなかでは美徳自体に取って代わるものなのです」。〈哲学的〉名誉は、これとは対照的である。
哲学における名誉とは、気高い純粋な魂がそれ本来の威厳さのために持つ甘美な感情以外のものではなく、理性をその基礎とし、義務感と一体となるものです。それは、神以外に証人はなく、良心以外を判断としないもので、他人の視線からも離れて存在するものでしょう。
判断の審級となるのは、外面ではなく内面にあり、前者が他人の意見であるのに対して後者は自分の良心である。この哲学的名誉とは、〈美徳〉と言い換えられるものである。
君主政では不可避的に地位や身分が必要とされ、生まれによって人を評価するような慣習があるが、その場合に評価の基準となるのは外見である。ロベスピエールはこれを他人の意見ないし「世論(l’opinion publique)」の評価とみなし、「偏見」と深く結びついていることを問題にする。これに対して、「真の共和政」は哲学的名誉(=美徳)と呼ばれる内面から湧き上がる感情、良心に基づく政治であり、そうでなければならない。その政治の具体的な方策が示されているわけではないが、その方向性が示唆されている点にアカデミー入会演説の意義がある。
最終的にロベスピエールは、同演説ないし論文のテーマである罪人の家族への加辱についても同様な偏見に基づくものだと指摘し、論難した。その貧しさや身体の不自由、性別のために、無実を証明できない民衆は、被告の家族までもその訴訟に巻き込まれるのだ、と。この主張には、民衆=善ではないとしても、やはり「抑圧された人々」のために働くロベスピエールの姿がある。これもまた、未来の革命指導者の政治のヴィジョンを示すものであるに違いない。ただ、彼のなかでその思想と行動が一致し激しく動き出すためには、パリの寄宿舎でその作品を読み耽った心の「師」との出会いが必要だった。
-

-
高山裕二
明治大学政治経済学部准教授。博士(政治学)。専攻は政治学・政治思想史。著書に『トクヴィルの憂鬱』(白水社、サントリー学芸賞受賞)、共著に『社会統合と宗教的なもの 十九世紀フランスの経験』(白水社)、『近代の変容(岩波講座 政治哲学 第3巻)』(岩波書店)などがある。
この記事をシェアする
「ロベスピエール 民主主義の殉教者」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 高山裕二
-
明治大学政治経済学部准教授。博士(政治学)。専攻は政治学・政治思想史。著書に『トクヴィルの憂鬱』(白水社、サントリー学芸賞受賞)、共著に『社会統合と宗教的なもの 十九世紀フランスの経験』(白水社)、『近代の変容(岩波講座 政治哲学 第3巻)』(岩波書店)などがある。
連載一覧

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら