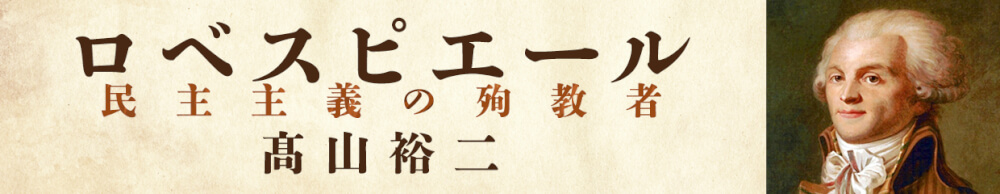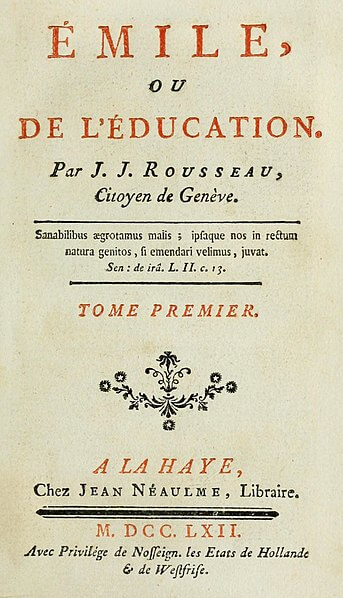「グレッセ」への讃歌
デビュー演説の翌年、未来の革命家の思想を読み解くうえで意想外に重要な論考が執筆された。「グレッセへの頌詞」(1785年)である。これはアミアン[アラスと同じフランス北部にある、ピカルディー地方の中心都市]のアカデミーの懸賞論文に応募するために書かれた論考で、その課題は、地元の詩人ジャン=バティスト=ルイ・グレッセ(1709-77年)への頌詞だった。賞金1200リーブルも魅力的だっただろうが、応募動機はこの主題自体にあった。

グレッセは、アミアンのイエズス会士の学校で教育を受けた後、ロベスピエールと同じルイ=ル=グランに学び、コレージュで人文学を講じるかたわら『ヴェルヴェル』(1734年)に代表される詩を書いて高い評価を受ける一方、イエズス会の学校生活を赤裸々に描いて「不敬虔」だと論難された。その後、劇作でも大きな成功をおさめ、アカデミー・フランセーズ会員に選出されたが、生まれ故郷のアミアンに隠退、自然=田舎を賛美した。
喜劇『意地悪』(1747年)でも、パリの〈都市の喧騒〉と〈田舎の風景〉を対照させ、前者の虚しさを描写した。ロベスピエールは、そうした詩人のキャラクターそのものに共感を覚えたのだろう。ヴォルテールと対比させることで、ロベスピエールはグレッセとその詩の美質を浮かび上がらせようとする。ヴォルテールとは「ありとあらゆる種類の栄誉への強烈な野心に導かれた」ものを象徴する名であることを示唆したうえで、両者を次のように対比するのである。
おそらく人々がヴォルテールのなかに見いだすのは、より多くの知性や真理、精巧さや正しさだろう。それに対してグレッセのなかには、より多くの調和や豊かさ、自然さが見られるだろう。そこには、こうした心地よい飾らなさや幸福な自由奔放さが感じられ、これがその詩の第一の魅力をなしている。ヴォルテールの優雅さはより輝かしく飾られ、激しく、機敏に見える。それに対してグレッセの優雅さはより簡素で単純、陽気で感動的なものに見えるだろう。
これは、人工的なものや洗練と自然的なものや純朴との対比である。ここで私たちが注目したいのは、ロベスピエールによるグレッセへの称賛は、翻って、〈現代人〉に対する辛辣な批判をなしているということである。試みに、同論の別の箇所から引用しよう。「グレッセの真っ直ぐで健全な心は、こうした自然に対する力強い愛着を保っていたが、それは大部分の人間においては世論や虚栄心が作り出した偽りの幸福への愛好によって消え去ってしまったものである」。世論が作り上げる「偽りの」評価や幸福観に対する批判は、すでに前回見たような、ロベスピエールが偏見と同一視した「名誉」に対する批判と重なり合っている。
加えて、同論における宗教的感情に対する評価も見逃せない。「グレッセに対して文学的教養のある人々の嘲笑を引き起こしたのとまさに同じものが、私に彼を称賛させる」。そう言ってロベスピエールがグレッセの〈美徳〉とともに称賛したのは、「彼の宗教への愛着」だった。宗教的「組織」と対立しながらも、その「感情」を尊重したグレッセに、自身の宗教に対する両義的な態度を映し出しているようである。それは、ヴォルテールに代表される理性や科学をただ信じ込むような啓蒙主義とは一線を画する態度であるといえよう。
こうして「グレッセへの頌詞」を一瞥すると、哲学や思想に少しでも関心のある読者なら、ある人物の名を連想せずにはおれないだろう。ジャン=ジャック・ルソー(1712-78年)である。『人間不平等起源論』(1755年)の著者は人間の自然を賛美する一方で、世論=外観に支配された文明(人)を糾弾したことで知られる。ロベスピエールはグレッセのうちにルソーその人を見たのではないか。頌詞には、グレッセは「ルソー」に称賛されたと書いているが――実際に称賛したのは同じルソーでも詩人のジャン=バティスト・ルソー(1670-1740年)だったが――、未来の革命家にとって「グレッセ」への頌詞は「ルソー」への頌詞でもあっただろう。
アラスのアカデミシャンのひとり、ド・フォスは、「グレッセへの頌詞」の写しを受け取ると、長い詩を付した返事で若い友人を絶賛した。それはロベスピエール自身が目指す人間像を映し出す内容でもあるので、その最後部をそのまま引用しておこう。
不幸な人を支え 無実の人の敵を討つ
君は美徳、甘美な友情のために生きる
だから君は、私の心に同じものを求めてよいのだ(マクフィー『ロベスピエール』から重引)
私の心に同じものを求めてよいのだ――。この一節を見てロベスピエールは何を思っただろうか。大きな確信、自己充足を覚えたに違いない。このとき、グレッセがかつてその詩を称賛されたのと同じ26歳を迎えていたロベスピエールは、本当は「ルソー(ジャン=ジャック)」から称賛されたかっただろうが、その承認欲求は友人によっていくらか満たされただろう。
「師」との邂逅
ルソーとの「出会い」は、パリのルイ=ル=グラン学院時代に遡る。
もともと同学院はイエズス会士たちによって運営・管理されていたが、ルイ15世暗殺未遂事件をきっかけにして1762年に閉鎖を命じられた。翌年再開されたときにはイエズス会士たちは追放され、国王の直接の監視下に置かれるようになっていたのである。つまり、ロベスピエールが入学した頃、同学院はその運営や教育方針をめぐって大きく揺れていたことになる。しかも閉鎖が命じられたちょうどその年、ルソーの問題作『エミール』(1762年)が刊行された。
同書は、ほぼ刊行直後にパリ司教によって糾弾され焚書となったが、それにもかかわらず、ベストセラーとなった。人間は本来善なる存在であり、社会によって堕落させられているというルソーの根本思想によれば、社会の汚れた影響から人間の善性を保護するのが教育のあるべき姿だということになる。「私は書物を嫌う」といった思想が散りばめられた同書の流行は当然、教育論争に火をつけることになったのである。
マクシミリアン少年が『エミール』をいつ読んだかは正確にはわかっていない。おそらく副校長のプロワイヤールの言う「不敬虔な書物」と「近代の哲学者」に少年が出会ったのは、1770年代後半のコレージュの最終課程(高校)の頃だったと推測される。人間は本来徳のない不誠実な存在ではなく、社会の悪徳によってそうなっているのであり、これと戦わなければならないという彼の発想は、ルソーに由来するに違いない。
その「出会い」はどれほど衝撃的だっただろうか――。寄宿舎で読み耽っていたのだろう。マクシミリアン少年は、ルソーが最晩年を過ごしたことで知られるパリ近郊のエルムノンヴィルをわざわざ訪れ、また実際にパリ周辺で、すでに年老いた孤独な(1778年に亡くなる)人物と出会った!それは彼の人生において格別な体験だった。そのときのことを彼自身が、「私は晩年のあなたに出会ったが、その記憶は依然として誇らしい喜びの源です」と回想している。
なるほど、この出会いを実証するものはなく、真偽は定かではないが――伝記作者は少なくとも「見かけた」のだろうと推察している――、それでも、これまで研究者や作家たちがこの出来事にほぼ必ず言及してきたのは、その邂逅があまりに象徴的な意味を持つからにほかならない。逆に、これがすべて空想だとすれば、かえって、少年をそのように心の中で空想させた「師」との邂逅の衝撃を物語る。その回想の文章の直前には次のように綴られている。
今日、かつてなく雄弁と美徳が必要とされている。神のような人よ、あなたは私に自己を知ることを教えてくれた。まだ若かった私に、自己の尊厳の真価を認め、社会秩序の偉大なる諸原理について熟考することを教えてくれた。
「古い建物は倒壊した。その瓦礫の上に新しい建物の柱廊玄関が聳え立ち、あなたのおかげで、私はそこにわが石材を持ち運んだ」。このように続く「回想」は、フランス革命勃発後の1789年か91年に書かれたと推測される、「ジャン=ジャック・ルソーの魂への献辞」と題された手稿である。美徳や誠実さという人間のあるべき原理を新しい社会の原理へと変革すべきだ、という考えにロベスピエールが至るには、ルソーとの邂逅が不可欠だった。
心の「師」の影響は、そのパーソナリティに共鳴した結果でもあった。それには、幼くして母を失い、父もいないに等しい精神的な「孤児」として育ったお互いの境遇の近さも関係していただろう。妹の回想によれば、アラスでロベスピエールに関心を抱く女性は多くいたが――そのなかで彼が唯一結婚を望んだ相手とされるのは叔母の継娘のアナイス(Anais Deshorties)である――、ある女性への手紙には、『ヌーヴェル・エロイーズ』(1761年にパリで刊行されたルソーのベストセラー小説)の恋文を思わせる、やや倒錯したロマンティックな情熱が滲んでいる。そう指摘するルース・スカーによれば、「彼はルソーがそうだったように特に自己陶酔的だった」というが、そうだとすれば、それは彼が「他者」を信じられないことの裏返しでもあったのではないか。
どちらかといえば神経質で臆病だったとされるロベスピエールは、妹の証言に反して、女性からもあまり好かれるようなタイプではなかったかもしれない。ただ、女性に鄭重で社交界での評判も良かったという証言もある。少なくとも、彼が女性の役割について「師」とは異なる考え方を有していたことだけは指摘しておかなければならない。というのも、ロベスピエールはルソーのように女性は自然に任せるべきだとは考えず、むしろ革命の戦端は女性によって開かれると論じたからである。
女性の「権利」
1786年2月、ロベスピエールはアカデミー会長に選出された。本業の弁護士業がもっとも忙しくなるなか(訴訟を24件担当)、同年4月、アカデミー会長として年に一度の公開会議を主宰した。そこでは4名の名誉会員が承認されたが、そのうちの2人は女性だった。そのとき彼が行った演説は、女性を学術の世界に受け容れることの歴史的意義を示し、この機会に女性の「権利」を擁護してみせるものだった。冒頭、その加入を祝した後、次のように述べた。
次のことを認めなければなりません。文芸のアカデミーに女性を入れることは、これまである種の異常なこととみなされてきました。フランスやヨーロッパ全体でも、その例は本当にごくわずかです。慣習の支配とおそらくは偏見の力が、この障害によってあなた方のなかに地位を占めたいと望みうる人々の願いを妨げてきたように思えます。(中略)〔しかし〕彼女たち〔今回選ばれた2人の女性〕の性別は、彼女たちの能力が与えた権利をなんら失わせることはなかったのです。
ロベスピエールにとって、女性の「権利」の主張は、偏見や無知との戦いの一環だった。「女性にアカデミーの門戸を開き、同時にその害毒である怠慢と怠惰を追放してください」。そして、「才能と美徳を育むのは競争です」と言って、性別の隔てない「競争」を科学の進歩の観点から称賛したのである。
この点で、「単純な、粗野に育てられた娘」のほうが「学識のある才女ぶった娘」よりもはるかにマシだと語った『エミール』の著者とは対照的だった。ルソーは同書でさらに次のように続けている。
こうした才能の大きい女性はみな、愚か者にしか畏敬の念を抱かせることはできない。(中略)彼女に真の才能があるならば、こうした見栄をはることでその才能の価値は下がってしまう。彼女の品位は人に知られないことにある。彼女の影響は夫の敬意のうちにある。彼女の楽しみは家族の幸福のうちにある。(樋口謹一訳)
確かに「弟子」のロベスピエールも、その演説で、男女にはきっとそれぞれに相応しい学問分野があり、女性は想像力や感情の点で豊かだと言っている点では、おそらくその時代に支配的な女性観を前提にしていると言えるだろう。その点では案外ルソーと近かったのかもしれない。しかしだからといって、女性は男性の付随物、「お飾り」ではなく、その能力で評価されるべき一個の人間とみなすべきだと彼が声高に主張し、その「権利」を擁護したこと自体は過小評価されるべきではないだろう。
前年、マリー・サマーヴィルというイギリス人女性の訴訟を引き受けたのも同様な観点からだっただろう。彼女が夫の死後、負債のために強制的に逮捕・監禁、晒し者にされた事件で、ロベスピエールは彼女を無償で弁護した。このことは、彼が社会の進歩の一環として、自由に能力を発揮する機会を女性に与える義務を主張していたことと平仄が合う。「この義務は、われわれが他のシステムを採用することができないなら、いっそう不可欠なものです」。
女性は「弱い性」で、そのかぎりで弁護すべき対象であるが、そうさせているのは社会体制の側であって、そのなかで女性の能力を発揮する機会が開かれておらず、彼女たちの社会実践が「未経験」であることに問題の根本がある。こう主張することでロベスピエールは再び、「抑圧された人々」と運命を共にし、彼女たちの側に立つと宣言したのである。
アカデミー会長としての演説に話を戻せば、〈戦い〉は封建時代のような戦闘における栄光ではなく、「新しい種類の栄光」を求めたものだと語っている。そして、こう締めくくられた。「文芸の火が再び点り始めました。それを自分たちでもたらす幸福な革命を加速させるのも女性なのです」。真に幸福なものになるかはともかく、来たるべき革命は確実に近づいていた。
-

-
高山裕二
明治大学政治経済学部准教授。博士(政治学)。専攻は政治学・政治思想史。著書に『トクヴィルの憂鬱』(白水社、サントリー学芸賞受賞)、共著に『社会統合と宗教的なもの 十九世紀フランスの経験』(白水社)、『近代の変容(岩波講座 政治哲学 第3巻)』(岩波書店)などがある。
この記事をシェアする
「ロベスピエール 民主主義の殉教者」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 高山裕二
-
明治大学政治経済学部准教授。博士(政治学)。専攻は政治学・政治思想史。著書に『トクヴィルの憂鬱』(白水社、サントリー学芸賞受賞)、共著に『社会統合と宗教的なもの 十九世紀フランスの経験』(白水社)、『近代の変容(岩波講座 政治哲学 第3巻)』(岩波書店)などがある。
連載一覧

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら