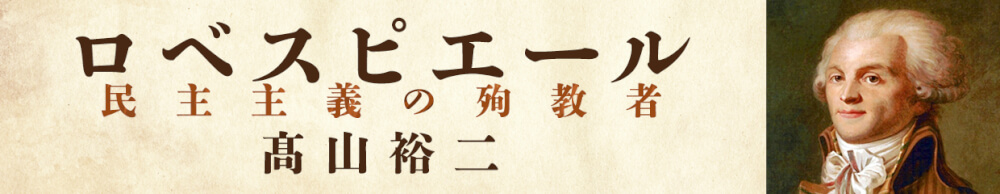最後の帰郷
ヴァレンヌ事件の直前、ロベスピエールは予期せずパリ県の検察官(革命期の役職)に選出され、代わりに前年の1790年10月から議員と兼務していたヴェルサイユ裁判所の裁判官を辞した。「暴政のもっとも恐るべき道具」と自身も称した検察官の職を引き受けるのにとまどいがなかったわけではない。受諾した翌日(1791年6月12日)、田舎の友人に宛てた手紙には、その重責が強いると思われる困難について恐怖しか感じないと、心情を吐露している。
しかし私は激動の運命に身を投じる宿命にあります。我が祖国のために可能なかぎり犠牲を払うまで、その流れに沿って進まなければなりません。私はつねに打ちのめされています。
このとき、心身ともに疲弊していた自分には休息が必要だとも語っている。しかし、議会内外の敵とその陰謀の存在が明らかになりつつあるいま、みずからが「恐るべき重責」を「全体の利益」のために引き受けなければならないと決心したと言うのである。

憲法制定議会の解散はひとまず田舎に帰って穏やかな休暇を与えるはずだったが、周囲がそれを許さなかった。帰郷前、妹に帰省の予定を知らせた際、できるかぎり公の歓迎行事はやめてほしいと伝えたのは、パリでの報道が加熱するのを避け、穏やかな帰郷を望んだからだった。しかし10月14日、アラス南方の町バポムで妹弟たちと合流すると、地方の愛国主義者や衛兵が集まってきて歓迎を受けた。そして同日夜8時、市街地に入ると、街中に繰り出した多くの市民に迎えられ、音楽が鳴り響くなか「ロベスピエール万歳!」の叫び声が上がったのである。
15日土曜日も歓迎ムードは続き、あたかも公共の祝祭のように人々は踊り歌ったという。翌日は地元のジャコバン・クラブで歓迎式展が行われた。ルイ=ル=グラン学院卒業後、県の行政官を務めていた弟のオギュスタンが、田舎の〈英雄〉の凱旋を同会で事前に告知していたのである。
一方で、地方のエリート(アリストクラシー)の冷淡さにもロベスピエールは気づいていた。アラスの社会も(旧)特権階級と愛国派(革命派)という二つの勢力に分断されていたのだ。それでも、彼は民衆の出迎えにはやはり感激した。思えば、ここで「抑圧された人々」と称される民衆のために弁護士活動を始めて政治家となり、地元から離れたヴェルサイユそしてパリでの議員活動を通じて改めて認識するに至ったのは、民衆と一体化する必要だった。そこで、30ヶ月ぶりに戻った故郷で一体化すべき民衆を再発見する必要が彼にはあった。その使命には、心の〈師〉との邂逅がやはり影響を及ぼしていたのは間違いない。
以前(第4回)紹介したように、この頃に書かれたと推測される手稿に、「ジャン=ジャック・ルソーの魂への献辞」がある。そのなかでロベスピエールは、自己と社会の変革の必要をルソーとの「邂逅」を通じて教えられたと書いていたが、続けて次のように語っている。
かつてなく世界を揺り動かす偉大な出来事の渦中にあって、私はある役割を担うことを運命づけられている。専制の断末魔と真の主権の目覚めを目にして……私は自分に責任を負わなければならず、同胞市民に対してもやがて私の思想や行動に対して弁明する責任を負わなければならなくなるだろう。あなたの手本が私の目の前にはある。あなたの感嘆すべき『告白』。この上なく純粋な魂のこの素直で大胆な発露は、芸術のモデルというよりも美徳の奇跡として後世に残るだろう。
ここで言及されているルソーの『告白』は、第2部の刊行が革命直前で、ロベスピエールもちょうど読んでいたのだろう。同書には、悪いのは社会であって自己=人間ではないという信念が綴られている(この思想が直接示されるのは、同書に言及がある「マルゼルブに宛てた4つの書簡」[1779年発表]においてである)。つまり、「清廉の人」は革命の渦中でルソーを通じて、民衆の「善良さ」を再発見する使命を再認識したのではないか。そのためにみずからを犠牲にする覚悟が、「献辞」にも見いだせる。
その手稿でロベスピエールは、ルソーに会った際、「真理の崇拝に捧げられた高貴な生のあらゆる苦悩を理解した。それが私をたじろがせることはなかった。同胞の幸福を望んだという自覚が、有徳の士に与えられる報酬なのだ」と語ったあと、さらにこう続ける。
やがて諸国民の感謝の念が、同時代人が否定した名誉で彼の記憶を包む日がやってくる。私もあなたのように、困難な生活を送っても、早すぎする死という代償を払ってでも、善をなしたい。
前述の田舎の友人への手紙と合わせて読むと、アルトワ州アラスへの帰郷は単なる休暇でなくなることは避けられなかったように思われる。伝記作家のマクフィーは、「このアルトワへの旅は、彼の人生にとっての転換点となった」と断じるが、確かにロベスピエールが一つの覚悟をもって帰った田舎で体験するのは、ある種の思想上の転回と呼べるようなものだった。
聖職者の「公務員」化
ロベスピエールは、アルトワの農村地帯に友人を訪ねて旅行したり、農場で休暇を過ごしたりした。また、町の教会のミサを訪れ、その時の様子を知人[パリで住居を提供してくれたデュプレ]への手紙(10月16日)で語っている。
それは、「宣誓拒否聖職者」(後述)が執り行っていたミサにおいて、足に重傷を負っているとされる男が突如松葉杖を放り投げて両手を挙げて歩き出すという「奇跡」が起き、その妻が神に感謝を捧げたという出来事である。「私には場違い」だったと言う教会をまもなく立ち去ったロベスピエールは、その光景を残念に思ったという。このような「奇跡」が起こるのは地方の修道会では珍しいというわけではなかったが、彼にショックを与えたのは、革命後にもそれを賛美する民衆の「狂信」であり、それを利用する「宣誓拒否聖職者」の影響力の大きさだった。
別の手紙(11月4日)では、「宣誓拒否聖職者」のことを「貴族の聖職者」と呼び、新信者を見つけては「革命の敵にしている」と非難している。「というのも、彼が惑わしている無知な人々は宗教の利益と国民の利益を区別できないため、彼は宗教の見解と見せかけて専制と反革命を説き聞かせているのである」。つまり、ロベスピエールが田舎で発見した民衆は「無知な人々」であり、聖職者によって惑わされることで「革命の敵」になりかねない存在だった。
そのため、彼は今あるがままの民衆と一体化するわけにいかなくなる。たとえ本来は善良な存在だとしても、今目の前にいる民衆は惑わされている。そうだとすれば、みずからが彼らを教え導く存在にならざるをえないのではないか。このとき初めて、ある意味でライヴァルの存在として浮上したのが聖職者、特に「宣誓拒否聖職者」である。逆に、それまでロベスピエールが「聖職者」を特別扱いすることはなかった。
ここで「宣誓拒否聖職者」の存在を理解するために、革命の「反キリスト教」化の経緯を簡単に確認しておこう。もともとフランス革命は、当初から反キリスト教を目指したわけではなく、社会の非キリスト教化を求めたわけでもなかった。聖職者のなかには革命に協力的なものも少なくなく、彼らは1789年8月の封建的権利の廃止にも同意した。また、国家財政が逼迫するなか、教会の全財産を国有化しようという提案が聖職者議員タレイランによってなされた。その結果として、収入源を失った聖職者が「公務員」化するのはある意味で必然となったが、これは革命と宗教が激しく反目し合う原因となった。
1790年7月12日、聖職者市民(=民事)化基本法が成立。聖職者の職務・任用や報酬などを規定した同法は、聖職者を国家から給与が支払われる「公務員」にするというもので、同法を含む憲法への宣誓を義務づけた。市民化法は、俸給が極端に下がる高位聖職者にとって望ましくなかったばかりか、なにより聖職者に叙任するのは教皇、その背後にいる神であるという戒律を破壊するという点で、教会にとっては譲れない一線を超えるものとみなされた。

パリなどでは「縛り首か宣誓か?」という民衆による圧力があり、国内の宣誓聖職者は5割を超えたが、それでも特に地方では宣誓聖職者は逆に「裏切り者」と呼ばれ、糾弾されることも少なくなかった。ロベスピエールはこの時点で、全国的な宣誓拒否への根強い支持を十分に認識ないし警戒していなかったかもしれない。司祭が結婚する権利も擁護したことで、「信仰の要塞」と呼ばれたアラスの市民のなかで彼への反感が強まった。
ただ、ロベスピエールは宗教(キリスト教)を批判するというよりも、《民主主義》を貫徹することが目的だった。つまり、聖職者も主権者(=人民)によって選ばれることに同法の意義を見いだしたのである。他方、この観点からカトリック以外の宗教を排除することなく、すでに89年12月23日、あの〈二つの国民〉案を批判した頃の演説で、プロテスタントやユダヤ教徒に対して平等な市民権を要求していた。彼にとって、これは宗教・宗派の種類の問題というよりも、あくまで民主主義の宗教であるかどうかが肝心だったと言える。
ところが、帰郷したアラスでの経験は司祭あるいは教会の「政治的」影響力に対する警戒心をロベスピエールに抱かせることになった。と同時に、彼らの影響力を排除しながら、民衆をいかに教育し啓蒙していくかが当面の課題となる。この課題に取り組むため、民主主義によりふさわしい革命の宗教が必要ではないかという意識もまたのちに前景化してくることになる。
「人民の一員である」
46日間の田舎での滞在を終え、ロベスピエールは11月28日パリに戻った。24日、立憲議員時代に連絡を取り合っていたリール[仏北部の都市]の「憲法友の会」に招かれて演説し、喝采を浴びた直後だった。帰京して2日後、今度はパリのジャコバン・クラブで熱狂的な歓迎を受けた。「清廉の人」の人気は同クラブで衰えてはいなかった。
しかし、政治状況は大きく変わっていた。国王が国境付近の町ヴァレンヌで逮捕されて以後、特に91年8月27日にピルニッツ宣言[オーストリア皇帝のレオポルト2世とプロイセン国王フリードリッヒ=ヴィルヘルム2世がザクセンのピルニッツで会見し、ヨーロッパの君主たちに向けてフランスに対し準備が出来次第「緊急の行動」をとることを要請したもの]が発表されて以降、対外戦争の恐怖が煽られていた。実際、王弟が亡命宮廷を作り、同年には6千人の貴族将校たちが亡命したという推計もある。これは「反革命」の動きとみなされ、またカリブ海植民地で起きた「反乱」によって敵国による干渉がなされるという憶測がその恐怖に拍車をかけた。
ジャコバン・クラブ内では、ジャック=ピエール・ブリソの一派(のちにジロンド派と呼ばれる人々)によって、主戦論が主導されていた。ブリソはひと月前、亡命者に関する法案を議会に提出、ヨーロッパ列強との戦争を示唆した。1754年生まれのブリソはシャルトル[仏中部の都市]近郊の仕出し屋の息子で、パリに出て革命前後に文筆で名をなし、国民議会に選出されていた。アラスへの帰郷前、ロベスピエールもその才能を認めていた人物だが、その後二人は同クラブで最大の政敵関係となる。
12月16日、長い不在の後、会合に姿を現したブリソが沈黙を破った。彼は革命の勝利には戦争での勝利が不可欠だという信念を語り、執行権力(国王)が戦争を宣言するが、仮に国王が国民を裏切ることがあっても、「人民がそこにいる、心配すべきことは何もない」と言って、国民の不信を打ち消そうとした。演説はジャコバン・クラブで喝采を浴びた。

2日後、ロベスピエールは真っ向から反対した。「戦争を欲するのは、国民の利益がそれを欲する場合である。国内の敵を制圧しよう。続いて、まだいるとすれば、国外の敵に立ち向かおうではないか」。「これらの敵のうちでもっとも多くもっとも危険なのは、コブレンツ[プロイセンの町]にいるだろうか。いや、われわれの中にいるのだ」。実際、いま対外戦争を望んでいるのは宮廷であり政権である。われわれが想定しうる戦争、それは「革命の敵」との戦争でしかありえない。また、戦時には、執行権力が恐るべき力を得ることに警戒すべきだ。そのように訴えたのである。主戦論で圧倒された同会で、彼の演説は冷ややかに受け止められた。
では、〈国内の敵〉との戦いとは何か。それは翌92年1月2日、ロベスピエールの二回目の主要演説のなかで明らかにされる。「なによりも重要なことは、われわれの努力の成果がどうであれ、その真の利益と敵の利益について国民を啓蒙することである」。今は対外的な戦争をするときではなく、国内の反革命派と戦い、そのために国民を「啓蒙すること」が必要なときである。続けてロベスピエールは、ブリソ派が自分のことを人民の「守護者」を自認し彼らを堕落させようとしていると言うが、その非難はまったく当たらないと力説した。
まず、私が人民の守護者ではないことを知ってほしい。かつてそのような肩書きを要求したことは一度もない。私は人民の一員である。これまでそれ以外の者では決してなかったし、私はただ人民でありたいと望んでいる。
「人民の一員である」という告白を額面通りに受け取るわけにはいかない。というのも、続けてロベスピエールは、「人民」であるためには彼らをそのまま眠らせておくのではなく、その欠陥から守る必要があると言っているからだ。つまり、今あるがままの人民の一員だと言っているわけではないのである。そして、ロベスピエールは続けて次のように言う。
この点で、『人民はそこにいる』というのは非常に危険な言葉である。ルソーほど、われわれに人民の真の理念を見せてくれた人はいない。なぜなら、彼ほど人民を愛した人はいないからだ。『人民はつねに善を欲するが、つねに気づくわけではない』。
ここで確認すべきなのは、アルトワでの体験に基づいた思想上の転回であり、そのままの人民を超えて昇華された〈民衆=人民〉という理念をルソーに代わって示すというロベスピエールの使命への自負である。
その後、ブリソはジャコバン・クラブの会合でロベスピエールへの評価を示すとともに、和解を呼びかけ、結果的に二人は抱擁し、大喝采が起こった。しかし、このときも自分の意見は変えないと宣言していたロベスピエールが、「終戦」に応じることはなかった。
「国民主権の原理を傷つける」全国会議員を懲戒処分にしようではないか――。翌月、そのように語ったロベスピエールは〈民衆=人民〉の理念を追い求める。そして、闘争は激しさを増してゆく。
-

-
高山裕二
明治大学政治経済学部准教授。博士(政治学)。専攻は政治学・政治思想史。著書に『トクヴィルの憂鬱』(白水社、サントリー学芸賞受賞)、共著に『社会統合と宗教的なもの 十九世紀フランスの経験』(白水社)、『近代の変容(岩波講座 政治哲学 第3巻)』(岩波書店)などがある。
この記事をシェアする
「ロベスピエール 民主主義の殉教者」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 高山裕二
-
明治大学政治経済学部准教授。博士(政治学)。専攻は政治学・政治思想史。著書に『トクヴィルの憂鬱』(白水社、サントリー学芸賞受賞)、共著に『社会統合と宗教的なもの 十九世紀フランスの経験』(白水社)、『近代の変容(岩波講座 政治哲学 第3巻)』(岩波書店)などがある。
連載一覧

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら