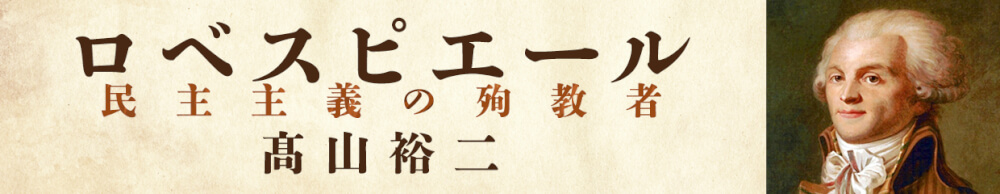宣戦布告
1792年3月、ルイ16世はブリソ派に内閣を組織させた。そして、革命の理念を世界に広めようとする同派と、逆に敗戦によって革命を止めようとする国王の思惑が一致、ついに4月20日オーストリアに対して宣戦布告がなされた。議会で反対票を投じたのは、わずか7名だった。
開戦に反対したのは、ロベスピエールやジャン=ポール・マラなど少数で、しかも彼らはこのとき議員ではなかった(マラはスイス・ヌシャテル生まれの医師で、革命勃発後に新聞『人民の友』を発刊しパリ民衆の支持を得て、のちに国民公会議員となる)。孤独は深まった。とはいえ、ブリソや国王らが一致して開戦に踏み切ったという事実は、国内にいる「革命の敵」たちが裏で結託しているという「陰謀」を裏づけるものでもあった。少なくとも、ロベスピエールがそのように主張するには十分な理由となった。彼は検察官の職を辞し、政治活動に専念する。ジャコバン・クラブで毎日のように演説した。

よく知られているように、この後戦線は拡大していき、革命の成就にとって致命的な足枷になることからすると、開戦に踏み切ったことは革命期のターニングポイントとなり、失策でさえあったかもしれない。が、この十年の間にジュネーヴ、オランダ、ベルギーの革命運動はいずれも外国の軍事介入によって鎮圧されており、ポーランドは分割を経験、この頃着手された改革も国内の改革反対派の要求を受けるかたちで介入したロシアの軍隊につぶされた。そう考えると、フランスの住民、とりわけ革命家たちが外国勢力の干渉を恐怖するのは自然だった。そして、革命の進展を考えれば、このとき仮に開戦しなくとも、いずれ対外戦争に踏み切らざるをえなかっただろう。それでも、今踏み切るべきではなかったのだ。それはなぜか。当面の敵は、革命を転覆させようとする「陰謀」を抱く主戦論者たちだからだ。
ところが、そう主張したロベスピエールこそ、実はフランス政府内で暗躍する「オーストリア委員会」の代理人ないし工作員だと非難された。そこで彼は、4月27日のジャコバンの会合でこれを否定し、同委員会の影響がどこまで深く宮廷に及んでいるかを私は知らないと述べた。「私が知っているのは、ただ一つの行動原理である。それは人権宣言と憲法の諸原理である」。そのうえで、絶えずそれを毀損する「野心、陰謀、策略、マキアヴェリ主義」の存在を示し、主戦派の「陰謀」を糾弾した。同じ頃、ロベスピエールの旧友デムーランは冊子を出版し、敵と結託して「仮面が剥がれたブリソ」を攻撃した。
ところで、「オーストリア委員会」とは何か?これは以前から、議会と革命自体を転覆させようと画策する謎の組織として知られ、オーストリア政府、具体的には「マキアヴェリ主義的」宰相ヴェンツェル・フォン・カウニッツがそれを使ってフランス政府、その反革命派を操っていると考えられた。その存在をとくに明示的に証明するものはないものの、それが陰で大きな影響力を及ぼしているという断定は、「陰謀」論の典型的な特徴である。ただ、人々にそう思わせる「事実」が出てくると、それはますます力を増してゆくことになる。
「オーストリア委員会」は、1791年初期に初めて急進派メディアに登場したと考えられている。それは、ジャコバン・クラブが「祖国のすべての敵」を非難する宣誓を決議し、「陰謀」の追及と告発が同会の常套のレトリックとなった時期と重なる(T. Tackett, ‘Conspiracy Obsession in a Time of Revolution,’ 2000)。それはすなわち、陰謀論が革命の政治文化となったことを意味する。ブリソは、宣戦布告の翌月、早くも戦況が悪化する中、「オーストリア委員会」のようなスパイの存在を指摘し、それに戦況悪化の原因を着せようとした。双方が陰謀論を交えて論駁し合っていたのである。
確かにロベスピエールも、議員になる以前から特権階級の「陰謀」について語り、彼らの「仮面」の下に隠された真実を暴く必要を訴えていた。だが、人々を「陰謀」に駆り立てたのは彼自身ではない。たとえば、論敵を非難する「愛国主義の仮面」という表現は、遅くとも1789年11月にマラによって『人民の友』のなかで用いられ、翌年にはブリソ自身が使っている。
こうして革命家たちは、「陰謀にたいする強迫観念」にとりつかれていた。歴史家のリン・ハントは、それは革命当初からのものだったとして、次のように説明している。
フランスでは、陰謀は〔フランス革命と〕兄弟のようなものであり、それゆえ兄弟殺しのようなものだったのであり、それへの没頭は1789年以降ますます強くなっていくばかりであった。(中略)革命家たちは陰謀という隠れひそんでいる亡霊にとりつかれていたのであり、絶えず仮面を剥ぐことについて語った。(中略)すでに1789年7月には、『国民の告発者』というタイトルの新聞があった。1793年までには、陰謀という語句は革命的言説にとって恒常的で不可欠な部分となっていた。(『フランス革命の政治文化』1984年)
革命は人々を「陰謀」へと駆り立て、対外戦争がそれを加速させた。戦況の悪化、またその後に明らかとなる両国王室の交信は、国内に「陰謀」が実在することを証明するものとみなされ、その力はますます大きなものとなってゆく。相手が本当は「裏切り者」でないかという疑心暗鬼が、「仮面」の剥がし合いへと発展してゆくのである。
『憲法の擁護者』の発刊
ロベスピエールは真っ先に戦況悪化のスケープゴートとされた。彼はこれに対抗するかたちで、自己主張を展開する新聞『憲法の擁護者』を92年5月に発刊、創刊号では、国民衛兵の司令官ラファイエットと結託しているとされるブリソ、およびジロンド派のコンドルセを名指しで批判した。
新聞名になっているように「憲法」を擁護するということは、現行の立憲君主制、言い換えれば「君主のいる共和国」(本連載・第8回)を擁護することを含意する。創刊号で、私は共和政主義者であるとしながら君主政主義者でもあるとしているのは、そのことを意味する。彼にとって肝要なのは、政治体制の分類ではなく人権宣言の尊重であり、人民主権の実現だった。
とはいえ、ロベスピエールが「君主」の存在にこだわる理由は何か?人民主権の実現を考えれば、国王のいない共和政を採用するほうが自然ではないか。なるほど、彼にとっても国王はフランス国家の〈象徴〉だったはずである。ただ、この頃にはもはや尊重すべき対象ではなかっただろう。実際、この2ヶ月後、彼は国王の廃位を主張することになる。つまり、このとき「憲法」を擁護する理由が他にあったはずなのだ。
3月2日のジャコバンの会合では、「共和政主義者という言葉は何者でもない」、そう名乗る敵たちは、「国民が完全に啓蒙される前に」あなた方から自由を奪おうとしていると主張した。よって、あらゆる偉大な精神が現れるのは確かに共和政だとしても、「より成熟した経験によって啓蒙された一般精神」に導かれるまで、われわれは「断固とした憲法の友」でなければならない、と。つまり、今共和政を主張しているのはその敵たちであって、むしろ真の共和政を樹立するにはまず、彼らの「仮面」を見破る人民を教育することが肝心だと言うのである。
加えて、ここでもルソーの名前を挙げ、本来「人民は善良で公正で高邁である」と強調し、改めて自身を人民の煽動者とする中傷に反論して「私自身人民である」と宣言した。
『憲法の擁護者』では、ロベスピエールがとくに懸念していた敵たちの危険が具体的に明らかにされ、「憲法」を擁護する理由がよりはっきりと示されている。
貴族からなる上院や独裁者の鞭のもとにひれ伏して堕落した人民よりも、王はいるが人民を代表する議会と、自由で尊重された市民のほうを私は見たい。チャールズ1世よりもクロムウェルを好むというわけではないのだ。
クロムウェルとは、イギリスのチャールズ1世処刑後に現れた「護国卿」、軍事独裁的な指導者である。この論説でロベスピエールは、今日共和主義を唱えている主戦論者たちが言葉(仮面!)の背後に隠し持つ野心として、戦争・軍隊を利用した「独裁」の危険を告発しようとしたのである。それを防ぐため、とにかく啓蒙された〈人民=民衆〉が現れるまでは国王が存在している必要があったのだろう。確かにラファイエットは貴族出身だが、アメリカ独立革命に従軍して名声を博し、フランス国民の中でも大きな影響力を有していたため、このときロベスピエールの批判の矛先はブリソ以上にこの「革命」の英雄に向かっていた。

しかし同月、王政の崩壊の端緒となる大きな事件が起こる。戦況が悪化する中、議会では全国から2万人の連盟兵[フェデレ=もともと連盟祭の参加者を指す言葉で、実態は国民衛兵]を徴募する法令が採択されたが、国王は同時に採択された宣誓拒否聖職者の国外追放を可能にする法令とともに承認を拒否したのである。そこで、パリのサン=キュロットが宮殿に押し寄せた。このとき、ルイ16世は政治的譲歩はしなかったものの、民衆の要求に従うかたちでフリージア帽[古代ローマの解放奴隷が被ったとされ、民衆の自由のシンボルとなっていた]を被った。これは、民衆こそが主人であることを内外に示す前兆となる。
6月、ラファイエットが行政の無秩序とジロンド派の陰謀を非難、ジャコバン派を攻撃した(16日)。そして、前線からパリに帰還(27日)、クーデタを企てるが失敗に終わった。彼を嫌っていたマリ=アントワネットが、パリ市長になっていたペティヨンに通報し発覚したとされる。
ロベスピエールは、ラファイエットがジャコバン派を攻撃した翌日、同会の演壇に立ち、この男は穏やかな外見のもとに野心を隠し持ち、今みずから「仮面」をとったところだと論難した。そして、軍事行動を通じて独裁権力を握ろうとする手法はクロムウェルのそれだと改めて訴えたのである。この事件は期せずして、ロベスピエールの懸念を証明するかのように、軍事独裁の野心、「陰謀」の実在を明らかにするものとなった。
議会では、オーストリアとプロイセンの連合軍の攻勢の知らせを受け、7月11日「祖国は危機にある」宣言が発せられた。これに対して、同日ロベスピエールは、「この宣言以前から、陰謀家の司令官が我が軍のトップにいることは分かっており、腐敗した宮廷がわれわれの自由と憲法に対して絶えず陰謀を企んでいたのも分かっていた」と、ジャコバン・クラブで述べた。つまり、祖国の危機の本質は国内、政府およびそれと結託した司令官にあるというのである。
3日後の7月14日、革命勃発から3周年を記念した全国連盟祭が開催された。この機会に連盟兵が全国から集まってきて祭典に参加し、パリにとどまった。祭典後に到着した兵士も少なくなく、なかでもマルセイユからやってきた連盟兵が有名である。道中、彼らが歌っていたのが「ラ・マルセイエーズ」と呼ばれる軍歌で、これが今のフランスの国歌となっている。
そのときロベスピエールは『憲法の擁護者』で、連盟兵はパリに残って愛国者たちと団結するべきだと主張した。と同時に、危機にある祖国を救うのは、議員ができなければ人民自身がやるしかないと訴えかけた。同紙の読者にとって、それが意味するところは実力行使だったとしても不思議ではない。そして7月29日、彼はついに国王の廃位を要求、行政権力と立法府の再生の必要を訴えることで、事実上「憲法の擁護者」の立場を放棄した。
「美しい革命」
8月3日、プロイセン軍の司令官ブラウンシュヴァイク公がコブレンツで出した声明がパリ住民に伝わった。彼らが即座かつ無条件に国王に服従しなければ、パリを徹底的に弾圧するという驚くべき内容だった。これは民衆にとって「陰謀」の実在を裏づけるものだった。
国民は反発し、これを機にパリに48あるうちの47のセクション[それぞれ市民総会を有するパリ市内の地区]が国王の廃位を要求した。この請願は、9日に議会で審議されることになったが、議会は当日になると取り上げることもなく散会した。そこで市民たちは議会の対応に失望し、翌日朝5時頃に蜂起した。48セクションに立脚した「蜂起コミューン(自治組織)」が設立されチュイルリ宮殿を襲撃、昼には宮殿が陥落した。議会は国王の監禁と権限の一時停止を決定、普通選挙による国民公会の召集を布告した。翌日、6人の大臣からなる執行評議会が設置された。

さらにコミューンの圧力のもと、議会は反革命容疑者の逮捕を全国の市町村長に許可(11日)、ついで彼らを裁くための「特別刑事裁判所」の設置を承認した(17日)。すると、同月30日、プロイセン軍によるヴェルダン攻略の知らせがパリに届き、住民の恐怖が増す中、コミューンは600名の反革命容疑者の逮捕を命じた。それは非合法であると議会は解散を要求したが、コミューンはそれを拒否。この間、コミューンの評議会メンバーに選ばれたロベスピエールも、議会による解散の決定を峻拒した。彼はこの蜂起をかつてない「美しい革命」と表した。逆にブリソ派にとっては、いつ逮捕されるのかと、一連の出来事は恐怖でしかなかっただろう。
しかし、「革命」はこれで終わらなかった。9月に入ると、反革命容疑者が革命派の殺害に乗り出すという噂が住民の間に広まった。ここまでくると、「陰謀」は実在を裏づける必要もなかった。2日、武装した群衆が監獄に押し寄せ、みずから即席の「裁判」をして死刑判決を出し、殺害を始めた。これは5日まで続き、およそ1300人が殺害されたという。「9月虐殺」である。

そこで問題となるのは、ロベスピエールの虐殺への関与だが、彼がそれを奨励したり黙認したりしたことを示す証拠はない。逆に、のちに行われた彼の医師へのインタビューで、ロベスピエールは「9月の日々について語るときはいつも恐怖をあらわにし」、奴らは革命を血で溺れさせてしまったと叫んだという証言もある。それが仮に事実だとしても、ロベスピエールが国王そして議会を否定し、人民による直接的な行動を容認、さらには支持したのは事実である。彼が「美しい革命」と呼んだ8月の王宮襲撃でも、600人のスイス人傭兵が虐殺された。
ロベスピエールは臨時裁判所の設置を議会に求め、「陰謀家」たちを処罰するように求めてもいた。また、虐殺が起こる前のことだが、コミューンのうちに人民そのものを見いだし、第2の革命で「人民の意志」が行使されたと評議会で主張した(Raymonde Monnier, ‘Robespierre et la commune de Paris,’ 1994)。少なくとも彼は民衆の蜂起を止めることはなかった。
とはいえ、その点では他の政治家もほとんど同じだったことを見逃してはならない。革命期の特徴は、政治指導者たちが陰謀論にとりつかれたことにあるが、それは当然民衆にも伝染し、虐殺にまで行き着く彼らの強迫を、止められる議員はいなかったといえる。
リン・ハントは書いている。「しかし陰謀のみが、革命家たちが大衆政治という新しい経験に直面したとき、体系的な強迫観念となったのである」(前掲書『フランス革命の政治文化』)。確かに、食糧不足の元凶を大臣や地主に帰す噂の類を含め、陰謀論は旧体制下にも存在した。しかし革命後、陰謀論はメディアの発達を背景に一般化・体系化すると同時に、社会と国民を二手に分断するような妥協不能な性格を帯びたのである。その原因は「大衆政治」、すなわち大衆=人民の意志に基づく政治の登場にあった。
《民主主義》とは、「人民の意志」の支配である。それは、人民が単一にして不可分の「一般意志」を持つことを前提とし、それに反する意志は認めない。そこで、相反する意見を述べる者は「敵」認定され、人民の意志に反する「陰謀」を企てていると考えられる。だからこそ、《民主主義》を求める人々のあいだで「陰謀」への強迫が一般的になる。しかし、人間の内面にある「意志」は証明できないがゆえに、悪意の追及は終わることなく、いきおい生死をかけた闘争となろう。
さあ、明日はいよいよ国民公会の開幕である。
-

-
高山裕二
明治大学政治経済学部准教授。博士(政治学)。専攻は政治学・政治思想史。著書に『トクヴィルの憂鬱』(白水社、サントリー学芸賞受賞)、共著に『社会統合と宗教的なもの 十九世紀フランスの経験』(白水社)、『近代の変容(岩波講座 政治哲学 第3巻)』(岩波書店)などがある。
この記事をシェアする
「ロベスピエール 民主主義の殉教者」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 高山裕二
-
明治大学政治経済学部准教授。博士(政治学)。専攻は政治学・政治思想史。著書に『トクヴィルの憂鬱』(白水社、サントリー学芸賞受賞)、共著に『社会統合と宗教的なもの 十九世紀フランスの経験』(白水社)、『近代の変容(岩波講座 政治哲学 第3巻)』(岩波書店)などがある。
連載一覧

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら