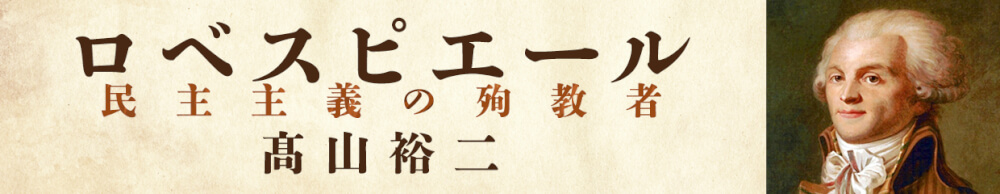死刑執行人の使命
これは、バルザックの短編「恐怖時代の一挿話」(1831年)の一節である。
死者の遺骸もなく、彼らは死者のミサをするのであった。ばらばらの屋根瓦と衣摺のもとで、四人のキリスト教徒は、これからフランス王のために神にとりなしをし、柩もない葬儀を行おうとしているのである。あらゆる献身のもっとも純なもの、微塵も底意のない忠誠の驚くべき行為であった。神の目には、それは疑いもなく、もっとも高い徳業と重さに甲乙のない一杯の水のようなものであった。神父と二人のあわれな童貞の祈りのうちには、君主政治のすべてがあった。けれどもおそらく大革命も、この見知らぬ男によって代表されていたのであろう。いまや限りない悔恨の祈誓を果たしつつあるのだと思うまいとしても、彼の顔にはそれを裏切ってあまりにも甚だしい良心の苛責があらわれていたのである。(水野亮訳)
真冬のパリ、ある神父と二人の修道女の隠れ家で行われたというミサの様子が、ここには描かれている。「ある高貴な方」の御魂を鎮めるため、見つかれば死罪になりうる危険を冒して執り行われた追悼のミサだった。その執行を懇請した「この見知らぬ男」の名は、シャルル=アンリ・サンソン(1739-1806年)という。サンソン家は代々、パリで死刑執行人の職を務めてきた。シャルル=アンリは、その4代目当主で、フランス革命の登場人物たちを次々と断頭台(ギロチン)で死刑に処してきた人物として、その名を歴史に残している。
彼は、「ある高貴な方」すなわちルイ16世の死刑を執行した翌日、囚人のミサを秘かに依頼したのだった。サンソンはその日以前に国王と会う機会が2度あった。二度目は一年ほど前、チュイルリー宮殿で行われたある会合に呼ばれたときのこと。それは、新しい死刑執行機械の設計図を検討する非公式の会合で、その製造に携わった侍医ルイによって考案者のギヨタンとともに呼び出されたのである。ルイ16世はもともと金具製造を趣味にしていたが、先頃人道的な観点から考案された機械「ギロチン」に関心を抱き、意見を求めたのである(ギロチン[英語読み。仏語ではギヨティーヌ(guillotine)]はギヨタン(Guillotin)の名に由来する)。

旧体制下のフランスでは、斬首刑がなされるのは貴族だけで、あとは罪の種類によって絞首刑から八つ裂きの刑までいくつかあったが、車輪刑がかなり一般的に執行されていたという。マクシミリアンも以前から訴えていたように、その残酷さは革命前から問題にされていた。
サンソンの回想によれば、人道の観点から斬首刑も「確実に」行えるよう、国王の提案に基づき、ギロチンの刃は三日月型から斜面へと変更になったという。翌年、この刃によって国王自身が斬首されるとは、歴史の皮肉である。ルイ16世本人はもとよりサンソンも想像すらしなかった悲劇だろう。筋金入りの王政主義者だった死刑執行人は、1793年1月20日、国王の死刑判決確定の一報を聞いたとき、激しく動揺したのだった。
裁判は1月7日に結審、その後評議され、387名が死刑、334名がそのほかの刑を要求し、28名が棄権・欠席した。19日と20日には「死刑に執行猶予をつけるか」が問われたが、賛成310票、反対380票で否決され、死刑が正式に確定した。その結果は午後2時頃、国王にも伝えられた。
個人的には、「高貴な方」の死刑を執行したくはない。だが、サンソン家は代々、死刑執行人の職を務めてきたことを誇りにしていた。その一族の「使命」を果たさないわけにはいかない。シャルル=アンリはその狭間で葛藤していた。そこで、国王が死刑執行の場(革命広場。現在のコンコルド広場)に到着する前に救出されるという噂に一縷の希望をつなぐが、叶わなかった。「もはや疑いようもなければ、幻でもない。近づいてくるのは、まぎれもなく殉教者だった。/私の視線は混乱し、身体中がガタガタと震えた」(柴田道子ほか訳)。
1月21日午前10時過ぎ、サンソンの期待も虚しく、ギロチンの刃が「不幸な王」の首に落ちた。最期の言葉は、「私は告発されたすべての罪について無実のまま死んでいくのだ」、だったという。この人を殺めてしまったという「良心の苛責」が、死刑執行人をして冒頭のようなミサを秘かに行わせた。いや、そのような創作意欲をバルザックに湧かせたのである。その「忠誠の驚くべき行為」には、立場は違えど、マルゼルブによるルイの弁護を思わせるものがある。
驚くべき忠誠が向かう対象は、王という国の〈象徴〉だった。確かに、92年9月に王政は廃止され、それは地に堕ちたはずだった。王国を象徴する父としての君主に代わって、共和国を象徴する母としての女神が各地で飾られ、聖性は転移してゆく。それでも、ある人々の心のなかで国王は聖なる象徴であり続けたのだろう。しかも「殉教者」となることで、ルイ16世そして王家はある種の神聖さを纏うことになる。多くはその信奉者である「反革命」と呼ばれる人々とブリソ派(ジロンド派)、モンターニュ派(山岳派)による〈象徴〉をめぐる三つ巴の戦いは最終局面を迎える。

「どこもかしこも陰謀だらけなんだ」
国民公会が開幕した頃、92年8月の「第2の革命」と9月虐殺によって激化した対立は終息するのではないかという期待が人々にはあった。だが、ブリソ派はモンターニュ派を執拗に攻撃し、「虐殺」を彼らの責任にして逮捕を目論んだ。議会の多数派はブリソ派にシンパシーを抱いたが、それには議長をはじめ要職を同派が独占していたことも一因とされる。しかし、絶えざる激論の中、他の解決すべき議題が話し合われず、議員たちも次第に飽き飽きしてきた。また、ルヴェによる激しい口撃にもロベスピエールが屈せず首尾よく反論することで、山岳派に対する多数派議員の不安はある程度落ち着いた。さらに、国王の死刑を阻止しようとしたブリソ派には、国王支持者(=反革命的?)という負のイメージが残ることになった。
ジロンド派の議会内での優勢はなお続くが、同派が主導してきた戦争によってその支配は揺らいでゆく。最初のきっかけは、30万人動員令(93年2月24日)だった。前年11月にデュムリエ将軍率いるフランス軍がオーストリア軍を破ったあと、国民公会は自由の回復を求める他国民を援護する法令(11月19日)を発し、サヴォワやニースを併合、93年2月にイギリスやオランダに宣戦布告するものの、戦況は徐々に行き詰まりを見せる。そもそも志願兵を中心とした軍の編成や規模には限界があり、そこで全国各市町村から30万人を徴兵しようという命令が出されたわけだが、各地で不満そして反乱が続出したのである。

3月、農家では人手のいる時期、徴兵は死活問題だった。なかでも農民蜂起で有名になったのは、仏西部ヴァンデー地方である。共和国軍を一時負かし、粘り強く抵抗したのだ。その知らせがパリに届いた頃、ネールヴィンデン(現ベルギー領)でのデュムリエ将軍敗退の一報が伝えられ、議会は混乱した。同地方の反乱は、英国首相ピットの資金援助や亡命貴族の関与などを連想させ、「反革命派」に対する陰謀論が再び噴出することになる。この頃、英国およびピットの介入は、「オーストリア委員会」に代わる陰謀家のお気に入りの題材となった。
同月10日、国民公会では、陰謀を企む者たちを裁くことを目的に「特別刑事裁判所」が設置されたが、それはブリソ派の反対を押し切るかたちで決まった。その背景には、この頃食糧不足のために全国各地で騒擾が生じ、同派の支持が議会内外で低落していたことがあった。
13日、ロベスピエールはジャコバン・クラブで演説を行い、陰謀が国内外、とりわけ国内の隅々にまでいかに浸透しているかについて熱弁した。「陳情を口実に、陰謀家がセクションの中に〔まで〕紛れ込み、そこで混乱を広げている」。「われわれの敵たちは諸集団の中にいる密使である」。これに対して、不完全な蜂起(=暴動)は好ましくないとしながらも、国民公会に失望させられた今、「善良な市民が集結する必要がある」と主張したのである。
さらに、この危機の瞬間に対処するために設置されたという革命裁判所(=特別刑事裁判所)について、愛国者を告発するのに悪用されるのを防ぎながら、陰謀家を裁く場として活用されなければならないと訴えた。そのうえで、ロベスピエールの革命の哲学が開陳される。
最終的に彼ら〔国民公会の議員〕が真に熱狂的な愛国心に突き動かされるなら、みずからを告発する必要がある。そのとき愛国者たちは彼らを許すだろう。なぜなら、われわれは自由の敵全員の死を要求しているのではなく、彼らがみずから改心し生きることを要求しているからだ(〔議場では〕大きなざわめき)。
要するに、私は今あなた方に大きな陰謀があることを示したが、それを挫く手段は一つしか知らない。陰謀家たちに、すべての卑劣な行為をみずから打ち明けるように強いることである。
つまり、陰謀を企てていることをみずから告白しろ、というわけである。以前述べたように、陰謀を疑われた者はそのような「意志」がないことを証明することが求められるものの、それがないことを証明するのは究極的には不可能である。当人であればそれを証明することが可能で、その場合はわれわれによって許されると革命家は言うのだけれども……。これに対して、独裁者たろうとする勢力を許す余地はなく、妥協は「ありえない」と紙上で断言し、「終わりなき戦い」を宣告したのはブリソの側だった(3月10・16日)。
ともあれ、事態の悪化は避けられない事件が起きる。大きな陰謀を裏づける「事実」が発覚したのである。ベルギー戦線で敗北を喫したデュムリエ将軍が3月27日、軍隊をパリに向かわせ国民公会を解散させようとして失敗、しかもその後4月4日にオーストリア軍に投降したのである。彼は将軍になる前、ブリソの推薦で外務大臣を務めた人物であり、彼の「裏切り」はブリソ派の印象をさらに悪くしたことは言うまでもない。モンターニュ派にとってだけでなく、民衆にとっても、ジロンド派と反革命派を見分けることは困難となった。
それでも、ロベスピエールは彼らの「追放」には慎重だった。ジャコバン・クラブの会合(3月29日)で、人民自身が国民公会を救わなければならないとする一方で、(そのとき議題にのぼっていた)議員の不逮捕特権には手をつけず、議会の場で仮面を剥がすべきであると訴えた。同特権を剥奪する法令が出された4月1日も、ロベスピエールは祖国・共和国を救う手段は議会、国民代表制であって、これを侵食するのは愚の骨頂であると繰り返したのである。
同月3日、かつてはロベスピエールとパリ民衆の人気を二分したペティヨン法相[元パリ市長で、国民公会ではジロンド派に属した弁護士]は、こう訴えた。「われわれの国外の敵がいかに恐ろしくとも、国内の敵のほうがよりいっそう恐ろしい。彼らから偽りの人気の仮面を剥ぎ取るべきときだ」。これに対して、今度はロベスピエールが、ブリソや同派のデュムリエとの関係を明らかにしたうえで、祖国のためには国民公会の場で「陰謀のモーター」であるブリソの仮面を剥がす必要があると反駁した。
こうして両派はやはり、陰謀論を楯に同じ言語を用いて論駁し合っていたのである。前回(第11回)掲載されたヴィクトル・ユゴーの長編小説『九三年』(1874年)の「架空の会談」でマラは、マクシミリアンとダントンに向かって次のように語っていた。「いいかい、次のことをしっかり心得ておくんだぜ。危険は、きみたちの頭上にあるんだ、足もとにあるんだ。陰謀だ、陰謀だ、どこもかしこも陰謀だらけなんだ」(辻昶訳)。
4月12日、ジロンド派はそのマラの逮捕を要求した。マラがジャコバン・クラブで同派出身の大臣の罷免を要求したという反乱煽動の罪が表向きの理由だったが、それは明らかに政敵を排除するための口実だった。同日、ロベスピエールは「人民の代表の特性は尊重されるべきだ」と述べたうえで、確かにその言動が「非合法に見える」としても、裏切り者たちを死に追いやるようなものではなかったと、マラを擁護した。彼にとって、代表ならびに議会は尊重されるべきで、敵への攻撃もあくまで「合法的」に行なわれる必要があった。
むしろ、なりふり構わぬジロンド派の行動は一線を超えたものに見えただろう。司法大臣のペティヨンは同日、かつての友に向かって次のように言い放った。「ついにすべての卑劣な言動が終わるときである。裏切り者と中傷者の頭を死刑台に送るときなのだ。私はここに、彼らを死に追いやるまで追及することを約束する」。さらに、「私の忍耐は限界なのだ。裏切り者たちの仮面を剥がすことを誓う」というお決まりのフレーズが続く。かくして、いくら感情的になったからとはいえ、相手を「死に追いやる」とまで口撃するような議場での発言は、一線を超えたと言うべきだろう。しかも、つい3ヶ月前に国王が死刑台に送られたことを考えれば、その発言にはある種のリアリティさえあった。
24日、パリの革命裁判所はマラを無罪にし、彼は国民公会に堂々と凱旋した。そのとき、ジロンド派の劣勢は決定的となった。この事件は国民公会にとって一つの大きな節目となる。
ブリソ派の追放
マラの告発と前後して、ロベスピエールはクラブや議会で、敵に買収された新聞の禁止を訴え、言論・出版の自由を否定するような発言をした。ここにきて論調の変化が見られるものの、5月になっても、「人民の英雄的行動」がなければ腐敗に立ち向かえないと話す一方で、国内の敵に対して暴力には訴えないよう、民衆には平静を保つように訴えてもいた(10・12日のジャコバン・クラブ演説)。その後、翌日から十日ほど(13〜24日)、体調を崩して議会を欠席している。病欠は初めてではなく、彼が心身ともに疲弊して休むことは珍しくなかった。
ロベスピエールの長期欠勤の間に、ジロンド派は最後の巻き返しを図る。同月18日、国民公会を破壊する陰謀の証拠を発見することを目的にした委員会を設置したのだ。12名の議員からなるその委員会のメンバーはすべてブリソ派で占められ、パリの騒擾を煽動しているという過激派(アンラジェ)を排除することを意図していた。すぐに調査を開始し、パリのコミューンの役員でサン=キュロットの指導者であるエベールやヴァルレを含む活動家たちを逮捕、それに反対するデモ参加者の多くも――その中には女性も含まれる――収監された。
さらに22日、ブリソが同コミューンの解散とジャコバン・クラブの閉鎖を訴える。また25日、ジロンド派議長イスナールが、〈静かな多数派〉の支持が得られるという認識のもと、まもなくパリは軍隊によって制圧されるという見通しを示した。これはパリ民衆の活動の火に油を注ぐ結果となった。26日、マラに同調するかたちでロベスピエールも人民に蜂起を訴えた。
ブリソ派によって法が犯された今、それは正当化されると言明したのである。「人民が立ち上がるとき、これらすべての人間〔反革命派〕は消え去る。(中略)あらゆる法が犯されたとき、専制が絶頂に達したとき、誠意や貞節が踏みにじられたとき、人民は蜂起しなければならない」。基本的に代議員が責任を持って「人民の政府」を樹立しなければならないが、人民の声が議員に聞かれないとき、「人民主権が侵された」とみなしうる。そのとき、蜂起は正当化されるのだ。
29日、パリ民衆はコミューンが蜂起するための委員会(司教館委員会)を設置し、12人委員会の廃止を要求、蜂起の準備を進めた。そして30日夜、正式に蜂起を宣言、翌日蜂起を開始した。司教館委員会によって国民衛兵司令官に任命されたフランソワ・アンリオの指揮のもと、サン=キュロットたちが国民公会を包囲する中、議会では12人委員会の廃止が宣言された。それ以外の要求は認められなかったが、6月2日再度議会が包囲されると、議員たちは短い議論の末、29人のジロンド派議員の逮捕を決定したのだった(6月2日の革命)。

これら一連の事件は、「革命」を維持するためなら法を超えたすべての手段が許されるという「教訓」を残した。このとき、陰謀や敵、仮面とともに「根絶」が政治のキーワードとなったのは偶然ではない。どんな手段を使おうと、〈やらなければやられる〉という発想がそこにはある。ただ、その発想のもと、当初は国外の敵に用いられたこの言葉を議会に持ち込んだのはブリソ派だった。
今から見れば、暗い時代の入り口にさしかかっていた。が、不思議と多く人々が〈前に進んでいる〉という実感を持てた時代でもあった。ユゴーは『九三年』の中で次のように述べる。
芸術家も、雄弁家も、予言者的な政治家も、(中略)「進歩」というただひとつの目標をめざして前進しようとしていたのだ。彼らは何ものに出合っても挫折しなかった。国民公会の偉大さは、世に不可能事と呼ばれるものの中に実現可能なものを求めようとした点にあるのだ。
それでも、「進歩」の名の下に進む国民公会、そして革命それ自体には両面性があった。一方にはジロンド派のコンドルセのような「明哲な夢想家」が、他方にはモンターニュ派のロベスピエールのような「実行家」がいたと、ユゴーは説明する。「ところで、老朽したひとつの社会が断末魔の危機にある際には、実行は往々にして皆殺しを意味するのだ。どの革命にも上り坂と下り坂との二つの斜面がある」。実行家ないし活動家が夢想家ないし理論家を追放し、一方が他方を根絶やしにしようとする時代、恐怖時代はまだ始まったばかりである。
-

-
高山裕二
明治大学政治経済学部准教授。博士(政治学)。専攻は政治学・政治思想史。著書に『トクヴィルの憂鬱』(白水社、サントリー学芸賞受賞)、共著に『社会統合と宗教的なもの 十九世紀フランスの経験』(白水社)、『近代の変容(岩波講座 政治哲学 第3巻)』(岩波書店)などがある。
この記事をシェアする
「ロベスピエール 民主主義の殉教者」の最新記事
ランキング
MAIL MAGAZINE
 とは
とは
はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。
「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。
どうして自分が「考える人」なんだろう――。
手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。
それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。
それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
「考える人」編集長
金寿煥
著者プロフィール
-

- 高山裕二
-
明治大学政治経済学部准教授。博士(政治学)。専攻は政治学・政治思想史。著書に『トクヴィルの憂鬱』(白水社、サントリー学芸賞受賞)、共著に『社会統合と宗教的なもの 十九世紀フランスの経験』(白水社)、『近代の変容(岩波講座 政治哲学 第3巻)』(岩波書店)などがある。
連載一覧

ランキング





ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら